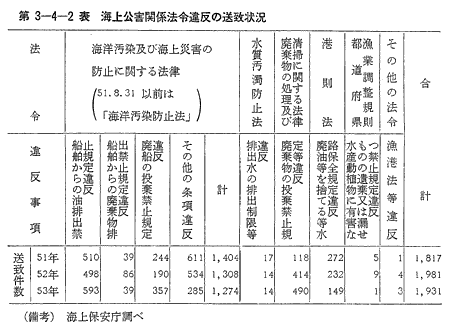
2 海洋汚染防止対策
(1) 海洋汚染の未然防止対策
ア 船舶に対する規制
船舶からの油及び廃棄物の排出による海洋汚染を防止し、海洋環境の保全を図るため45年に制定された「海洋汚染防止法」については、その後、逐次規制が強化されるとともに、51年には海上災害対策を強化するための改正が行われ、題名も「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」と改称された。
同法では、船舶からの油及び廃棄物の海洋への排出を原則として禁止しており、安全の確保上やむを得ない場合、その他一定の条件に従った場合のみ例外的に排出を認めている。
また、これらの排出規制を担保するため、一定の船舶に対するビルジ排出防止装置の設置義務、廃棄物、排出船の登録制度等を定めている。
しかしながら、海洋汚染防止に関する国際世論の高まり等にかんがみれば、今後なお一層、対策を充実していく必要があり、54年3月第87回国会に、1972年の「廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約」の批准・国内法化を図るとともに併せてビルジの排出規制の対象船舶の範囲を拡大することを目的として「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」の一部を改正する法律案を提出した。
イ 廃油処理施設の整備
船舶内において生ずる油性バラスト等大量の廃油を処理する廃油処理施設は47年度までに整備を完了し、53年度においては前年度に引き続き法規制の強化に伴い改良が必要となる保安施設の整備を行った。
操業中の廃油処理施設は、54年1月18日現在、港湾管理者、民間事業者等の運営するものを併せて81港129か所である。
(2) 海洋汚染防除対策
ア 防除体制の整備
海上保安庁は、タンカー等の船舶及び沿岸の石油関係施設から油が流出した場合に対処するため53年度においては、所要の部署に海上防災係を置くとともに、油防除艇、油回収装置、オイルフェンス等の整備を図ったほか、「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」の油回収船等の配備に関する規定に関して、油回収船等の性能基準、油回収船等を配備すべき海域等について所要の省令を制定するとともに、同規定の施行を54年5月21日とする等汚染防除体制の充実強化に努めた。
また、従来から全国の主要港湾に設置されている流出油災害対策協議会等の指導・育成を図るとともに、全国各地において、官民合同の大規模流出油事故対策訓練を実施した。
更に、「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」に基づき、51年11月に設立された海上防災防止センターの指導・育成を図っており、53年11月に四日市港で発生した隆洋丸流出油事故等に際しては、同センターに指示し、流出油の防除のための措置の実施に当たらせた。
消防庁においては、石油コンビナート等特別防災区域に係る災害を防除するため、石油コンビナート等災害防止法の規定に基づく油回収船の備え付けに関して、油回収船の能力及び隻数について所要の省令の規定の整備を行うとともに、同法に基づき特定事業所の自衛防災組織に備え付けるべきオイルフェンス、オイルフェンス展張船及び油回収船の備え付けについて指導を行った。
イ 港湾及び周辺海域の浄化対策
港湾及びその周辺海域の海洋浄化のため、53年度には、公害防止計画に基づく港湾公害防止対策事業として東京港、四日市港、水島港等13港において汚泥のしゅんせつ等を行った。また、港湾環境整備事業として東京港、大阪港等13港で廃棄物埋立護岸又は港湾等において発生する海洋性廃棄物の処理施設を整備したほか、港湾区域内の浮遊ごみの清掃のための清掃船を建造した。
運輸省では、48年度以後建造した油回収船4隻、ごみ清掃船6隻及びごみ・油回収船2隻を用いて東京湾、伊勢湾、大阪湾及び瀬戸内海において浮遊油の回収及び浮遊ごみの清掃を実施し、また、52年度から2か年計画で伊勢湾、瀬戸内海のごみ、油回収船各1隻、東京湾の油回収船1隻を建造するとともに、51年度に建造した油回収機能を備えた大型自航ポンプしゅんせつ船を完成した。このほか、52年度に引き続き東京湾、伊勢湾、大阪湾及び瀬戸内海の海底に堆積している汚泥の処理等についての基礎的調査を実施した。
(3) 監視・取締り及び指導の状況
海上保安庁は、従来から我が国周辺海域における船舶あるいは陸上から排出される油・廃棄物及び臨海工場からの排出水等について監視・取締りを強力に実施してきたが、最近は、違法行為が悪質、巧妙となり、潜在化する傾向がうかがわれる。
このため、53年度においても引き続き監視・取締り要員の増員、巡視船艇・航空機の整備増強、公害監視用VTR、分析測定機器等の各種資機材の整備強化を行い、これらを効率的に運用し、全国的あるいは地域的な一斉取締りを実施するなど、きめ細かい監視及び重点的な取締りを実施した。
最近3か年における海上公害関係法令違反の送致状況は、第3-4-2表のとおり、53年は1,931件で、52年に比べ50件(約3%)減少している。このうち、船舶あるいは陸上からの油・廃棄物の排出等海洋汚染に直接結びつく実質犯は1,649件で、全体の85%を占めている。
また、燃料油取扱い作業中の船舶からの漏油事故は依然として多発しているため、「船舶による漏油事故防止推進期間」を設けて全国一斉の臨船指導及び関係会社等に対する指導を行い、事故防止体制の改善に努めている。
更に、7月20日から31日までの「海の旬間」に、官民協力による海洋汚染防止活動を実施したほか、社団法人日本海難防止協会が、名古屋、福岡等8か所で行った海洋汚染防止講習会の機会を利用して、海事関係者等に対し海洋汚染の実態とその防止対策の周知・啓蒙を図った。
(4) 海洋汚染防止技術の研究開発
運輸省ではIMCO(政府間海事協議機関)の「1973年の船舶からの汚染の防止のための国際条約に関する1978年議定書」により船舶に設置が義務付けられる機器のうち、油分警報装置及び高性能舶用油水分離器の研究開発を51年度から引き続き行うとともに、汚水処理装置の研究開発に3年計画で着手した。更に、50年度から開発を進めている大量の油流出事故に対応できる高性能のオイルフェンス及び油回収装置については、最終年度としてこれらの総合評価を行った。
また、海洋の浄化技術として、伊勢湾等における海水交換と汚染物質の希釈拡散機構等を解明するための水理模型実験、汚泥しゅんせつ技術の開発等を行った。
(5) 海洋汚染防止に関する国際条約
船舶による海洋汚染の問題は古くから条約による国際的な防止対策が進められており、我が国もこれに沿って所要の措置を講じているが、近年の国際的な動向は、なお一層の規制強化の方向にあり、今日、我が国が対応を迫られているものとして、次の2条約がある。
1つは1972年の「廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約」で、その内容は、船舶、航空機等からの主として陸上で発生した廃棄物の投棄による海洋汚染を防止するため、各国が採るべき措置等について定めているが、53年10月に開かれた第3回締約国協議会議において附属書の一部改正が行われ、我が国では未規制の洋上焼却についても規制されることとなった。
また他の1つは「1973年の船舶からの汚染の防止のための国際条約に関する1978年議定書」であるが、本条約では、油(軽質油を含む。)、ばら積み有害液体物質、汚水等の排出規制のほか、一定のタンカーについては、SBT(分離バラストタンク方式)、COW(原油洗浄方式)等を義務付けるなど船舶に対する大幅な構造・設備規制をも規定している。
我が国は、前者については、その批准・国内法化を図るため、54年3月に第87回国会に「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案」を提出した。なお、後者についてもできるだけ早期に批准・国内法化するため、運輸省を中心としてその準備作業を行っている。