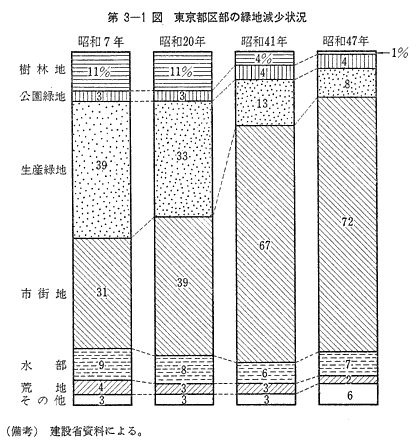
2 その背景
快適な環境への関心が高まってきている主な背景として、次の三つを挙げることができよう。第一は、戦後の急速な経済成長期を通じて、緑や水辺、静けさなど快適な環境を構成する諸要素が急速に失われたことである。第二は、所得水準が高まり余暇が増加するなど、生活全般にわたって著しい改善が進むにつれて、住宅及びそれを取り巻く生活環境が相対的に低水準にあることが自覚されてきたことである。第三は、従来、環境問題の中で大きな部分を占めてきた公害対策が相当の成果を収めてきた結果、より広い視野から環境問題に取り組んでいくことの必要性が認識されてきたことである。
(快適性の低下)
戦後の急速な人口と産業の都市への集中は、大気や水質等の汚染などの公害を引き起こしたばかりでなく、市街地のスプロール的拡大や都市周辺における工場立地の無秩序な進行をもたらした。
市街地は、既存の市街地の周辺を中心として農地、樹林地等の宅地、道路等への転換により拡大を続けてきたが、その際、しばしば十分な緑化やオープンスペースの確保、また、河川等の水辺の保全などがなされないまま進行しがちであった。そのため、既成市街地の周辺地域に転入してきた住民及びその地域に以前から居住していた住民にとって、緑の減少や河川の汚濁などの生活環境の質の低下がもたらされたといえよう。更に、既成市街地の住民にとっては、一方で、かつて自然と触れ合いの場であった郊外の農地や樹林地が減少し、他方で、市街地内の過密に伴い緑地が減少し、交通騒音の増大等により静穏が失われてきたことなどから、同様に、快適性の低下がもたらされたといえよう(第3-1図)。
工場用地の拡大は、面積的には市街地の拡大に比べると少ないものであったが、その多くが大都市周辺の臨海部に集中したため、広範囲にわたり、地域住民が享受してきた美しい浜辺の景観や、海水浴、潮干狩などの海辺における快適さが失われがちであった。(第3-2図)。
これらの快適性の低下は、都市における土地利用が、ややもすると、主として経済的効率性の観点から進みがちであったことの結果であるといえよう。
(生活水準の全般的上昇)
所得水準の上昇は、生活環境に対する考え方に幾つかの大きな影響を与えた。第一は、耐久消費財等をはじめとして、物財の豊かさがある程度充足されたことにより、これまで必ずしも高い関心が払われてこなかった生活環境の持つ質的な快適さ……美しさ、うるおい、ゆとり、静けさなど……の分野に人々の関心が移ってきつつあることである。第二は、余暇の増大による旅行等の増加及びテレビ等マスメディアの発達により、国外を含め各地の生活環境に関する情報に接する機会が飛躍的に増大し、居住地の生活環境の質の水準について再認識する機会が増えたことである。特に、近年増大している海外旅行により、我が国の生活環境、なかでも市街地景観などが、欧米諸国と比べて見劣りする面があることを、多くの人々が実感として認識しつつあるように思われる。
(公害対策の進展)
我が国におけるこれまでの環境政策は、公害防止、その中でも公害による健康被害の防止を第一の目標として進められてきた。その結果、この面においては、相当の成果を収めてきた。今日、生活環境に対する人々の関心は、単に公害の防止にとどまらず、快適性までを含めたより広い範囲に広がってきていると見られる。快適な環境を享受するためには公害が防止されていることがまず必要であるところから、今後とも公害対策を推進していくことは当然のこととして、快適な環境を目指して、より積極的な行政を展開していくことの必要性が認識されてきた。