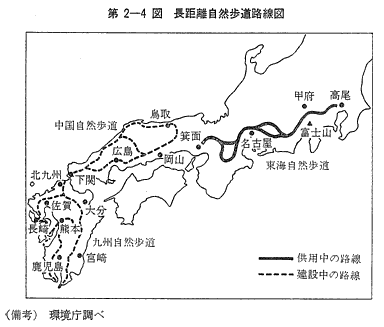
2 今後における自然環境保全対策の方向
(1) 科学的知見の集積と活用
自然環境保全行政をより説得力をもったものとし、かつ適正なものとするためには、科学的知見の集積とその行政的活用が不可欠である。そのためには、「自然環境保全法」第5条に基づく自然環境保全基礎調査(いわゆる「緑の国勢調査」)の更に一層の充実をはじめ、野生動植物の生息、生存状況、自然景観の形質、特徴等自然環境保全に必要な知見を科学的手法を用いて収集し、整理するといった地道な作業とそのためのシステムづくりが要求される。精緻かつ複雑な自然のメカニズムを解明することは容易なことではないが、人間活動と自然の関係、物質の循環、生態系の保全技術等についての科学的データの整備は急を要する問題である。
しかしながら、現時点においては、これらの研究課題に専門的に取り組む研究機関が設置されていない実情にあるので、今後においては、これらの部門の研究体制を整備するとともに、研究者及び研究の成果を具体的施策に反映させる技術者の養成が当面の大きな課題であると考えられる。
(2) 身近な自然の再評価
緑と自然に包まれ、安らぎに満ち郷土愛の強い、そしてみずみずしい人間関係が脈打つ生活環境を整備することが国民から求められている。このためには、都市の持つ高い生産性、良質の情報と身近な田園の持つ豊かな自然、うるおいのある人間関係を高次に結合させることが必要とされている。
自然公園は、一般的にこのような国民の要請を充たす上で大きな役割を有するものであるが、特に都道府県立自然公園は、田園における都市住民の日帰り行楽圏の中になり、身近な自然として高く評価されるべきものである。このような地域において健全な野外レクリエーションの場や、国民の誰もが自然に対する認識を深めることができるような観察研究の場を確保することが重要な課題である。そのため今後においては、自然公園の施設整備等の助成を国立公園、国定公園に限らず都道府県立自然公園にも広げるといった対策について検討する必要があると考えられる。
また、長距離自然歩道については、東海自然歩道が49年に完成し、更に、九州自然歩道、中国自然歩道もそれぞれ55年度、57年度完成を目標に目下建設中である。(第2-4図)が、この自然歩道は、地域住民が自動車を避けて自然に親しむ恰好な場として好評を博しているので、今後は、この自然歩道を通じて身近な自然を楽しむためのネットワークを形成していくという方策も有益であると考えられる。
更に、鳥獣保護区は人と野鳥の交歓の場、また野鳥を通じて自然のメカニズムに目を開き、野鳥のさえずりに自然の摂理を聞く場となるべきである。このためには鳥獣保護区の適切な管理運営によってその利用価値を高め、それが人々にとって身近な存在となる必要がある。この意味で鳥獣保護区における野鳥観察の指導、探鳥会の実施、案内板の設置、観察・教育の施設の整備等が望まれよう。
(3) 自然保護行政推進体制の整備
自然公園の美化清掃、施設の補修管理、利用の適正化といった業務は、国、都道府県、市町村といった行政機関が中心となって地元民間団体の協力を得ながら実施されてきた。しかしながら現下の行財政事情にかんがみ、現在のような行政機関中心の体制で520万haにも及ぶ自然公園の地域を適正に保全していくことはおのずから限界があるといわざるを得ない。自然公園は広く国民の保健・休養、教化のために設けられているものであり、それ故、自然の恩恵を享受する者、自然を媒体として利益を得る者等広く国民に呼び掛けを行い、自然環境保全のための実践的活動への積極的参加を求めるとともにそれを組織化することを検討する必要がある。このような点において、現在設立の準備が進められている(財)自然公園美化管理財団(仮称)は、現在の自然公園の管理体制の不十分な点を補う民間組織の一つとして、今後の成長が期待される。
(4) 自然保護のための費用負担の問題の検討
自然保護を円滑に進めていくためには、各種の助成対策のほか、それなりの費用又は負担が必要であり、それはしかるべきルールにのっとって行われるべきであると考えられる。自然環境のために必要となる地方公共団体の費用、自然公園、自然環境保全地域等の地域内の私権者の負担をどのように考え、どのように対処すべきか、という問題は極めて難しい問題であるが、自然公園の利用者、受益者の負担の問題にも焦点を合わせつつその具体的あり方について検討する必要がある。
この問題の具体的な例として、本州四国連絡橋の建設の協議の際採られた自然環境の保全措置と(財)自然公園美化管理財団(仮称)の設立が挙げられる。
本州四国連絡橋(児島・坂出ルート)の建設について環境庁は、53年5月に本州四国連絡橋公団から自然公園法第40条の規定に基づく協議を受け、同年9月に同意した。この問題に際して、同ルートが瀬戸内海国立公園における多島海景観の核心部に設定されるため、環境庁、事業者である本州四国連絡橋公団の監督庁である運輸省及び建設省等の関係者は、同ルートに係る自然環境保全対策について協議を行い、その結果次のような対策が講じられることとなった。
? 本州四国連絡橋公団による事業用地等の修景緑化
? 鷲羽山地区等の道路、駐車場等の道路整備
? (財)自然環境保全基金(仮称)の設立
? 関係者から成る連絡協議会の設置
以上の措置は、本ルートの設定について出された自然環境保全審議会自然公園部会本四連絡橋問題小委員会の意見の中に示されている「さらに本州四国連絡橋の建設やそれに伴う利用者の増加などのために生ずる自然環境への影響を最小限に防止し、又はその回復を図る等自然環境保全に必要な事業を本州四国連絡橋公団がその事業の一環として実施する等自然との有機的融合を図るための措置が必要である。」という考え方を受けて講じられたものと考えられる。
また、国立公園、国定公園等の自然公園の環境美化と適正管理を図るため、自然公園美化管理財団(仮称)の設立に対し助成することとしている。この財団法人をもって利用者の増大等に伴い自然環境の破壊が進みつつある自然公園地域においてきめ細かに美化管理を行うこととしているが、この美化管理に必要となる費用の一部は、自然公園内の駐車場利用者に対し駐車料金という形で負担を求めることとしている。
自然公園内の駐車場利用者に負担を求めるという点については、自然公園の利用者の大部分が自動車を利用しているという実情から見て、即これが特定の者のみ著しい負担を強いるということにならないと考えられる。しかし、その具体的な実施方法については、今後とも、地元住民、利用者等関係者にも十分理解が得られるよう努めていく必要がある問題であると考えられる。
(5) 地域振興対策との調和と連携
自然環境保全施策は、国民の理解と協力のもとに、地方公共団体と連携を図りつつ、強力に展開しなければならない。そのためには、開発行為に対する規制、土地のもつ公共的性格の重視等につき、勇断をもって臨まなければならないが、同時に国土保全その他の公益との調整に留意するとともに、地域住民の生業の安定ないし福祉の向上のために必要な施策を総合的見地から講じていく必要がある。
この点において、自然保護対策と離島振興、過疎地対策との緊密かつ適切な連携、協力が現在最も強く求められる課題であろう。そのためには、恵まれた自然を活かしながら自然レクリエーション対策、農林漁業対策、交通通信施設の整備等地域振興の多彩な方策が総合的かつ強力に推進されることが必要とされる。
また、地域によっては農林漁業経営の安定化の上で鳥獣による被害が一つの障害として問題にされているがこれに対しては、被害発生のメカニズムを明らかにする努力を行うとともに、被害防止に関する技術等の開発、鳥獣の生息数の適正なコントロール等、総合的に施策を行うことが必要である。
(6) 貴重な自然としての鳥獣の保護施策の充実
自然のなかで国家的見地からみて重要なものについては、国がその保全に当たるのが通例である。しかしながら鳥獣については、例えば鳥獣保護区の設定を見ても分かるように、そこにおける保護の対象となる鳥獣の重要性に視点をおいて、国の役割分担が決められてはいないという状態にある。
そこで、今後においては従来の考え方を改め、その保護が国民全体の責務である絶滅のおそれのある鳥獣や国際的保護の対象である渡り鳥について、その生息地、渡来地、中継地等枢要な箇所に国設鳥獣保護区を設定して、保護管理計画に基づき計画的にその保護を図っていく必要がある。
また、狩猟鳥獣といえども自然との接触の機会が少なくなっている現在ではその捕獲には厳しい節度が求められている。この点からいって、また、秩序ある狩猟、安全な狩猟の面からいっても、猟区での狩猟、特に養殖され放鳥獣された鳥獣を捕獲させる放鳥獣猟区での狩猟へ誘導していくことが推進されるべきであろう。
(7) 国際協力の推進
自然は、かけがえのない、人類共通の財産でありその保全は人類共通の関心事である。
このため、これまでも各種国際団体を通じて、自然環境保全のための国際的研究の実施、技術協力、情報の交換、国際的な自然保護思想の普及啓蒙等が行われてきている。我が国も、自然保護の面における国際的責任を果たすべく積極的に活動していくことが望まれるが、この点、環境庁が53年にIUCN(国際自然保護連合)の国家機関会員となったことはIUCNが自然保護の面での国際協力の中心団体であることから、大きな意味を持つものである。
自然環境保全面での国際協力で大きなウエートをしめるのは鳥獣保護の分野である。鳥獣は、例えば多くの渡り鳥のように国境を越えて移動することが多く、また、鳥獣のなかには、国内市場だけでなく、国外の顧客のために捕獲され、取引されるものもあるからである。この鳥獣資源の国際性から、鳥獣保護のための国際条約も二国間条約から多数国間条約まで数多く存在している。そのなかには我が国がまだ締約国となっていないものも多く、我が国が鳥獣保護の面で積極的に国際協力を進める上で、これら国際条約を締結することが強く望まれている。
このうち、国境を越えて渡りをすることの多い水鳥の生息地として国際的に重要な湿地を国際協力により保全することを目的とするラムサール条約は第87回国会に提出され、条約加盟へと大きく前進している。また、絶滅のおそれのある野生動物の保護を図るため、これらの動植物の輸出入等を規制するワシントン条約についても、その早期批准のための努力が続けられている。