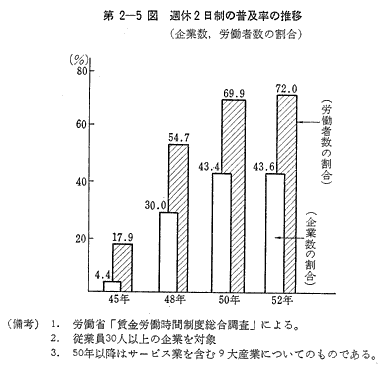
3 自然環境の適正利用
自然は人間生活にとって生命をはぐくむ母胎であり、それを保全していくことは、豊かな人間生活を営むための不可欠の条件であり、豊かな緑の中で清浄な大気を呼吸し、清冽な流れに足を浸しあるいは野鳥のさえずりに耳を傾けるなど、自然そのものに親しむことは、うるおいとゆとりある生活を営むための重要な要素である。
経済が高度成長から安定成長へと移行する中で、国民の意識も生活にゆとりとうるおいを求める方向に変化してきつつあり、また、国民の自由時間についても、45年に従業員30人以上の企業数の約4%、労働者数の約18%にしか及んでいなかった週休二日制が、52年には企業数の約44%、労働者数では約72%まで普及しており(第2-5図)、更に週休以外の休日日数も51年には1企業平均で16.2日となるなど増加の傾向を示している。
このような状況の中で、国民の野外レクリエーション需要はますます増大するものと思われる。
これに対応するには、歩道、園地、野営場、野鳥観察施設等自然の利用施設を拡充整備していくことが不可欠である。
このため、自然公園等においては、その健全利用を推進するため、園地、野営場等の施設整備が行われている。国においても総理府所管の集団施設地区において直轄の施設整備事業を実施しているほか、都道府県の行う施設整備に対し、その費用の一部を補助している。
また、自然環境に恵まれた休養適地には、国民の誰もが、低廉で快適に利用できる国民宿舎が、年金積立金還元融資(特別地方債)を受けて、設置、運営されている。
更に、長距離自然歩道、国民休暇村、国民保養温泉地、国民休養地、野鳥の森などが整備され国民の利用に供されている。
今後とも、これらの利用施設、特に日常生活に密着した野外レクリエーション施設を拡充整備していくことが必要である。
公園等の自然環境の利用の増大に伴い、近時、幾つかの問題が生じてきている。
第一は、ごみの問題である。主要利用地域においては、空きかん等による汚れが目立ってきている。富士山などにおいて登山道を中心に空きかん、ごみくずが散乱しているのは周知のとおりである。これらの利用地域は、海辺あるいは山の中など日常生活圏から離れていることが多く、地理的特性からいっても、通常の廃棄物処理や清掃活動により処理すること困難なことが少なくない。国、地方公共団体においても、これに対処するため、美化清掃団体に対し補助金を交付するなど、美化清掃に努めているが、基本的には、ごみをできるだけ出さないようにし、また、出たごみはできるだけ持ち帰るように、公園利用者自身が、公園を汚さないよう心掛けることが最も重要であろう。
第二は、自動車利用の増大による自然環境の悪化である。近時の道路建設の進展と自動車、特に乗用車の普及により、自動車による自然公園の利用が増大してきた。自動車が自然公園の簡便が利用に大きな役割を果たしていることは否定できないが、一方、それによりもたらされるマイナス面、すなわち、道路の拡幅等による地形、植生の改変、排出ガス汚染による動植物の生育・生息環境の悪化、更には、静穏や安全を損なうことなども無視することができない。自動車利用に対しては、中部山岳国立公園上高地地区、日光国立公園尾瀬地区等において、国の関係機関、地元の地方公共団体等が協力して、交通整理、駐車禁止、自家用車の乗入れ禁止などの適正化対策が講じられている。今後も、これら適正化対策を拡充するとともに、国民に対し、健全利用の必要性の理解を広く求めていく必要があろう。
第三は、過剰利用の問題である。夏期などの利用シーズンには、特定の利用地域に利用者が集中し、例えば尾瀬などでは利用者が歩道にじゅずつなぎになり場合によっては保護すべき湿原に足を踏み入れるなど、適正な利用という面から大きな問題となっているところもある。また、利用者の増大に対処するため、宿舎、休憩所などの増設が進められ、これがかえって周囲の自然環境に少なからぬ悪影響を与えている場合もある。このような問題に対処するため、何らかの方法で利用を誘導していくことは、十分検討に値しよう。
自動車利用の規制と過剰利用の問題に関して参考となる事例として中部山岳国立公園立山地区の例がある。
立山地区は日本の山岳景勝地として有数のものであり、その生態系は植生、野生動物、地形地質ともに貴重かつ人為的干渉に対し弱いものとなっている。立山を訪れる観光客は46年の「立山・黒部アルペンルート」の開通以来、それまで20万人程度であった年間利用者が一挙に70万人に増加し、それに伴い過剰利用により自然環境の保全及び利用の快適性の確保が難しい状況となった。そのため富山県は49年から「立山・黒部アルペンルート」の一部である有料道路について、マイカーの乗入れを禁止し、バスのみの通行を認めることとした。この措置により立山地区における過剰利用による弊害の防止はある程度成功し、動植物の保護、美化清掃の実施等他の対策の成果ともあいまって、立山においては自然環境の保全及び快適な利用は現在も確保されている。また、環境庁が52年度に実施した立山地区での利用者の意識調査においても、マイカー乗入れ規制に賛成する意見が73%を占め、実際に立山を訪れた人にとっては、マイカー利用による交通の利便性よりも、マイカー規制による自然環境の保全及び快適な利用の確保を選択すべきであるという意見が強いという結果になっている。
以上のことから、公園利用者が、今後も好ましい環境のもとで立山の自然を享受しようとすれば、今後ともマイカーの乗り入れの規制を継続することが望ましいと考えられるが、この場合、規制によって生ずる有料道路の料金収入の減少分の負担について、環境保全等の観点から検討されるべきものであると考えられ、現段階では収入減収分の一部を何らかの形で利用者に負担させることもやむを得ないものと考えられる。
なお、この利用者の負担額は、現行の有料道路の料金が、既に相当の高水準にある点を考慮し、著しく高額とならないよう配慮すべきである。同時に、公園利用者が環境保全のために費用を負担してもよいという理解を得るための広報、サービス、施設・整備等の方策を講ずることが必要である。