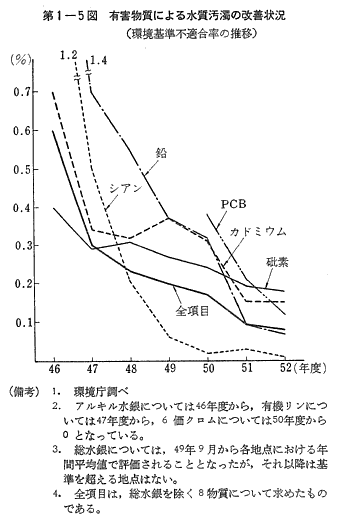
2 水質汚濁
(有害物質による汚濁)
環境基準の定められている項目のうち、カドミウム等人の健康に有害な9物質による水質汚濁は、著しく改善されている。52年度公共用水域水質測定結果によると、全国5,100地点における総検体数のうち、環境基準に適合していない検体数の割合(不適合率)は、0.08%(51年0.09%)となっている。
有害物質の種類ごとに見ると、総水銀、アルキル水銀、有機リン及び6価クロムの4物質については、前年度に引き続き環境基準不適合の地点は全くなく、その他の物質についてもすべて改善が見られる(第1-5図)。
(有機物質等による汚濁)
利水上の障害等をもたらす汚濁項目(pH、DO、BOD又はCOD、SS、大腸菌群数)について見ると、53年3月までに環境基準の類型当てはめが行われた水域の6,337地点における環境基準不適合率は、52年度において、河川20.0%、湖沼34.7%、海域17.8%となっており、長期的には改善の傾向が見られるものの、51年度に比べて河川、湖沼はほぼ横ばい、海域においてはわずかに悪化を示している(第1-6図)。
また、52年4月までに環境基準の類型当てはめが行われた2,769水域(河川2,166、湖沼88、海域515)について、有機汚濁の代表的指標であるBOD(湖沼及び海域についてはCOD)の環境基準達成状況を見ると、環境基準を達成しているのは1,694水域(河川1,267、湖沼31、海域396)と全体の61.2%であり、達成率は若干上昇しているものの依然として約4割の水域では環境基準が達成されていない。水域分類別に見ると、河川58.5%(51年度57.6%)、湖沼35.2%(同40.7%)、海域76.9%(同76.4%)であり、河川及び海域で改善、湖沼では悪化という結果になっている。しかしながら、都市内中小河川、都市を貫流する大河川等においては、年々改善傾向を示しているものの汚濁の程度が高く(第1-7図)、また、瀬戸内海等広域的な閉鎖性水域についても水質の改善状況ははかばかしくない(第1-8図)。瀬戸内海については改善の方向にあるものの、環境基準達成率は、広域的な閉鎖性水域(瀬戸内海、東京湾、伊勢湾)を除く海域よりも低く、また、東京湾及び伊勢湾についても、環境基準達成率は、東京湾で52年度61%(51年度67%)と前年度に比して低下しており、伊勢湾でも50%に達成していない状況にある。
加えて、湖沼や内海等の閉鎖性水域においては、窒素、リン等の栄養塩類の流入により、いわゆる富栄養化状態が生じている。また、プランクトンや藻類の異常増殖現象がしばしば生起している。
このため、琵琶湖南湖や霞ヶ浦等の湖沼では、水道原水の着臭や、ろ過障害、魚類のへい死等の問題が生じており、また、瀬戸内海等の内海、内湾でも、赤潮により魚介類のへい死等の被害が見られ、特に、瀬戸内海については、赤潮の発生件数は50年300件(うち被害を伴う件数29件)、51年326件(同18件)、52年236件(同27件)、53年176件(同19件)と減少しているものの、赤潮による被害には依然として大きなものがある。
(海洋汚染)
我が国の海洋汚染の発生件数は、53年に1,437件と52年に比べ313件の減少となっているものの依然として多く、特に、油による海洋汚染が全体の約76%を占めている。
海域別に見ると、全体の約57%に当たる816件が、東京湾、伊勢湾、大阪湾及び瀬戸内海において発生している。また、タンカーから投棄されるバラスト水等の油分に起因すると推定される廃油ボールについては、依然として、南西諸島から本州南岸に至る黒潮流域に沿った海域を中心にして我が国沿岸への漂着は後を断たない現状にあり、加えて日本海等今まで汚染の少なかった海域においても量的に多いところがあり、今後の推移を見守る必要がある。