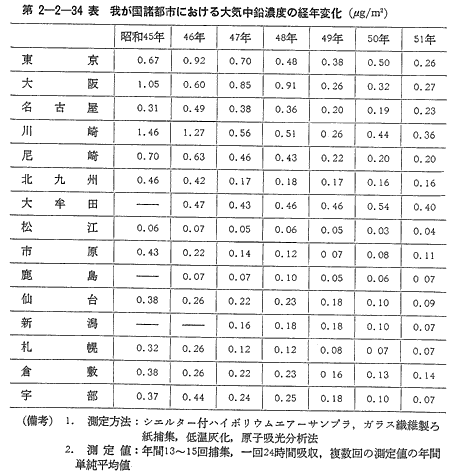
6 その他の大気汚染物質対策
(1) ばいじん、粉じん対策
浮遊粒子状物質による大気汚染は、硫黄酸化物、窒素酸化物によるものと同等に重要であり、かつ、これらが相互に関連して健康影響をもたらすということで、浮遊粒子状物質の原因物質であるばいじんと粉じんについて対策を進めている。
ばいじんの排出規制については、46年に規制が強化され、基準値が定められている(参考資料13)。ばいじんの排出基準は、施設の種類及び規模ごとに定められており、更に施設が密集し、汚染の著しい地域においては、新・増設の施設に対し、より厳しい特別排出基準を定めている。現在、特別排出基準は9地域で定められている(参考資料14)。
また、骨材破砕機や石炭ヤードのように物の破砕等の機械的処理又はたい積に伴い発生、飛散する粉じんについても、46年に、構造、使用及び管理に関する基準が定められている(参考資料15)。
なお、ばいじん及び粉じんの排出基準等は46年以来強化されていないが、浮遊粒子状物質に係る環境基準の達成状況が低いことにかんがみ、その達成に向け、52年度においては、現状の技術開発状況等につき、専門家の意見を聴くとともに、集じん装置開発メーカーからのヒヤリング、並びにばいじん排出調査等を実施し、効果的なばいじん等の対策の検討を行っているところである。
(2) 有害物質に対する対策
ア 有害物質の規制基準
現在、「大気汚染防止法」では、ばい煙発生施設から発生する?カドミウム及びその化合物、?塩素及び塩化水素、?弗化水素及び弗化珪素、?鉛及びその化合物、?窒素酸化物の5種類を有害物質として規制している。このうち、?窒素酸化物については本節3で詳述したので、ここでは、窒素酸化物以外の4種類の有害物質の規制基準を参考資料16に掲げる。
有害物質に係る規制基準は、有害物質の種類ごとに極めて限られたばい煙発生施設に対してしか設定されていないが、これは、有害物質の発生が特定の原料に起因しているためである。このほか、明示的には規制されていない微量の粒子状の物質については、成分の如何によらず「ばいじんん」として規制が行われている。更に、都道府県は、「大気汚染防止法」第4条に基づき、地域の社会的、自然的条件に応じて、ばい煙発生施設から排出される有害物質について国の定める全国一律の排出基準にかえて適用される上乗せ排出基準を定めることができることとなっている。
なお、常時の排出実態がない施設であっても、事故時において特定の有害な物質を大気中に大量に排出する可能性のある施設については、事業者に対し、事故の拡大防止、再発防止策をとるべきことを都道府県知事が命ずることができることとされており、現在、アンモニア、弗化水素等28の物質を発生する全ての施設が特定施設として規制の対象となっている。51年度には、これら施設に関して立入検査が2,909件行われ、事故時の措置の命令が2件行われた。
イ 廃棄物焼却炉の塩化水素排出基準の設定
廃棄物焼却炉から排出される塩化水素については、排出口において高い濃度が測定されたこともあり、排出規制が必要であると考えられていた。
環境庁では、部内に専門家による検討組織を設け、塩化水素の生態影響、測定法、廃棄物焼却炉に関する排出防止技術等について検討を行い、50年3月に報告書をまとめた。さらに処理装置メーカー等の調査を実施することにより処理技術の水準等の確認も行った。これらを踏まえ、また、廃棄物焼却炉は一般的に高煙突を有していることから既に法律により規制されている製造施設とは異なり稀釈効果が見込めるという報告書の考え方を踏まえて、規制基準を排出口濃度で700mg/Nm
3
とし、「大気汚染防止法施行規則」の改正を52年6月16日に行った。
この基準は新設の施設については52年6月18日に施行と同時に適用することなり、また既設の施設(51年度で約7,500施設)については54年12月1日より基準を適用することとした。
ウ 鉛
大気中の鉛の健康影響については、中央公害対策審議会において、46年より大気中鉛の環境基準の設定という観点から、鉛に係る環境基準専門委員会を設け検討を重ねてきたが、51年8月13日に環境庁長官に対する答申が行われた。答申では、大気中鉛濃度が現状程度に維持される限りにおいては人体に対して健康に好ましくない影響を及ぼすとは考えられないこと、また、現在の大気中濃度レベル以上のいかなる濃度において健康影響が生じ得るかについて十分に判明していないことの2点から、現時点において環境基準を設定する必要が認められないとしている。しかしながら、交通頻繁な交叉点付近や鉛を排出する工場周辺等においては、大気中鉛濃度のは握に努め地域住民の健康に留意するとともに、自動車用ガソリンの無鉛化対策及び固定発生源に対する排出規制を継続する必要があるとしており、52年度においても、引き続きこれら規制等が実施された。
なお、我が国における都市の一般環境の大気中の鉛濃度の測定結果は、第2-2-34表のとおりであり、各種の対策の効果により近年鉛濃度の減少傾向が著しい。
(3) 有害物質等に係る規制強化等の検討状況
ア 塩化ビニルモノマー
塩化ビニルモノマーについては、49年度、50年度に大気中への排出濃度に関する測定法の研究を行ったのに続いて、51年度には塩化ビニルモノマー及びポリマー製造工場等の排出口等における実測調査を実施するとともに、専門家からなる研究会を設け、排出防止技術等を中心に検討を行った。
更に、52年度には、排出量の大きい乾燥器からの排出をは握するため、乾燥器に入る前のレジン等に残留する塩化ビニルモノマーを簡便、正確に測定する方法の検討を行った。
環境庁としては、これらの成果を踏まえてできるだけ早く規制等を実施に移すこととしている。
イ その他の物質
大気汚染の原因となる可能性を持つその他の物質に関しては、必要に応じ、順次、文献情報の収集、整理、測定法、排出実態、環境濃度等の調査を行うこととしているが、これらの物質のうち、フタル酸エステル及びアスベストについては52年度及び53年度の予定で排出実態の調査を行っており、調査の結果および有害性等から必要に応じて今後の対策を検討することとしている。