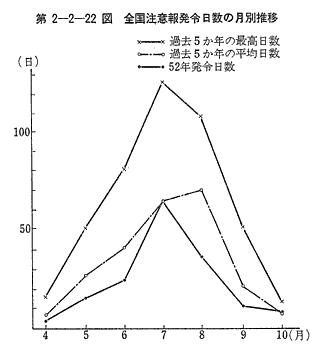
5 光化学大気汚染対策
(1) 光化学大気汚染の発生状況と緊急時対策
45年度夏以来、毎夏光化学大気汚染によると思われる目の刺激、のどの痛み、胸苦しさ等を典型的な症状とする健康被害が発生しているが、地方公共団体では、オキシダント緊急時対策要綱を定めて、オキシダント濃度と気象条件に応じて、予報、注意報、警報等を発令し、発生源対策と住民対策を実施してきた。
52年のオキシダント注意報(オキシダント濃度の1時間値が0.12ppm以上で気象条件から見て汚染の状態が継続すると認められるときに発令される。)は、19都府県で発令され、延べ発令回数は167回であった。この発令回数は過去5年間で51年に次いで2番目に少なく、47年とほぼ同じレベルであった(第2-2-22図)。また、45年以来毎年発令されていたオキシダント警報(オキシダント濃度の1時間値が0.24ppm以上で気象条件から見て汚染の状態が継続すると認められるときに発令される)。は51年に引き続き52年にも、1度も発令されなかった。
52年の光化学大気汚染によると思われる被害者の届出は11都道府県であり、延べ届出人数は、2,669人で45年に初めて被害者の届出があって以来最も少なかった。
光化学オキシダントの発生は各地域の気象条件、煙源状況、移流の状況等の地域条件の差異に大きく影響を受けると考えられることから、
東京湾地域(東京、神奈川、千葉、埼玉)
伊勢湾地域(愛知、三重)
大阪湾地域(大阪、京都、兵庫、奈良)
瀬戸内海地域(岡山、広島、山口、香川、愛媛)
の4ブロックに区分し48年〜52年の注意報等発令日数の整理を行った(第2-2-23図)。
52年の全国の発令日数に対し、この4ブロックの発令日数の合計は約80%を占めている。4ブロックの中では、48年〜52年にかけて東京湾地域における発令日数が常に最も多く、全国の約40%程度であり、大阪湾地域、瀬戸内海地域、伊勢湾地域という順に続いている。
また、東京湾地域では、1都3県全域に注意報の発令された日数は49年に7回、50年に9回、51年に4回、52年に1回と、全域にわたる広域的発令が顕著に減少した。注意報発令日数については、減少傾向が顕著であったが、発令日の最高濃度がどう推移しているかについて、東京湾地域を例にとり整理した結果を第2-2-24図に示す。
まず、各年の注意報等発令日における最高濃度の分布の推移をみると、52年は最低であった。
特に、光化学オキシダントの発生に寄与する気象条件である気温、日射量は、共に48年〜50年とほぼ同レベルであったにもかかわらず、52年の最高濃度が大幅に減少した事は、注目される。
なお、ここ数年の東京、埼玉地区における光化学大気汚染の発生しやすい気象条件に該当する日数に対する実際にオキシダント注意報を発令するに至った日数の割合を見ると、横ばいないし減少の傾向にある(第2-2-25表)。
次に注意報等発令が多かった濃度ランクをみると、おおむね0.14ppm及び0.18ppmを中心とした2山のパターンを示しているが、本年は0.18ppm付近に明確な山がなく、高濃度になるに従いなだらかに発令日数が減少していた。また各濃度ランク毎の発令日数も49年、50年と比べ全体的に大きく減少していた。
(2) 光化学大気汚染調査研究の推進
光化学大気汚染の防止のための調査研究は第2-2-26図に示すような体系の中で光化学大気汚染の発生機構から移流拡散等の気象の影響、要因物質の排出量調査、健康影響調査、植物影響調査に至る広範な分野にわたって行われており、貴重な知見が得られている。
光化学大気汚染は大気中の一次汚染物質である窒素酸化物及び炭化水素が紫外線を受けて反応し、オゾン等のオキシダント、硝酸塩及びアルデヒド類が生成されるものであることは、これまでの調査から明らかにされている。
環境庁では、52年度において、改良を加えた移動用スモッグチャンバー及び国立公害研究所に設けた大型スモッグチャンバーを用いて、光化学反応機構を更に詳細に、また正確には握するための実験研究を継続している。
これらの研究結果では、従来注目されてきた主要生成物であるオゾン以外に、その人体影響が重要視されている、アルデヒド類、パーオキシアセチルナイトレート(PAN)等の生成が、定量的に確認されつつある。アルデヒドの生成量は、初期炭化水素濃度に、また、PANは、初期窒素酸化物濃度に依拠することが明らかになってきているが、初期濃度との詳細な定量的関係については、今後更に研究を進める必要がある。
気象との関連については、地域ごとの気象要素を考慮した光化学大気汚発生の条件を調査している。また夏期に光化学大気汚染発生地域で気象観測を行い、地方公共団体に気象情報の提供を行っているほか、全国8か所の大気汚染気象センター及び11か所の大気汚染気象通報業務担当官署で、光化学大気汚の発生しやすい気象条件の解析と予報を行い、地方公共団体に通報を行っている。更に数値モデルにより、理論的に光化学大気汚の予測が可能になりつつあり、52年度は、伊勢湾地域において、ケーススタディーを行って、モデルの改良を図った。また、50年度より実施している湿性大気汚染調査から、硫酸煙、硝酸の生成が、オキシダントの生成と関連が強いことが明らかにされているが、今後ともより詳細に調査検討を行うこととしている。
健康影響調査においては、光化学オキシダント発生時に報告される、粘膜刺激症状を主とする急性被害をもたらす直接的な原因となる微量物質の究明に重点を置いた研究が進められている。
(3) 光化学大気汚染の原因と防止対策の考え方
既に述べたように、光化学大気汚染の主要な要因物質は窒素酸化物と非メタン炭化水素であることが明らかにされ、また、オゾンが主要生成物であるとされてきた。
アメリカにおける光化学大気汚染対策は、オゾン低減を第一義として実施されており、要因物質の1つである炭化水素の削減対策が従来重点的になされてきた。
一方、我が国においては、窒素酸化物そのものの有害性に着目して窒素酸化物の低減を図るとともに、非メタン炭化水素を低減させ、光化学反応に関係する物質の総量を抑制することによりオキシダントを減少させる対策をとっている。
アメリカの光化学大気汚染対策の根拠は、スモッグチャンバー内における光化学反応実験及び反応の数値シミュレーションから得られた光化学反応における非メタン炭化水素―窒素酸化物―オゾンの三者の定量的関係(オゾン等濃度線)におかれている。その代表的例を第2-2-27図に示した。
この図はロスアンゼルスという都市の気象条件等を想定し、シミュレーションしたものである。これによれば要因物質のうち非メタン炭化水素の削減がオゾンの低減化に最も有効であり、同時に窒素酸化物の削減を行う場合にはオゾンの低減効果が弱められるおそれのある場合もある。一方、国立公害研究所では、スモッグチャンバーを用い、オゾンが最高濃度に達するまで照射を行った結果から、プロピレン(非メタン炭化水素の一種)―窒素酸化物―オゾンの定量的関係(オゾン等濃度線)を求めた(第2-2-28図)。これによれば、窒素酸化物の削減を行ってもオゾン濃度が上昇する事はない事が示されている。
このようにアメリカと国立公害研究所の結果には差異があるが、実際の大気中では一次汚染物質の混入や、生成したオゾンの移流等があり、この結果を実際の大気中の光化学反応と全く同一の反応と見る事はできないという点に留意する必要がある。
近年我が国では郊外におけるオキシダントの発生が問題とされているが、これは都市から郊外へのオキシダントの移流現象が重要な要因の一つと考えられている(第2-2-29図)。また、アメリカでは都市域における炭化水素の重点的低減対策に伴い都心部ではオゾン濃度はある程度低下したが、逆に移流の下流にあたる郊外地域ではオゾン濃度が上昇する現象が観測されている。このように郊外におけるオキシダント問題に対しては都市だけに着目した対策の検討だけでなく広域汚染の観点からの検討が行われなければならない。
また、PAN、アルデヒドのオゾン以外の二次生成物質については、健康影響の点から重要視されており、PANは窒素酸化物、アルデヒドは非メタン炭化水素濃度に依拠することから、オゾンの低減化対策のみでは、複合大気汚染としての性格を有する光化学大気汚染の防止対策としては十分ではない。従って、大気の移流拡散現象をも考慮して、広域にわたる光化学大気汚染の発生を効果的に防止するためには、窒素酸化物及び非メタン炭化水素の双方を低減することが必要である。
我が国では、基本的には、このような考え方に基づいて窒素酸化物と炭化水素の低減化対策を並行して推進している。
第2-2-29図 関東地域の主要流跡線上におけるNO2
(4)炭化水素類排出抑制対策
以上の考え方に基づき、要因物質についてそれぞれ固定発生源対策及び移動発生源対策が進められている(窒素酸化物については前述3「窒素酸化物対策」参照)。
ア 固定発生源からの炭化水素類排出防止対策
51年8月13日に、中央公害対策審議会は光化学オキシダントの濃度が環境基準に適合するためには午前6時から9時までの3時間平均のメタンを除いた炭化水素(非メタン炭化水素)濃度が0.20〜0.31ppmC以下が適当である旨の指針値を示すと共に、光化学オキシダントの原因物質である炭化水素の排出低減が急務であることにかんがみ、炭化水素の排出抑制のための有効な方策を実施する必要がある旨の答申を行った。
光化学オキシダントのもう一つの原因物質である窒素酸化物については、その固有の有害性に着目して既に排出規制が実施されている。一方、炭化水素類については自動車排出ガスについての規制が行われてはいるものの、工場等の固定発生源からの炭化水素類の排出規制については、一部の地方公共団体でタンク類、受け払い施設等に関して部分的に実施されているが、国レベルでは現在行われていない。
このため、環境庁では固定発生源からの炭化水素類の排出を抑制するため、専門家の指導の下に、排出抑制技術の検討を続けて来たが、その結果を52年10月にとりまとめた。この検討結果のうち、炭化水素類排出施設及び施設ごとの排出防止技術について評価したものが第2-2-30表である。
炭化水素類の防止対策としては蒸発防止設備あるいは処理装置の設置のように設備改善を行う方法と低公害塗料あるいは低公害印刷インキの使用により炭化水素類の排出を削減する方法とが考えられる。
タンク等に対する蒸発防止装置及び各種の排出源に対する処理装置は技術的に一応確立されているとみられ、一部適用しがたい施設を除き、適当な装置を選択することにより排出防止を行うことは可能と考えられる。
固定発生源から大気中に炭化水素類を排出する産業施設は多種多様にわたると見られるが、排出量の約50%を占めると考えられる塗料関係の需要についてみると第2-2-31表のようであり、塗料の使用形態、工場の規模等から見て必ずしも処理装置だけでは対応しきれないことが考えられる。このため、これらのものについては、低公害塗料等の使用拡大を図る等により有機溶剤そのものの使用量を低減する対策をとることが有効と考えられる。現在、低公害塗料等については一部に実用化されているものはあるが、技術的に開発されたものについても、設備の変更の必要、消費者の嗜好等に配慮して積極的に採用されない面もある。低公害塗料等の開発及び使用については、省資源の観点からも、今後更にこれを積極的に行う必要があると考えられる。
以上のような技術評価等を踏まえ、検討結果では、次のような炭化水素類排出抑制対策に係る今後の方針が示された。
(1) 石油等炭化水素類のタンクやタンクからこれを移し替える時の炭化水素類排出を防止する。
(2) 塗装工場、印刷工場等炭化水素類を使用する工場、事業場からの炭化水素類の排出を防止する。
(3) 低公害塗料、低公害印刷インキの研究開発を促進し、その使用範囲の拡大を図る。
(4) 塗装業者、印刷業者に低公害性のものの使用促進のためのPRの活発化を図る。また、塗装作業等についても光化学オキシダントの多発する季節をできる限り避けるようPRを図る。
なお、以上の対策のほか、石油化学工業等プラントからの炭化水素類の排出量も地域によっては大きな部分を占めるため、有効な排出防止対策をとる必要がある。
環境庁としては、今後の対策に円滑に対処できるよう、これらの技術評価結果及び今後の対策の動向等について都道府県等に対して周知・要請を図った。今後は、非メタン炭化水素の環境濃度の測定体制の充実に努めるとともに、規制手法、発生源における測定法等について、2年間を目途に検討を進めることとしている。
イ 移動発生源における炭化水素類排出防止対策
乗用車、トラック、バス等から排出される炭化水素類に対しては、45年に、ガソリン車、LPG車に関しブローバイガスについて規制が行われ、47年にはガソリン車、LPG車の燃料蒸発ガスが、48年に、50年には排気管から排出される炭化水素がそれぞれ規制された。また、軽油を燃料とするディーゼルエンジン車に関しても、49年以来排気管から排出される炭化水素が規制されている(前述4「自動車排出ガス対策」参照)。
これら規制の効果を乗用車一台当たりで見ると第2-2-32図のとおりであり、排気管から排出される炭化水素は未規制時に対して93%の削減となっている。
(5) 湿性大気汚染対策
49年7月初旬と、50年6月下旬から7月上旬にかけて、北関東を中心にいわゆる酸性雨による目の刺激を訴える事例が発生した。
この現象は、当時の状況から特殊な気象条件により、高温度大気中において、複雑な過程を経て生成された汚染物質に原因するものと考えられ、「湿性大気汚染」と称することとした。
湿性大気汚染は、その発生メカニズム、眼等に対する刺激原因物質等が十分解明されていないので、対策のためにはこれらの究明が必要である。このため、50、51年度の調査結果を踏まえ、52年6月から関東一円において、
ア ヘリコプターを用いた上空のガス状物質の測定並びに雨水及び雲水中の成分分析
イ 地上における大気汚染物質及び雨水の調査分析
ウ 気象条件調査
等の実地調査を行なうとともに、チャンバーを用いた酸性エーロゾルの形成過程の実験も行った。
なお、52年度には湿性大気汚染による被害の届出はなかった。
湿性大気汚染の機構に関与するものとして、今まで硫酸ミストが考えられてきたが、3年間の調査結果では硝酸の影響も考えられるようになってきた。また、第2-2-33図に示すとおり、硫酸塩、硝酸の生成割合(RS、RHNO3)は、オキシダント濃度と似た動きをすることが明らかになり、湿性大気汚染と光化学大気汚染との関連が重要視されてきている。この調査結果から、光化学大気汚染の原因物質の1つである窒素酸化物が、湿性大気汚染においても重要な役割を果たしていることも考えられ、この点を今後の研究で明らかにしてゆく必要があろう。