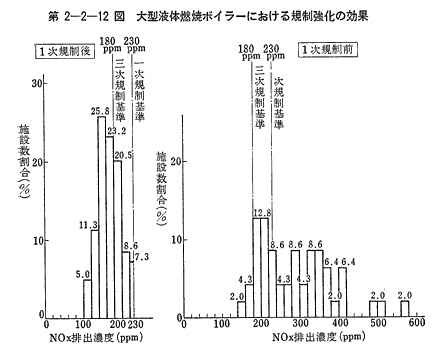
3 窒素酸化物対策
(1) 窒素酸化物対策をめぐる動き
窒素酸化物対策についての過去1年間の動きを簡単にまとめてみる。
まず、固定発生源及び移動発生源について技術的に可能な限りの厳しい規制の強化が行われたことである。すなわち、固定発生源については、52年6月に第3次の規制が決定され、移動発生源については、52年12月の中央公害対策審議会の答申を踏まえ、トラック、バス等に係る54年規制が53年1月に告示された。
次に、中央公害対策審議会は、52年12月、自動車排出ガスの許容限度について、ジーゼル車やガソリントラック等に係る長期目標をとりまとめて環境庁長官に答申した。
また、53年3月、NO2に係る環境基準の基礎となる判定条件について、近年得られてきたNO2の健康影響に係る新たな知見をもとに検討を加え、その結果をとりまとめて環境庁長官に答申した。
一方、52年12月には通商産業大臣の諮問機関である産業構造審議会は、今後の窒素酸化物汚染防止対策に関する諸問題につき検討した結果をとりまとめ、通商産業大臣に答申した。
(2) 環境基準の達成状況と判定条件等に関する中央公害対策審議会の答申
二酸化窒素の環境基準は、47年6月にとりまとめられた中央公害対策審議会の専門委員会報告を基礎に、48年5月に決定され5年以内に、一般地域においては、環境基準を達成し、大都市地域などにあっては、中間目標を達成することとされた。そして、環境基準の設定以来その達成を目標に移動発生源、固定発生源に対し、その時点で実行可能な最大限の対策を段階的に実施した。しかし我が国に多くの地域において、環境基準及び中間目標を当初の予定である53年5月までに達成することは不可能であると判断されるに至っている。
現在の環境基準の基礎となっている専門委員会報告がとりまとめられた47年当時は、その時点で利用可能な知見が乏しく、そのため環境基準の設定には大きな安全性を見込んで判断せざるを得ない状態であった。その後、我が国においては45年以来全国の6都市で継続されていた疫学調査である「複合大気汚染健康影響調査」や「自動車道沿道住民健康影響調査」の結果がとりまとめられ、また国際的には、51年8月東京でWHO(世界保健機関)の窒素酸化物の環境保健クライテリア専門家会議が開催されるなど、内外で知見の集積と評価が進んだ。一方、公害対策基本法第9条第3項には、環境基準については「常に適切な科学的判断が加えられ、必要な改定がなされなければならない」とされている。このため、環境庁では中央公害対策審議会に対し、52年3月28日、環境基準の基礎となる人の健康影響に関する判定条件等についての諮問を行った。諮問を受けた中央公害対策審議会は、大気部会に医学、公衆衛生及び測定に関する専門家20名よりなる「二酸化窒素に係る判定条件等専門委員会」を設置し、52年5月以来検討を開始し、53年3月20日に専門委員会報告をとりまとめた。この報告を受けた中央公害対策審議会は3月22日にこれを了承し、政府においては、この報告を参考とし、現在の二酸化窒素に係る環境基準について、公害対策基本法第9条第3項の規定の趣旨にのっとり、適切な検討を加えるべき旨答申した。
答申の内容となった専門委員会報告の概要は次の通りである。
? 専門委員会は、二酸化窒素の人の健康に係る判定条件とそれに関連する分野として、(?)我が国の窒素酸化物による大気汚染状況の解析(?)二酸化窒素の測定法の技術的評価(?)二酸化窒素の生体影響(?)検討結果の総合評価と人の健康保護のための指針などについて検討を行った。
? 環境大気中の二酸化窒素の濃度レベルと濃度変化の特徴について述べるとともに、日平均値、年平均値等の相互関連性について解析し、暴露レベルの考察の資料とした。
? 二酸化窒素の測定法については主に自動測定器として実用化されているザルツマン法、化学発光法について技術的評価を行った。
ザルツマン法については現行の校正法である静的校正を施して使用する場合においても、現時点で最も実用性の高い測定法と評価されその際、ザルツマン係数は現状の0.72よりも2割程度高く、変更する必要がある。
一方化学発光法は、研究目的で使用するなど使用条件が整っている場合には、現時点でも化学発光法の測定性能はザルツマン法と同等とみなされる。
また、この二つの測定法を通じて今後、動的校正法採用のための標準ガス供給における信頼性向上と実用化のための努力を継続する必要があるとしている。
? 二酸化窒素の生体影響に関する知見には、動物に対する実験室的研究、人の志願者における研究、疫学的研究があるが、専門委員会は、これらに関する内外の最新の知見を評価した。
? 専門委員会は、二酸化窒素の判定条件等に関するこれらの成果を総合的に判断し、地域の人口集団の健康を適切に保護することを考慮し、環境大気中の二酸化窒素濃度の指針として、次の値を参考とし得ると提案した。
短期暴露については1時間暴露として0.1〜0.2ppm。
長期暴露については、種々の汚染物質を含む大気汚染の条件下において、二酸化窒素を大気汚染の指標として着目した場合、年平均値として0.02〜0.03ppm。
ここで、提案された指針の性格は、その濃度レベル以下では、高い確率で人の健康への好ましくない影響を避けることができると判断されるものである。更に、この指針が目標とした健康影響のレベルについては、疾病やその前兆とみなされる影響を判断基準としては採用せず、健康が維持され、人の機能の恒常性の維持機構が負担なく機能をしている状態で判断している。
以上が今回の報告の概要であるが、47年の環境基準専門委員会報告当時と比較した場合窒素酸化物にうち、一酸化窒素の影響については、試験管実験により、ヘモグロビンとの親和性の高いことが指摘され、一酸化窒素の影響に注目しなければならないことが強く示唆されていたが、その後動物実験によって、当時考えられた程の多量の一酸化窒素へモグロビンは生体内では生成しないことが証明された。
また、二酸化窒素の低濃度長期暴露後にインフルエンザに感染させたマウスは、非暴露群より末梢気道に腺腫様増殖が多く見られ、その所見が注目された。しかし、その後の研究では、発がんを見たと考えられる結果は報告されていない。
今回の答申は環境基準についてではなく、現時点で利用可能な知見から判定条件を示し指針を提案したものであり、政府としては以上のような状況をふまえ、今後の窒素酸化物対策の長期的総合的対策について、改めて方針を樹立し、国民の健康を確保するため、窒素酸化物対策を着実に軌道に乗せてゆくこととしている。
(3) 固定発生源対策
ア 規制の現況等
窒素酸化物の排出基準は48年8月に設定され(第1次規制)、その後、50年12月に対象施設の拡大等が行われ(第2次規制)、更に52年6月に基準値の強化、対象施設の拡大が行われた(第3次規制)。
第1次規制では、大型のボイラー及び加熱炉並びに硝酸製造施設を対象に排出基準値を設定した(第2-2-12図参照)。第2次規制においては、基準値を強化し、対象施設を中型施設にまで拡大するとともに、セメント焼成炉及びコークス炉(いずれも新設のみ)を新たに規制対象に加えた。
また、53年6月の第3次規制では、52年2月に発表した技術評価に基づき全国一律の排出基準として可能な限りの規制強化を実施した。今回の規制強化は、大気汚染防止法第3条に基づく地域格差のない全国一律の排出基準であるため、排煙脱硝技術によらなければ達成できない基準値とすることなく、原則的には低NOx燃焼技術によって達成可能な値とした。
今回の規制強化の主な内容は次のとおりである。
? 第1次規制で排出基準を設定した既設大型施設(排ガス量10万Nm
3
/h以上のボイラー、4万Nm
3
/h以上の金属加熱炉及び石油加熱炉)について基準を強化した(第2-2-12図参照)。
? 既設のボイラー、金属加熱炉、石油加熱炉について新たに排ガス量5千Nm
3
/h以上のものまで規制対象を拡大した。
? 新設の焼結炉、アルミナ焼炉、廃棄物焼却炉、既設の焼結炉、コークス炉、セメント焼成炉を規制対象に加えた。
? 新設施設の基準は、低NOx燃焼技術の最先端を適用することを前提にして設定、強化した。
以上のような今回の規制強化(基準値については参考資料11参照)により、規制対象施設数は従来の約3,400施設から約13,000施設に増加し、全ばい煙発生施設からの窒素酸化物排出量の約73%が規制対象となり、既設については50年時点の窒素酸化物排出量と比べ約10%削減されると考えられる(第2-2-13図参照)。この削減率は現在の二酸化窒素汚染状況からみて決して十分なものではないが、低煙突の小規模施設に対しても規制強化したことにより、自動車排出ガス規制の効果と相まって環境濃度の着実な低減が期待される。
今回規制の対象としなかった金属溶解炉、ガラス溶融炉等の未規制施設及び第3次規制施行時点で第2次規制の既設基準の適用猶予期間中にあった施設に係る今後の対策については、窒素酸化物対策の今後の進め方に関する検討結果に従い、また、これらの施設に係る技術評価の結果を踏まえて、検討を行うこととしている。
このため52年度においては、前年度に引き続き専門家の意見を聞き、固定発生源から排出される窒素酸化物の排出低減技術について検討を行った。環境庁大気保全局は53年1月から2月にかけて窒素酸化物防除装置の開発メーカーからヒヤリングを行い、別途、実稼働施設に対する実態調査を実施した。現在、これらの結果を踏まえ、固定発生源対策の今後の長期的なスケジュールの検討を行っているところである。
イ 窒素酸化物排出低減技術の開発状況
固定発生源から排出される窒素酸化物の低減技術としては、排煙脱硝、低NOx燃焼技術等がある。
排煙脱硝技術については、LNG等の燃焼排ガスのように硫黄酸化物やばいじんをわずかしか含まない、いわゆるクリーン排ガスについては、50年時点で既に実用化されている。51年時点では重油燃焼排ガス程度の硫黄酸化物やばいじんを含むダーティ排ガスについても、実用規模装置による運転実績からみて、実用化の域に達しつつあるとされ、また、焼結炉排ガス等のよりダーティ排ガスについてはパイロットプラント等による試験段階にあった。
更に52年度内では、重油燃焼排ガス程度のダーティな排ガスについて触媒層の方式等が改善されるとともに、空気予熱器に対する酸性硫安等の問題についてもアンモニア注入量の適切な制御、空気予熱器のエナメルコーティング等によって対処されている等技術の信頼性は向上している。昇温、熱回収を伴う脱硝装置については、その設置に必要な用地や稼動に必要なエネルギーが大きいことが指摘されており、特に既設施設に脱硝装置を設置する場合にはこれらの制約が大きい。しかしながら、前述の技術開発状況を踏まえれば、施設の構造からみて脱硝に必要な温度領域の排ガスを取り出すことが可能な施設においては、大きな用地、エネルギーが必要な昇温、熱交換なしに脱硝が可能となっている。
更に、ダーティな焼結炉排ガスについても、触媒方式によるパイロットプラント等の試験研究の成果が蓄積され、技術的な信頼性は向上した。このほか、石炭燃焼排ガス、セメントキルン排ガス等についてもメーカー、ユーザーの脱硝技術開発の努力が見られた。
一方、低NOx燃焼技術は、脱硝に比べ簡便に適用できる技術であり、ばい煙発生施設本体の変更による二段燃焼、排ガス再循環、各種低NOxバーナーの使用等数多く開発され、適用例も多い。これらの技術は、再循環された排ガスの吹き込み位置の最適化が図られるなど技術の細部にわたって改良されてきており、ほぼ熟成の域に達している。また、各種対策の組合せ技術の進歩により、対策の効果、信頼性も増大している。このほか、乳化燃料についても、添加剤を用いない方式が適用された例がみられるなど進歩があった。
燃料から窒素分を除去することは技術的経済的に難しい点もあり、これを主目的とした装置はない。重油脱硫装置で硫黄分を除去する際に、少量ではあるが窒素分も除去され、脱硫後の低硫黄燃料を使用することはNOx対策上も望ましい。このほか、液体燃料ではないが焼結原料の脱室技術の研究も進められている。
ウ 今後の固定発生源対策の検討状況等
今日までの固定発生源対策は、施設の種類ごとの排出濃度に関する全国一律の規制として行われており、その基準値は、技術的には最善のNOx燃焼技術を前提にしたものとなっている。しかしながら、既に述べたとおり、この排出規制によっても、大都市等の高濃度地域においては移動発生源、ビルなどの中小煙源の寄与が大きい箇所が多く、大幅な汚染の改善を今後に期待することは困難である。
固定発生源対策、移動発生源対策の全般にわたる窒素酸化物対策の今後の進め方については、中央公害対策審議会の答申等を踏まえ、国民の健康保護を大前提として、また、今日までの窒素酸化物対策の実施状況、汚染の状況、排出抑制技術の現状、エネルギーの需給等を勘案しつつ、現在、政府において慎重に検討がなされているところである。今後の固定発生源対策は、この検討結果に沿うこととなるが、現在の全国の二酸化窒素による汚染状況からみれば、地域によって相当な汚染程度の差があり、また、汚染の構造にも違いがあるため、地域差を考慮した対策が検討されることとなろう。更に、超長期的には、排出規制による対策にも限界が生ずるので、公害対策基本法第9条第4項にあるとおり、土地利用状況の改善、工場、事業所等の熱源の共同化等の各種の施策を採用し、総合的に対策を進めなければならない。
今後、固定発生源対策を計画的、合理的に進めていくために、52年度内においては、次のような検討が行われた。
(ア) 窒素酸化物汚染予測手法の確立等
窒素酸化物対策を効果的に実施していくためには、環境濃度に対する各種汚染源の寄与を明らかにする等汚染の構造をは握する必要があり、このため、窒素酸化物汚染予測手法の開発が進められている。
窒素酸化物拡散シミュレーションについては、硫黄酸化物拡散シミュレーションの場合とは異なった問題点が存在している。その第一は、自動車、ビル等の低煙源も環境濃度の寄与として大きな位置を占めることから、測定データの的確な評価、発生源データの一層の精密化を図る必要があるとともに、低層局地的な場における窒素酸化物の挙動を説明できる拡散モデルを開発する必要があることであり、その第二は、窒素酸化物は大気中で炭化水素類とともに複雑な光化学反応系を形成しており、このため、発生源から排出された一酸化窒素(NO)の二酸化窒素(NO
2
)への変化を、目標値の設定の仕方を含めたシミュレーションモデルの中で何らかの形で取り扱わねばならないことである。
これらの点について、各方面で窒素酸化物シミュレーションモデルの確立のための研究が進められている。52年度までの研究結果の概要は第2-2-14表のとおりである。なお、ここに掲げた以外にも多くの考え方があり、それぞれ研究が進められている。
第2-2-14表にみるとおり、窒素酸化物の汚染予測手法は、NOx(NO+NO2)としての予測を行うNOxシミュレーションとNO2としての予測を行うNO2シミュレーションとに大別される。対策の目標となる環境濃度と計算濃度とはこのシミュレーションの種別に応じて、NOxまたはNO2として照合されなければならないが、環境基準がNO2設定されていることから、NOxシミュレーションでは、NOからNO2への反応の問題を目標値の設定の仕方において解決する必要がある。これに対してNO2シミュレーションでは、拡散モデルの中にこの反応をどういう形で組み込むかが問題となる。以下では、NOxシミュレーションモデルとNO2シミュレーションモデルとに分けて、開発状況を見ることとする。
(?) NOxシミュレーション
NOxシミュレーション(第2-2-14表中D)については、窒素酸化物を全体としてみれば硫黄酸化物の挙動と同様と考えられるので、硫黄酸化物総量規制に用いられた正規型プリューム拡散式による長期平均値シミュレーション手法を利用することが可能である。
正規型プリュームモデル拡散式を用いたシミュレーションは、工場煙突等の高煙源には適合性が良いが、自動車等の低減煙には必ずしも適合性が良いとはいえず、このような拡散については、鉛直方向の拡散幅を修正する等の改良を試みているほか、拡散を記述する微分方程式の数値解による方法、非正規型プリューム拡散式を用いる方法、風洞実験等の検討を行っているところである。しかしながら、NOxシミュレーションにおける対策上の環境目標値の設定に当たっては、NO2とNOxというように異なる汚染質問の変換を取り扱うための確立された手法がなく、統計的にその関係を見い出す以外に現状では適切な方法が考えられないので、なお、検討課題が残されている。
(?) NO2シミュレーション
NO2シミュレーションについては、一つの方法として減衰モデルを応用することが考えられる。まず、NOの減衰をこのモデルで表わし、NO2はNOx-NOとして計算されることとなる。(表中B)。また、減衰割合を指数関係ではなく、NOからNO2への転換率として統計的に求める手法も提案されている(表中C)が、これらの減衰モデルにせよ、転換率を与えるモデルにせよ、NOxとNO2との関係がどのような気象条件、どのような平均化時間で安定的であるかが重要となる。この点については、最近かなりの知見が得られつつあるが、今後とも一層の知見を得る必要がある。
このほか、NOからNO2への変化を光化学反応系の中の一つの反応として捉え、オゾン、炭化水素類、窒素酸化物、紫外線量等との相互の反応の反応速度論的な考察から、NO2の濃度を直接に求める方法(表中A)も、光化学オキシダントの予測手法の開発とあいまって検討されている。しかしながら、この方法についても、オゾン、炭化水素類、紫外線量等に関する長期連続的なデータが得られにくいことから、規制のための汚染予測手法としての実用化の見通しは、現段階では明るいものとはいえない。なお、対策上の環境目標値を設定する場合、同じ汚染質の濃度を、異なった平均化時間の濃度間で変換することについては、硫黄酸化物総量規制で用いた手法や、ラーセンモデル等の手法もあり、NO2シミュレーションにおける環境目標値の設定はそれ程困難ではない。
以上述べたように、各種の窒素酸化物汚染予測手法にはそれぞれ一長一短がある。そのどれを選択すべきかは今後の検討に委ねられるべきものであるが、その判断に当たっては、実際に対策を行うまでに許容される期間の長さや、対策の過不足を許容し得る程度をどのように見積もるかが最も重要な判断要件となろう。
このほか、シミュレーションや施策の立案の前提として測定値を的確に評価することも重要である。微量の大気汚染物質の測定は誤差を伴いやすいので、測定器の性能を向上させるとともに、保守管理を徹底する必要があり、今後とも測定法の検討、保守管理の指導等に一層努めていくこととしている。また、測定局の設置場所によっては、特定の煙源の影響を強く受ける等地域の対策の目安となる汚染程度を必ずしも的確に測定していない場合もあり、地域の対策の立案の観点からは、今まで以上に測定値を注意深く取り扱うことが必要である。
(イ) 固定発生源に対する規制手法
窒素酸化物による汚染は大都市において際立っており、このような地域では一般に移動発生源、ビル等の中小煙源の寄与が大きい場所が多く、窒素酸化物対策を困難にしている。したがって、このような地区では固定発生源対策の効果は限られたものとなるが、一般に、汚染程度の地域差、対策強度の地域差を反映し得る規制手法として「大気汚染防止法」上採用が可能なものには、同法第4条に基づく都道府県条例で定める上乗せ排出基準と同法第5条の2に基づく総量規制とを適用することが考えられる。
上乗せ排出基準は、総量規制が適用される地域ほど汚染の程度は著しくないが、全国一律の排出基準によっては、目標とする環境濃度が達成できないと予想される地域に適用されるものであり、その規制基準値は、全国一律の排出基準より厳しいものが設定されることとなる。
他方、総量規制は、「大気汚染防止法」第5条の2に定められているように、工場又は事業所が集合している地域で排出基準、上乗せ排出基準によっては、大気環境基準を確保することが困難であると認められる地域について、個別施設に対する排出基準に加えて付加的に適用される基準である。これは、工場ごとの排出総量を規制するものである。
環境庁においては、52年度にはこれらの規制手法について基準式等の検討を行った。