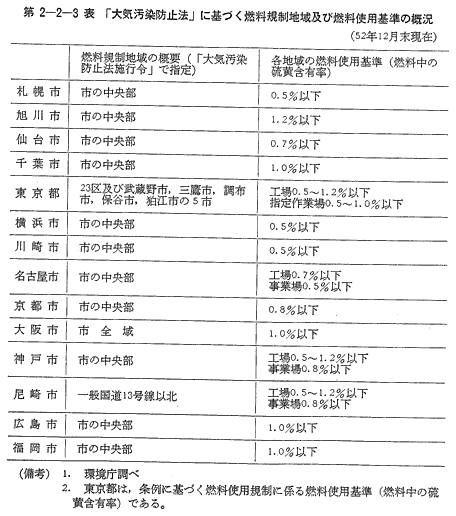
2 硫黄酸化物対策
(1) 規制の方法
硫黄酸化物の排出規制は、施設単位に排出基準を定める方法を中心として、高汚染地域に対してはさらに工場単位に総量規制基準を定める方法が併用されている。排出基準及び総量規制基準については、新増設施設に対してそれぞれ特別排出基準、特別総量規制基準を定めることができ、新増設に対するチェックの役割を果たしている。
この他、ビル暖房地域等では暖房等の中小煙源のために季節的に局地的に高濃度汚染を生ずるが、このような地域に対しては、石油系燃料に関し季節的な燃料使用基準を定めることができ、また、総量規制地域にあっては、総量規制基準の適用の対象とならない小規模工場、事業所に対しても石油系燃料に関し工場等単位の燃料使用基準を定めることができる等、硫黄酸化物対策に万全を期している(第2-2-3表)。
(2) 排出基準
施設単位の排出基準は、排出口の高さに応じて排出量の許容量を定めるK値規制といわれる次の式で与えられている。
Q=K×10
-3
×He
2
Q:硫黄酸化物の許容排出量
K:地域毎に定める定数
He:有効煙突高(煙突実高+煙上昇高)
K値規制は、Kの値が小さい程厳しい基準となる。二酸化硫黄の環境基準の段階的達成を目標として、Kの値は第2-2-4表のように8回の改訂が行われており、現行排出基準では51年9月に定められた第2-2-5表に掲げる値が用いられている。
また、施設集合地域において法で定める限度を超える汚染が生じるおそれのある場合は、新増設施設に対し特別排出基準を定めることができる。特別排出基準を設定している地域は第2-2-6表のとおりである。
(3) 総量規制基準及び総量規制指定地域における燃料使用基準
工場又は事業場が集合している地域で、排出基準のみによっては大気環境基準を確保することが困難である地域については、国が総量規制指定地域として指定を行い、都道府県知事が総量削減計画を作成し一定規模以上の特定工場等に対しては総量規制基準を、また、特定工場等未満の規模の工場等に対しては燃料使用基準を定めることとしている。
総量規制方式は、49年6月の大気汚染防止法改正の際に導入されたもので、電子計算機等を利用して拡散式に基づく理論計算を行う方法、又は風洞実験による方法等、気象、発生源の状況、地域特性等を考慮した科学的な汚染予測手法を用いて排出量と環境濃度とを対照させ、大気環境基準を確保するよう地域全体の排出総量を削減するための総量削減計画を作成し、その計画の中に燃総量規制基準、燃料規制基準を位置づけようとするものである。総量規制指定地域は、現在までに24地域(人口及び燃料使用量で全国のそれぞれ約33%、約56%を占めている。)が指定されており(第2-2-7表)、全地域で52年中に総量削減計画が作成され、燃総量規制基準及び燃料使用基準が定められている(参考資料9及び10参照)。
53年3月末にはこれらの大部分の地域で総量規制基準及び燃料使用基準が適用されることとなり、高汚染地域においても二酸化硫黄の大気環境基準が確保されるものと期待されている。
なお、総量規制基準は次の2種類の式を基本として定めることとされている。
? Q=a・W
b
Q:硫黄酸化物の許容排出量
W:工場等における燃料使用量の合計(重油換算量)
a、b:知事の定める定数
これは、工場等でのエネルギー使用量に応じて許容排出量を定めるもので、bの値を0.8以上〜1.0未満の間で定めることによって大規模工場に相対的に厳しくなる方法である。
? Q=Cm/Cm0・Q0
Cm0:現状の最大重合着地濃度 Q0:現状の硫黄酸化物排出量
Cm:知事の定める定数
これは、各工場に等しい最大重合着地濃度を許容しようとするもので、工場単位のK値規制とも考えられる方式である。
また、新増設工場に対する特別総量規制基準は、総量規制基準の方式に応じて、それぞれ、基本とするべき算式が定められているが、その大体の考え方は、既設工場等に許容される排出量に対して、新増設工場等にはその0.3〜0.7倍を許容排出量として割り当てようというものである。
(4) 季節による燃料使用基準
大都市のビル暖房地域等では、暖房期に局地的な汚染を生ずる場合があるが、このような地域に対しては、暖房期に限って、石油系燃料の硫黄含有率を規制する季節による燃料使用基準を定めて対処している(前掲第2-2-3表参照)。
(5) 硫黄酸化物の排出規制に対応する発生源対策として、?輸入燃料の低硫黄化 ?重油の脱硫 ?排煙脱硫等の対策が講じられてきている。
?については、LNG、LPG等の硫黄をほとんど含有しない燃料の輸入拡大を含め、我が国の一次エネルギー供給源の約7割を占める石油系燃料の低硫黄化が進んでおり、例えば、輸入原油の平均硫黄含有率は第2-2-8表のように着実に低下してきている。?の重油脱硫については、42年以来、直接脱硫、間接脱硫装置が建設され、51年度末の重油処理能力は、それぞれ10基6.3万kl/日、31基15.2万kl/日に達している(第2-2-9図)。このような原重油等の低硫黄化、重油脱硫等により、内需要重油の平均硫黄含有率は、42年度2.5%から51年度1.41%に低下、硫黄含有率1%以下の重油が占める割合は、42年度8.6%から51年度45.5%に上がってきている(第2-2-10図参照)。
?の排煙脱硫装置については、41年から通商産業省による大型工業技術研究開発として研究開発が進められ、45年から実用装置が稼動を始めている。排煙脱硫黄装置は、第2-2-11図のとおり42年度90基、処理ガス量約500万Nm3/hであったものが、51年度には、それぞれ1,143基、約1億Nm3/hと急速に増加してきている。
これらの対策により、我が国は二酸化硫黄に係る大気環境基準を確保するために必要な程度までに燃料の低硫黄化を図ること等にほぼ成功を収めたといえよう。53年度以降は、二酸化硫黄の環境基準を維持していくため、エネルギー源の多様化に伴い石炭燃焼施設における排煙脱硫装置が、また、輸入原油の重質化に対して軽質化装置がそれぞれ必要となろう。なお、これらの脱硫装置の稼働により副生する石膏等についての処理、再利用対策の推進を図ることも重要である。