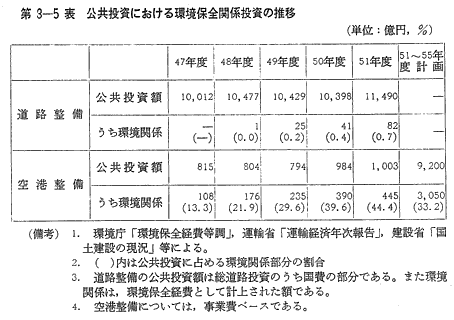
3 交通公害と国土利用
いわゆる産業公害については、世界でも最高水準ともいえるような技術と資金の投入を行ってきたことにより、一部には顕著な改善を見るようになっている。一方、空港、新幹線鉄道、道路等の交通施設に関する公害にも強い関心が払われるようになってきており、自動車交通公害や航空機騒音に関して訴訟が提起されるなど各地で問題化している。また、公通施設のと国土利用に占める位置は、量的にも質的にも大きくなっているものと考えられる。例えば、国土庁の調査によれば、50年現在の道路面積は、97万haであり全国土の2.6%を占めている。交通に起因して生じる騒音、振動及び排出ガスによる大気汚染などの交通公害に対しては、従来から各方面において努力がなされてきた。まず、これまで講じられてきた交通公害対策を概観してみよう。
第1に、自動車交通による公害に対しては、発生源対策として自動車単体から発生する一酸化炭素・炭化水素・窒素酸化物等の排出ガス及び騒音について、それぞれの許容限度を定めて規制が実施されている。特に乗用車については、世界で最も厳しい窒素酸化物の排出ガス規制が実施されている。また、トラック、バス等の排出ガスの許容限度の強化については、52年12月の中央公害対策審議会の答申(「自動車排出ガス許容限度長期設定方策について」)に基づき、53年1月、騒音の規制強化と併せ54年規制として告示が行われたが、更に排出ガス・騒音とも今後長期的な許容限度目標値達成に向けての技術開発の促進が図られている。更に、交通管制システムの確立強化、幹線道路における最高速度の制限、信号機の系統化、大型車の通行区分の設定、住居地域内の道路における通過交通の排除や歩行者用道路の設定等の交通規制、高速道路等自動車交通量の多い幹線道路と住居が近接している地域でのしゃ音壁、環境施設等の設置、高速自動車国道等の周辺の住宅のうち騒音による影響の特に著しいものに対して緊急的措置として防音工事の助成、更に緩衝建物の建築資金の一部交付等の周辺対策等が実施されている。
第2に、航空機による公害に対しては、48年に航空機騒音に係る環境基準が設定され、これを達成維持するための発生源対策、空港周辺対策等が実施されている。発生源対策としては、機材の改良、便数の調整、深夜便離着陸の規制、騒音軽減運行方式の採用等が実施されている。周辺対策としては、航空機騒音による障害が著しいと認められる飛行場を特定飛行場に指定し、また自衛隊等の防衛施設周辺については「防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律」に基づき、学校、病院など公共施設の防音工事に対する助成等の対策が実施されている。更に、特定飛行場のうち空港周辺が市街化していたり今後市街化が予想されるため計画的な整備をする必要があると認められる空港を周辺整備空港に指定し、都道府県知事が策定した空港周辺整備計画に基づき、空港周辺の再開発、代替地造成等の事業が実施されている。なお、航空機騒音対策における大きな問題は、空港の周辺に新しい住宅ができることによって問題が拡大することであったが、53年4月、「特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法」が制定され、空港周辺における建築制限、防音工事の義務付け等の土地利用にの規制によりこの問題についての予防的措置がとられることとなった。
第3に、新幹線鉄道による公害に対しては、50年7月に新幹線鉄道騒音に係る環境基準が設定され、この環境基準の円滑な達成に資するため、51年3月に音源対策及び障害防止対策、土地利用対策等の基本方針に関して「新幹線鉄道騒音対策要網」が閣議了解され、国鉄は、これを受けて新幹線鉄道の騒音・振動対策について「新幹線鉄道騒音・振動障害防止対策処理要網」を策定し、住宅及び学校等の防音工事等に要する費用の全部又は一部を助成するとともに、沿線の関係地方公共団体の強力をも得て、これらの障害防止対策を実施している。
道路、空港、新幹線鉄道等の整備事業における防音工事、住宅移転対策などの環境保全関係投資は、ここ数年急速な伸びを示している。また、51年度を初年度とする空港整備5箇年計画でも、環境保全関係経費が全体の投資額の33.2%計上されるなど、各方面でその対策の充実が図られてきている(第3-5表)。しかしながら今後、交通公害をより根本的に解決するためには、これらの諸対策を長期的スケジュールのもとに一層充実強化するとともに、交通公害の未然防止の観点から将来のあるべき交通体系を展望し、適切な土地利用計画、都市計画の積極的活用等総合的な対策の推進が必要であろう。
具体的には、第1に、将来のあるべき交通体系を地域開発計画の中に適切に位置付けるとともに、飛行場、新幹線鉄道、道路等の交通施設の建設に当たっては、良好な環境を維持するために、事前に環境影響評価を実施し、これらの交通施設が地域環境との調和を保ちつつ適切に設置されるよう十分配慮することが必要である。その際、交通施設の周辺の土地利用規制の可能性についても検討することが必要であろう。我が国では、これまでこのような土地利用規制はほとんどなされていないが、我が国のように平地面積が少なく、交通施設の立地できる範囲が限られている場合には法的な規制が必要な場合もでてこよう。ただし、この場合であっても、公共の利益のために制約される地域住民の私権に対する十分な配慮が必要であることはいうまでもない。
第2に、都市における交通公害は、窮極的には都市政策の問題であり、都市の機能についての現状と将来を見きわめた長期的対策が必要なことである。この観点から、都市における物流機構の円滑化、合理化を図るなど都市機能の再編、再配置等を一層促進することが必要であろう。