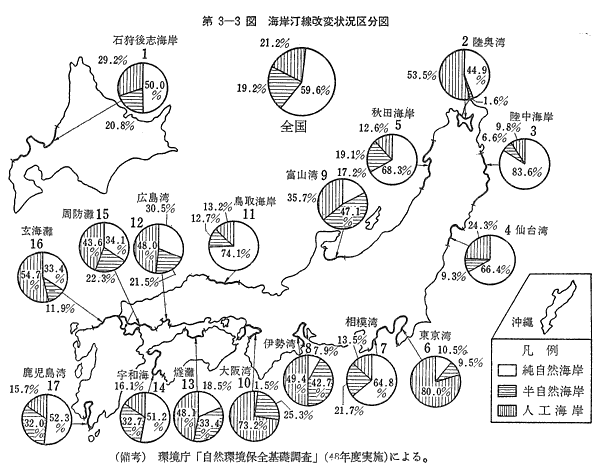
2 自然環境保全のいくつかの課題
我が国では、戦後の高度成長の過程において、欧米諸国の先進技術の導入を図りつつ重化学工業化が積極的に推進され、規模の利益を求めて巨大な重化学コンビナート群が臨海部に集中して建設された。これらの工場用地は主として海岸の埋立等によって確保された。40年から50年にかけて埋立てや干拓により造成された土地は、約4万haとなっており、これは琵琶湖の面積の約6割に相当する。埋立や干拓による環境への影響としては、自然の景観の喪失や水生生物、鳥類の生息地の喪失、水質浄化機能が変化する場合があることなど、埋立や干拓そのものによる直接的影響のみならず、埋立地に立地する工場の影響の他、背後の都市活動による大気汚染、水質汚濁の進行が大きな問題となった。
第3-3図は、我が国における海岸汀線の改変状況を見たものであるが、東京湾、大阪湾、伊勢湾、瀬戸内海など工業開発や都市化が進んだ地域を中心に、海岸の改変が進み、そこに残された自然は今日貴重なものとなっている。海岸の改変には地域防災の観点から要請されるものがあり、また、下水道処理場、廃棄物処理施設など生活関連施設用の埋立の需要の増加も見込まれているが、海岸の保全・利用に当たっては海岸のもつ自然そのものの重要性を十分勘案する必要があろう。更に、地域住民の手軽な海水浴、魚釣り、散策、語らい等の場の確保を望む声がますます強まっており、この声に如何に対応するかが重要な課題となっている。
このような海岸の改変だけでなく、戦後の経済の高度成長に伴い、我が国の自然は各種開発の下で急速に改変されてきている。
48年に実施された自然環境保全基礎調査(いわゆる「緑の国勢調査」)により、我が国の自然環境の状態を見よう。
第3-4図は、植物群落の種類によって、人為による自然への影響の度合をは握したものであり、その指標を植生自然度をもって示している。
全国の植生自然度を見ると、自然度が?と?の人為のほとんど加わっていない地域は国土の23%にすぎず、国土の約80%までが何らかの形で人為が加えられている。なかでも、東京(23区)、大阪市等の大都市は約90%が市街地などの緑のほとんどない自然度?の地域で占められており、いわば「都市砂漠」の状況を呈している。これら大都市における緑の回復、潤いの回復は、そこに住む者にとっての切実な願いとなっている。ここで重要なことは、このような大都市において求められている自然は、何も手つかずの原生自然ではなく、神社の境内にある木立や河川敷などに見られる「ありふれた自然」であることである。このようなちょっとした自然、身近な自然を大切に残し、育てていくこともこれからの課題のひとつであるといえよう。
また、これまでややもすれば、高度成長期の無秩序な工業開発や都市化の進行によって農山村地域の自然は失われがちであったが、農山村地域における自然環境を保全するためには、農山村地域の住民が安んじて生活しうるような農林業の経営基盤を整備することも重要であることを忘れてはならないだろう。