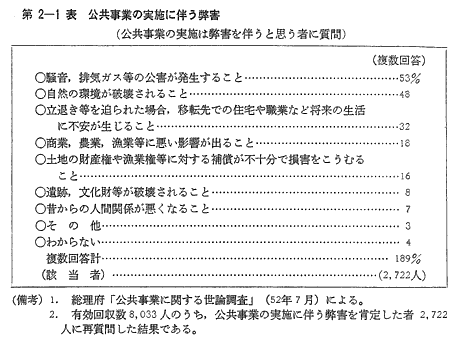
2 多様化する環境問題
(1) 環境問題の推移
「公害対策基本法」の制定後、同法に基づく公害対策の進展により、それまで汚染の著しかった川崎、四日市等では改善が見られるようになったが、他方、法律に基づく規制措置が実施されていなかった地域で大気汚染、水質汚濁等が問題となった。
また、従来の四大公害訴訟である富山県イタイイタイ病訴訟、三重県四日市訴訟、新潟県新潟水俣病訴訟、熊本県水俣病訴訟に見られる硫黄酸化物や有機水銀等による健康被害問題ばかりでなく光化学スモッグ、自動車排出ガス、窒素酸化物等の新たな大気汚染問題が生じた。
さらに、45年に行われた工場、鉱山等を対象とする全国総点検の結果、各地におけるカドミウムによる農作物や土壌汚染等蓄積性汚染物質による汚染問題が判明するなど公害問題はますます複雑かつ多様な問題となった。
このような事態に対処すべく、総合的な公害対策の具体化を図るため、45年末の公害国会において「公害対策基本法」の改正を含む14の公害関係法の制定若しくは改正が行われた。続く、第65回通常国会においても各省庁において個別に行われてきた環境行政を調整し、総合性・統一性の確保を図るために環境庁が設置されることとなった。
以上このような対策の進展を反映して、40年代中ごろ以後、二酸化硫黄、一酸化炭素等の汚染因子については改善の傾向が見えてきた。他方、40年代後半から、民間のみならず国あるいは地方公共団体が実施する大規模な地域開発に伴う生活環境及び自然環境破壊の問題、さらに「ごみ戦争」とさえ称される飛躍的に増大する廃棄物の処理問題及び自動車、航空機、新幹線鉄道などに起因する交通公害などにも強い関心が払われるようになってきた。
とくに交通公害については、その運行が拡大されるとともに大気汚染、騒音、振動等は深刻になっており、大阪国際空港公害訴訟等のように差止請求及び損害賠償請求を請求の趣旨とする訴訟もいくつか提起されている。
(2) 地域住民の動向
環境問題が複雑かつ多様化し、また、国民の生活水準が向上し、良好な生活環境へのニーズが強まるに伴い、環境保全に関する地域住民の国や地方公共団体及び企業に対する要望は多様化してきている。これらの要望が行政的対応や企業努力等によって満たされない場合、同じ考えをもつ人々からなる団体を組織して直接的な反対運動を展開したり、訴訟の提起という手段をとったりする事例も見られる。
まず、環境問題を生じるおそれのある事業が行われるとき、地域住民がどのような対応をとるかを推測するために52年7月に総理府から発表された「公共事業に関する世論調査」の結果を見ることにする。
「公共事業を実施すると生活にいろいろな弊害が出てくると思うか」という問に対し、「そうは思わない」と弊害を否定する者が49%おり「そう思う」と弊害を肯定する者の34%を上回っている。
住宅、下水道、ダム、高速道路等を整備する公共事業は、生活環境の改善、災害の防止、地域社会の発展などを目的とし、国民生活の向上及び国土全体のバランスある発展に不可欠のものであるが、他面では一部の公共事業の実施により弊害が生じる場合があることは否めず、約1/3の者は、事業の実施は弊害を伴うと考えている。約1/3を占める弊害を肯定する者に、その弊害は何かと具体的に挙げてもらうと、第2-1表のとおり、53%の者が「騒音、排気ガス等の公害が発生すること」を、また48%の者が「自然環境が破壊されること」を弊害の1つとして挙げている。
次に、「居住地で公共事業が行われる場合、意見や希望があれば、それを計画に反映させるため何かするか」という質問に対して、「何かする」と積極的な回答をした者は33%にとどまっている。「何かする」と回答した者に、さらに「意見や希望を反映させるための最も有効な方法」として何をとるかを質問すると、45%の者が「近所の人で同じ考えをもっている人をつのり、共同して国や地方公共団体に働きかける」と回答している一方、「直接国や地方公共団体に出向いて意見をいう」などの単独行動を挙げる者は少ない。
このほか、「公共事業が住民との関係で円滑に実施されるために一番大切だと思われる事項」については、「計画を決める前に事業の必要性などについて住民に説明する」ことを挙げた者が最も多く39%を占めており、「居住地で実施される公共事業に関して住民に対する説明会が開かれたら参加するか」という質問については、「参加する」と回答した者が53%と過半数を占めている。
以上のようなことから、ともすれば環境問題を生じるおそれのある公共事業に対して関心を持っている者は少なくなく、場合によっては、自らの希望、意見の実現のため何らかの行動をとろうと考えている者もいることがうかがわれる。
次に環境問題に関する訴訟の実態を把握するため、52年2月現在係属中の環境問題に関する訴訟で、かつ、国、都道府県、9大市及び特殊法人が調査時点において訴訟内容をは握している68件(同一事件について複数の訴訟が提起されているときは、それらをまとめて1件と数えたものである。)について、環境庁が行った訴訟状況調査の結果をみることとする。
まず、環境問題に関する訴訟の原因となった対象施設別の件数をみると、第2-2図のとおり、「道路、鉄道、空港、飛行場」という「交通関連施設」に係るものが19件と最も多く、以下「ごみ、下水道、し尿処理場」といった生活環境の保全のための施設に係るものが14件、宅地開発、工場立地、河川工事及びその他各種工事等の「各種開発計画等」に係るものが13件、休廃止鉱山あるいは現に工事等の操業に伴う「企業活動」に係るものが10件、火力又は原子力の「電源立地」に係るものが9件となっている。
また、原告の請求の趣旨についてみると、生活環境ないしは自然環境の悪化の未然防止を求めているものは、「交通関連施設」、「ごみ、下水道、し尿処理」、「電源立地」などに係る訴訟に多くみられ、調査件数全体の約2/3にあたる42件あり、金銭賠償を求めているものは22件ある。
なお、環境問題のうち、大気汚染、水質汚濁、騒音等の公害に関して、これまでの訴訟に係属中の事件について、最高裁判所事務局資料により、各年ごとの第1審係属件数を調べると、第2-3図のとおりになっている。汚染類型別に見ると、騒音、振動が最も多く52年で全体の368件中の223件と約6割を占め、この中でも建設工事によるものは全体の約4割を占めている。