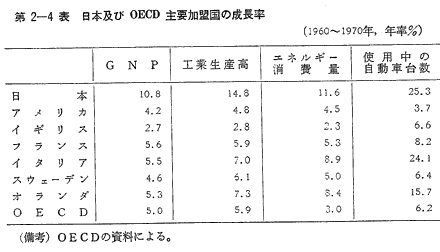
3 我が国の環境政策の変遷
(1) 環境政策の目的
我が国の経済発展の過程をふりかえってみれば、第2-4表のとうり、1960年から1970年の間に、国民総生産で年平均10.8%という経済成長を遂げ、欧米諸国のそれをはるかに上まわっているほか、工業生産高、エネルギー消費量及び使用中の自動車台数の年平均成長率も他国より高い値を示しているなど、世界に類を見ない高度成長を続けてきたといえる。
また、可住地の単位面積当たりの国民総生産、エネルギー消費量等について見ると、第1-11表のとおり他の先進工業国よりはるかに高い値を示しており、生産活動及び消費活動が狭い国土できわめて活発に行われてきたことがわかる。
このように急速な重化学工業及び都市化の進展による高密度経済社会の形成の過程で発生する環境汚染物質の量は急速に増大し、十分な事前の公害対策を伴わなければ、公害問題が発生するのも避けられない状況にあったといえる。
しかし、当時、一般的には、人々にとって清浄な空気や水はかけがいのないものであり、ひとたびそれが損われ環境汚染が進行するや人間の生命さえも脅かされるという認識が十分になかったことは否めない。
しかも、我が国においては、上述のように短期間に著しい経済活動の拡大が続き、予め環境汚染を防除する十分な措置が講じられなかったため、生活環境の悪化はもとより、不幸にも水俣病に代表されるような健康被害が発生した.
このような事態に及んでようやく本格的に公害対策が行われるに至ったことから、我が国の環境政策の目的は公害から国民の健康を保護することに特に重点がおかれた。「公害対策基本法」第1条は、その目的として、「国民の健康を保護するとともに、生活環境を保全することを目的とする。」と規定しているが、まず国民の健康保護に係る対策が何よりも優先されたといえる。
なお、「公害対策基本法」制定当初においては、国民の健康の保護は絶対的なものとして規定された一方、生活環境の保全については、第1条第2項において、「生活環境の保全については、経済の健全な発展との調和が図られるようにするものとする。」とのいわゆる「調和条項」が定められていた。このような「調和条項」はともすれば経済優先を規定していると誤解されがちであったことから、45年の公害国会において削除された。また、これと同時に、第1条の目的に関する規定の中に「国民の健康で文化的な生活を確保するうえにおいては公害の防止がきわめて重要であることにかんがみ」との語句が加えられ、公害防止に取り組む国の姿勢がより明確にされることとなった。
今日、生活環境の保全は、環境政策の目的として明確に位置づけられているが、さらに、既にみてきたように、環境問題が複雑かつ多様化し、地域住民の関心も高まるに伴い、環境政策の目的は、より積極的に環境汚染の未然防止、国民の快適な生活環境の確保もめざすなど拡大してきている。
これらの目的達成のためには、近年とくに関心事となってきている一部の公共事業の実施に伴い発生が予想される環境問題あるいは交通機関の運行に起因する環境問題に重点的に対処していかねばならないが、その過程において、これらによってもたらされる利便と地域住民の生活環境の保全との調整という問題が生じてきている。
この点について、51年に制定された「振動規制法」の第15条第3項においては、公共性のある施設又は工作物に係る建設工事に対する配慮を規定するとともに生活環境への配慮も明文化されている。また、48年の航空機騒音の環境基準や50年の新幹線騒音の環境基準においても住民の生活環境保全に重点がおかれている。(注)
(注)(「振動規正法」第15条第3項)
都道府県知事は、当該施設又は工作物に係る建設工事の工期が遅延することによって公共の福祉に著しい障害を及ぼすおそれのあるときは、当該施設又は工作物に係る建設工事として行われる特定建設作業について前二項の規定による勧告又は命令を行うに当たっては、生活環境の保全に十分留意しつつ、当該建設工事の実施に著しい支障を生じないよう配慮しなければならない。
(2) 「公害対策基本法」に基づく施策の実現
我が国の公害対策については、前述のような深刻な公害問題に対処するために「公害対策基本法」を頂点として、同法に基づき環境基準の設定をはじめとして、各種の施策がとられてきたが、なかでも人の健康影響に係る大気汚染の改善、水銀等有害物質の規制を優先させねばならなかったので、主として各種規制法の整備による規制という手段が進められた。
以下、「公害対策基本法」の趣旨にのっとり、主な施策がどのような狙いにの下にどのような具体的手段を用いて実現されてきたかについて見ることとする。
ア 環境基準の設定
環境基準は、人の健康を保護し、生活環境を保全するうえで維持することが望ましい大気の質、水質、静けさ等を定めたもので、いわば総合的な対策によって達成すべき努力目標であるといえる。そして、この目標達成をめざして、排出規制や土地利用計画などの施策が合理的、効果的に推進されることが期待されている。
現在のところ第2-5表のとおり土壌汚染に係るものを除いて設定されている。
環境基準は総合的行政判断に基づき設定されるものであるが、当然のこととして科学的に究明された汚染物質の濃度(量)と人の健康や生活環境への影響との関係を基礎として設定されるものであることから、科学の進歩に伴う新たな影響に関する知見、測定技術等の開発の進展などにより常に適切な科学的判断が加えられ、必要に応じて改定されねばならない。
現に、44年に硫黄酸化物に係る環境基準が設定された後、対策の進展を反映して大気中の硫黄酸化物の濃度は漸次減少したが四日市地区等における疫学調査の結果から閉そく性呼吸器系疾患の新規発生に関する新規のデーターが報告され、知見がより正確さを増したこともあって硫黄酸化物に係る環境基準は、48年5月に、二酸化硫黄に係る環境基準として大幅に改定強化され、現在に至っている。
環境基準は、前述のとおり望ましい行政目標であり、人間の健康等の維持のための最低限度としてではなく、それよりもさらに一歩も二歩も進んだところに設定されているので、環境基準をこえる測定値が得られた場合においても、直ちにそれが人の健康に被害をもたらすというものではない。従って、環境基準は、拘束力をもっていないが、この目標を達成するため各種施策が強化されてきている。
イ 規制の強化
環境基準という目標を達成するための手段の中心となるのは、「大気汚染防止法」、「水質汚濁防止法」等の各種規制法による原因者及び原因物質に対する厳しい直接規制であり、排出基準違反には、直接罰則が科せられるほか、改善命令、操業停止命令が適用されることとなっている。
各種規制法が本格的に整備されたのは、「公害対策基本法」制定後、とくに45年末の公害国会においてであり、その整備の経緯は第2-5表のとおりである。このように各領域において規制法がほぼ整備されてきているが、規制の方法についても、環境汚染の改善を図るために新たな手段が導入されてきている。
一つの例として、硫黄酸化物に係る排出規制方法の変遷を見てみると、まず、37年に制定された「ばい煙の排出の規制等に関する法律」においては排出口における濃度規制がとられた。次に、43年に「大気汚染防止法」が制定され、地表濃度改善を目的とした排出規制として、排出口の高さに応じて硫黄酸化物の排出量の許容限度を定めるK値規制方式が導入された。さらに、49年の「大気汚染防止法」の改正により、現行の排出基準のみでは環境基準の確保が困難と認められる地域において、環境基準に対応する環境目標値を確保するように地域総排出量を算定し、それに基づいて個別の汚染発生量を規制するという総量規制方式が導入された。
ウ 公害防止計画の策定
公害の発生が著しい地域、または人口や産業の急速な集中により公害が著しくなるおそれのある地域においては、個々の発生源に対する排出規制だけでは公害の防止を図ることが著しく困難であるため発生源規制のみならず、土地利用の適正化、下水道、緩衝緑地等公害防止に役立つ公共施設の整備等の施策を総合的に講ずる必要があることから、これらの地域について各般の施策の有機的連けいの下に総合的に講ずるための公害防止計画を策定することとした。
過去、45年に、第1次地域として、千葉・市原地域、四日市地域及び水島地域について計画が策定され、その後52年の第7次まで延べ50地域についての計画が策定され、国土面積のうち約10%、総人口のうち約55%が計画策定地域となり、大都市や主な工業地帯はその全部がほぼ含まれることとなっている。
計画地域における環境汚染は、総体的には、一部の汚染因子を除いて漸次改善の傾向にあるといえるが、環境基準達成という観点からは、なおかなりの改善を図る必要がある地域もあることから、更に達成に努めることとしている。
エ 公害に係る紛争の処理及び被害の救済等
公害による被害は、その原因が人為的なものであるから、一般の民事上の手続によって紛争の解決や救済を求め、あるいは、民事調停のかたちで調停を求めることはできる。しかし、加害者を特定し、因果関係や故意過失の有無を立証することはかなり困難であり、かつその結論を得るまでに長期間を要することを勘案すると、公法上の紛争処理、公法的な救済の途を開く必要があるため、「公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法」(以下「救済法」という。)、「公害紛争処理法」が制定された。また、大気汚染と水質汚濁に係る健康被害に関して、企業の無過失賠償責任を法制的に確立するため「大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律」(いわゆる「無過失損害賠障責任法」)も制定された。
しかし、「救済法」においては、逸失利益に対する補償がない等給付の内容が限定されているという問題があり、また、「無過失損害責任賠償法」においては民事訴訟という手段によるため、その解決には相当の努力と日時を要するという問題があって被害者の救済に万全を期しているとはいい難い状況にあったため、48年に「救済法」を発展的に解消し、新たに「公害健康被害補償法」が制定された。
また、国は地方公共団体が蓄積性汚染物質の除去事業や緩衝緑地設置事業を実施するにあたって、事業者に対してその汚染に寄与した割合に応じて費用を負担させる「公害防止事業者負担法」も45年に制定され、事業者の負担のあり方が明らかにされた。
以後、同法が適用され、事業者に費用負担を課した事例は、52年末までに40件ほどに達している。
(3) 新たな施策の展開
「公害対策基本法」においては、環境基準について維持されることが望ましいとして規定(第9条)し、公害が著しくなるおそれがある地域に対する施策として、公害の原因となる施設の設置を規制する措置(第11条)と公害防止計画における「人口及び産業の急速な集中等により公害が著しくなるおそれがあり云々」の地域の分類を設け(第19条)、さらには地域開発施策等における公害防止の配慮について規定する(第17条)など、制定当初から直接的な排出規制のみならず予防的観点に立った施策の実施についても配慮がなされている。
また、45年の公害国会における改正により、新たに自然環境の保護に関する規定(第17条の2)も加えられた。
しかし、40年代に実際行われてきた対策は、排出規制が中心であった。また、そもそも「公害対策基本法」における生活環境の保全対策については、公害の防除による生活環境の保全という観点が中心であり、同法に基づく施策だけでは自然環境の保全あるいは環境問題の抜本的解決に結びつくと考えられる土地利用問題などに十分対応できなくなってきていることも事実である。
すなわち、今日の環境政策は、従来の「公害対策基本法」に基づく健康の保護及び生活環境の保全に加え、自然環境そのものを主体としてとらえるという観点からの自然環境の保全、さらには、人間の生活環境と自然環境の基盤となる国土の計画的利用等を含めた広い視野に立って、総合的、計画的に展開されることが要請されている。そして、これに応えるべく次のような新たな施策が展開されつつある。
ア 「自然環境保全法」の制定
自然環境の保全については、「自然公園法」、「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律」等の諸法令が定められていたが、いずれも法令の目的の点あるいは保護対象の点において十分なものとはいえなかった。45年には「公害対策基本法」が改正され、「政府は……公害の防止に資するよう緑地の保全その他自然環境の保護に努めねばならない。」と自然環境の保護に関する規定(第17条の2)が新たに設けられた。しかし、これでもなお公害の防止に資するという観点からの自然環境の保護の規定であるといわれた。
そこで、人間が健康で文化的な生活を享受するためには、「公害対策基本法」でいう生活環境の保全よりさらに広い視点に立って、良好な自然環境もまた確保されることが不可欠であることから、47年に「自然環境保全法」が制定された。以後、同法に謳われている基本的理念及び基本的方針に沿って、自然環境の保全を目的とする各種施策が実施されている。
また、長期的視野に立った自然環境保全政策の確立に資するため、51年12月自然環境保全審議会から「自然環境保全に関する長期計画のための基本的具体的構想について」が答申された。本答申の中では、国又は地方公共団体が自然環境保全のために実施すべき施策の目標が現時点における知見に基づいてできるだけ明確にされるとともに、自然環境保全関連施策の決定、実施に当たって、自然環境保全上配慮すべき事項、自然環境保全に関する各種施策の総合調整の指針等が明らかにされている。
イ 環境汚染の未然防止
環境汚染を未然に防止するためには各種の開発行為等で環境に著しい影響を及ぼすおそれのあるものについて、それが環境に与える影響を事前に調査・予測し、環境への影響を予めチェックする環境影響評価の実施が必要である。
47年6月に「各種公共事業に係る環境保全対策について」の閣議了解が行われ、各種公共事業の実施主体に予め必要に応じ環境に及ぼす影響の内容及び程度、環境破壊の防止策、代替案の比較検討を含む調査研究を行わしめ、その結果を徴し、所要の措置を行うこととされた。
さらに、48年には、開発等に伴う環境影響についてのチェックを一層進めるため「公有水面埋立法」の一部改正等が行われ、これに基づいて環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業・計画等について、環境保全の見地からの検討が数多く行われている。
また、PCBなどによる環境汚染の事例にかんがみ、化学物質の開発、実用化にあたっては、それがもたらす効用と影響を事前に予測、評価することにより環境汚染を未然に防止する必要があるが、48年に「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」が制定され、新規化学物質の事前審査並びに難分解性の性状を有し、魚類等に蓄積し、かつ、人の健康を損うおそれのある化学物質(特定化学物質)の製造、輸入、使用等の規制が行われている。
ウ 「国土利用計画法」の制定
我が国における高密度経済社会の形成と土地利用に対する配慮の欠如及び周辺の土地利用との不十分な調整等による国土利用の地域的偏在は、公害の発生、緑地の減少、乱開発による自然環境の破壊等の問題を生じた。このため、環境保全等に配慮しつつ国土の適切な利用を確保することが緊急の課題となっている。
このような状況にかんがみ、各種個別法に基づき様々の土地利用規制が行われていたが、これらの個別法のいわば基本法として、土地に関する諸問題を解決し、均衡ある国土の発展と環境保全を図る見地から総合的かつ計画的な国土利用を推進するため「国土利用計画法」が49年に制定された。これにより、開発関係の法律、「都市計画法」、「建築基準法」等とあいまって、一連の法体系が整うこととなった。
「国土利用計画法」は、土地対策の要となる基本法の性格をもっており、国土利用計画(全国計画、都道府県計画、市町村計画)及び土地利用基本計画の策定、土地取引の規制の強化、遊休土地に関する措置等を内容としており、51年5月には、今後の我が国の国土利用のあり方を示す行政上の指針ともいうべき全国計画が策定された。
これに基づき、現在、都道府県計画策定の作業が進行中であり、53年2月末までに34道県の都道府県計画が決定されている。なお、51年5月に閣議決定された全国計画は都道府県計画が全て策定された際に、必要があれば見直されるという性格のものである。
エ 環境保全に資する長期計画
望ましい環境水準の達成のためには、長期的視点に立った総合的、計画的な環境行政の推進が必要である。そこで我が国全体の環境保全目標を設定し、その目標に対する環境政策上の課題を明らかにし、かつ政策課題を達成するための政策手段を整合的に掲げる長期計画を策定する必要があることから、52年5月に、環境庁は同庁の今後の指針として「環境保全長期計画」をとりまとめた。
また、総合的な開発計画策定にあたり、環境保全に十分配慮し、人間居住の総合的な環境の創造という観点に立ち、長期的開発計画を策定することが望ましいといえるが、このような要請に応えるため、52年11月に「第3次全国総合開発計画」が策定された。
本計画においては、限られた国土資源を前提として、地域特性を生かしつつ、歴史的、伝統的文化に根ざし、人間と自然との調和のとれた安定感のある健康で文化的な人間居住の総合的環境を計画的に整備することを基本目標とし、開発の方式として、人間が定住するための生活圏の整備という観点に立った「定住構想」を採用している。
オ 国際的動向への対応
環境問題は、次のような点で国際的問題であり、その解決には国際協力が不可欠である。
第1に、海洋環境の保全は、一国では達成しえないすぐれて国際的な問題であり、近年特に海洋汚染防止のための国際的規制の動きが活発である。すなわち、1970年の第25回国連総会において、新たな海洋秩序の基本原則を確立するため、第3次海洋法会議の開催が決議され、1973年のニューヨーク会議を皮切りに、現在まで6回の会議がもたれているが、その第3委員会において、船舶起因汚染、陸上起因汚染モニタリング、海底開発起因汚染、海洋投棄及び海洋科学調査等の問題について国際的合意の成立を図るため包括的な討議が行われてきている。
一方、船舶からの油の排出については、従来からIMCO(政府間海事協議機関)を中心に国際的規制の整備拡充が図られ、現在まで「1954年の油による海水の汚濁の防止のための国際条約」ならびに同条約の規制内容を強化した1962年及び1969年の改正条約が発効しており、さらに、船舶からの油の排出規制を大幅に強化するとともに、油以外の海洋汚染物質を規制する「1973年の船舶からの汚染の防止のための国際条約」が制定され、その早期発効の促進のための国際的検討が行われてきたところ、1977年3月米国カーター大統領の提案に基づいて同条約を修正した1978年の議定書の成立をみた。この結果1980年代においては、タンカーへのバラスト水専用タンク又は原油洗浄装置の設置が義務付けられる等、船舶起因汚染防止の国際的規制が大きく前進することが期待されている。
また、廃棄物の海洋投入に関しては、1972年のロンドン国際会議において「廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約」が採択され、これに基づき国際的規制が行われてきている。
第2に全地球的規模での環境汚染を調査するために、広範なモニタリングや調査研究の必要性が挙げられる。例えば大気汚染が気象に与える長期的影響が懸念されているが、これを調査するためには、地球上のいろいろな地点で同一の項目を同一の測定方法で長期間測定してはじめて科学的な判断が得られ、適切な行動計画に結びつけることが可能であろう。
第3に、環境悪化防止に関する知識や経験の国際的交流を促進し、それぞれの国の環境政策に反映させることである。わが国の場合は、米国をはじめとする欧米諸国の知識や科学技術を吸収利用して汚染対策の成果をあげてきているが、一方、日本がより進んでいる分野では知識の輸出(情報伝達)を行っている。また開発途上国に対しても、わが国の貴重な公害対策の経験を生かしての積極的、かつ大幅な技術援助が期待されている。
第4に、渡り鳥保護の必要性があげられる。我が国の鳥類は、その約8割が日本とアメリカ、ソ連、中国、オーストラリア、東南アジア等の各国間を移動する渡り鳥で占められており、渡り鳥を保護するためには、これらの諸国との国際協力を推進することが不可欠である。
このような国際協力の必要性が深まったのは、1972年にスウェーデンのストックホルムにおいて開催された「国際人間環境会議」からであるといえる。
本会議は、環境問題についての問題意識が国際的にも大きな高まりを見せ、人類共通の課題として国際協力によりこれに対処しようという気運の盛り上がりを示したものである。その後1975年に「国連人間居住会議(HABITAT)」が、1977年には「国連砂漠化防止会議」が開催されるなど、世界の環境問題に対する意識は人間環境の広い分野に拡がってきている。
先進国の国際機関であるOECDにおいては、1970年7月に環境委員会が設置され、環境問題は科学的、技術的側面のみならず経済的、政策的側面も含めて検討されている。本委員会はじめその下部機構である大気管理、水管理、化学品、経済専門家等の各グループではOECD加盟国の公害問題に対する関心の高さを反映して活発な活動がなされている。
また、開発途上国においては、工業活動による水質汚濁問題等の公害問題が生じているところも一部あるが、むしろ農業による公害とか上下水道設備の欠如、貧弱な衛生施設等経済的な貧しさ故に起きている環境問題が多い。
このように、環境問題は国際的に関心をもたれており、その解決のためには国際協力の必要性が改めて強調されねばならない。日本は、これまでに、例えばOECDの活動の一環として「日本の環境政策レビュー」会合を東京で開催するなど積極的に国際機関の活動に参加してきた。今後も、環境問題に関して歴史と経験を有する国として、国連、OECD環境委員会、国連環境計画(UNEP)等の国際機関の活動などを通して重要な役割を果たすことが期待されている一方、国内においても各方面で国際的動向に対応した政策を展開していく必要がある。