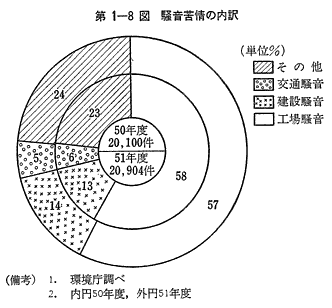
3 騒音、震動、その他の公害の現況
(騒音)
騒音は各種公害のなかでも日常生活に関係深い問題であり、また発生源も多種多様であることから、例年、騒音に対する苦情件数は、公害に関する苦情のうちで最も多数を占めている。
51年度においても騒音に関する苦情件数は、全苦情件数の約3割を占めている。このうち工場騒音が最も多くを占め、建設騒音がそれに次いでいる(第1-8図)。自動車、航空機等の交通機関に起因する騒音の苦情件数は、騒音に関する苦情全体から見れば少ないが、近年、訴訟等も提起され社会問題となっている。このうち道路交通に起因する騒音について、それが現に問題となっているか、又は問題となりそうな地域について騒音レベルを測定した結果(自動車交通騒音実態調査)を見ると、環境基準に適合する測定地点数の全測定地点数に対する割合は、51年で21.3%となっている。
一方、「騒音規制法」に基づく要請基準を超えない測地点は、51年で79.7%となっている。
また、新幹線鉄道や航空機による騒音については、現在、都道府県知事が環境基準の地域類型の当てはめ作業を進めている。
今後は、環境基準を維持達成するために必要な音源対策、障害防止対策や交通施設の周辺対策等の都市計画、土地利用対策を含む総合的な対策が要請されている。
(振動)
振動は、工場、建設作業場、交通機関等がその主要発生源であり、このため51年に「振動規制法」が施行され、これに基づき現在地域指定、規制基準の設定等の作業が進められている。
防振対策としては、これまでのところ種々の発生源対策がとられているが、今後は震動の伝播性や家屋防振構造等を考慮した周辺対策を含む総合的な対策を検討する必要がある。
(悪臭)
悪臭は、人のきゅう覚に直接訴え、生活環境を損う公害であるため、例年騒音、振動に次いで苦情件数が多く、51年度においても同様である。
苦情原因の中では、畜産農業に対する苦情が大きな割合を占めている(第1-9図)。現在、「悪臭防止法」により、アンモニアなど8物質が規制されているが、悪臭の防止方法の開発、悪臭の評価方法の改良等の悪臭対策の充実が望まれている。
(土壌汚染)
土壌汚染については、「農用地の土壌の汚染防止等に関する法律」により、カドミウム、銅、砒素及びそれらの化合物が特定有害物質として指定されており、51年末までの調査結果によると、基準値以上の有害物質が検出された農用地は、全国で114地域、約6,200haとなっている。このうち、農用地土壌汚染対策地域として52年末までに指定されているのは、35地域、約4,300haで、更に、このなかで農用地土壌汚染対策計画が策定され、対策事業が進められているのは、19地域、約1,650haとなっている。その他の地域については、都道府県の単独事業が35地域で実施されているほか、44地域について調査、地域指定への検討がすすめられている。
(地盤沈下)
地盤沈下について、現在地盤沈下が認められている主な地域は、全国で、34都道府県、58地域となっている。これまで激しい沈下が生じていた大都市地域及び一部の地方都市では、地下水採取規制及び水源転換の結果、沈下の速度がかなり鈍化の傾向にある。しかし、その他の地域では、依然として沈下が認められ、特に埼玉県中東部で年間最大14cm余を記録したのをはじめ、横浜市郊外、濃尾平野の愛知県及び三重県にまたがる地域、大阪府の泉州地域などの大都市近郊では、なお沈下が著しく、これに次いで、佐賀白石平野等の農業地帯の沈下が目立っている。
地盤沈下の原因は、地下水の過剰な採取にあると考えられているが、現行の法制においては、地盤沈下の予防及び防止の観点から必ずしも十分でない点もあり、地下水の採取規制を強化しつつ、水使用の合理化、代替水源の確保等総合的な対策が必要である。
(廃棄物)
廃棄物は主として日常生活に伴って生じる一般廃棄物と事業活動に伴い生じる産業廃棄物に大別される。
一般廃棄物は、ごみ及びし尿が大部分を占めており、その発生量は50年度において、それぞれ4,205万t、3,900万klとなっている。産業廃棄物の発生量については、現在正確なデータは得られていないが、45年から49年にかけての調査によれば年間約3億2000万tと推計されている。
廃棄物の処理については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」による規制が行われているが、同法については、50年の六価クロム事件を契機に、産業廃棄物の処理に関する規制及び監督の強化等を内容とする改正が、51年に行われ、産業廃棄物の適正な処理を確保するための規制処置等が強化された。
しかし、毎年の公害事犯件数において、廃棄物の不法処理関係の件数が相当大きな割合を占めていることにも示されているように、廃棄物の適正な処理を確保するための施策を、今後とも一層強力かつ総合的に推進することが環境保全上の大きな課題とされている。