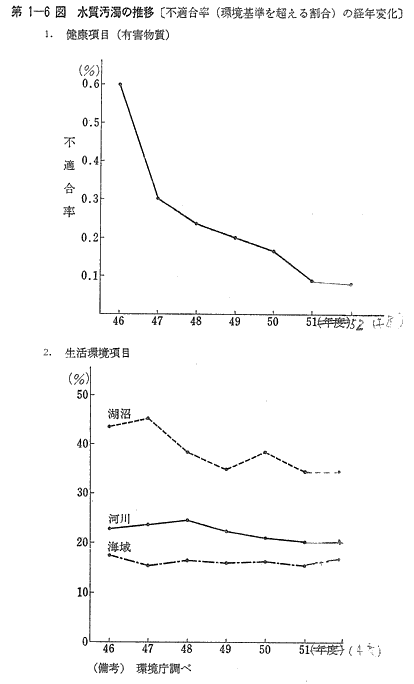
2 水質汚濁の現況
(有害物質による汚濁)
最近における水質汚濁の状況を見ると、有害物質に係る水質汚濁については年々改善されてきている(第1-6図)。すなわち、水質汚濁に関する環境基準のうち、人の健康に関する項目(カドミウム、シアン、アルキル水銀などの9物質)について、環境基準に対する不適合率を見ると、51年度は0.09%と非常に低く、50年度における総水銀、アルキル水銀及び有機リンに加えて六価クロムについても環境基準を越える地点は全くなく、ほとんどの水域で問題のない状況にまでなっている。また水銀、PCBなどの有害物質が含まれているヘドロについては除去事業が進められている。
(有機物質による汚濁)
利水上の障害などをもたらす有機汚濁(BOD、COD、PHなどの生活環境項目)について、51年度までに環境基準類型の当てはめが行なわれた水域の6,062地点(河川3,686、湖沼272、海域2,104)における、環境基準に対する不適合率を見ると、51年度は河川20.2%、湖沼34.4%、海域15.6%であり、経年的にやや改善の傾向が見られる(第1-6図)。
また、有機汚濁の代表的な指標であるBOD(湖沼、海域においてはCOD)について見ると、近年の排出規制の強化等を反映し総体的には改善傾向にあるものの、最近は横ばいの傾向にある。すなわち、52年4月までに環境基準類型の当てはめが行われた2586水域におけるBOD、CODの環境基準(例えばAA水域では日間平均値1ppm以下、また、E水域では同10ppm以下)の達成率は51年度60.5%となっており50年度の達成率59.6%より若干上昇しているものの未達成の水域も多く、大都市内の中小河川、その沿岸海域、また内湾、内海等の閉鎖性水域における汚濁の改善ははかばかしくなく、依然汚濁の程度が高い(第1-7図)。
(瀬戸内海の汚濁)
瀬戸内海の水質汚濁については、その海域が比類ない美しさを誇る景勝の地であり、貴重な漁業資源の宝庫であることにかんがみ、水質汚濁防止対策を進めることが重要な課題となっている。このため48年に「瀬戸内海環境保全臨時措置法」が制定され、これに基づく産業排水に係るCOD汚濁負荷量を2分の1に削減する等の施策の実施により、水質の汚濁状態には改善の兆しが見られる。しかし、CODに関する環境基準に対する適合率は、51年度で82%と、広域的な閉鎖性水域を除く海域より低く、また、窒素、リン等の栄養塩類の流入に伴う富栄養化が進行していると見られ、今後、引き続き総合的な水質保全への努力が要請されている。
(海洋汚染)
海洋汚染について見ると、汚染発生件数は、ここ数年減少傾向にあるものの依然として多く、52年度も1,750件となっている。特に、油汚染によるものが全体の約77%を占めているため、漏油防止指導等の施策を更に推進する必要がある。
また、沖縄や南西諸島などの黒潮流域等においては、タンカーから投棄されるバラスト水等の油分に起因すると推定される排油ボールが漂流・漂着し、水産資源及び漁業活動に悪影響を及ぼす等海洋利用の障害を生じさせており、このため、タンカーからの廃油処理対策など汚染防止対策が進められている。
しかしながら、海洋汚染の防止は、一国のみの努力によって達成されるものでなく、本来、国際的な防止体制が不可欠である。
このため、国連等の国際的討議の場を通じて、国際的な海洋汚染防止対制の整備が進められてきており、我が国も、その検討に積極的に参加、協力しているところである。