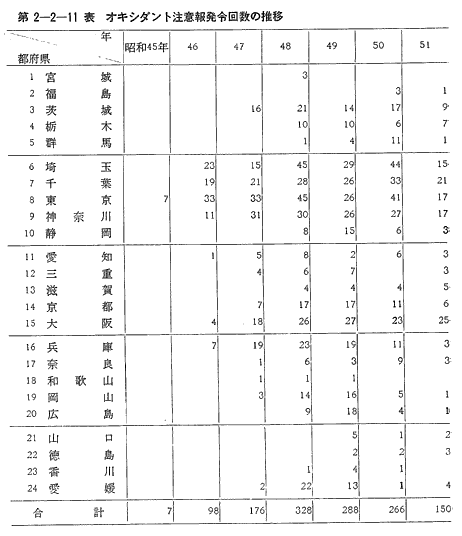
5 光化学大気汚染対策
(1) 光化学大気汚染に対する緊急時対策と被害届出状況
45年夏以来、毎夏光化学大気汚染によると思われる目の刺激、のどの傷み胸苦しさ等を典型的な症状とする健康被害が発生しているが、地方公共団体では、オキシダント緊急時対策要綱を定めて、オキシダント濃度と気象条件に応じて、予報、注意報、警報等を発令し、発生源対策と住民対策を実施してきた。
51年のオキシダント注意報(オキシダント濃度の1時間値が0.15ppm以上で気象条件から見て汚染の状態が継続すると認められるときに発令される。)は21都府県で発令され、延べ発令回数は150回であった。この発令回数は過去5年間で最も少なく、47年とほぼ同じレベルであった。特に南関東地域は50年に比べて大幅に減少した(第2-2-11表)。また、45年以来毎年発令されていたオキシダント警報(オキシダント濃度の1時間値が0.30ppm以上で気象条件から見て汚染の状態が継続すると認められるとき発令される。)は51年には1度も発令されなかった。
51年の光化学大気汚染によると思われる被害者の届出は15都府県であり、延べ届出人数は、4,215人で45年に初めて被害者の届出があって以来最も少なかった。(第2-2-12表)。
また、オキシダント濃度をより正確に測定するため各方面で測定法改善のための技術開発が進められていたが、その結果を集約した形で、51年11月、日本工業規格(JIS)B7957「大気中のオキシダント自動計測器」が制定された。今回のJISによる測定法は、主として計測器の校正方法に起因して、同一の大気中のオキシダントレベルに対して、従来広く用いられてきた測定法に比べ2割低い値を示すため、緊急時の発令レベルを強化ではなく、同一に保つため、大気汚染防止法第23条第1項に係る濃度(注意報レベル)を0.15ppmから0.12ppm、第4項に係る濃度(重大緊急時レベル)を0.5から0.4ppmに改正することとし、測定法に関し、1年間の経過措置(従来の測定法による測定値には0.8を乗じて、新基準値と対比する。)を設けた上、52年4月2日から施行することとした。
(2) 光化学大気汚染調査研究の推進
光化学大気汚染の防止のための調査研究は第2-2-7図のような体系の中で光化学大気汚染の発生機構から移流拡散等の気象の影響、原因物質の発生原単位、健康影響調査、植物影響調査に至る広範な分野にわたって行われており、貴重な知見が得られている。
光化学大気汚染の発生機構については、移動用スモッグチャンバー調査により、大気中の一次汚染物質である一酸化窒素(NO)がニ酸化窒素(NO2)に変化し、さらに同じ一次汚染物質である炭化水素(HC)と反応し、オゾン(O2)等のオキシダント、硝酸塩類及びアルデヒド類が生成することが確認された。また、オゾンの最高濃度と窒素酸化物(NOX)と炭化水素(HC)の初期濃度の関係を定量的に示すことを試みている。
気象との関連については、地域ごとの気象要素を考慮した光化学大気汚染発生の条件を調査しているほか、数値モデルによる解析的な光化学大気汚染の予測が可能になりつつあり、今後精度の向上を図ることとしている。
健康影響調査によっては、オキシダントが高濃度になるとともに粘膜刺激症状の訴えを中心とした被害届出者数が増加するということが確認されている(第2-2-8図)。
また被害の態様の個人差を調査することによって、起立性調節障害、アレルギー体質等の影響もある程度明らかとなってきた。
しかし、オキシダントの上昇時にも被害の届出があることや、オキシダントの主成分と考えられるオゾンのみでは目やのどの粘膜の刺激症状を十分に説明することはできないことから、光化学反応の過程において、中間的に生ずる励起物等(炭化水素などが紫外線を受けてエネルギーが高くなったもの)が光化学大気汚染の被害に関与していることも考えられる。ただし、これらの物質は反応性は非常に高いが定量が困難であるので、指標としてはオキシダントを採るとしても、その対策については単にオキシダントを減少させるための対策だけではなく、光化学反応に関与するすべての一次汚染物質について効果的な減少を図る必要がある。
植物影響については、オキシダント等の汚染物質により葉に可視害徴を発現しやすい、いわば大気汚染に敏感な植物を選び、それらへの被害程度と大気汚染物質濃度との関連の調査を実施した。
また、都道府県、読売新聞社の主催で、アサガオによる光化学スモッグ観察調査が49年から51年かけて行われた。
その結果によると、第2-2-9図のように光化学スモッグによるアサガオの被害はほぼ全国に広がっていることが報告されている。
以上に今までの調査によって明らかとなった知見を簡単に述べたが、今後は光化学汚染において健康被害をもたらす直接の原因を究明することに重点を置いた調査を行うこととしている。
(3) 光化学大気汚染対策の考え方
光化学大気汚染については、主として次の2つの異なった考え方がある。
1つは、窒素酸化物を放置しておいて、非メタン炭化水素だけを減少させればオキシダントを下げることができるという考え方であり、他の1つは、非メタン炭化水素を減少させるとともに窒素酸化物を減少させることが、オキシダントを下げる方法であるという考え方である。
2つの考え方の基礎になっているのは、ともに一次汚染物質である窒素酸化物と非メタン炭化水素を実験室に閉じ込め、紫外線を照射して人工的に光化学大気汚染を発生させる実験(スモッグチャンバー実験)の結果である。前者の根拠とするのは、アメリカのディミトリアデスらが行った実験であり、後者の根拠とするのは、環境庁が47年から行った実験である。両方の実験結果は第2-2-10図、第2-2-11図のとおりである。図はともに、横軸に非メタン炭化水素の濃度、縦軸に窒素酸化物の濃度をとり、実験の初期の一次汚染物質の濃度の交点に、実験中のオキシダントの最大値を数値で示している。図上の線はその数値の分布を示す等濃度線である。等濃度線が異なるのは、実験条件の範囲の違いなどによるものと考えられる。これらの実験では、実験装置の制約から実験時間がディミトリアデスの場合6時間、環境庁の場合は5時間に限定されていることと、実際の大気では光化学反応を起こしている間にも一次汚染物質の混入があることなどにより、実際の大気中の光化学反応過程と全く同一の反応とすることができないことに留意しなければならない。
これらのグラフに東京都内の現在の大気汚染濃度(6〜9月の午前6〜9時)の範囲を入れてみると、図中で示すようになる。
ディミトリアデスらの実験からは、東京の現状では非メタン炭化水素を減少させれば、オキシダントを減らすことができることは明らかである。
環境庁の実験では、非メタン炭化水素か窒素酸化物、あるいはその両方を減少させることによってもオキシダントを減らすことができることを示している。環境庁では二酸化窒素の有害性を重く見ているので、窒素酸化物対策に重点を置いているが、今後は炭化水素の現象にも力を入れていかなければならないことが示されている。
また、オキシダントの発生機構を見ると、非メタン炭化水素と窒素酸化物によってオキシダントが発生するが、同時にアルデヒドや硝塩酸も発生することが判明している。環境庁では光化学大気汚染予測モデル作成事業の中で、これらの数値シュミレーションを実施している。
アルデヒドや硝塩酸については、光化学大気汚染や湿性大気汚染による被害の一因とも考えられ、これらの防止も今後必要と考えている。シュミレーション結果によると、アルデヒドは炭化水素から硝塩酸は窒素酸化物から主に生成すると思われるのでこの点からも双方に着目して対策を進めていかなければならない。
環境庁は、窒素酸化物を抑え、非メタン炭化水素を抑えて、全体の反応量を抑えるという立場に立っている。
一方、アメリカでは、窒素酸化物排出規制はかえってオキシダント濃度を高くするとして、窒素酸化物はほとんど規制せずに、専ら炭化水素規制に重点を置いている。
このように我が国とアメリカとの対策が異なっているのは、両国の光化学大気汚染の発生条件となる汚染物質の濃度等が相違していたことによるものと考えられる。光化学大気汚染が極めて激しかった当時のロスアンゼルスは、現在の東京、大阪などと比べて、光化学大気汚染の重要な要因物質である窒素酸化物、非メタン炭化水素がかなりの高濃度であり、オキシダントの濃度も著しく高かった。この対策として、アメリカでは炭化水素の排出規制を強化することにより、ロスアンゼルス都心である海岸部においては、1時間値0.5〜0.7ppmといった非常に高いオキシダント濃度の出現は防ぐことができた(第2-2-12図)。
しかしながら、最近ロスアンゼルス地方の内陸部では、窒素酸化物濃度が上昇するとともに、海岸部とは逆にオキシダントの濃度が上昇するという現象が見られている。
第2-2-11図 O2
(4) 光化学大気汚染対策の推進
以上の考え方に基づき、次のように対策を進めている。
窒素酸化物については、別途ニ酸化窒素の環境基準が設定されており、これに向かって、移動発生源と固定発生源対策が進められている(前述3窒素酸化物対策参照)。
炭化水素については、炭化水素と光化学オキシダントの生成との定量的関係を求めて、中央公害対策審議会で総合的な検討がなされ、51年8月に光化学オキシダントの生成を防止するための大気中炭化水素の濃度の指針が提言されたところであり、この達成に向け、炭化水素の発生源対策を進めていくこととしている(後述6(2)参照)。
以上の要因物質対策のほか、緊急時対策として、夏期に光化学大気汚染発生地域で気象観測を行い関係地方公共団体に気象情報の提供を行ったほか、全国7か所の大気汚染気象センター及び9か所の大気汚染気象通報業務担当官署等で、光化学大気汚染の発生しやすい気象条件の解析と予報を行い、地方公共団体の公害防止担当機関に大気汚染気象通報を行っている。また高濃度の光化学大気汚染の発生が予想されるときには、「スモッグ気象情報」として放送機関により一般に発表しているとともに、移流、拡散反応を組み入れたシュミレーションによる予測システムの作成を試みている。
また、地方自治体において、予報体制の整備、保健対策の充実が図られている。
ここ数年の我が国の光化学大気汚染状況を見ると東京、埼玉地区における光化学大気汚染の発生しやすい気象条件に該当する日数に対する実際にオキシダント注意報を発令するに至った日数の割合は、横ばいないしは減少の傾向にあり、このことは、我が国の対策を評価する上で注目すべき点である(第2-2-13表)。
(5) 湿性大気汚染対策
49年7月初旬と、50年6月下旬から7月上旬にかけて、北関東と中心にいわゆる酸性雨による眼の刺激を訴える事例が発生した。
この現象は、当時の状況から特殊な気象条件により、高湿度大気中において、複雑な過程を経て生成された汚染物質に原因するものと考えられ、「湿性大気汚染」と称することとした。
湿性大気汚染は、その発生メカニズム、眼等に対する刺激原因物質等が十分解明されていないので、対策のためにはこれらの究明が必要である。
このため、50年度の調査結果を踏まえ、51年6月から関東一円において、
ア 係留気球を用いた上空のガス状物質及び粒子状物質の測定並びに雨水及び雲水中の成分分析
イ 地上における大気汚染物質及び雨水の調査分析
ウ 気象条件調査
等の実地調査を行うとともにチャンバーを用いた酸性エアロゾルの形成過程の実験も行った。
なお、51年は天候不順等のため湿性大気汚染などによる被害の届出はなかった。