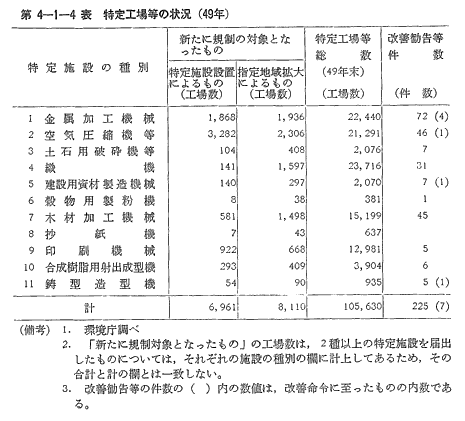
2 騒音防止対策
工場・事業場騒音、建設作業騒音、自動車騒音等については「騒音規制法」によって規制が行われている。
(1) 工場・事業場騒音
「騒音規制法」により騒音について規制対象とされているのは、法に定められた特定施設を設置している工場又は事業場のうち、都道府県知事が騒音を規制する必要がある地域として、指定した地域に立地しているものである。規制対象となっている工場及び事業場の数は49年末において105,630に及んでいる(第4-1-4表参照)。また、都道府県知事による地域指定の実施は、49年末現在で、47都道府県において、563市576町86村23特別区に及んでいる。これらの工場・事業場に対しては、規制基準の遵守義務が課せられており、都道府県知事は、計画変更勧告や改善勧告、更には改善命令を行うことができる。49年中に発せられた改善勧告等は225件、改善命令は7件となっている(第4-1-4表参照)。
なお、現在規制の対象となっていない板金及び製缶作業場、自動車修理作業場等からの騒音についてもかなり問題が発生しているので、これらについても、「騒音規制法」で規制すべく必要な調査を行った。
また、住工混在の土地利用の現状も騒音公害の発生する大きな要因になっており土地利用の適正化が強く望まれている。具体的には工場団地の整備、育成等が今後の公害対策の1つの重要な手段となっているが、騒音が問題となる工場・事業場の多くは中小規模であり、資金的な面から移転が困難な場合が多いので、公害防止事業団等において、共同利用建物の建設、あるいは、工場団地の造成を行い、中小工場にあっせんしている。
公害防止事業団が49年度までに金属加工業等騒音発生型の工場の移転のために実施した事業は、共同利用建物の建設12か所、工場団地の造成51か所である。また、49年度には中小企業金融公庫、国民金融公庫等からも公害防止関係融資として総額で240億円余が融資されている。
(2) 建設作業騒音
建設騒音は、工場・事業場騒音と異なった特殊性を有している。すなわち、建設作業自体は一時的なもので短期間で終了するのが通例であるが、建設作業の場所等に代替性がない場合が多く、工場騒音のように敷地の広さ、建屋の配置、しゃ音壁などの操作により騒音を防止することができにくため、今後における施工方法の改良、開発を待たない限り建設騒音の防止については極めて困難な面が多い。
産業活動が活発な我が国においては全国いたるところで建設作業が進められており、全国的に騒音公害が発生している。建設作業についても、「騒音規制法」によって対象となるものを特定建設作業として定めている。これらの建設作業の規制については、規制される騒音の大きさの基準も工場騒音の場合よりも高く、また、規制の方法も音を下げることと同時に夜間作業や日曜、休日における作業の制限といった面に主眼が置かれている。都道府県知事は、特定建設作業に伴い発生する騒音が一定の基準に適合しないことにより生活環境が著しく損なわれる場合においては必要な勧告、命令の措置を採ることができ、49年中には6件の勧告が実施されている(第4-1-5表参照)。
(3) 道路交通騒音防止対策
自動車騒音は、エンジン、吸排気管、ファン、ラジエーター、トランスミッション、タイヤ等から発生するが、実際には、自動車の種別、走行条件、道路構造等の各種の変動要素が複雑に絡み合って道路交通騒音となっている。
道路交通騒音の低減対策として、自動車本体から発生する騒音の大きさそのものを減らす対策として、特殊自動車を除くすべての自動車及び原動機付自転車を対象として、新車及び使用過程車について、許容限度を設定して規制が実施されてきたが、当面、道路交通騒音に対する寄与度が特に大きい大型自動車及び二輪車に重点を置く許容限度の強化を行うこととし、50年9月に第4-1-6表のとおり加速走行騒音を3ホン程度低減させる許容限度の改正を行い、乗用車及び小型トラックを除く車種について51年1月から、乗用車及び小型トラックについては52年1月から規制が実施されることとなった。この規制は、自動車が市街地を走行する際に発生する最大の騒音である加速走行騒音について規制を強化するものであり、現在の騒音低減技術から見ても、また国際的に見ても厳しい法的規制である。
更に、長期的観点から複雑な発生機構を有する自動車騒音の規制強化を図るべく、中央公害対策審議会自動車騒音専門委員会において、「騒音規制法第16条第1項に基づく自動車騒音の大きさの許容限度の設定についての長期的方策はいかにあるべきか」について審議を行っている。
このような発生源対策に加え、都市内においては、住みよい生活環境の確保をも目的とした都市総合交通規制が実施されており、幹線道路においては、最高速度の制限、信号機の系統化、大型車の通行区分の指定等の騒音対策を、住居地域内の道路については、通過交通の排除や歩行者用道路の設定等の騒音防止に寄与する対策が推進されている。また、高速道路等自動車交通量の多い幹線道路と住居が近接している地域では、しゃ音壁の設置等の対策に加え、49年度から環境施設帯を設置する施策が進められているが、長期的には、土地利用の適正化、都市再開発等の道路周辺における環境整備が必要である。