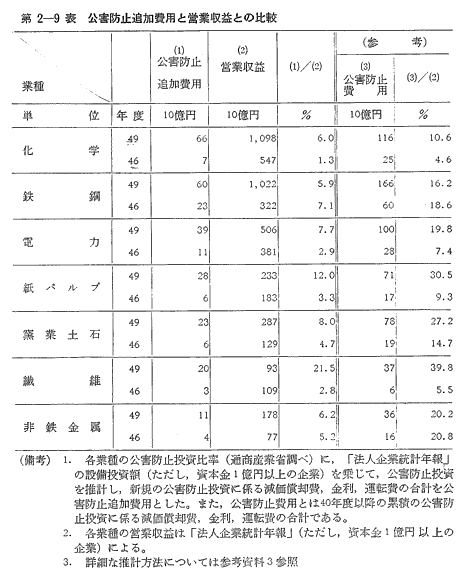
2 公害防止費用の増大
これまで見たように、公害防止設備投資の伸びが鈍化してきているが、このことから直ちに企業の公害防止費用負担が少なくなると見ることはできない。すなわち、企業の公害防止費用は、単に新たな公害防止投資や公害防止投資比率の大きさで決まるのではなく、投資に伴う減価償却費や金利、運転費及び投資とは直接関係しない燃料転換や公害防止のための研究開発等に要する経費より構成されるからである。
このような公害防止費用のうち、公害防止投資とは直接には関係しない燃料転換等に要する費用については資料上の制約もあるので、ここでは、公害防止投資に関する減価償却費、金利、運転費の合計額について、化学、鉄鋼、電力、繊維、紙パルプ、窯業土石、非鉄金属の7業種を対象として試算してみることとしよう(参考資料3参照)。
なお、この試算は各業種(ただし、資本金1億円以上の企業を対象)について行ったものであり、プラントごとの公害防止費用とは異なっている。
まず、新規の公害防止投資によって追加的に必要となる費用について見ると、40年度においては、いずれの業種でも10〜20億円で、売上原価や営業収益にはほとんど影響を及ぼさないオーダーである。しかし、近年になって、この費用は企業経営上無視し得ない規模になりつつある。
第2-9表は、各業種の公害防止追加費用と営業収益を46年度と49年度について比較したものであるが、鉄鋼、化学の追加費用は600億円程度でその額は大きいが、営業収益が1兆円を超えているので、費用の収益に対する比率は約6%であり、やや影響は小さいと見られる。しかし、紙パルプでは、追加費用は、収益の1割を超えており、窯業土石、電力でも約8%に達するなど、その影響度合いが大きくなっている。更に、繊維では、49年度の収益は、個人消費の停滞を主因として、前年度の3分の1以下に減少したために、追加費用の収益に対する比率は、実に2割以上に達している。一般に、不況期になって収益が減少すると、企業の費用負担感は強くなるが、公害防止のための費用もその例外ではないといえよう。
次に、累積した公害防止投資によって生ずる公害防止の費用を売上原価と比較してみると、第2-10図に見られるように、売上原価に占める公害防止費用比率は、傾向的に上昇してきている。なかでも、窯業土石、電力、紙パルプの3業種は比率においても高い上に、それが急カーブで上昇してもおり、49年度には3%以上となっている。また、鉄鋼、非鉄金属は、46年度まではその比率の上昇が急激であるが、近年は、上昇度合いがやや鈍っており、逆に、化学、繊維では、49年度の比率が1%強という低い水準ではあるが、その上昇度合いは、他の業種とそん色のないくらい急テンポである。
このように企業の公害防止費用の負担の割合は、近年、急速に高まってきているが、環境基準の達成状況等から見て、環境保全のためには、今後一層の努力が必要とされており、それに対応した環境保全施策の推進により、公害防止投資をなすべき分野も、また、その額も決して小さくないと見込まれる。
例えば、窒素酸化物については、環境基準の達成を目指して、今後更に規制強化が進められることとなるが、これに伴い、燃焼方法の改善のための装置、排煙脱硝装置の開発や建設が進められることになり、これらに要する総投資額はかなりの規模になるものと見込まれる。
また、BODなどについて一部業種について適用されている「暫定基準」は、51年6月から「一般基準」に切り替えられることとなっており、更に「下水道法」の改正強化の方向ともあいまって、汚濁水の排出規制の強化が水質汚濁防止施設への投資増大をもたらすこととなろう。
更に、産業廃棄物処理施設への投資額は、現在、年間で500〜600億円にすぎないが、後述のように、年間約3.4億トンに上る産業廃棄物発生量の大きさや「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の改正強化の方向から見て、その投資額は、もっと増加していくこととなろう。
他方、前述したように、これまで増大してきた公的部門による環境保全経費の増大も、今回の不況を契機として一つの曲がり角に差し掛かっている。すなわち、公的部門の環境保全経費は、国民の税負担及び国民の貯金等をもとにした財政投融資によって賄なわれるものであり、今後の安定成長への移行によって、これまでのような租税の大幅な自然増収などを期待することが難しくなってきているからである。
51年1月に発表された「昭和50年代前期経済計画概案」によれば、51〜55年度の我が国経済の平均成長率は、実質で6%強、名目で13%強(41〜47年度は、各々10.8%、16.4%)であるが、そのフレームの下での今後5か年間の公共投資総額は、50年度価格で100兆円である。前回の「経済社会基本計画」における公共投資額90兆円(47年度価格)は、50年度価格ではおよそ131兆円と見込まれ、今回の計画額は実質的に厳しいものとなっている。そのなかにあって、下水道、廃棄物処理施設、都市公園、自然公園の整備に要する環境保全関連の公共投資額は、9兆8,900億円で、その全体に占めるシェアは、9.9%となっており、「経済社会基本計画」の8.5%より高く、環境保全に関連した社会資本の整備がより重点的に進められると見ることができよう。しかし、「経済社会基本計画」における環境保全関連公共投資総額は、47年度価格で7兆6,900億円であり、これを50年度価格に換算すれば、およそ11兆2,000億円に上るものと見込まれるので、今回の9兆8,900億円はやはり厳しいものとなっていることが分かる。
したがって、下水道の整備を例にとれば、その事業の進ちょくに際しては、水質の改善を図るために、まず、公害防止計画策定地域などにおいて重点的に下水道の整備を進めることが必要になる。
また、新幹線、高速道路等の交通施設については、騒音防止のための周辺対策等環境整備のための費用が相当額に上ると見られるが、こうした費用を利用者に負担させることによって外部不経済を内部化させることを考慮すべきであろう。
以上のように、公的部門の環境保全経費等は、今後、これまでのような「高度成長」を期待できない状況にある。今後の環境保全経費等については、まず、負担面において事業者等の汚染者に究極的な負担をさせることにより、資金の制約を少しでも小さくするとともに、更に、効果対費用の比が高い代替案を検討するというプロセスを経た厳しい選択を行うことが要請される。