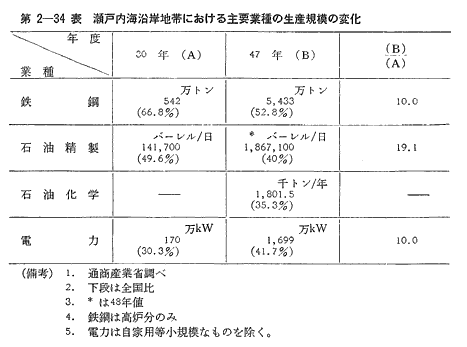
2 開発と環境アセスメント
(1) 環境アセスメントの意義
以上みてきたように従来の工業開発や高速輸送網の急速な整備は、その結果として周辺地域に環境破壊及びそれによる各種の公害をもたらす事例を生ずることとなった。環境アセスメントは、こうした開発のあり方を反省し、今後の開発に際し、それが環境に与える影響を、あらかじめ科学的、総合的に調査し、環境破壊を未然に防止しようとするものである。先に四大公害裁判の一つとして社会的にも大きな問題となった四日市公害裁判の判決は、その判決理由において「生産過程において、いおう酸化物などの大気汚染物質を副生することの避け難い被告ら企業が新たに工場を建設し、稼動を開始しようとするときは、右汚染の結果が付近の住民の生命・身体に対する侵害という重大な結果をもたらすおそれがあるのであるから、そのようなことのないように事前に排出物質の性質と量、排出施設と居住地域の位置・距離関係、風向、風速等を総合的に調査研究し、付近住民の生命・身体に危害を及ぼすことのないよう立地すべき注意義務があるものと解する。」と述べ、その欠如をもって被告企業の「立地上の過失」があるとしたが、これは、コンビナート建設等の工場立地に当たり環境アセスメントの必要なことを判例上明確にしたものとして注目に値する。環境アセスメントがいかに重要であるかということを瀬戸内海地域を例にとってみることにしよう。
瀬戸内海は、古くから我が国の代表的な景勝地として、貴重な漁業資源の宝庫として、また、海上交通の衝として重要な役割を果たしてきた。瀬戸内海において、30年以降の経済の高度成長期を通じ、海岸海域の埋立、塩田や農地の転用等による重化学工業化が推進され、工業の集中と人口の増大がもたらされた。30年から46年にかけて沿岸11府県の工業出荷額は24,320億円から248,079億円へと10.2倍に増大したが、更に主要産業の生産規模についてみると、第2-34表のとおり瀬戸内海の重化学工業化がいかに急速に進められたかがわかる。これは、我が国の重化学工業が飛躍的成長の時期にあったこと、埋立に適した遠浅の海岸や2千万人を超える沿岸人口を擁した内湾として瀬戸内海が工業立地上極めて好条件であったこと、新産業都市、工業整備特別地域22地域の3分の1に当たる7地域が指定されている等工業開発を促進する措置がとられたこと等によるものと考えられる。
しかしながら環境保全への十分な配慮を欠いた瀬戸内海地域の急速な工業の成長は、一方で様々な環境上の問題をひきおこすこととなった。
その第1は、各種汚染の増大である。
第2-35表はCOD、いおう酸化物、窒素酸化物について排出量を試算したものであるが、沿岸地域に立地した産業に起因するCOD発生負荷量は、1,350トン/日と推定され、環境基準上B類型以上に当たるCOD2ppm以上の海域は、瀬戸内海全域の26%に当たる5,700k?に及んでいる。
第2は、上記水質悪化及び埋立て等による漁場環境の悪化である。瀬戸内海においては、30年から45年にかけて工業用地造成のため16,312haにわたる埋立てが行われたが、これらの埋立て等により魚の産卵に適した多くの藻場が消滅することとなり、魚類の生育条件の悪化をもたらした。また、水質の悪化や赤潮の発生による高級魚の漁獲高の低下、養殖魚の被害及びタンカーによる油濁による被害が毎年かなりの額にのぼり、瀬戸内海における漁業は大きな被害を受けている。
第3は、自然景観の損傷、汚染によるレクリエーション価値の減少である。瀬戸内海は、国立公園として多数の国民に利用され嘆賞されてきたが、埋立てや砂利採取による自然海岸や海水浴場の消滅、景観の損傷が著しくなっている。また、大気汚染による生活環境の悪化や農作物等の被害を生じている。
以上のような現象は、瀬戸内海は、島しょが多く海水の交換性に乏しい閉鎖的な海域であること、平野部に山地が迫っている地形がほとんどであること、等の環境条件を十分配慮することなく、鉄鋼、電力、石油化学、紙・パルプ等の環境資源多消費型産業の立地を行ってきたために生じたものであり、工業開発に際して十分な事前の環境影響評価を行わなかったことが今日の瀬戸内海の破壊をもたらした最大の原因であるといえよう。
このような反省から瀬戸内海の回復を望む国民的要望が高まり、48年10月瀬戸内海環境保全臨時措置法が公布され、水質汚濁防止法の規制対象となる一定規模以上の企業立地に際して環境アセスメントが義務づけられる等瀬戸内海の環境保全を目的とした各種の施策が進められることとなった。アメリカ・オレゴン州におけるウィラメット川の浄化が半世紀を要したという例をみてもわかるように、一たん破壊された環境を回復することは容易なことではなく、瀬戸内海についても、今後の忍耐強い努力が必要である。
(2) 環境アセスメントの現状と問題点
瀬戸内海の例からも明らかなように、環境に対する影響を事前に十分に評価することなく開発行為が行われる場合、その影響は広範に、かつ、深刻に及び、それを原状に戻すことは容易なことではない。したがって、公害や自然環境破壊を未然に防止することが今後の国土の環境保全施策の基本とされなければならないが、環境アセスメントは、このための重要な基礎である。
既に、新産業都市、工業整備特別地域、大規模工業基地等の工業地帯については、39年の三島沼津地域における産業公害総合事前調査を初め、通商産業省において40年以降約50地域にわたって事前調査が工業開発に伴う産業公害を防止する目的で、大気関係では主としていおう酸化物を、水質関係では主としてCOD(又はBOD)を対象として実施されてきた。これは工業開発に関する環境アセスメントであるが、その他各種公共事業をも対象とするとともに自然環境等をも評価対象に含めた本格的な環境アセスメントの実施が指向されるようになったのは、47年6月の閣議了解「各種公共事業に係る環境保全対策について」のなかで環境アセスメントの必要性が確認されて以来のことである。この閣議了解に基づき環境庁及び各事業所管省庁において港湾計画、電源立地、大都市圏の工業団地造成事業等についてその実施の促進が図られている。この際のチェックの一例としては大気(SOx、NOx、浮遊粒子状物質、CO、HC、光化学オキシダント等)、水質(健康項目、BOD又はCOD、SS、温排水等)、自然環境(景観、レクリエーション、鳥獣類、樹林地等)、騒音、廃棄物、地盤沈下等の項目について、事業種別、規模等に応じ、その現状、環境目標、将来予測、防止対策等を第2-36図に示すような考え方に立ってみることとしている。
また、先の第71回国会で成立した瀬戸内海環境保全臨時措置法において特定工場の許可申請に際して環境影響事前評価に関する書類の添付が義務づけられるとともに工場立地法においては、前記産業公害総合事前調査が法制化されることとなった。更に、公有水面埋立法の一部改正法においては、環境保全に配慮する規定が盛り込まれるとともにその具体化として同法施行規則において環境保全に関し講じる措置を記載した図書が埋立免許申請の際の必要書類として規定される等、環境アセスメントに関する法制度面での整備も進みつつある。
環境アセスメントは、我が国においても逐次その実施が進められ、手法の開発や体制の強化も図られてきており、また、各部道府県等においてもその必要性が強く認識されつつある。しかしながら現在の環境アセスメントの実情については、なお幾つかの問題を残している。
第1は、環境アセスメントの手法が十分確立されていないことである。開発事業の実施に際して環境アセスメントを効果的に行うためには、地域開発、空港、新幹線、高速道路の建設、発電所の新増設や宅地開発等事業の種類及び事業実施地域の特質等に応じてその手法や調査項目等が明確になっていることが必要であるが、現在この点十分なものがない現状である。その影響予測の方法についても、大気汚染、水質汚濁の主要問題については、シミュレーション等による予測方法が開発されつつあるものの、手法的にはなお問題を残しており、また、計量化し難いもの、特に自然環境への影響等シミュレーションによる予測が困難なものもあり、今後これらをも含めた総合的な環境保全の視点に立つ環境アセスメントの手法の確立が必要となっている。また、環境基準のような客観的な基準のない環境要素についての評価方法をどうするかということも今後の大きな課題である。
第2は、環境アセスメントの実施時期の問題である。環境アセスメントは、様々な効用を有しているが、一つには開発主体自らが環境保全に配慮しつつ計画決定を行う際の一手段を提供するものであり、このためには環境アセメントを実施する時点は、その結果を計画決定に適切に反映させうる段階であることが必要とされる。第2-37図は大都市圏における工業団地の造成過程を示したものである。この場合、現在は、工業団地造成に関する都市計画決定から施行計画決定の段階では、アセスメントは必ずしも十分行われておらず、処分管理計画の段階で行われることが多い。このため、その結果を計画に反映しにくい現状となっている。一方、環境アセスメントは、計画の熟度が低く、発生源条件等の前提条件が不明確な場合には、内容が不十分なものとならざるを得ないという性格をもっている。したがって、今後の環境アセスメントの実施に当たっては、構想の段階、基本計画の段階、実施計画の段階等計画の進行と熟度に応じて各段階ごとに精度を高め、評価、再評価を繰り返し行うことが必要である。
第3は、住民の理解と意見を求める問題である。一般に、開発は当該地域の住民に広範囲な影響を及ぼすという点で、科学技術等の分野における専門家の検討とあわせて、地域住民の意向が基本的に重要である。このためにはその前提として開発の内容及び開発が環境に及ぼす影響について、住民に適切な判断を可能にするような情報を提供し、全体として最も望ましい意思決定がなされるような努力が必要であろう。
環境アセスメントについては、今後検討すべき問題も多いが、その目指すべき方向としては、単に、大気汚染や水質汚濁等の主要汚染因子についてのみでなく、自然環境の保全や騒音防止問題等を含めた総合的な環境保全の視点に立って実施されなければならない。
また、環境アセスメントは、その結果を開発計画にフィードバックし、しかも計画の熟度が高まるごとに再評価を繰り返すという方法で実施し、開発に伴う環境保全の確保に万全を期すことが重要であり、同時に、このような方法をとることにより、環境に関する科学的知見がなお不十分な現段階におけるアセスメントの結果について、その確実性を高めていくことが可能となろう。