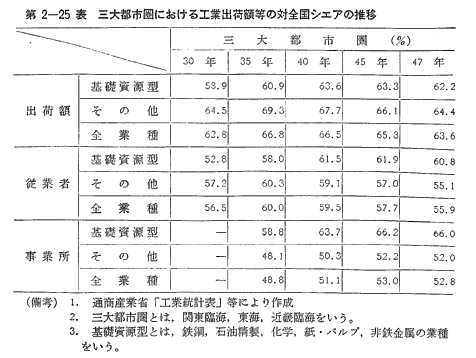
1 各種開発と環境汚染
(1) 工業開発の動向と環境汚染
最近における工業出荷額の動向をみると関東臨海、東海、近畿臨海の3地域の割合は第2-25表によっても明らかなように、40年頃から若干その比重が低下してきているものの、依然として極めて高い集中度を示している。これによって3地域の所得も1人当たり35年の14万3千円から46年度の60万6千円へと約4.2倍に上昇したが、このような工業開発の過程で必ずしも十分な環境保全対策がとられてこなかったため、同時に環境汚染も著しく深刻化することとなった。第2-26表はいおう酸化物及び窒素酸化物の可住地面積当たり排出量を試算してみたものである。これによると、30年から46年にかけていおう酸化物は16.2トンから131.3トンに、窒素酸化物は1.9トンから49.8トンに増大しており、全国平均でみた増大量と比較してはるかに大きいものとなっている。
なお、汚染濃度についても、いおう酸化物は、近年改善の傾向にあるものの、全般的にはほとんどの地域で新たに強化された環境基準を超えているとともに光化学スモッグ等の複合汚染の広域化及び窒素酸化物が増加傾向にある等問題の多い状況にある。
次に、これら3地域以外においては、新産業都市、工業整備特別地域等において計画的な工業開発が進められてきたが、これらの地域のうち、一部では、重化学工業の急速な拡大や生活基盤整備の立遅れの傾向がみられたこと等により大気汚染や水質汚濁等の環境汚染が進行した地域もある。
また、工業開発の最近における他の特徴は、これら地方の開発の進行により3地域の集中の度合が若干低下していることである。これは第2-27図のごとく最近の工業立地動向をみると明らかであり、これを鉄鋼、石油化学、紙・パルプ等の基礎資源型産業の立地についてみても、三圏全体で43年の48.8%から47年には41.4%と同様の傾向がみられる。
一方、現在、苫小牧東部、むつ小川原等、地方圏における大規模工業開発が計画されているが、このような工業の地方進出は、大都市圏における新規土地取得の困難、水不足、雇用難、各種公害規制の強化等により今後更に促進されるものと考えられる。
これらの地方における工業開発に当たっては、従来の公害発生のパターンの繰返しとならないよう、関連周辺地域をも含む環境アセスメントの実施、関連対策の検討等事前の措置を十分行い環境保全を図りうる範囲内で開発を行うことが必要である。
工業開発における最近の特徴のもう一つは、環境資源多消費型産業の立地が公害やエネルギー等の面からなかなか進まないという傾向がみられることである。例えば、火力発電所の建設は、電源開発調整審議会において47年度、48年度の2年間に、59か所1,091万kWが承認されたが、これは計画2,803万kWの38.9%に過ぎず、それ以前に承認になったもので、未着手のものが350万kWもある。昨年12月の石油審議会においては、16製油所113.3万BPSDの設備の新設が認められたが、石油危機等の問題もあり、行政指導により工事施工を繰り延べているという状況にある。
これらの国内事情も一要因となって、近年企業の海外立地、特に開発途上国への進出が第2-28図にも示すように強まっており、今後一層増加することが予想される。開発途上国では「環境問題の大部分は低開発から生じている」と人間環境宣言にも述べられているように、開発が最も重要な課題となっているが、これらの国に対する我が国の企業進出が公害源として非難されないよう、企業において相手国の主権を前提としつつ、公害防止のための最良の実際的な措置をとることを基本原則として、国としても必要な情報や技術の提供等による国際協力を強化していく必要がある。
(2) 高速輸送機関による交通公害の激化
道路、空港、鉄道等の輸送網の整備は、第2-29図にみられるように年平均増加率約20%の投資により進められてきたが、近年これらの整備に伴い、輸送機関が環境に与える影響について問題とされる事例が増加してきている。道路建設等が自然環境に及ぼす影響の問題については、前に述べたので、ここでは、現在、これら輸送機関網の整備とその利用を巡って生じているその他の交通公害問題についてみてみよう。
その第1としては、道路の整備に伴う自動車交通量の増大による自動車公害の問題がある。
我が国における高速自動車道の整備状況は、現在、第2-30表に示すとおりであり、主要道路における自動車交通量は第2-31表のように年々増大している。自動車交通は周辺の環境に各種の影響を与えているが、試みに規制の効果等を考慮しないで、自動車交通量等から自動車の排出ガス量を主要道路(高速自動車道、国道、主要地方道)について計算すると、46年度においておよそ窒素酸化物60万トン/年、炭化水素77万トン/年、一酸化炭素347万トン/年程度と推定され、環境に対し相当の汚染をもたらしていることがわかる。
また、自動車交通による騒音も大きな問題となっている。例えば、東京都が47年度に環状7号線道路について行った調査によると道路端の騒音レベルは1日中を通じて70〜80ホンの間にあり、第2-32表にみるようにほとんどの測定地点で環境基準を上回っている。
第2に航空機による騒音公害の問題がある。現在航空運送事業の用に供されているジェット機が就航している空港は16か所あるが、騒音による影響が最も問題となっている大阪国際空港においては、運輸省の調査によると、WECPNL(加重等価感覚騒音レベル)90以上の地域面積は、4.7k?に及び、この範囲の居住人口は約3万8千人となっている。また、48年度に航空公害防止協会が同空港周辺住民について行った調査によると、多くの住民が、会話、テレビ、電話障害等各種の日常生活の支障のほか、一部集中力の減退、不眠、頭痛等の影響を訴えており、騒音問題の深刻さを示している。これについては、現在、移転補償、教育施設等の防音工事等の騒音対策が進められている。また、現在関西国際空港の建設が計画され、運輸省において環境アセスメントも行われているが、その建設に際しても、環境保全対策を強力に推進していくことが必要であろう。
第3に新幹線鉄道による騒音公害等の問題がある。本鉄道は既に東京−岡山間の676kmが営業されているが、騒音公害が各地で問題とされるに至っている。
環境庁が47年度に行った実態調査によると新幹線による騒音は、第2-33図にみるように広範囲に影響があり、一部沿線地域の住民に対し、大きな影響を与えている。このような現状に対処するため、環境庁は47年12月新幹線鉄道の騒音に関し、緊急対策の勧告を行っているが、このなかで示されている住居等の存する地域を対象とした当面の暫定基準の80ホンですら沿線のかなりの地域で超えている状況にある。