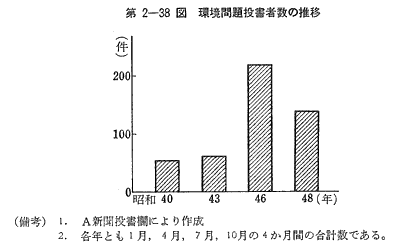
3 環境問題と地域住民
(1) 環境問題を巡る住民の動き
先にみてきたように従来の我が国の開発が環境資源多消費型産業や各種公共事業等を中心に行われる一方、事前の調査及び環境保全対策が必ずしも十分でなかったために、この過程で各種公害の激化や自然環境の破壊等マイナス面が顕在化し、これらを契機として国民の意識が急速に変化することとなった。
全国紙の投書欄における環境問題投書者数の変化をみても第2-38図のように最近は若干減ってきているものの、光化学スモッグ等が問題となった45年頃から急激に増大してきている。公害についての苦情件数も全体で41年度の20,502件から47年度の87,764件へと6年間に4.3倍に増大するとともに都道府県別では、この5年間の増加率は、鹿児島県78倍、秋田県77倍、栃木県12倍、新潟県11倍と地方県における増加が著しく、環境問題は全国的な広がりをもつようになってきている。国民の公害に対する不安感にも根深いものがある。例えば、総理府が48年11月に行った世論調査によると、第2-39図にみるように58%もの者が公害が自分や家族に悪影響を与えているのではないかと不安感を抱いているとともに将来の公害についても国民の半数以上にわたる53%の者が「ますますひどくなる」と予想している。また、同調査では、経済活動を多少犠牲にしても環境保護を優先させるべきであると考えている者が50%と、経済活動を重視するとする者20%を大きく上回る結果となっているが、これらの事情を背景に、近年環境問題を巡る住民運動が各地で増大している。これは、公害に対する住民団体数が第2-40表にみられるように急速に増大してきていることにも表れているが、地方自治協会が住民運動一般について47年度に秋田県と兵庫県を対象に行った調査によっても、公害や自然環境等環境問題が原因となっているものが兵庫県では55.2%、秋田県でも34.6%と首位を占めており、これによっても環境問題が地域住民にとっていかに重大な問題となっているかがわかる。
これら住民運動が求めているものとしては、第2-41図にみるように声明や法制化対策の強化のほか、原因行為に全面的に反対しているものがかなりあり、兵庫県のみをとると第1位を占めている。このように住民の開発や公害被害等に対する姿勢には厳しいものがあり、現在、大規模開発や火力発電所等のほか、新幹線や高速道路等の建設を巡って、環境問題を理由として住民との間に意見の対立を生じている事例がかなりの数にのぼっている。このような問題に関しては、現行制度上都市計画策定における計画案の公衆への縦覧、意見提出、公聴会の開催規定や公共用地の取得に際しての住民への説明に関する規定等一定の手続を定めているものもあるが、このような手続規定のないものについても、住民の意見を反映させるための説明会の開催等様々な努力が払われているものもある。また、昨年制定された瀬戸内海環境保全臨時措置法においては環境影響評価の結果の一般への縦覧を義務づけているが、これは瀬戸内海における環境問題に関して住民の意見反映の手続を定めたものであり、今後はその他のものについても、このような方向に向ってのルールの確立が必要であろう。
(2) 環境関係訴訟の動向
環境保全に関する地域住民の国や地方公共団体及び企業に対する要望は、多様化し高度化してきているが、これらの要望が行政的対応や企業努力等によっては十分満足されない場合、直接的な反対運動等のほか裁判という方法がとられることがある。先の四日市裁判や水俣裁判等のいわゆる四大公害裁判は、その被害が広範囲にわたることや人命や健康に及ぶものとして、環境行政上も一転機を画するものであったといえるが、これらはいずれも企業活動に起因する公害による健康被害に対する損害賠償請求を中心とするものであった。これら裁判による救済が公害被害の事後的、かつ金銭賠償的性格を有するものであったという点が大きな特徴であった。しかしながら最近の環境関訴係訟の動向をみると、損害賠償も依然として大きな比重を占めているものの、幾つかの新しい傾向がうかがわれる。
その一つは、請求の内容が従来の事後的金銭的なものから、原因活動の事前の差止め等未然防止的なものとなってきていることである。その二つは、従来の公害訴訟の対象が企業活動による公害を対象としている場合が大部分であったのに対し、最近では、国や地方公共団体の活動、公共事業を対象とするものが増大していることである。
これらの点については、第2-42表のように火力発電所、空港及び高速道路等の建設、利用を巡って差止め等を求める訴訟が増大していることに示されている。
また、大阪国際空港訴訟事件については、本年2月第1審判決があり、午後10時から翌朝7時までの空港使用の差止めと過去の損害賠償を認めたが、本件については、原告及び国ともにこれを不服として控訴し、目下大阪高等裁判所に係属中であり、最終的な結論を得るに至っていない状況にある。
その三つは、環境保全という価値が最も重視されるべきものと考えられるようになってきていることである。行政訴訟ではあるが、48年7月東京高裁から判決のあった日光太郎杉事件は、自然景観の保護を優先させるか自動車交通の渋滞の解消を図るべきかということで社会的にも注目を集めた事案であったが、判決は、被告は事業認可に際し「本件土地附近のもつかけがえのない文化的諸価値ないしは環境保全という本来最も重視すべきことがらを不当、安易に軽視し、その結果右保全の要請と自動車道路の整備拡充の必要性とをいかにして調和させるべきかの手段方法の探究において、当然尽すべき考慮を尽さなかった」という理由で、原告の請求を認めた。環境保全を重視した考え方は、46年7月大分地裁から判決のあった大分県臼杵セメント事件判決においても示されている。
今後は、以上みてきたような最近の訴訟の動向等も勘案しつつ、各種公共事業の実施に際して、あらかじめ十分な環境保全措置を講じていく必要があろう。