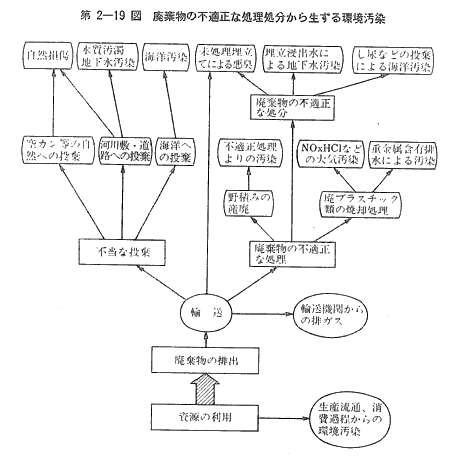
2 廃棄物等を巡る環境問題
廃棄物の排出量の増大は、最終的な自然還元に至るまでに様々な経路を通じて多様な環境問題をひきおこすこととなるが、その発生の態様は第2-19図にみるように大別される。
まず、自然環境への不当な投棄による問題についてみると、警察庁の調べによれば、第2-20図のように48年の廃棄物処理法違反件数は、1,056件に達し、前年の420件に比べ2倍以上となっている。一方、海洋については、48年に海上保安庁が確認した汚染発生件数は、2,460件で逐年増加の傾向にあり、同庁が送致した油及び廃棄物等の不法排出又はその容疑のある事犯は48年には1,064件に達し、前年の803件を大幅に上回っている(第2-21図)。廃棄物の自然環境への投棄の結果、第2-20図に示した警察庁の調べによってもわかるように、水質汚濁、悪臭、土壌汚染等をひきおこしている。
また、観光客の投げ捨てた空かん等により国民共有の財産である自然の景観が損傷されてきており、例えば、阿蘇国立公園の九重地区やまなみハイウェイで回収された廃棄物は、46年でハイウェイ1km当たり6.9トンにのぼった。
次に、不適正な処理から生ずる問題がある。産業廃棄物については、自社敷地内に野積みしておくケースがみられるが、野積みを放置すれば、悪臭や地下水汚染等につながることとなる。
また、家畜ふん尿は、有用な有機質肥料であるため、主として土壌還元利用による処理がなされているが、一部適正な処理が行われていないため、水質汚濁、悪臭等の環境汚染問題の発生がみられる。農林省の行った「畜産経営に起因する環境汚染問題発生状況に関する調査」によれば、47年の汚染問題発生件数は10,212件に達し、35年に比べ約2倍の増加となっている。汚染問題発生件数の地域的推移をみると45年には都市近郊の占めるウエイトが高かったが47年には平地農村や山村の割合が高まっており、汚染問題発生地域の広がりがみられる。
一方、廃棄物を処理するうえにおいて清掃工場を建設し、運営していくことが必要であるが、最近、清掃工場から排出される塩化水素ガスや重金属等の汚染物質が問題となっている。このような事態は、廃棄物中に塩化ビニル等が多量に含まれるようになったためであるといわれるが、環境保全のための施設である清掃工場が大気汚染や水質汚濁の発生源となることは防がなければならない。第2-22図は、東京都における清掃工場の排ガスの分析結果であるが、分別収集等の対策を反映して汚染物質の排出は減少の傾向にある。
更に、廃棄物の最終処分の形態としては、埋立処分と海洋投入処分とに大別される。
まず埋立てについてみると、第2-23図のように、汚でいの約53%、一般ごみの約34%が埋立処分されている。廃棄物の不十分な前処理や不適切な方法による埋立てが行われる場合には、埋立浸出水により地下水を汚染したり、嫌気性分解の結果発生するガスにより悪臭をもたらしたり、管理の不十分から、ネズミや害虫を発生させたりすることとなる。
また、海洋投入についてみると、海洋汚染防止法施行令により廃棄物の排出規制が行われた47年6月25日から同年12月までの間に法令の定める基準に従い排出された廃棄物は、廃酸・廃アルカリ等の産業廃棄物が275万トン、し尿等の一般廃棄物が305万トン、しゅんせつ活動に伴う水底土砂が2,347万トンであり、合計2,927万トンにのぼっている。瀬戸内海へのし尿の投棄についてみると、同期間に62.9万トンが排出されていたが瀬戸内海の富栄養化の進行、赤潮による被害の多発にかんがみ、48年4月からし尿の瀬戸内海への投棄が禁じられることとなった。
海洋環境を保全するためには、できうる限り、廃棄物投棄による汚染負荷を増大させないことが必要であり、適正な処理方法が確保される限り、埋立てによる陸上処理を行っていくことが望ましい。「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」において、埋立てによる処分に特に支障がある場合を除き、海洋投入処分を行わないこととしているのもこうした趣旨によるものであり、このためには、陸上処理体制の早急な整備が必要とされよう。