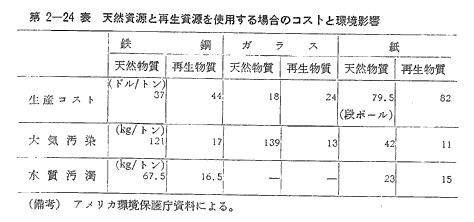
3 廃棄物管理への方向
廃棄物問題の解決のためには、基本的には、環境保全の観点から廃棄物問題をその発生段階から最終的な自然還元に至るまで、廃棄物の流れをいかに制御していくかという廃棄物の管理の問題としてとらえなくてはならない。このような認識に基づき、廃棄物を管理していくうえで解決を迫られている問題として以下のような点があげられる。
第1は、消費、廃棄の段階では、規制の困難な製品が多いので、生産の段階において、あらかじめ廃棄物問題を考慮していくことである。製品のサイクルは、販売や消費によって終わるものではなく、廃棄され最終処分を通じ自然に適正に還元されることによって完結するものといえよう。これまでは製品の開発に当たっては、製造、消費の際の便益面の評価にのみ重点がおかれ、廃棄後の処理費用や環境汚染等の社会的費用、処理の技術的可能性について十分には評価されてこなかった。社会的費用の計量化は困難であるが、例えばプラスチックの処理費用について東京都の清掃審議会が行った試算によると1kg当たり32円に達し、これはプラスチックの生産コストの28%に相当する額である。
今後、このような社会的な費用を製品の開発段階で適切に評価し、適正な処理方法と処理コストをあらかじめ織り込んだ形で製品を製造するというメカニズムの制度化を早急に検討していく必要がある。
第2は、処理体制の整備である。事業者が不法投棄や不適正処理を行う一因として、高度な処理を行う能力がなく、適当な処理体制が欠けていることがある。例えば、大阪市の産業廃棄物に占める従業員300人以下の事業所からの廃棄物の割合をみると環境保全上処理を要する廃油、廃酸、廃アルカリについてみると35ないし38%を占めているが、技術面、用地の確保等で能力の低いこれらの事業所では、専門的な処理業者に期待するところが大きい。他方では、全国の廃棄物処理業者のうち、48年8月末で輸送、処分を専門とする者が9割弱を占め、中間処理を行う者は1割強に過ぎず、廃棄物の適正な処理のためには、廃棄物処理業者の育成と適正な規制を通じて、廃棄物処理体制の整備を図る必要がある。
最近、大阪、愛知、長野等の府県で産業廃棄物処理のための公社を設立し、また、民間においても企業が共同で処理会社を設立する動きのあることは、このような観点から注目される。公害防止事業団、日本開発銀行等においても、産業廃棄物処理業者の育成のため、同処理業者の設置する施設に要する資金の融資を行っている。なお、運搬過程での汚染を防ぐためのパイプ等による自動収集システムや環境に悪影響を与えない埋立工法等の開発や実施が望まれている。
第3は、廃棄物の再生利用を図っていくことである。
廃棄物を再生利用することにより、資源の利用効率が高まり最終廃棄物発生量が減量し、汚染へのポテンシャルを低減することができる。例えば、46年の我が国の故紙発生量1,246万トンのうち、再生可能故紙量は706万トンといわれる。このうち実際に再生されたものは63%にすぎず、仮りに、100%再生利用されれば、廃棄物として排出される故紙の量を259万トン減少することができる。
また、廃棄物を原料とする生産は天然資源を原料とする場合に比べ、環境に与える負荷を軽減できる効果もある。第2-24表は、アメリカの環境保護庁が行った廃棄物と天然資源をそれぞれ利用して製品を製造した場合の環境への影響とコストの比較である。この表をみると、廃棄物利用の場合、鉄鋼の生産では、大気汚染では86%、水の汚染では76%汚染因子が減少する等環境へ好影響を与える。
近年、廃棄物の再生利用に対する認識は高まりをみせ、各方面でこのための試みが行われている。東京都豊島区で47年8月から行われている再生可能ごみの分別排出運動では、1年間で530トンの再生可能ごみを回収する実績をあげており、一方、民間においても例えば日本商工会議所が中心となって、廃棄物の再資源化等の啓もう、普及を行うクリーンジャパン運動が展開されつつあり、また、鳥取県下の高校生徒の手によって、日常生活から生ずる身近な廃棄物である空かん等を素材に、スズや鉄、塗壁材料等を再生することが試みられた。可塑物の成形加工に対する特許の出願件数の45年から46年への推移をみても、全体としては7%の減少となっているのに、廃プラスチック製品を利用する成形加工技術は79%の大幅な伸びを示している。また、企業も資源の再生利用のための技術開発に積極的に乗り出してきており、廃プラスチックの熱分解による燃料油化、廃プラスチックを棒、杭等に再生する技術、塩化ビニル樹脂のモノマー化などが開発されプラント化されたという報告もある。
地方自治体においても、例えば兵庫県の工業試験所において古タイヤの再生技術が開発され、県ではその技術を利用し公社を設立してゴム製品の回収再生利用を進める方針であるといわれる。
しかしながら、再生利用の場合、コスト面では第2-24表のように、アメリカ環境保護庁の資料によると、鉄鋼で16%、ガラスで35%、紙で4%高くなっている。このようなコストの増加が、資源化と再生利用を阻害している一因となっている。
再生利用は、公害防止のコストが節約されることを考慮すれば、天然資源を利用する場合との実質的なコストの差はその分だけ縮小されることとなるので、民間における再生利用を促進する観点から、天然資源と再生資源を利用した場合のコストの平準化を図るための措置について検討を行うべきである。