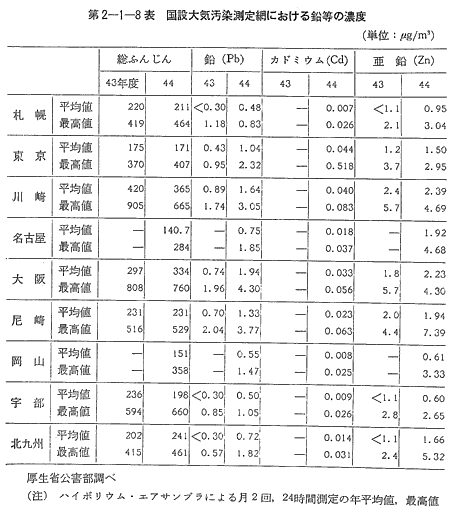
4 浮遊ふんじん等
浮遊ふんじんは、ハイボリウムおよびローボリウム・エアサンプラならびにデジタルふんじん計により重量濃度で測定する方法と、テープエアサンプラを用い濃度指数を求める方法とがある。
ハイボリウムまたはローボリウム・エアサンプラによる測定は、単に浮遊ふんじん総量を測定するだけでなく、その成分として有機物質、硫酸イオン、硝酸イオン、各種金属等をも測定しうる利点がある。これらの測定は、常時自動測定ができないのでデジタルふんじん計やテープエアサンプラとの併用によって監視測定が行なわれている。
厚生省が設置している国設大気汚染測定網9測定点におけるハイボリュウム・エアサンプラによる測定結果を43年度と44年度とに対比して第2-1-8表に示す。これによると、これら測定点における浮遊ふんじん総量の年間平均値は、43年度で175〜420μg/m3が、44年度では140.7〜365μg/m3、また年間の日平均最高値でみると、43年度で370〜905μg/m3が44年度では284〜760μg/m3となっておりやや改善の傾向がみられる。
これらの国設大気汚染測定所では、浮遊ふんじん中に含まれる鉛、カドミウム、亜鉛、マンガン、バナジウムなどの金属成分についても測定されているが、このうち鉛、カドミウムおよび亜鉛の値を第2-1-8表に示している。とくに、昨年の東京都新宿区牛込柳町の鉛害事件以来注目をひいている鉛は、43年度よりも44年度において全体的に増加している。
また、光化学スモッグの起因物質となる炭化水素は、東京では1時間値の月平均がプロパン換算で0.7〜1.5ppm存在し(第2-1-9表参照)、このおもな成分はメタンといわれている。炭化水素の中には発がん性のある物質も含まれているので、炭化水素の組成とその推移の追求が今後の課題となろう。
総酸化性物質(オキシダント)については、測定方法等に今なお解明すべき問題点が多々あるが、重要な大気汚染物質であるので、厚生省では、東京および大阪の国設大気汚染測定所で研究的に調査を行なってきた。東京と大阪の間には、濃度で2倍から10倍のひらきがみられる。これが地域の実態を、そのまま示すものかあるいはまた測定方法の差異によるものかどうか今後検討する必要がある。