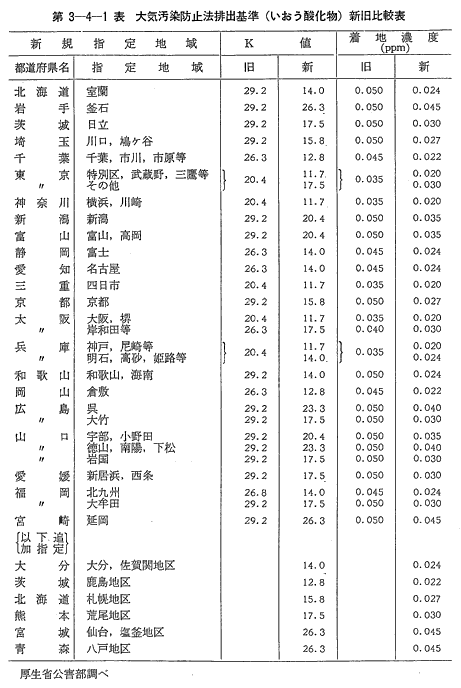
3 いおう酸化物に係る排出基準の強化
指定地域内のばい煙排出者は、指定地域ごとに定められた基準を遵守することとなるが、いおう酸化物に係る排出基準は次の拡散公式によってK値として算出される方式をとっている。これはその地域の汚染状況に応じて決めた最も不利な条件のもとでの最大地上濃度と有効煙突の高さの二つの条件から算出したいおう酸化物の1時間当たり最大の排出量の限度を決めている。K:q=K×10
−3
He
2
(qは、いおう酸化物の量:Heは、有効煙突高の高さ)。この排出基準は、45年2月1日から大幅に強化改訂されている。今回の改訂は、指定地域ごとの大気汚染の現況、その地域におけるばい煙発生施設の現行基準に対する適合状況、今後の燃料、原料の使用量の推計等を基礎として、いおう酸化物に係る環境基準を所定の時間内に計画的段階的に達成することを目標として行なわれた。この場合、計算の基礎として48年度に達成すべき目標値を設定し、これに向かって46年度にさらに再改訂を行なうことを前提として、当面2年間に適用する基準として定めたものである。基準値は、第3-4-1表にみられるとおり、従来3段階であったのを8段階とし、最もきびしい基準が適用される東京特別区等、川崎、横浜、大阪等5地域はKの値で11.7(ばい煙発生施設1か所あたり着地濃度0.02ppm)であり、現行の20.4(0.035ppm)からみて相当きびしくなっている。また、千葉、倉敷といった発展型コンビナート地域にあっては、著しい燃・原料の増加が見込まれるため、あらかじめ基準の強化を行ない環境基準の維持を図ることとしており、新たに指定地域になった鹿島および大分地域においても同様の趣旨から事前予防に努めることとし、あらかじめきびしい基準が設定されている。
このように、今回の改訂は、環境基準に照し、全指定地域について排出基準を大幅にきびしくしており、この基準を達成するためには、相当の努力を必要とするが、さきに述べたように、今回の改訂が環境基準の維持達成を目標として科学的合理的な根拠をもって行なわれたものであり、しかも、総合エネルギー調査会における低いおう化対策に関する報告に示されている改善方針にも合致するものであるので、その完全遵守を至難のこととすることはできない。
大気汚染防止法では、指定地域のうち政令で定める限度をこえる大気の汚染が生じ、または生ずるおそれのある地域に対しては、区域を限ってこの区域に新増設されるばい煙発生施設に対し、一般の基準よりもきびしい特別排出基準を適用することとしており、44年7月、東京都の特別区、横浜市・川崎市の臨海部およびその後背地、四日市市の臨海部およびその後背地、大阪市、堺市んも臨海部およびその後背地ならびに尼崎市の区域について、K値で5.26(着地濃度で0.009ppm)の特別排出基準を設定した。これらの区域は、44年3月の施行令の改正により定められた大気汚染限度値(年平均0.06ppmまたは0.2ppm以上の年間出現時間175時間)を原則として2年間2測定点においてこえた区域である。大気汚染の状況が、現在のところ特別排出基準を設定するまでには至っていないが、これに近い汚染地域としては、室蘭、富士等があげられる。