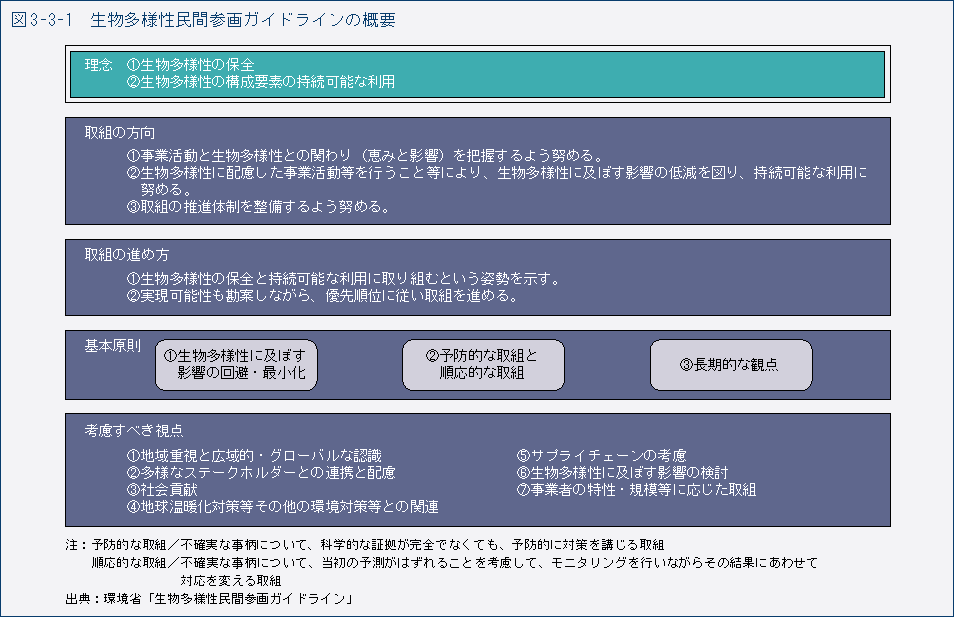
人と自然の共生を実現し、生物多様性に配慮した社会経済への転換を図るためには、生物多様性の保全と持続可能な利用を、地球規模から身近な市民生活のレベルまで、さまざまな社会経済活動の中に組み込む(生物多様性の主流化)必要があります。
このため、これまでかかわりが薄いと考えられてきた企業活動や都市と生物多様性との関係を明らかにするとともに、生物多様性に配慮したライフスタイルへの転換の必要性や、主流化に向けた各主体のすぐれた事例を示します。
生物多様性とビジネスに関する国際的な動きは、2006年(平成18年)にブラジルのクリチバで開催された生物多様性条約 COP8で、民間事業者の参画の重要性に関する決議が初めて採択されたことに始まります。生物多様性に関する民間事業者の参画の遅れを指摘しつつ、[1]生物多様性に大きな影響力をもつ民間事業者が模範的な実践を採択・促進していくことは、生物多様性の損失防止に相当な貢献ができること、[2]政治及び世論に対する影響力が大きい民間事業者は、生物多様性の保全と持続可能な利用を広める鍵となること、[3]生物多様性に関する知識・技術の蓄積及びより全般的なマネジメント・研究開発・コミュニケーションの能力が民間事業者にはあり、生物多様性の保全と持続可能な利用の実践面での活躍が期待できること、といった民間事業者が果たし得る貢献への期待が決議に盛り込まれました。
また、2008年(平成20 年)のCOP9(ドイツ・ボン)の閣僚級会合では、生物多様性条約の目的達成に民間企業の関与をさらに高めるため、ドイツ政府が主導する「ビジネスと生物多様性イニシアティブ(B&Bイニシアティブ)」の「リーダーシップ宣言」の署名式が行われました。この宣言は、生物多様性条約の3つの目的に同意し、これを支持し、経営目標に生物多様性への配慮を組み込み、企業活動に反映させるというもので、日本企業9社を含む全34 社が参加しました。さらに、2007年(平成19年)、2008年(平成20年)、2009年(平成21年)のG8環境大臣会合などにおいても、生物多様性が重要議題となり、産業界を巻き込む政策の強化、生物多様性の損失に伴う経済的影響を検討する必要性などが示されました。
一方、国内では、上記のような国際的な動向を踏まえ、平成19年に策定された「第三次生物多様性国家戦略」において、企業の自主的な活動の指針となるガイドラインを策定することが示されました。また、20年に施行された生物多様性基本法(平成20年法律第58号)では、事業者や国民などの責務が規定されたほか、国の施策の一つとして生物多様性に配慮した事業活動の促進が規定されました。さらに、21年8月には、事業者が自主的に生物多様性の保全と持続可能な利用に取り組む際の指針となる「生物多様性民間参画ガイドライン」を環境省が発表しました。ガイドラインでは、事業者が生物多様性に配慮した取組を自主的に行うに当たっての理念、取組の方向や進め方、基本原則などを記述しています(図3-3-1)。
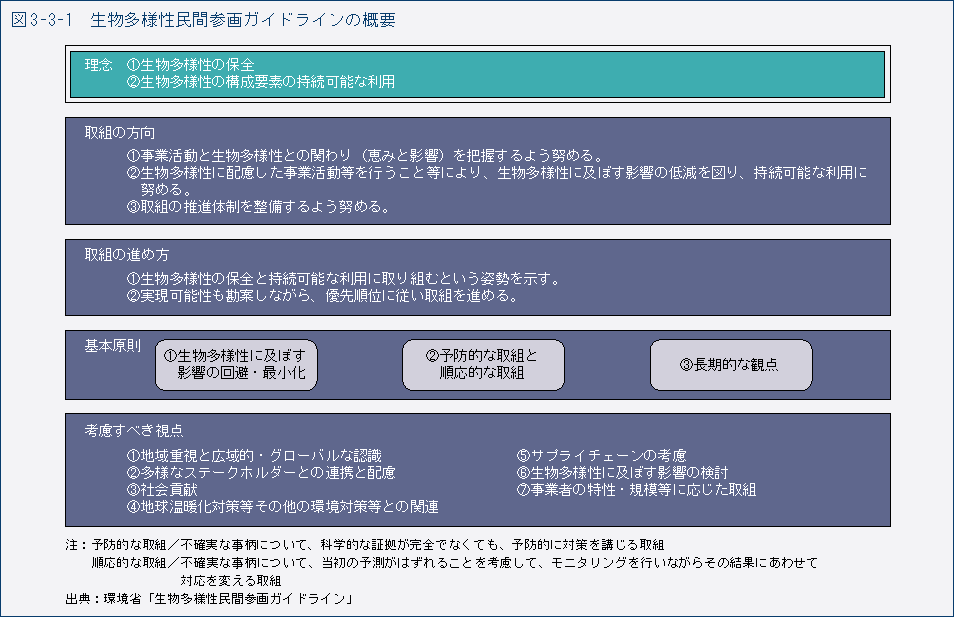
こうした中、経済界の取組も始まっています。平成21年3月には、(社)日本経済団体連合会が「日本経団連生物多様性宣言」を発表し、生物多様性に積極的に取り組んでいく決意と具体的な行動に取り組む際の指針を示しています。また、20年4月には、生物多様性の保全と持続可能な利用に関する学習などを目的とした日本企業による「企業と生物多様性イニシアティブ(JBIB)」が設立されました。さらに、21 年4月には、滋賀経済同友会が、企業活動を通じた生物多様性保全のモデル構築を目指し、「最低1種類もしくは1か所の生息地の保全に責任を持ちます」などの10 項目の宣言文からなる「琵琶湖いきものイニシアティブ」を公表するなど、さまざまな取組が始まっています。
また、生物多様性のための取組が意識される以前から、本業あるいはCSR活動の一環として生物多様性保全につながる活動を行っている企業もあります。
例えば、ある総合商社が、ボルネオ島のマレーシア領で実施している、危機的状況にある熱帯林の生態系を早期に限りなく自然林に近い状態に再生する実験プロジェクトは、社員と専門家や地域の人々が連携して取り組み、平成2年から20年間も続けられています(写真3-3-1)。

ある損害保険会社は、平成19年度に、自然エネルギーの利用や植林したマングローブによる二酸化炭素吸収・削減効果によって、国内事業所から排出される二酸化炭素を相殺するカーボンニュートラルを実現しています。同社がNGOとのパートナーシップの下、10年間行ってきたマングローブの植林は、インドネシア、タイ、フィリピン、ベトナム、ミャンマーとフィジー諸島で約5,900haにも及んでいます(写真3-3-2)。また、契約者との契約更新時に発行する約款を、紙ではなく、ウェブサイトで閲覧することに賛同してくれた契約1件につきマングローブ2本の植林に相当する金額を同社が寄付するプロジェクトも始まっています。

ある林業会社では、国内の社有林による平成20年度の二酸化炭素吸収量は11万6,000トンであり、同年に同社が販売した木造住宅に使用された木材に固定されている二酸化炭素は21万トンになるとしています。このように本業で環境保全に貢献している企業もあります。また、林業は、二酸化炭素吸収の面だけではなく、生物多様性保全にも貢献するものです。同社はすでに18年に社有林全てが、『緑の循環』認証会議(SGEC)から適切に管理されている森林と認証されています。これをきっかけに、皆伐地を中心に動植物の生息、生育状況をモニタリングする調査を開始しています。また、同社はインドネシアで年間190万haもの森林減少が起きていることへの対策として、22年以降の5年間で国立公園の保護林300haと保護林以外の荒廃地に1,200haの植林を行うことを決めました(写真3-3-3)。

このように、国内外で生物多様性に配慮した企業活動が盛んになってきています。
1988年(昭和63年)に保全生物学者のノーマン・マイヤーズが提唱した「生物多様性ホットスポット」という言葉は、その地域に維管束植物の固有種が1,500種以上生育し、高い生物多様性を有する一方で、自然植生が70%以上損なわれていて破壊の危機に瀕している地域を指します。世界で34の地域が指定されており、わが国もその一つに入っています。ホットスポットは、地球の表面積のわずか2.3%であり、人口が集中する地域を多く含むことから、開発の圧力が高いことがうかがえます(図3-3-2)。
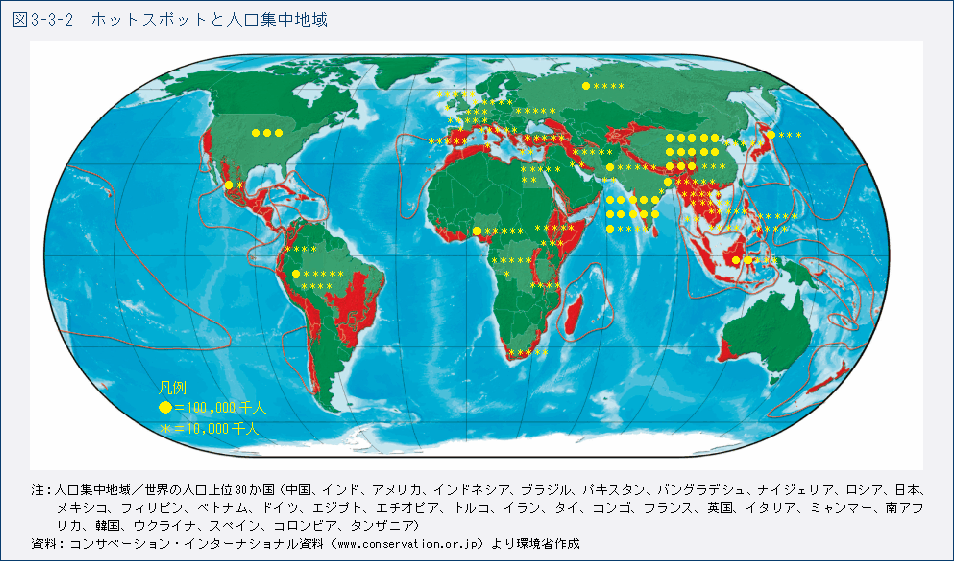
また、序章でみたとおり、今や世界人口の半分は都市で生活しており、面積的には地球のたった2.8%の土地に住んでいる状況です。都市の人口は増加を続け、2050年には世界人口の2/3が都市で生活すると予測されています。都市の住民と経済活動は、人類が使用する資源の75%を消費しており、都市は、周辺からもたらされる生物多様性の恩恵(生態系サービス)にかなり依存しているといえるでしょう。実際に、農林水産省が発表している各都道府県の平成19年度の食料自給率をみると、東京都1%、大阪府2%、神奈川県3%といったように、大都市はその地域内で食料を賄っていない実態が明らかです。
しかし、都市の成り立ちはさまざまであり、土地の利用形態、市街化の程度、経済・社会・文化といった背景も異なっています。また、図3-3-3や第2部図5-1-5のように生物の分布が都市の発達に応じて、後退している場合と拡大している場合があるため、それぞれの都市に合った生物多様性との関係の構築が必要と考えられます。
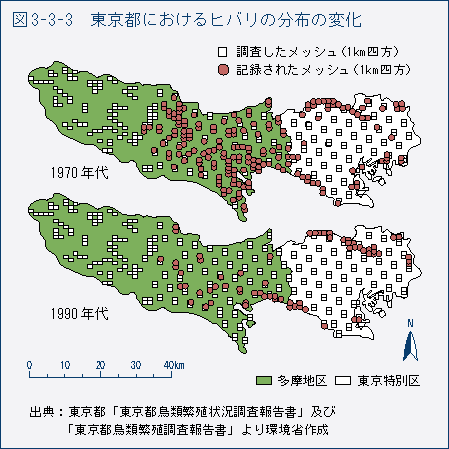
平成21年11月には、国内103の地方自治体が参加して「生物多様性自治体会議2009(主催:愛知県、名古屋市、COP10支援実行委員会)」が愛知県名古屋市で開催されました。COP10にあわせて開催予定の「生物多様性国際自治体会議」に向けて、国内の地方自治体共通の課題を抽出し、生物多様性保全の取組に関する情報交換を行いました。会議総括では、「生物多様性」という総合的視点、循環共生の知恵など、今後地方自治体が取組を進める上で重要と思われる事項が確認されました。
こうした地方自治体の連携は、世界的にも展開されており、すでに平成2年に43か国200以上の自治体がニューヨークの国連に集まって開催した「持続可能な未来のための自治体世界会議」で持続可能性を目指す自治体協議会(ICLEI(International Council for Local Environmental Initiatives))が発足しています。平成21年12月現在、世界で68か国、1,100以上の自治体が参加しています。同協議会は、気候変動防止、総合的な水管理、生物多様性の保全、持続可能な地域社会づくり、持続可能性の管理といったテーマで自治体間の連携を行い、地域でつくられた施策が、地域、国家、世界全体の持続可能性を実現する費用対効果の高い方法であるという考え方で活動しています。また、20年に開催されたCOP9では、都市及び地方自治体の参加促進に関する初の決議が採択され、生物多様性条約の下で都市や地方自治体の果たす役割が認識されました。
都市と生物多様性に関する取組では、国内で新しい試みが検討されています。名古屋市では、都心部の建築物について容積率を緩和することと引き替えに、市の郊外で民有地の森林を保全(都市計画制度の運用)する仕組みを検討中です。
国内の民間事業者では、例えば、都市再開発における緑地計画で、現況調査や文献調査をもとに在来種や潜在自然植生に配慮し、自然の再生を目指す取組が日本で初めて行われました。この再開発では、JHEPという第三者機関による客観的な定量評価が行われ、最高ランクを取得しています(図3-3-4)。JHEPとは、1980年代にアメリカ内務省で開発された、ハビタット(野生生物の生息地)の観点から自然環境を定量的に評価する方法である「ハビタット評価認証(HEP)」の日本版として新たに構築されたものです。HEPは、客観性や再現性にすぐれ、分かりやすさなど合意形成のツールとしてもすぐれている点が評価され、アメリカでは環境アセスメントや自然再生事業でも広く使われています。また、企業などが積極的に保全・活用に取り組む優良な緑地を認定する「社会・環境貢献緑地評価システム(SEGES)」により、平成22年3月末現在、33サイトが認定されており、緑地保全に関する活動の意欲の向上や取組の強化に役立っています。
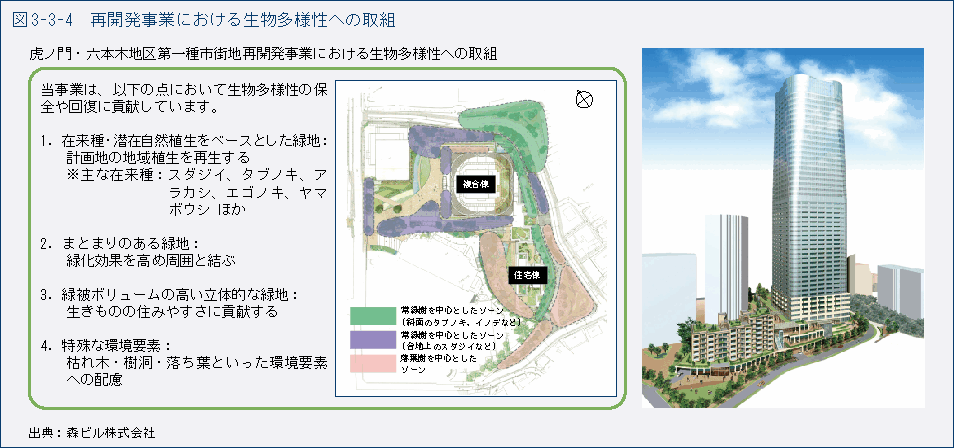
これまで見てきたとおり、人間の衣食住に不可欠な資源や原料は、大半が生態系からもたらされる生態系サービスとして供給されています。ここでは、消費者の立場として、私たちができることを述べていきます。まず、基本的なことは、生態系サービスは、再生可能なものとして自然のサイクルの中で生み出されることから、その再生産の機能を損なわない持続可能な形で生態系サービスを得ていくことが必要となります。内閣府が平成21年に行った世論調査によれば、生物多様性に配慮した生活のためのこれまでの取組として、「環境に配慮した製品を優先的に購入している」と答えた人の割合は26%にとどまっており、今後、さらに生物多様性に配慮した製品の普及を促進していく必要があります(図3-3-5)。次に、木材、漁業資源、農産物について、持続可能な生産を行っている取組と、私たち消費者が選択できることを紹介していきます。
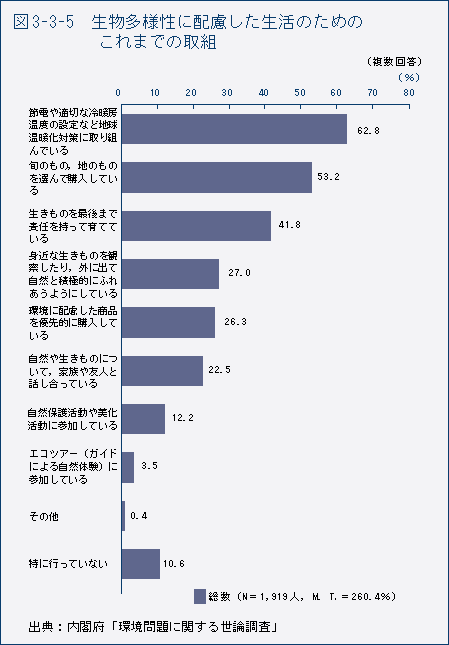
平成20年の国内の木材需要量(用材)は7,797万m3ですが、わが国はそのうち約76%を輸入に頼っています。輸入先は、主に北アメリカ、東南アジア、ロシア、ヨーロッパ、オーストラリアとなっていますが、例えば、インドネシアでは、森林火災や違法伐採により年間約190万ha(四国の面積に相当)の森林が失われています。違法伐採を減らして、原産国の生物多様性を維持するために私たちができることの一つとして、合法性・持続可能性の証明された木材・木材製品を購入することが挙げられます。政府は平成18年から「グリーン購入法」に基づき、合法性・持続可能性の証明された木材を政府調達の対象としています。また、持続可能な森林運営を推進するため、わが国が利用を推進する木材・木材製品が備えるべき要件をガイドラインとして国内外に示してきました。こうした取組により、全国で合法性・持続可能性の証明された木材・木材製品の調達が可能となっています。消費者は、木材だけでなく、家具や文具、生活雑貨、紙といった木を原料とする製品を購入する際、こうした製品を選ぶことで、生物多様性の保全と持続可能な利用に貢献することができます。合法性・持続性の証明された木材を選ぶ際に参考になるのが森林認証です。森林認証とは、「法律や国際的な取決めを守っているか」、「多くの生物がすむ豊かな森であるか」などの観点から、森林が適切に管理されているかを第三者機関が認証し、その森林から産出される木材を区別して管理し、ラベル表示を付けて流通させる民間主体の制度です。森林認証制度には、森林認証プログラム(PEFC)、森林管理協議会(FSC)、『緑の循環』認証会議(SGEC)などがあります。FSCの認証を受けた森林の面積は世界中で増加しており(図3-3-6)、SGECの認証を受けた国内の森林は、平成22年3月現在で93件、面積にして816,438haに広がっています(図3-3-7)。
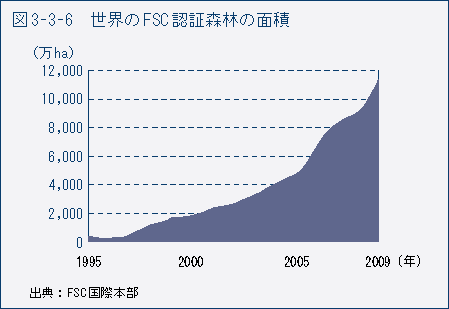
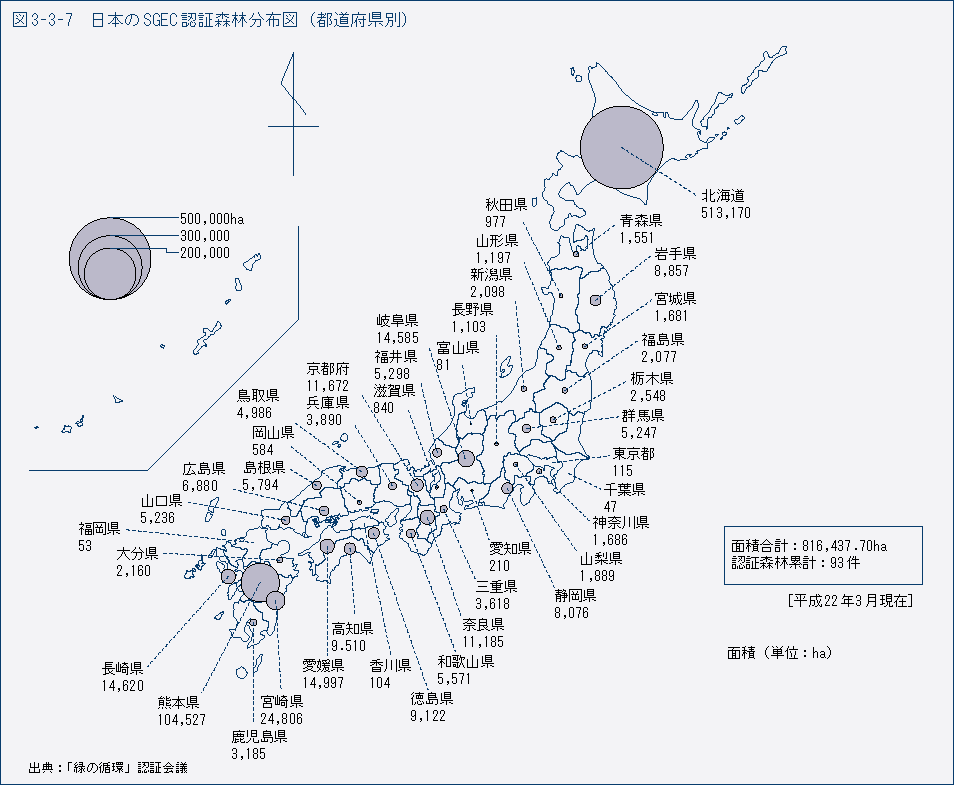
日本人の1人当たりの水産物消費量は、世界第3位で、世界平均の4倍程度もあります(図3-3-8)。豊富な水産資源を安定して得るためには、それを供給する生物多様性が保全されている必要があります。持続可能な漁業を行うためには漁獲量や種類、期間、漁法などに一定のルールを決め、漁業資源を枯渇させない取組が必要です。こうした取組を行っている漁業に対して第三者機関による認証を与える制度として、海洋管理協議会(MSC)やマリン・エコラベル・ジャパン(MELジャパン)などの認証制度があります。MSCラベルの製品は世界で販売を拡大しており、平成22年1月には、3,855品目に達しています(図3-3-9)。また、国内では、21年6月現在で約170の製品が流通しています。
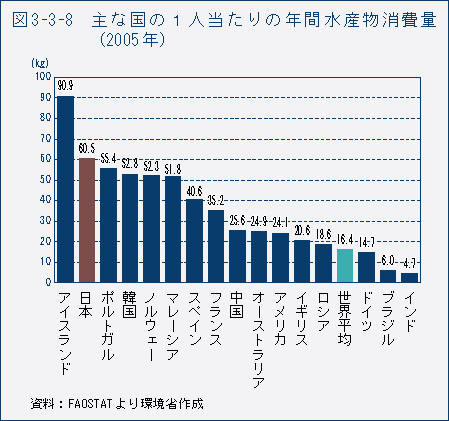
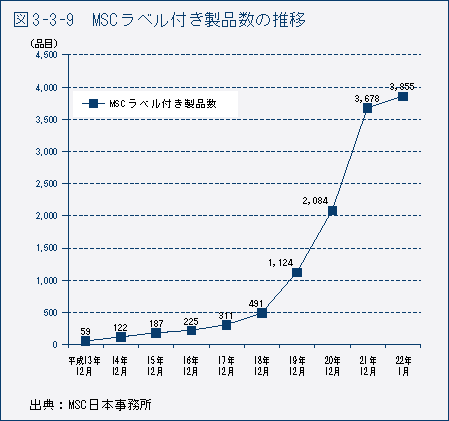
有機農産物の生産は、平成13年4月から施行された農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和25年法律第175号)に基づき、統一したルールの下で行われています。これは、有機JAS規格を満たす農産物について、認定事業者が格付け表示の認定を行い、その農産物に有機JASマークを付けることができる制度です(図3-3-10)。有機農産物の生産方法の基準は、[1]堆肥等による土づくりを行い、原則として(播種・植付け前2年以上及び栽培中に)化学肥料及び農薬は使用せず土壌の性質に由来する農地の生産力を発揮させること、[2]農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した栽培管理方法を採用したほ場において生産されること、[3]遺伝子組換え種苗は使用しないこととされており、これにより農業の自然循環機能の維持増進を目的としています。私たちが、有機JASマークの農産物を購入することで、農薬による生物への影響といった環境負荷の少ない農業が促進され、生物多様性の保全につながります。実際、13年~20年の間に、国内の格付け数量は、33,734トンから55,928トンへと約1.7倍増加しています(図3-3-11)。総生産量に占める有機格付けの割合は、まだ低い状況であり、有機農産物の普及のためには、私たちの賢い選択が必要です。
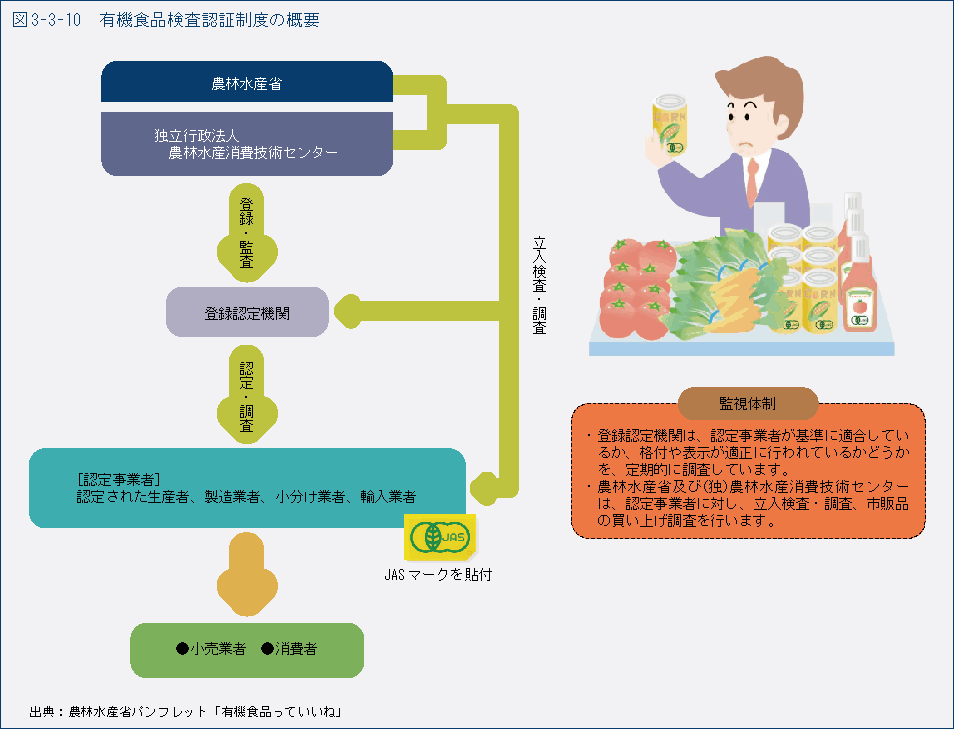
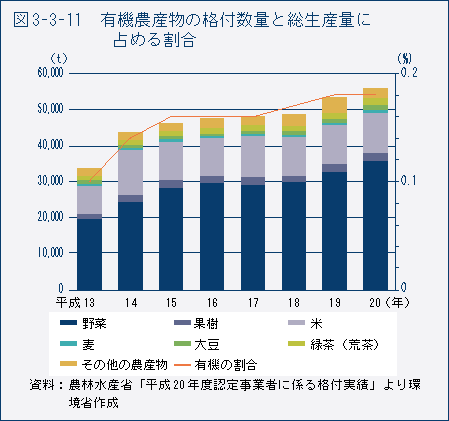
わが国では、年間約1,900万トンの食品廃棄物が排出されており、そのうち、本来食べられるにもかかわらず廃棄されている、いわゆる「食品ロス」が約500~900万トンあると推計されています(図3-3-12)。食品関連事業者が排出する食品廃棄物のうち、焼却・埋立処分されたとみなされる量は、年々減少傾向にあり、6割程度になっています(図3-3-13)。一方で、一般家庭からの排出量のうち、再生利用されている量は約64万トンであり、残りの94%が焼却・埋立処分されている状況です(第2部 表3-2-4)。
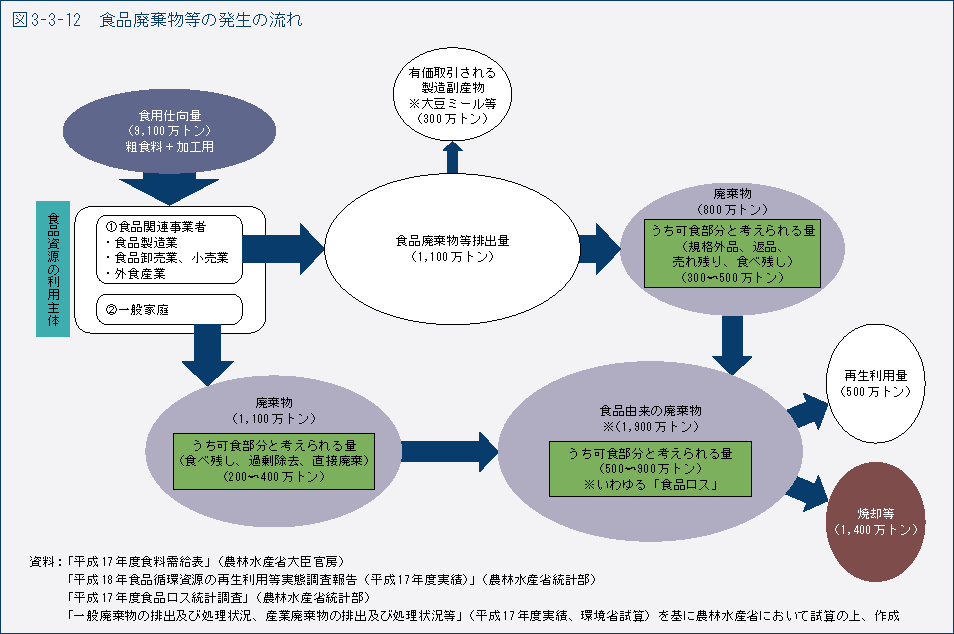
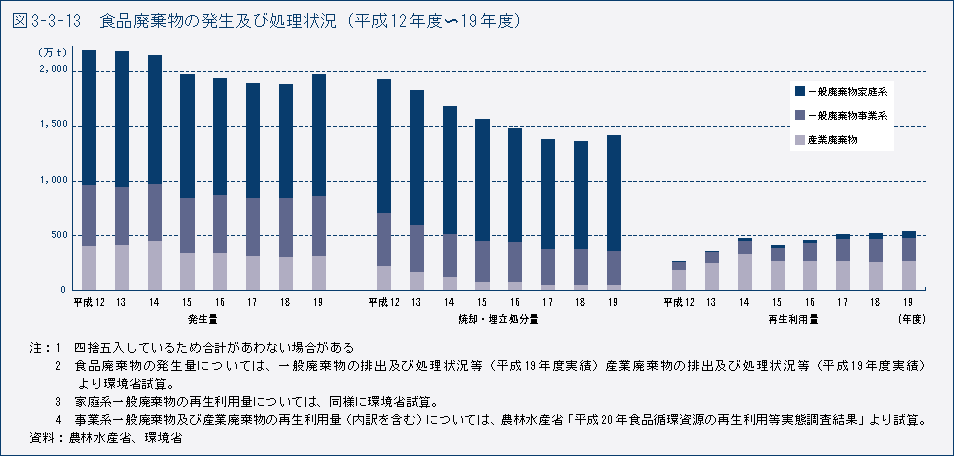
FAOによると、2009年の栄養不足人口は、世界で10億2,000万人にも達し、初めて10億人を超えたと推定されています。わが国は、カロリーベースでみると、平均2,473kcal/人・日(平成20年度)に相当する食料が供給されています(図3-3-14)。国民全体(1億2,769万人、平成20年10月1日現在)では、約315,777百万kcalとなります。供給熱量と摂取熱量の差が食料の廃棄や食べ残しの目安といわれており、わが国では、この差が国民1人1日あたり708kcal(平成19年度)であることから、国民全体で90,405百万kcalが1日で無駄になっていると考えられます。成人が栄養不足にならない最低限といわれる2,200kcal/人・日で割ると、約4,193万人分の栄養に相当します。世界には十分に食料を得られない人々がいる中で、生態系サービスからもたらされる食料を効果的に行き渡らせる必要があります。
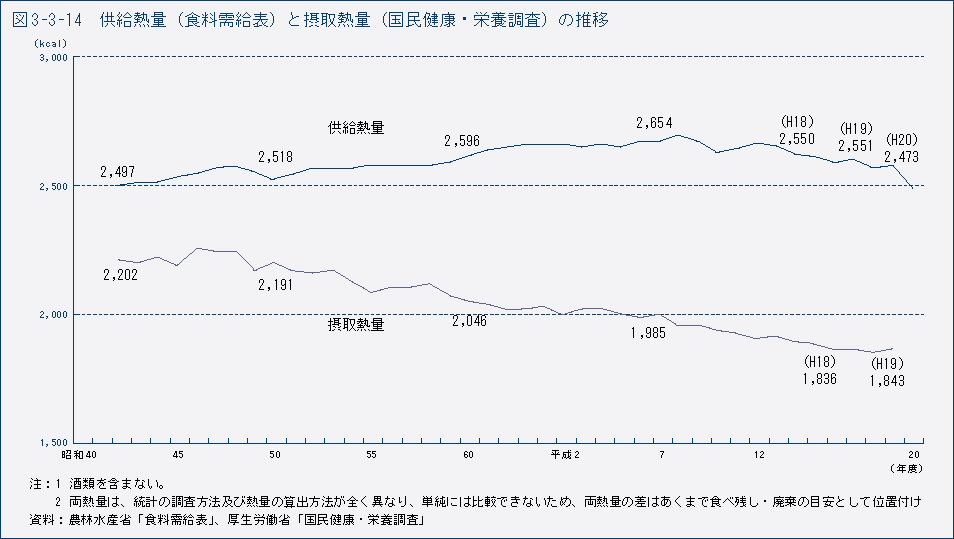
近年、米飯給食の促進や地域の農作物を給食で用いるなど、食育が盛んになってきていますが、その目指すところは、食べものへの感謝の心を大切にして、「残さず食べる」「感謝の心をもつ」といった基本的な習慣を身につけることにあります。その基本は、家庭で食品の廃棄を減らす場合でも同じです。個人ですぐにできることは、例えば、賞味期限や消費期限の意味を正しく理解し、賞味期限を過ぎてもすぐに食べられなくなる訳ではないので、きちんと食品を使い切るようにすること、食品を買いすぎないために買い物の前に冷蔵庫にある食品の種類や量を確認すること、日頃から賞味期限や消費期限を確認して順番に使い切ることなどが挙げられます。
事業者は、製品やサービスを通じて、生物多様性の恵みを広く社会に供給する重要な役割を担っています。平成21 年6月の内閣府の世論調査では、生物多様性に配慮した企業活動を評価するとした人が82%に上ります。事業者の活動は、消費者の意識に支えられており、国民一人ひとりの消費行動に応じて変わらなければならないと同時に、その活動をより一層生物多様性に配慮したものにし、生物多様性に配慮した製品やサービスを提供することを通じて、消費者のライフスタイルの転換を促していくことも期待されています。
また、事業者の活動は、さまざまな場面で生物多様性に影響を与えたり、その恩恵を受けたりしています。例えば、食料、木材、紙、繊維、燃料、水などは、事業活動に不可欠です。多様な遺伝子は、医薬品の開発、品種改良などに役立ちます。物質の供給以外にも、気候の安定、がけ崩れや洪水等の自然災害の防止も、安定的な事業活動に必要なものです。さらに、自然界の形態や機能からヒントを得て、技術革新につながることがあります。これは生きものの真似という意味で「バイオミミクリー」と呼ばれ、カワセミのくちばしをまねた、空気抵抗の少ない新幹線の先頭車両のデザインなどが有名です。
一方、鉄などの鉱物資源、石油などの化石燃料などの開発・利用は、土地の改変や地球温暖化などにより、生物多様性に影響を及ぼします。また、廃棄物の処分、排水の処理、事業所や工場の建設などは、その過程で、生物多様性に影響を与えることがあります。さらには、こうした経済活動への投融資や社会貢献活動などを通じて、生物多様性にかかわることもあります。
このように、農林水産業、建設業、製造業、そして小売業や金融業、マスメディアなどであっても、生物資源の利用、サプライチェーン、投融資などを通じて、生物多様性に影響を与えたり、その恵みに依存したりしています。また、このような恵みや影響は、国内外を問いません。特に、天然資源に乏しいわが国は、その多くを海外に依存しており、海外の生態系サービスを利用することで、現在の私たちの生活が成り立っているということを忘れてはいけません。
これまでの事業者の取組は、どちらかというとCSR活動が中心でしたが、これからは、本業の中でも、生物多様性に取り組んでいくことが重要となります。「生物多様性民間参画ガイドライン」では、それぞれの事業者の取組の方向として、[1]事業活動と生物多様性とのかかわり(恵みと影響)を把握すること、[2]生物多様性に及ぼす影響の低減を図り、持続可能な利用に努めること、[3]取組の推進体制等を整備することを挙げています。生物多様性とのかかわりは、それぞれの事業者の業態や規模などによって異なっており、まずは自らの事業活動と生物多様性とのかかわりを把握し、実現可能性も考慮しながら、優先順位に従い取組を進めていくことが重要です。
事業者が生物多様性に取り組むことには、リスクとチャンスが存在しています(表3-3-1)。例えば、原材料調達を生物多様性の観点から洗い直す作業には追加的なコストが必要となりますが、原材料調達に係るリスクの低減により、経営の安定化が期待されます。日本は、食料の約6割、木材の約8割、鉱物資源や化石燃料のほとんどを海外に依存しており、その意味で生物多様性に関する取組は、資源戦略としても重要だといえます。
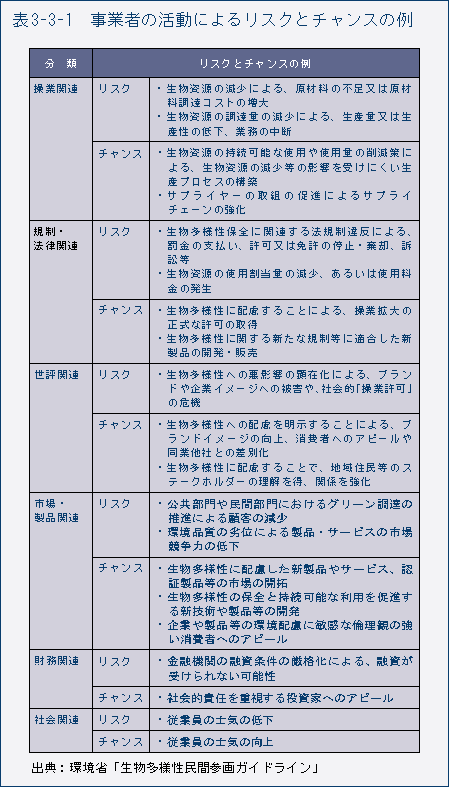
以上のように、事業者が、消費者を含めた多様な主体と連携しながら、生物多様性に取り組むことは、社会全体の動きを自然共生社会の実現に向けて加速させるだけでなく、自らの事業を将来にわたって継続していくためにも必要なことなのです。
例えば、あるオフィス機器メーカーでは、原材料の調達、設計・製造、輸送・販売、使用・保守、回収・リサイクルという一連の事業活動全体で、それぞれの段階において生物多様性との関係を把握し、事業活動による負荷を減らしていく取組を進めています。事業活動による生態系への影響としては、複写機事業を例にすると、紙パルプや金属資源などの原材料の調達、生産時に利用する水資源などが大きいことが分かりました。また、このメーカーでは、資源を投入して製品を製造し、最終的には環境中に廃棄する直線的な事業活動ではなく、地球環境の再生能力に収まる事業活動のあり方を目指しています(図3-3-15)。
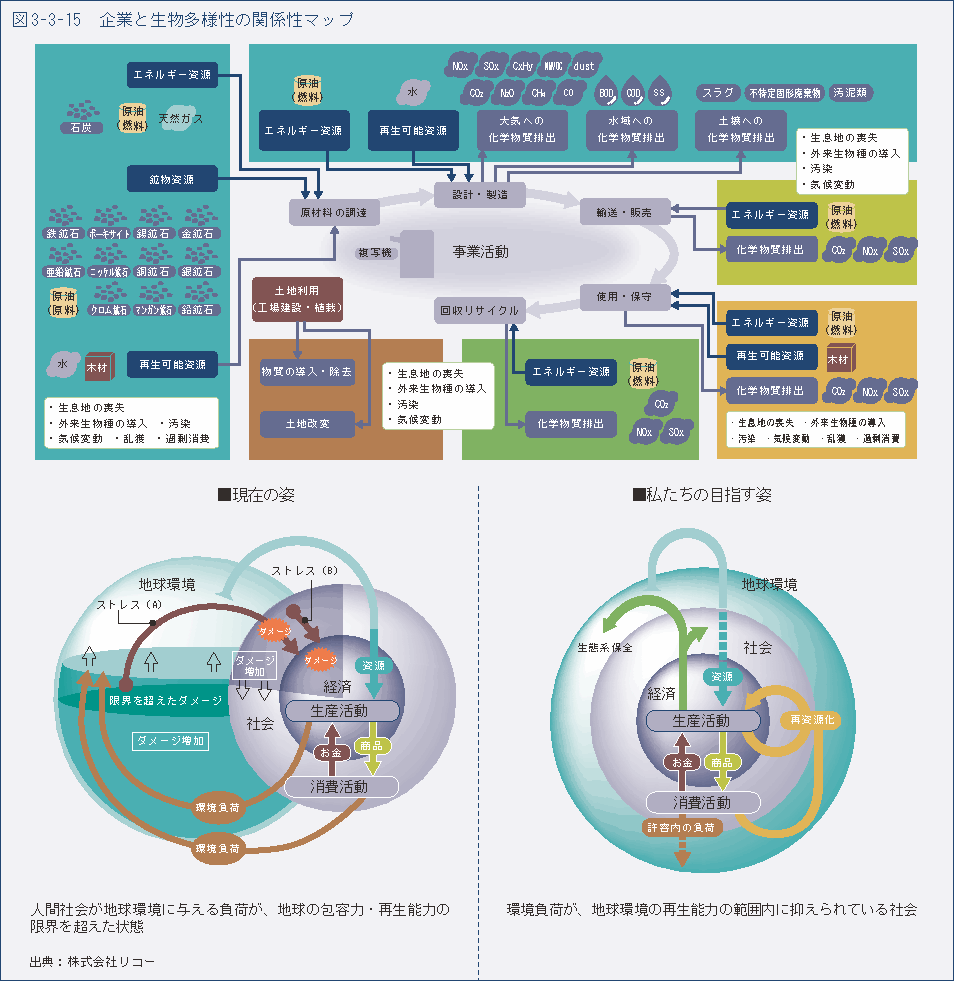
ある家電メーカーは、平成20年10月から、WWFが進める地球環境保護施策の一つである「北極圏プロジェクト」を支援することにより、生物多様性保全の取組を始めています。WWFのプロジェクトは、以下の4つの手法によって北極圏への理解を促進し、生態系を管理することを目指しています。
1.北極圏の気候変動が地球全体に与える影響について伝える
2.北極生物圏が新たな二酸化炭素の排出源にならないことを確認する
3.生態系を壊すような乱獲により引き起こされる環境上の負荷を取り除く
4.北極圏の生態系や生物を将来にわたって保護する体制を確立する
このメーカーは、「地球環境との共生」を事業活動の指針としており、「北極圏における環境破壊の脅威を取り除き、地球温暖化に大きな影響を与える北極圏一帯の環境を保全する」ことへの貢献は、まさに事業活動の目的に合致したものとなっています。支援は、主に資金援助の形で行われ、3年間に47万ユーロの支援が計画されています。双方の協力により、北極圏の環境分析・調査やホッキョクグマを頂点とする生態系を維持する取組が進められています。
フードバンク活動
近年「フードバンク」という活動が広がりを見せています。フードバンクとは、包装材の破損や印字ミスなど、食品としての品質には問題がないものの、通常の流通ルートでは支障がある食品や食材を、食品メーカーや小売店等から無償で寄付を受け、支援を必要とする福祉施設や団体に無償で寄贈するシステムで多くのボランティア活動で支えられています。アメリカでは約40年の実績(全米に220団体、年間取扱総量200万t)がある活動で、世界18ヵ国が加盟する国際組織も存在します。日本では、この国際組織にも加盟しているセカンドハーベスト・ジャパン(特定非営利活動法人2002年設立:東京都台東区)の活動が最も規模が大きいものとなっており、平成20年の年間取扱量は850トン、金額換算で約5億1千万円、食品提供企業の廃棄経費削減額の見込みが約9,200万円という実績を上げています。
同団体へ食品を提供する支援企業は、累計で約500社、このほか物流企業の協力など支援の輪が広がっており、企業のCSR活動の一環ともなっていると考えられます。扱う食品も主食(米、パン、麺類ほか)、副食類、嗜好品(菓子、飲料)、調味料、生鮮食品、冷蔵冷凍食品、インスタント食品、防災備蓄品など多岐にわたります。近年、全国に十数団体が設立され、都市部から地方へと活動の輪も広がっています。支援企業側と支援を受ける施設や団体の双方にメリットがある仕組みであり、また、食品を大切にするという本来の目的からも、さらなる広がりが期待されます。
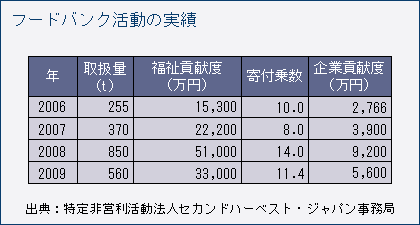

耕作放棄地の活用
全国には、平成17年度時点で約39万haの耕作放棄地があります。耕作放棄地とは、「過去1年以上作物を栽培せず、しかも、この数年の間に再び耕作するはっきりした考えのない土地」のことであり、昭和60年には13.5 万haでしたが、20年間で約2.5倍にも増加しています。耕作放棄地を再生・利用していく目的としては、中長期的な世界の食料需給のひっ迫が見込まれる中、食料の安定供給を図る必要があること、国土の保全、水源のかん養、病虫害・鳥獣被害の防止や中山間地の適切な管理による生物多様性の保全といったさまざまな機能を確保する必要があることなどが挙げられます。
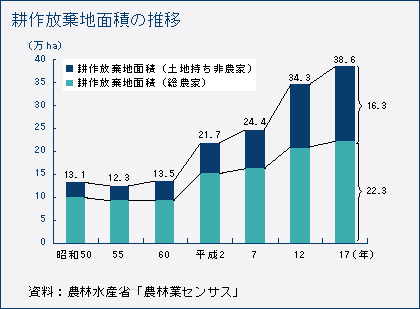
生物多様性に配慮した社会経済活動の取組は、すでにさまざまな主体によって始まっています。ここでは、地方公共団体や企業、NGOなどによる取組を、平成21年6月に、環境省と(財)イオン環境財団が生物多様性の保全と持続可能な利用の推進を目的に創設した「生物多様性 日本アワード」の第1回優秀賞に選ばれた取組を中心に紹介します。
都道府県や市町村では、従来から、自然公園などの保護地域の保全、野生鳥獣の保護管理、希少な野生生物の保護、都市緑地の保全・再生、外来種対策など生物多様性の保全に関するさまざまな取組を進めています。例えば、希少な野生生物の保護では、平成17年までにすべての都道府県でレッドデータブックやレッドリストが作成されており、21年度までに27都道府県で希少な野生生物の保護のための条例が制定されています。また、森林や、水源の保全を目的とした、森林環境税などの制度が21年度までに30県で導入され、これらを財源とした取組が進められています。
こうした取組に加え、地域の自然的社会的な特性に応じて、生物多様性の保全と持続可能な利用を総合的かつ計画的に進めていくため、生物多様性基本法に基づく生物多様性地域戦略の策定が進んでいます。平成22年3月末現在、埼玉県、千葉県、愛知県、滋賀県、兵庫県、長崎県、流山市、名古屋市、高山市などが策定済みのほか、多くの地方公共団体で策定に向けた検討が進んでいます。
ある建設会社では、関係機関と共同で、従来のエコロジカルネットワークに関する先行研究を発展させ、都市開発事業が地域生態系へ与える影響を分かりやすく評価するシステムを開発し、病院や業務ビルなどの実際の建設プロジェクトに適用しています。また、在来種であるニホンミツバチを飼育し、都市環境の指標種として、飛行経路や距離、蜜源植物などのデータを収集・解析し、生物多様性に配慮した都市づくりに役立てています。
ある住宅メーカーでは、持続可能な木材利用を可能にするため、木材供給事業者やNGOと協働し、平成19年に、調達木材の合法性だけでなく、生物多様性の保全や伐採地の住民の暮らし、国内林業の活性化など、幅広い視野をもった10の調達指針からなる「木材調達ガイドライン」を制定し、調達方針ごとの評価点の合計で木材を4つのランクに分類したうえで、より生物多様性に配慮した木材の割合を増やす取組を行っています。こうした取組は、供給事業者側にとっても、客観的な基準に沿って自主的に木材を変更できるといった利点もあります。
ある信用金庫では、地元・愛知県名古屋市で開催されるCOP10への関心を高め、生物多様性の重要性への理解を深めるため、「生物多様性について考えてみませんか定期」を販売し、約2万人を超える顧客一人ひとりと職員が面談し、相互に生物多様性の重要性やCOP10についての理解と関心を深める活動を行いました。この商品は、当初の予定よりも2か月早く完売し、4,164件(約3,400人)、30億7,600万円の契約があり、預入金額の0.01%がCOP10支援実行委員会に寄付されました。
ある洗剤メーカーでは、ヤシノミ洗剤の売上げの1%をマレーシア政府認可の「ボルネオ保全トラスト」に支援することで、熱帯雨林回復のための土地購入や、生息地を追われたボルネオゾウなどの保全活動に取り組んでいます。また、資金援助だけではなく、消費者を対象にしたボルネオ視察エコツアーを実施し、環境保全意識を高めるための普及啓発活動も行っています。こうした取組は、消費者からも大きな支持を集めています。
(財)知床財団は、世界自然遺産の知床半島のヒグマ、エゾシカ、海棲哺乳類、オジロワシなどの大型野生動物の生息状況に関する長期モニタリングや生態調査、遺伝的多様性に関する調査を行ってきました。また、それらの成果を活用した環境教育や体験型教育プログラムを通じて、地域住民や来訪者に対して、知床の自然と生物多様性の重要性を伝える活動を行っています。さらに、設立者である斜里町・羅臼町からの委託を受けて、ヒグマなどの野生動物の保護管理、わが国のナショナルトラスト運動の先駆けの一つである「しれとこ100平方メートル運動」など、多岐にわたる継続的な取組を通じて、地域の生物多様性保全に貢献しています。
特定非営利活動法人農と自然の研究所は、平成13年の設立以来、害虫でも益虫でもない「ただの虫」が水田環境を形成しているという視点に立ち、水田の動植物5,470種類を網羅する目録や生息分布の調査リストを作成し、研究機関に提出しています。また、水田の生物多様性を評価するため、動物植物それぞれ230種類を指標化する取組を行っています。さらに、無農薬栽培における水田と畦の生物種の調査分析を実施し、それらを活用した農業技術を開発し、その評価手法を提案しています。こうした研究成果を、農家、自然保護団体、環境教育関係者などに普及しています。
特定非営利活動法人アサザ基金は、霞ヶ浦の水源地である谷津田を再生し、平成20年から地域の酒造会社の協力により、再生された谷津田で生産された酒米を用いて日本酒を製造しています。販売に当たっては、地域の小売販売店との連携により大きな効果が得られており、売上げの一部は、谷津田の再生のために活用されています。また、同様の企業やボランティアとの協働による谷津田再生の取組を流域全体で展開しています。
兵庫県豊岡市では、野生復帰したコウノトリのエサ場となる生物多様性が豊かな水田を確保するため、JAたじま、コウノトリ湿地ネット、豊岡市、兵庫県豊岡農業改良普及センターなどが連携し、減農薬・無農薬で、安全・安心なお米と多様な生きものを同時に育む「コウノトリ育む農法」に取り組んでいます。また、農家自らが実施できる調査手法を確立し、市民や消費者と連携しながら水田の生きもの調査を実施しています。この方法で作付される「コウノトリ育むお米」の売上代金の一部は、豊岡市コウノトリ基金に寄付され、コウノトリのエサ場づくりなど生息環境の整備に利用されています。価格は、通常のお米と比べて無農薬米で5割、減農薬米で2割ほど高くなっていますが、販売は好調で、生産に取り組む農家も年々増加しており、平成20年産で520t(約200ヘクタール)、約1.7億円を売り上げています。
| 前ページ | 目次 | 次ページ |