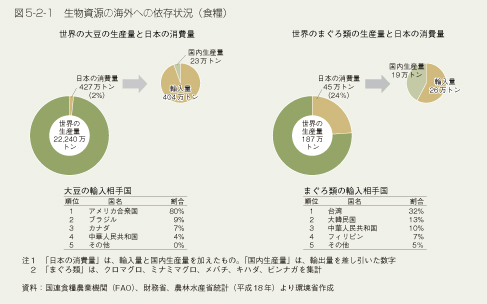
平成20年10月に開催された第4回世界自然保護会議で、IUCNより、世界中の絶滅のおそれのある野生生物のリスト(レッドリスト)の最新版が公表されました。既知の生物種約164万2千種から約4万5千種を対象に評価した結果、絶滅危惧種(絶滅危惧IA類、絶滅危惧IB類、絶滅危惧II類)は約1万7千種とされています。19年に公表されたレッドリストと比較してみると絶滅危惧種の数は621種増加していますが、毎年評価対象種数が増加しているほか、科学的な知見が充実した結果評価が変更になる種もあり、絶滅危惧種の指定数の増減のみをもって種レベルの生物多様性の状況を単純に評価することはできません。既知種5,488種すべてを評価対象としている哺乳類の20年度の結果をみると、約21%にあたる1,141種が絶滅危惧種とされています。オーストラリアのタスマニア島に生息するタスマニアデビルが新たに絶滅危惧種となるなど絶滅のおそれの評価が悪化した種がある一方、保全の取組により個体数が増え、絶滅のおそれの評価が改善された種(アフリカゾウ)や、野生のものが絶滅した種について飼育個体を野外に再導入する取組(例:北米大陸のクロアシイタチ(イタチの仲間))も報告されています。
生物多様性を総合的に評価する試みも行われています。国連の主唱により平成13年~17年にかけて実施された「ミレニアム生態系評価(MA)」は、95ヶ国から1,300人以上の専門家が参加して実施された、生態系に関する大規模な総合評価です。生態系の変化が人間の福利に及ぼす影響を評価することを目的として、生態系と人間の福利との間のつながりとして特に生態系サービス(生態系から得られる恵み)に焦点を当てています。24の代表的な生態系サービスについて地球規模での状態や変化を評価した結果、生態系サービスが向上したのは、わずか4項目(穀物、家畜、水産養殖、気候調節)のみであることが明らかになりました。その一方、15項目(漁獲、木質燃料、遺伝資源、淡水、防災制御など)では、生態系サービスが低下しているか、持続できない形で利用されていることが示されました。ミレニアム生態系評価は、生態系や生物多様性の評価を通じて、現在の人間活動や社会システムのあり方に警鐘を鳴らし、順応的な生態系管理の重要性を説いています。
平成18年に生物多様性条約事務局が公表した「地球規模生物多様性概況第2版(GBO2)」では、持続可能な森林や農地生態系等の面積、生態系の連続性と分断性など15の指標により地球規模の生物多様性の状況を評価しています。その結果、保護地域の指定範囲などを除く12の指標が悪化傾向となるなど、生物多様性の損失が依然進行していることが示されました。一方で、保護地域の指定や資源管理などのしかるべき対策をとれば、特定の生息・生育地あるいは種に関しては、この傾向を逆転できるとしています。さらに、今回用いた15の指標のうち、2010年までの生物多様性の損失速度の変化を判断することが可能な指標は、「特定の種類の生態系における生息・生育地の変化」、「特定の種の個体数と分布の推移」、「絶滅危惧種の現状」、「海洋食物連鎖指数」、「窒素蓄積」の5つであるとしています。
平成20年に開催されたCOP9では「生態系と生物多様性の経済学(TEEB)」の中間報告書が公表されました。これは、19年に開催されたG8環境大臣会合の成果であるポツダム・イニシアティブで、生物多様性の地球規模の経済的価値について検討することが指示されたことを受けて実施されたもので、気候変動による経済的損失や対策コストを分析したスターン・レビュー「気候変動の経済学」にならい、生物多様性の損失による経済影響を分析しています。TEEBは2段階で構成されるとされ、今回の中間報告はその第1段階に当たり、生態系や生物多様性の重要性のほか、何の対策も講じなかった場合の生物多様性に対する影響を提示しています。例えば、「早ければ2030年までにサンゴ礁の60%が漁業、汚染、気候変動による白化などにより消滅する」、「自然地域が、農地への転換や気候変動などにより2000年から2050年までの50年間に11%失われる」などといった深刻な結果を招くと報告されています。
以上のように、レッドリストのような取組に加え、近年、地球規模の生物多様性の状況を生態系サービスや経済的価値など、さまざまな視点から把握する取組も行われるようになり、その結果、世界の生物多様性の状況は急速に悪化しており、対策を講じなければその影響は将来にわたり続く可能性が高いという結論が出されています。
生物に国境はありません。例えば、ツバメは、春に日本に飛来して産卵・子育てし、冬は東南アジアへ移動する渡り鳥です。サケ(シロザケ)は、日本の川で生まれた稚魚が海に下り、ベーリング海等を回遊しながら大きくなり、生まれた川へ戻って産卵する回遊魚です。このように、日本で繁殖する生物の中には生涯を日本だけで完結しない生物が存在します。これらの生物を保全するには、日本だけでなく他の国々とも連携する必要があります。
日本人は食料をはじめ、生物多様性の恵みの多くを輸入に頼っており、海外の生物多様性の恵みなくして今の生活を送ることはできません。日本の生物多様性は、自然界における生物の移動だけでなく、私たちの生活においても、世界とつながっているのです。
味噌、醤油、納豆などの原料として日本人の生活に欠かせない大豆は、国内消費量の約96%を輸入に頼っています。世界の生産量に占める日本の消費量はわずか2%程度ですが、大豆生産のために原産国で農地開発が行われれば、間接的ではあるものの、日本人は知らないうちに原産国の生物多様性の第1の危機に荷担してしまう可能性があります。
寿司や刺身などとして日本人が好んで食べているマグロ類は、国内消費量のおよそ62%を海外からの輸入に頼っており、これは世界の生産量の約4分の1を占めています。マグロ類の養殖産業は始まったばかりで、多くは野生の漁獲物を利用しています。持続可能な範囲で利用している限り問題はありませんが、日本を含むマグロ類消費国は、知らないうちに世界中のマグロ類に対し第1の危機を与えうる立場にあります(図5-2-1)。
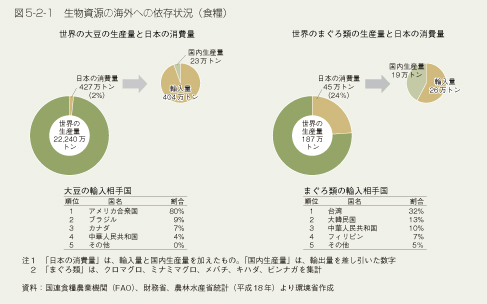
その他にも、わが国はペット用も含め多くの生きた生物を輸入しています。平成19年度には、76ヶ国から、哺乳類で約35万個体、鳥類で約4万個体、両生・爬虫類で約45万個体、昆虫で約6,445万個体が海外から日本に輸入されました。両生・爬虫類の大半の約40万個体を占めるカメ類を見ると、米国や中国をはじめとする30ヶ国から輸入されていることがわかります。輸入される生物には、養殖されたもののほか、野外から捕獲されるものもあります。特定の地域で特定の種が過剰に捕獲されれば、個体数に影響を与え、原産国で生物多様性の第1の危機を引き起こす可能性があります(図5-2-2)。
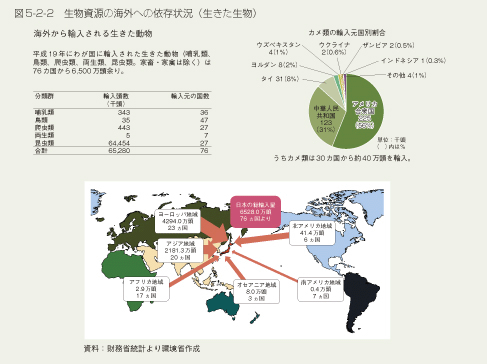
以上のように、我々の日常生活そのものが世界の生物多様性とつながっており、場合によっては、我々日本人は気付かないうちに海外の生物多様性に影響を与える可能性があるのです。
日本は、四方を海に囲まれ、6,800余りといわれる多くの島々から構成されています。国土面積は約3,800万ヘクタールと比較的狭いにもかかわらず、海岸線の全長は約35,000kmといわれ、海岸から深山幽谷にいたるまで複雑で起伏に富んだ地形が見られます。全国的に降水量に恵まれ、多くの地域に四季が存在し、南北約3,000km、標高差約3,800mの中に、亜寒帯から亜熱帯にいたる気候帯が存在します。この多様な自然環境の中に約9万種以上の生物種が確認されています。その中には日本だけにしか確認されていない固有種も多く、陸上の哺乳類の約4割、両生類の約8割がそれに当たります。
森林面積は世界的に減少していますが、日本の森林面積は、国土の約67%でほとんど変化がありません。日本は世界的に見ても森林率が高く、先進国ではフィンランドに次いでいます。また、国内の森林の蓄積量は年々増加していますが、これは人工林における樹木の生長量が多い一方、国内の森林資源の利用が少ないことなどが一因とされています。スギ・ヒノキなどの人工林では、林業の採算性の低下などから間伐などの手入れが十分行われないことで、森林の持つ水源涵養、土砂流出防止などの機能や生物の生息・生育環境としての質の低下が懸念されています。また、薪炭林や農用林などの二次林の環境に適応して生息・生育していた動植物にとっては、管理放棄による環境の変化が大きな痛手となっています(図5-2-3)。
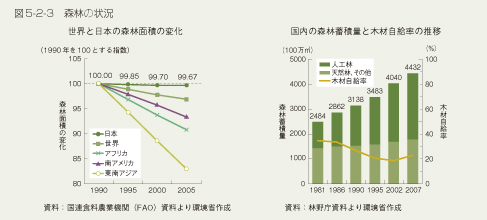
農地面積は世界的に増加していますが、日本国内の農地面積は減少し、国内の耕作放棄地の面積は年々増加しています。耕作放棄による農地やその周辺の環境の変化による生息・生育環境の質の変化によって、第2の危機に直面している生物も存在すると考えられます(図5-2-4)。
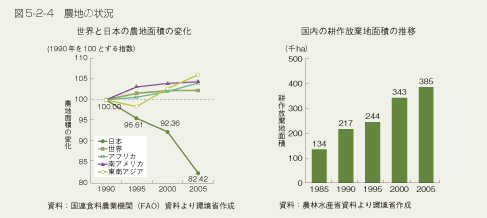
以上のように、里地里山のように人為が加わることで維持されてきた環境においては、農林業などの人間活動の縮小が、必ずしも日本の生物多様性によい結果をもたらしているわけではありません。
| 前ページ | 目次 | 次ページ |