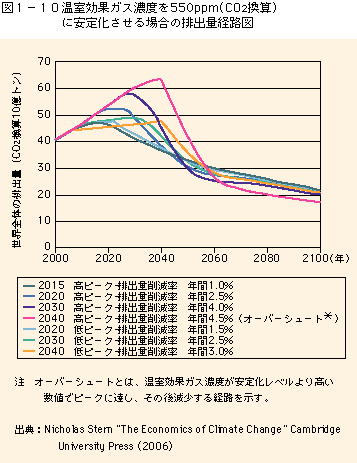平成18年度 環境の状況平成18年度 循環型社会の形成の状況
第1部 総説
総説1 進行する地球温暖化と対策技術
第1章 進行する地球温暖化
地球温暖化が進行しています。「地球温暖化」という言葉は一般にも広く知られるようになりました。しかし、地球温暖化によって何が起こるのか、それが私たちの生活にどのような支障を及ぼすのかといった情報については、十分に知られているとは言い難いのが現状です。
1 今直面している地球温暖化
温室効果ガスによる気候変動の見通し、自然、社会経済への影響評価及び対策に関する評価を担当している「気候変動に関する政府間パネル(IPCC)」において、現在、第4回目になる評価報告書の作成が進められています。
地球温暖化に関する科学的知見を集約している第1作業部会報告書によれば、大気中の二酸化炭素濃度は379ppm(2005年)と、産業革命前の約280ppmの約1.4倍となっています。また、1906年から2005年までの100年間で、地球の平均気温は0.74(0.56~0.92)℃上昇したとされています。さらに、最近50年間の長期傾向(10年当たり0.13(0.10~0.16)℃)は、過去100年のほぼ2倍の速さとされます。
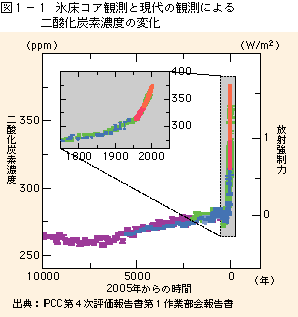
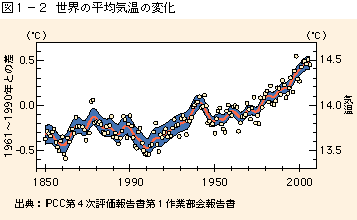
IPCC第4次評価報告書第1作業部会報告書によれば、1995年から2006年までの12年のうち、1996年を除く11年の世界の地上気温(陸上における地表付近の気温及び海面水温の平均)が、1850年以降で最も温暖な12年の中に入るとされます(図1-3)。2001年に公表されたIPCC第3次評価報告書においては、1861年以降の観測記録によると1990年代は最も暖かい10年間であった可能性がかなり高いとされていますが、2000年以降の各年の世界の年平均気温は、これを超える高い水準で推移しています。
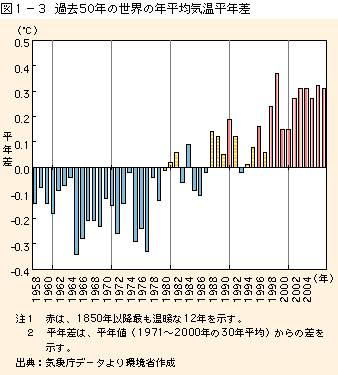
我が国でも、年平均地上気温は、長期的には100年当たり1.07℃の割合で上昇しており、特に1990年代以降、高温となる年が頻出しています(図1-4)。
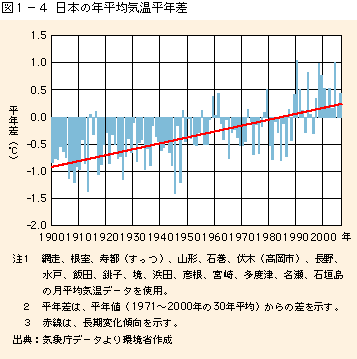
このデータは、1898年以降観測を継続している気象観測所の中から、都市化による影響が少なく、特定の地域に偏らないように選定された17地点の月平均気温データを使用しています。都市部においては、ヒートアイランド現象等の影響も考慮しなければなりませんが、気温の上昇傾向は更に顕著です(図1-5)。
二酸化炭素濃度の上昇と気温の上昇による影響と考えられる変化が、既に世界中のあちこちで現れ始めています。
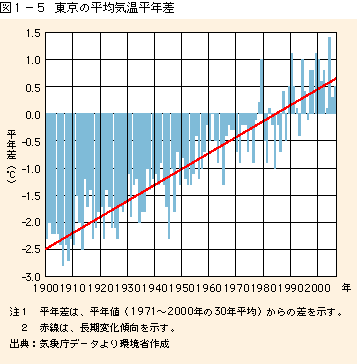
コラム 猛暑日の設定
気象庁では、天気予報等で用いる気温に関する用語として、日最低気温が0℃以下となる「冬日」や夜間の最低気温が25℃以上の「熱帯夜」などを定めています。このうち暑さについては、日最高気温が25℃以上の「夏日」と日最高気温が30℃以上の「真夏日」がありましたが、近年、都市部を中心として最高気温の記録更新が相次いでいること等を受けて、2007年4月から日最高気温が35℃以上の日を「猛暑日」とすることとなりました。
ア 異常高温の発生
2003年夏、ヨーロッパ中部・西部は史上まれに見る熱波に襲われました。フランスで1万人以上、ヨーロッパで5万人以上が死亡するなど、各国で大きな人的被害が発生しました。スイスのチューリッヒでは、6月の月平均気温が平年を6.9℃上回りました。2006年末から2007年初頭にかけては、北半球のほぼすべての地域で暖冬となり、2006年12月及び2007年1月の世界の月平均気温は、それぞれ12月及び1月の気温としては1891年以来最も高い値となりました。その背景には、温室効果ガスの増加に伴う地球温暖化の影響があるとみられます。
2004年、東京(大手町)では、1日の最高気温が30℃を超える「真夏日」の日数が観測史上最多の70日に達しました(1971~2001年の平均は46日)。東京消防庁によれば、同年5月1日から9月30日までに救急車によって搬送された熱中症患者は、東京都で793人に上りました(1996~2005年の平均は472人)。地球温暖化によってこうした異常高温が頻発するようになると、熱中症による被害が更に拡大することが予想されます。
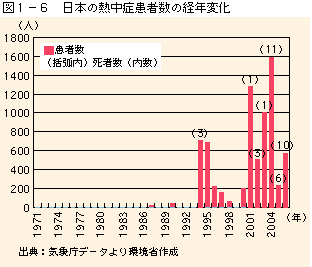
イ 強い熱帯低気圧の発生、大雨の発生頻度の増加
地球温暖化に伴って、1970年頃以降、熱帯の海面水温の上昇と関連した北大西洋の強い熱帯低気圧の強度の増加や、ほとんどの陸域における大雨の発生頻度の増加が観測されています(IPCC第4次評価報告書第1作業部会報告書)。
2005年8月、アメリカ南東部を襲ったハリケーン・カトリーナは、ハリケーンの強さを表すシンプソン・スケールで最高のカテゴリー5を記録し、死者1,300人以上という大惨事をもたらしました。国際防災戦略(ISDR)によれば、カトリーナによる米国内の損害額は1,250億ドル(約14兆6,000億円)に達するとされます。米国海洋大気庁(NOAA)によれば、この年、北大西洋からカリブ海にかけての一帯では従来の記録(19個)を大幅に上回る28個のトロピカル・ストーム(最大風速17.2m/s以上の熱帯低気圧)が発生し、そのうち、14個がハリケーン(最大風速32.7m/s以上の熱帯低気圧)にまで発達しました。地球温暖化により熱帯域の海面水温の上昇が更に進むと、強い勢力を持つ熱帯低気圧の発生頻度が増加すると予測されています。
日本でも、大雨の発生頻度の増加が指摘されています。気象庁「異常気象レポート2005」によれば、1975~2004年と1901~1930年を比較すると、日降水量100mm以上の日数は1.19倍、200mm以上の日数は1.46倍の増加となっています。
気象庁気象研究所の予測によれば、地球温暖化が進むと、太平洋高気圧が北上しにくくなり、梅雨明けが遅い年が次第に増えて、8月にずれ込む可能性が高いとされています。
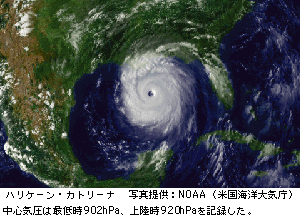
ウ 海面上昇
IPCC第4次評価報告書第1作業部会報告書によれば、20世紀を通じた海面水位上昇量は約0.17(0.12~0.22)mとされています。熱による海水の膨張や氷床の融解が主な原因として指摘されています。
南太平洋諸国では、既に多くの海岸沿いの地域が海岸侵食・水没の危機に瀕しています。ツバルは、南緯5~10度に点在する9つのサンゴ礁から成る面積わずか26km2の島嶼国で、約1万人の国民の半分が首都フナフティに住んでいます。フナフティのある平均標高1.5m以下のフォンガファレ島では、近年、潮位が高くなる1~3月に、浸水被害が激しくなっていると言われます。海岸線に並ぶヤシの木の一部は、海に投げ出されるように倒れています。これは、海岸の侵食が進んでいることを示していると考えられます。また、畑に海水が入り込み、作物が育たなくなる塩害も報告されています。
塩害の発生の背景には、人口増加によって浸水の起こりやすい地域にも畑や居住地が拡大されてきたという社会的な問題もありますが、地球温暖化が進めば、こうした被害が更に拡大することが予想されます。

エ 生物の生息・生育状況の変化
生態系の構成要素である生物も、敏感に反応しています。地球温暖化による影響と考えられる変化が生物に現れている事例が、世界中から報告されています。
地球温暖化に対して地球上で最も脆弱であると言われている地域の1つである北極圏では、ホッキョクグマの絶滅が危惧されています。ホッキョクグマは、主に、海氷に開いた穴から息継ぎのために顔を出すアザラシを捕獲して食べ、それを脂肪として蓄えて生存していますが、地球温暖化によって海氷がなくなるとアザラシが獲れなくなってしまいます。既に、カナダのハドソン湾に生息するホッキョクグマの平均体重に関する調査結果では、平均体重は295kg(1980年)から230kg(2004年)に減少したとされています。これは、ホッキョクグマが繁殖能力を維持する最低限度の体重に近いと言われます。氷の融解により長距離を泳ぐことを余儀なくされたホッキョクグマの溺死についての報告もあります。国際自然保護連合(IUCN)は2006年、ホッキョクグマを絶滅の危険が増大している種としてレッドリストに記載しました(Vulnerable(VU))。
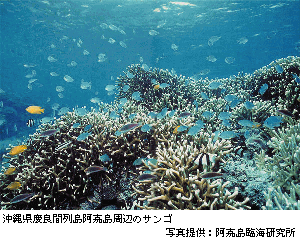
また、近年、世界各地でサンゴの白化現象(サンゴの体内に共生している藻類が死んだり抜け出したりする現象)が報告されています。サンゴ礁は、4000種類とも言われる魚類の産卵・生息場所として極めて重要であるとともに、自然の防波堤として沿岸域の住民の生活を守っています。このサンゴが白化を起こす原因は様々ですが、現在最も深刻なのは、海水温の上昇によるストレスであると言われています。1998年には、史上最大のエルニーニョ現象の影響もあり、世界のサンゴ礁の16%が損傷・破壊されたと推定されています。地球温暖化を背景にエルニーニョ現象の影響が加わって海水温が上昇すれば、これに匹敵する白化現象がごく普通に起きるようになると科学者たちは予測しています。また、二酸化炭素の増加に伴う海水の酸性化が進むほどに、サンゴは炭酸カルシウムから骨格を形成することが困難となるため、成長が阻害されるおそれを指摘する報告もあります。IPCC第4次評価報告書第1作業部会報告書によれば、全球平均した海面のpH値は、工業化以前の時代から現在までの0.1の減少に加え、21世紀には更に0.14~0.35減少すると予測されています。
地球温暖化に伴って、生物の生息・生育区域も変化しています。日本でも、ナガサキアゲハなど南方系のチョウ類が分布域を北方に広げていく現象が注目を集めています(図1-7)。また、近年、中山間地ではシカの分布域が拡大しており、これに伴う農林業被害も深刻な状況になっています。シカの越冬には積雪量が一定以下であることが必要とされており、越冬地の拡大と地球温暖化に関連がある可能性も指摘されています。
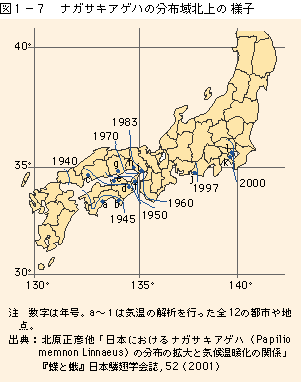
2 地球温暖化の将来予測
IPCC第4次評価報告書第1作業部会報告書によれば、今世紀末(2090年~2099年)の平均気温上昇は、環境の保全と経済の発展が地球規模で両立する社会においては約1.8℃(1.1~2.9℃)ですが、今後も化石燃料に依存しつつ高い経済成長を実現する社会では、約4.0℃(2.4~6.4℃)にもなると予測されています。
IPCC第4次評価報告書第2作業部会報告書によれば、これまで評価された植物及び動物種の約20~30%は、全球平均気温の上昇が1.5~2.5℃を超えた場合、絶滅のリスクが増加する可能性が高いとされています。
また、世界的には、潜在的食料生産量は、地域の平均気温の約1~3℃までの上昇幅では増加するものの、これを超えると減少に転じると予測されています。
サンゴについては、約1~3℃の海面温度の上昇により、白化や広範囲な死滅が頻発すると予測されています。また、気温の上昇に伴い、数億人が水不足の深刻化に直面するとされています。
今世紀の半ば以降、陸上生態系による炭素吸収は、弱まるか、排出に転じすらする可能性が高いとされています。これは、気候変化を増幅させるとされています(第2章第3節5参照)。
このように、全球平均気温の上昇が1990年比で約1~3℃未満である場合には、ある地域のある分野で便益をもたらす影響と、別の地域の別の分野でコストをもたらす影響が混在する可能性が高いが、気温の上昇が約2~3℃以上である場合には、すべての地域において便益の減少かコストの増加のいずれかが生じる可能性が非常に高いとされています。
現在のペースで人類社会が温室効果ガスの排出を続けていけば、この上昇幅はいずれ突破されることが予想され、まさに、「地球温暖化終末時計」の時が刻まれている状況にあると言えます。破局に突き進む時計の針を止めるため、地球温暖化対策の加速が喫緊の課題となっています。
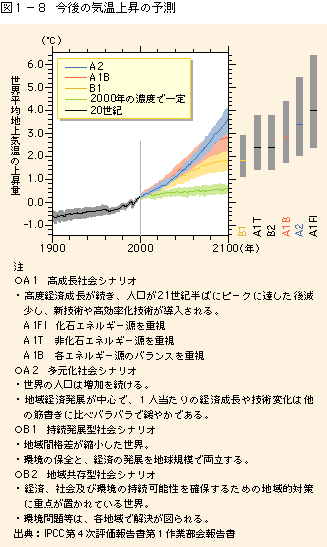
3 地球温暖化のメカニズムと早期対応の必要性
地球の気温は、太陽からのエネルギー入射と地球からのエネルギー放射のバランスによって決定されます。
地球は太陽からのエネルギーで暖められます。暖められた地球からは熱が放射されますが、大気に含まれる二酸化炭素を始めとする温室効果ガスがこの熱を吸収し、再び地表に戻しています(再放射)。これにより、地球上は、平均気温約14℃という生物の生存が可能な環境に保たれています。
ところが、産業革命以降の人間社会は化石燃料を大量に燃やして使うようになり、大量の二酸化炭素などの温室効果ガスを大気中に排出するようになりました。このため、大気中の温室効果ガス濃度が上昇し続け、地表からの放射熱を吸収する量が増えてきました。これにより、地球全体が温暖化しているのです。これが、地球温暖化のメカニズムと言われています。人類が化石燃料の消費によって毎年排出する二酸化炭素の量は約70億トン(炭素換算。以下「Cトン」という。二酸化炭素換算では約260億トン)であり(2000~2005年の平均値)、今後更に増加すると予測されています。一方、自然が年間に吸収できる二酸化炭素の量は約30億Cトン(二酸化炭素換算では約110億トン)にとどまると推定されています。気候を安定化させ、悪影響の拡大を防ぐには、温室効果ガスの排出量と吸収量のバランスを取ることが必要です。
一部には、人間の活動に起因する二酸化炭素排出の増加が地球温暖化をもたらすことに対して強い疑問を呈する科学者もいます。しかし、産業革命以後、とりわけ20世紀後半の二酸化炭素濃度と気温の急激な上昇は、人為的な二酸化炭素排出の増加を無視しては説明がつきません。
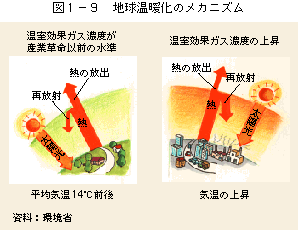
人為起源の二酸化炭素が地球温暖化の原因である説を否定する科学者は、しばしば、人為起源の二酸化炭素排出量約70億Cトンは、大気や海、生態系の間の炭素循環量約900億Cトンと比較すれば小さいと主張します。しかし、この70億Cトンは年間の排出量であり、人間活動による二酸化炭素排出量の累計は3500億Cトンとされています。これは、産業革命以前の大気中二酸化炭素残存量の6~7割にも当たり、自然界の炭素循環の過程で吸収できる量をはるかに超えています。
また、二酸化炭素濃度の上昇が地球温暖化の原因なのではなく、気温の上昇が二酸化炭素濃度上昇の原因であるとの議論もあります。すなわち、海面温度上昇によって海面から二酸化炭素が放出され、それが大気中の二酸化炭素濃度上昇の主な要因となっているとの主張です。しかし、仮にこの仕組みが働くとしても、過去数十年の急激な二酸化炭素濃度の上昇をうまく説明できません。また、近年の気温上昇が何に起因しているのかを説明していません。
G8諸国の学術会議は共同で、ここ数十年の地球温暖化の原因の大半が人間の活動に起因する二酸化炭素排出量の増加である可能性が高いとして、G8諸国に対して直ちに行動するよう呼びかける声明を発表しました(2005年)。IPCC第4次評価報告書第1作業部会報告書も、20世紀半ば以降に観測された世界平均気温の上昇のほとんどは、人為起源の温室効果ガスの増加によってもたらされた可能性がかなり高い(可能性が90%以上である)としています。地球温暖化が人間の活動に起因する二酸化炭素などの温室効果ガスの増加が原因であることは、世界の多くの科学者の間で一致した見解と言えます。
IPCC第4次評価報告書第3作業部会報告書は、2030年を見通した削減可能量は、予測される世界の排出量の伸び率を相殺し、更に現在の排出量以下にできる可能性があるとしています。2030年における削減可能量は、積み上げ型の研究によると、炭素価格が二酸化炭素換算で1トン当たり20米ドルの場合は、年90~170億トン(二酸化炭素換算)であり、炭素価格が同様に100米ドルの場合は、年160~310億トン(二酸化炭素換算)であるとされます。
また、安定化レベルが低いほど、排出量のピークとその後の減少を早期に実現しなければならず、今後20~30年間の緩和努力によって、回避することのできる長期的な地球の平均気温の上昇と、それに対応する気候変動の影響の大きさがほぼ決定されるとしています(表1-1)。2050年に温室効果ガスを710~445ppm(二酸化炭素換算)で安定化させた場合のマクロ経済影響は、世界平均でGDP+1%~-5.5%とされます。
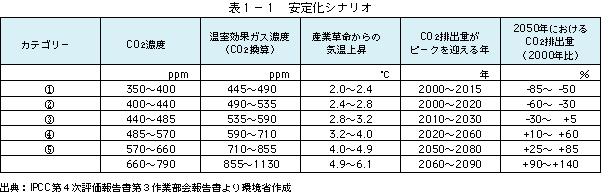
さらに、適切な投資、技術開発などへの適切なインセンティブが提供されれば、それぞれの安定化レベルは、現在実用化されている技術又は今後10年間において実用化される技術の組合せによって達成可能であるとしています。そして、排出緩和を促すインセンティブの策定のために各国政府が取りうる国内政策及び手法は多種多様であり、いずれの手法にも利点と欠点が存在するとしつつ、規制措置、税金・課徴金、排出権取引制度、自主協定、情報的措置、技術研究開発などを挙げています。
温室効果ガスの排出に価格が付くこと(炭素価格を設定すること)の政策は、生産者及び消費者における温室効果ガスの排出が低い製品に対する投資への顕著なインセンティブとなり、こうした政策は、経済的措置や政府の財政支援、規制的措置なども含むものと指摘されています。
2006年10月に、世界銀行のチーフエコノミストであったニコラス・スターン卿がイギリス政府及びイギリス財務省に提出した気候変動に関する報告書(スターン・レビュー)は、気候変動は経済成長と開発に非常に深刻な影響をもたらす可能性があるが、直ちに確固たる対応策をとれば、気候変動の悪影響を回避する時間は残されているとしています。そして、早期に断固たる対応策をとることのメリットは、対応しなかった場合の経済的費用をはるかに上回るとして、国際的規模での早急な気候変動への対応を求めています。取組への着手が遅れると、同じ二酸化炭素安定化目標であっても、より迅速に排出削減を実行しなければならなくなり、また、排出量のピーク値が高くなることを意味するので、対策に係るコストの増加を招きます(図1-10)。
取り返しのつかない結果を生むリスクを回避するため、予防原則に基づいて、今、地球温暖化に断固たる決意をもって対応することが必要です。地球温暖化の深刻さを真摯に受け止め、各国が協力して効果的かつ効率的な対応策をとることが求められています。