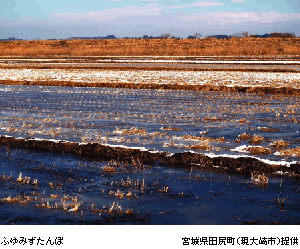
3 里地里山地域における環境保全の取組
(1)オーナー事業の活用による耕作放棄地の解消
棚田百選に選ばれた美しい農村景観が形づくられる京都府福知山市大江地区では、耕作放棄地の解消に向け、耕耘から、田植え、稲刈り等の一貫した農作業で米づくりができる「棚田オーナー制度」を平成10年より実施しています。平成16年の台風では、都市住民のオーナーが借用していた棚田も大きな被害を受け、農作業の継続が難しくなりましたが、オーナーと地元住民の強い熱意により、被害の少なかった休耕田を確保するなどして、活動が継続されました。また、被害を受けた畦畔、法面は、棚田の景観を守るため、石積みで改修することになり、今後も地元住民とオーナーが一体となった保全活動が期待されます。
(2)環境保全型農業による地域活性化
宮城県田尻町蕪栗沼(かぶくりぬま)周辺では、冬季に田に水を張る「ふゆみずたんぼ」(冬期湛水田)と呼ばれる取組により稲作を行っています。冬期湛水田は古くは江戸時代の農事書(農業の解説書)にも記載がある古い技術です。冬期に水を張ることによって夏場の雑草の生育を抑制するなどの稲作への効果をねらうものですが、これにより、マガン等の渡り鳥の冬場の渡来地が確保されるとともに、地下水のかん養など、環境面でもさまざまな効果が見られます。蕪栗沼・周辺水田は、マガン等の渡り鳥の重要な渡来地として、平成17年に国指定蕪栗沼・周辺水田鳥獣保護区に指定されるとともに、国際的に重要性が認められ、同年、ラムサール条約湿地に登録されました。また、「ふゆみずたんぼ」では雑草の生育が抑制でき、農薬の使用や施肥の回数を減らすことができることから、収穫された米は環境に配慮したおいしい米として販売され、地域の活性化につながっています。
(3)ボランティアによる里山の保全と管理
50年前まで日本三大たばこ産地であった神奈川県秦野地域では、たばこ生産の堆肥づくりのために落ち葉かきをしていました。たばこ生産が行われなくなった現在は、里山の多くが暗く湿った森となり、シカやイノシシに付いてヤマビルが侵入してきました。地元では落ち葉かきを行うことにより、ヤマビルが減少することが経験的に知られており、秦野市では約200名のボランティアの協力により、里山の落ち葉かき、下刈り・枝打ち・間伐、シカ柵設置、ヤマビル調査を一体的に実施しています。
(4)人と野生鳥獣とのより良い関係の構築
ア 人と野生鳥獣とのあつれきの未然防止
イノシシ、サル、シカによる鳥獣被害が深刻化していた滋賀県の東近江地域では、農業改良普及センターがコーディネーター役となってプロジェクトチームを結成して、総合的な鳥獣被害対策に取り組んでいます。対策に取り組んでいる地域では、捕獲、侵入防止等の従来型の対応策だけでなく、地域ぐるみで鳥獣が農地に侵入する原因となる未収穫農作物の除去や鳥獣が農地に近づかないよう人と鳥獣の間の緩衝地帯の設置、家畜放牧を行う等の総合的な対策を実施しています。その結果、同地域の竜王町薬師地域では平成15年度に農業被害額が167万円に上っていたものが16年度は被害額ゼロとなり、日野町中之郷地域では15年度に農業被害額が約300万円に上っていたものが、16年度は50万円以下、17年度は被害額ゼロとなり、また、近江八幡市白王町地域でも15年度は被害が著しかったものが16年度はゼロ、同市島町でも同様に被害が著しく減少するなどの高い効果を生んでいます。
イ 野生鳥獣の資源としての活用
北海道西興部村(にしおこっぺむら)では、NPO法人西興部村猟区管理協会によって、地元の村や農協、森林組合等で構成する西興部村猟区管理運営委員会の指導・監督のもと、有料猟区が運営されています。猟区では、入猟者へのガイド、狩猟初心者へのセミナーの実施による狩猟技術の継承、地元小学生等を対象とした野生生物の生態等についての環境教育など行っています。また、このような猟区の運営を通じて、村営ホテルの宿泊者が増加するなど、地域活性化の効果も上げています。
(5)エコツーリズムの推進による都市との交流
南信州18市町村と地元民間企業・団体が出資して設立された第3セクターでは、地域の自然、歴史、文化、技術など暮らしの中にある資源を掘り起こし、エコツアーや農林業体験など200ものツアープログラムを主に首都圏や関西圏の中・高校の修学旅行に提供しています。第3セクターでは、宣伝、インストラクターや受け入れ農家の確保のほか、ツアープログラムの手配、調整、精算など、一貫したシステムを構築し、年間延べ5万人を受け入れています。
(6)地域文化の継承と農村景観の保全
伝統的民家である笹葺き民家が残る京都府京丹後市五十川地区では、NPOが主体となり、専門家、地元住民を交えた里山景観保全の意見交換会を行いながら、里山景観の保全に努めています。特に笹を屋根材とするのは日本海側の一部に伝わる珍しい様式であることから、景観保全に加え、地域文化の継承のため、笹の刈り取り作業から屋根の修復までを地域住民と一体となって実施しています。