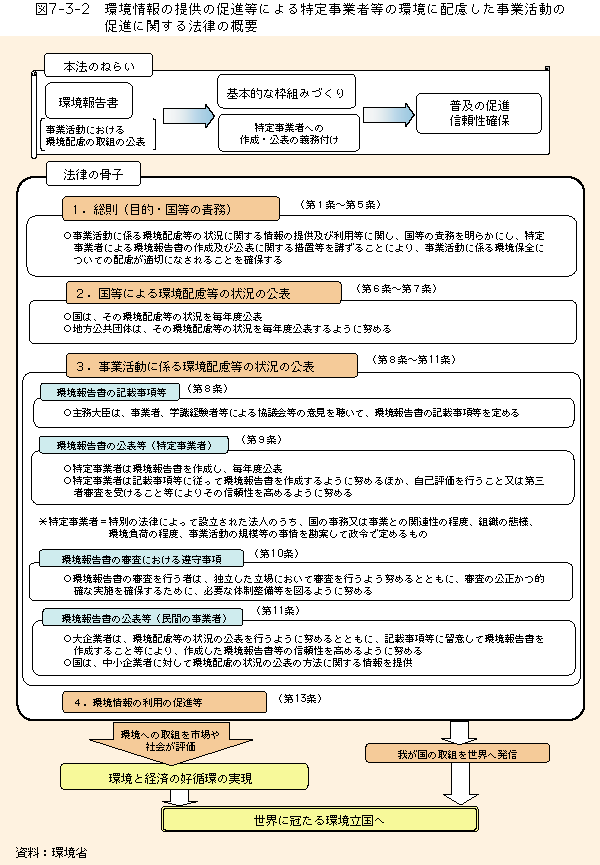
3 事業活動への環境配慮の組み込みの推進
(1)環境マネジメントシステム
環境マネジメントシステムの要求事項を定めた国際規格であるISO14001が平成16年11月に改正されたのを受けて、これを翻訳した日本工業規格JISQ14001を16年12月に改正し、この情報提供等を行うとともに、中小企業への環境マネジメントシステムの普及を図るため、環境マネジメントシステム構築融資制度により、事業者のISO14001認証取得及びそれに伴う環境対策投資を支援しました。また、全国各地で講習会を開催しました。こうした結果、国内のISO14001審査登録件数は、16年度末現在で18,869件となり、世界で最も取組が進んでいます(第1部第2章図2-4-3参照)。
(2)環境パフォーマンス評価
事業者が環境関連データを自主的積極的に収集し、環境パフォーマンス指標等の形で活用する状態を創出するには、これらのデータを収集・管理することの効用や効果を明確に示すことが必要です。このため、環境パフォーマンスを把握する範囲や企業の社会的責任(CSR)に関する指標など、新たな方向性について調査・検討を進め、報告書を取りまとめました。
(3)環境会計
事業者による効率的かつ効果的な環境保全活動の推進に資する環境会計システムの確立に向けて、環境会計ガイドライン2002年版を国内外の調査研究の成果や最新の実務動向も反映し、平成17年2月に「環境会計ガイドライン2005年版」として改訂しました。また、企業経営に役立つ環境管理会計手法の研究を推進し、その報告書を取りまとめました。さらに、環境会計の国際動向を把握するため、国連持続可能開発部環境管理会計専門家会合(UNDSDEMA−EWG)などの国際的な議論に積極的に参画しました。
(4)環境報告書
さまざまな規模、業種を含め幅広い事業者に環境報告書の作成と公表の取組を広げるため、「環境報告書ガイドライン(2003年度版)」と「GRIサステナビリティレポーティングガイドライン2002」との併用ガイダンスを策定しました。このほか、環境コミュニケーション大賞による表彰や環境コミュニケーションシンポジウムの開催、インターネット上に開設した環境報告書のデータベースの運用などにより、環境報告書への取組支援を行いました。
また、国による環境配慮等の状況の公表、特定事業者による環境報告書の公表、及び民間の大企業による環境報告書等の自主的な公表、並びに環境情報の利用の促進などを主な内容とする、環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律(平成16年法律第77号)が平成16年5月に成立し、17年4月の施行に向けて特定事業者の指定や環境報告書の記載事項等の策定などの整備等を進めました(図7-3-2)。
(5)中小企業の取組の促進
中小企業等においても容易に環境配慮の取組を進めることができるよう、環境マネジメントシステム、環境パフォーマンス評価及び環境報告を一つに統合した環境配慮のツールである「エコアクション21(環境活動評価プログラム)」について、平成16年4月に改訂版を公表しました。また、小規模事業者向けの支援ソフトウェアとして開発した「環境大福帳」を16年7月に公表したほか、エコアクション21や環境大福帳の普及促進を担う人材を育成するための指導者講習会を実施しました。
(6)公害防止管理制度
工場における公害防止体制を整備するため、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)によって一定規模の工場に公害防止に関する業務を統括する公害防止統括者、公害防止に関して必要な専門知識及び技能を有する公害防止管理者等の選任が義務付けられており、約2万の特定工場において公害防止組織の整備が図られています。
同法に基づく公害防止管理者等の資格取得のために国家試験が、昭和46年度以降毎年実施されており、平成16年度の合格者数は5,805人、これまでの延べ合格者数は29万6,287人です。
また、国家試験のほかに、一定の技術資格を有する者又は公害防止に関する実務経験と一定の学歴を有する者が公害防止管理者等の資格を取得するには、資格認定講習を修了する方法があり、平成16年度の修了者数は3,050人、これまでの修了者数は24万1,813人です。