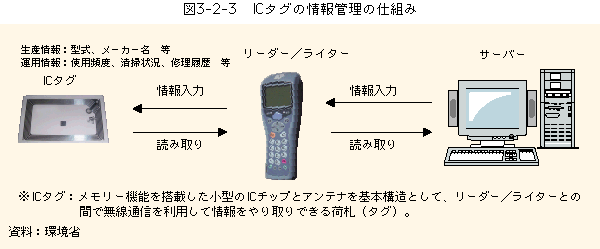
2 「しくみ」としての日本の環境政策
日本では、脱温暖化社会と循環型社会の構築に向けた「しくみ」として、次のような施策を行っています。
(1)脱温暖化社会の構築
地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)では、京都議定書発効の際に京都議定書目標達成計画を定めることとしています。平成17年2月の京都議定書の発効を受け、同年4月、京都議定書の6%削減約束を確実に達成するために必要な措置を定めるものとして、「京都議定書目標達成計画」が策定されました。
同計画では、地域・都市構造や交通システムの抜本的な見直し等によりエネルギーの効率的利用を構造的に組み込むことや、施設・主体単位で自らの活動に関連して排出される二酸化炭素の総体的な抑制を目指してさまざまな取組を行うこと、機器単体のさらなる省エネ性能の向上、普及を図ることなどが挙げられました。また、森林吸収源対策などの温室効果ガス吸収源対策を推進すること、京都メカニズムを適切に活用することなどが盛り込まれました。
また、知識の普及や国民運動の展開を図ること、公的機関が率先して温室効果ガス削減に取り組むこと、サマータイムの導入など、各部門の個々の対策を横断的に推進するための施策についても、同計画に盛り込まれました。また、環境保全と経済発展といった複数の政策目的を同時に達成するため、自主的手法、規制的手法、経済的手法、情報的手法などあらゆる政策手法を総動員し、それらの特徴を活かしつつ、有機的に組み合わせるというポリシーミックスの考え方を活用することとしました。経済的手法は、市場メカニズムを前提とし、経済的インセンティブの付与を介して各主体の経済合理性に沿った排出抑制等の行動を誘導するものであり、地球温暖化対策の経済的支援策としての有効性も期待されており、その活用に際しては、ポリシーミックスの考え方に沿って、効果の最大化を図りつつ、国民負担や行財政コストを極力小さくすることが重要であり、財政的支援に当たっては、費用対効果に配慮しつつ、予算の効率的な活用等に努めることとされました。経済的手法の一つである環境税については、国民に広く負担を求めることになるため、関係審議会を始め各方面における地球温暖化対策に係るさまざまな政策的手法の検討に留意しつつ、地球温暖化対策全体の中での具体的な位置付け、その効果、国民経済や産業の国際競争力に与える影響、諸外国における取組の現状などを踏まえて、国民、事業者などの理解と協力を得るように努めながら、真摯に総合的な検討を進めていくべき課題とされました。
(2)循環型社会の構築
循環型社会とは、天然資源の消費を抑制し、環境への負荷ができる限り低減される社会をいいます。具体的には、第1に製品等が廃棄物となることが抑制され、第2に排出された廃棄物等についてはできるだけ適正に循環的な利用がなされ、最後にどうしても利用できないものは適正に処分される社会のことです。
近年の世界人口の増加や経済社会活動の拡大に伴い、世界的に資源の需要が急増し、その一方で廃棄物の排出量も増加しています。これを背景に、循環資源を含む資源や製品などの国際流通が活発化しており、その中で有害廃棄物を有価物と偽った不法な輸出や、循環資源の不適切な処理による環境汚染が問題となっています。資源の有効利用と環境保護を推進するためには、3R(リデュース、リユース、リサイクル)による循環型社会の構築を国際的に推進することが必要です。
そこで、平成16年6月に米国ジョージア州シーアイランドで開催されたG8サミットにおいて、小泉総理大臣が3Rを通じて循環型社会の構築を目指す「3Rイニシアティブ」を提案し、各国首脳が合意しました。この合意に基づき、3Rイニシアティブを開始するための閣僚会合が、平成17年4月28日〜30日、東京で開催されました(第2部第7章第9節1参照)。
コラム 愛・地球博
平成17年3月25日から9月25日までの間、愛知県で2005年日本国際博覧会(愛・地球博)が開催されています。愛・地球博では、メインテーマに「自然の叡智」を掲げ、環境に配慮した取組や環境保全の普及啓発を目的とした展示などを行っています。
環境配慮の取組としては、例えば、日本館では、生ごみを使った燃料電池発電などのクリーン・エネルギーで電力のすべてを賄ったり、リユースを容易にするために建築物を解体しやすい設計とするなど、さまざまな取組を実施しています。それらの取組の一つとして、日本館では、ICタグを活用して情報を管理し、リユースに役立てようという実験的取組を行っています。リユース品は、残存価値に関する情報(使用頻度や劣化状態など)が不足しているため、価格が適正でなかったり、すぐに壊れるかもしれないという不安から活用されにくい場合があります。そこで、日本館では、エレベータ乗り場の操作ボタンや空調機器の吹き出し口などに名刺大のICタグを貼付し、リユース品の残存価値を把握するための情報を管理します。二次利用者を公募する際に、ウェブ上でICタグに入力された情報を公開することにより、二次利用者が安心してリユース品を買えるようになり、リユースの促進につながります(図3-2-3)。
また、環境保全の普及啓発を目的とした展示として、環境省が出展している「ECO LINK(エコ・リンク)」では、私たち一人ひとりの行動が地球環境にとって大きな意味を持つことへの気づきを促し、地球温暖化をはじめとした地球環境問題への取組として、ライフスタイルの変革を促進することを目的とした展示を実施しています。