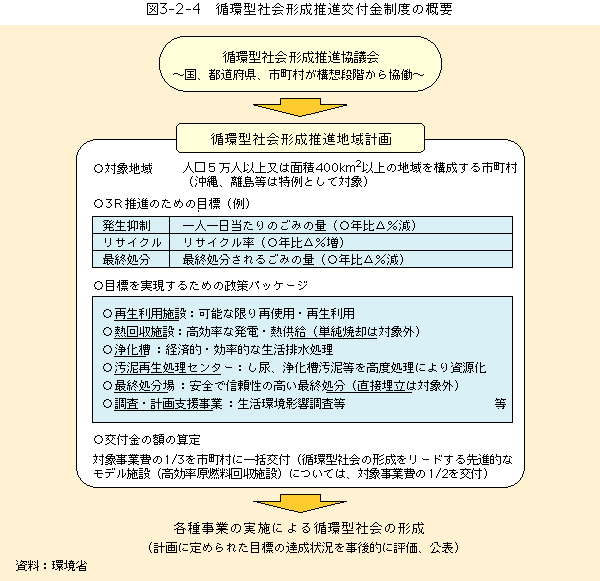
3 国と地方が連携した環境行政のあり方
今日の環境問題の多くは、地方公共団体の行政区域にとどまらず、広域的な、さらには国際的な広がりを持ったものとなっています。また、私たちの身近な活動から発生する環境負荷が環境問題の原因となっていることから、その解決には地域住民と一体となった取組が必要です。このため、地方公共団体と国が連携して、環境問題に取り組むことが必要になります。
政府では、近年地方分権などの行政改革を進めており、平成16年11月に政府・与党で「三位一体の改革について」をまとめたほか、12月に「今後の行政改革の方針」を閣議決定しました。これらの方針では、「民間にできることは民間に」「地方にできることは地方に」等の観点から、国と地方公共団体の役割を明確にして、国・地方を通じた簡素で効率的な行財政システムを構築することとしています。また、第2章第6節3で述べたように、規模の大きな地方公共団体は、環境基本計画の策定など、より環境行政に積極的に取り組んでいることから、市町村合併の進展に伴って、さらに地方における環境行政の進展を図ることが重要になります。
これらの改革などを踏まえ、国と地方公共団体が一体となって前向きに環境問題に取り組む「しくみ」を構築することにより、地域において効果的な環境行政が実現するとともに、より良い環境がより良い地域を創る基盤をつくります。そのいくつかの例を見ていきます。
(1)地域における循環型社会づくり
廃棄物の処理やリサイクルについては、平成15年に循環型社会形成推進基本計画が策定されるなど、近年、これまでの公衆衛生の向上や公害問題の解決から、日本全体として、さらには国際的な連携も視野に入れた循環型社会の形成という新しい課題に対する取組が求められるようになってきました。
そこで、環境省では、平成17年度から、従前の廃棄物処理施設整備に係る補助金を原則廃止して、新たな循環型社会の形成を推進していくための交付金制度を創設しました(図3-2-4)。これにより、市町村において、都道府県及び国と構想段階から意見交換を行って循環型社会の形成を推進するための計画を作成し、3R(リデュース、リユース、リサイクル)を推進するための戦略的な目標を設定するとともに、広域的かつ総合的に施設整備を推進していくこととしました。地方の自主性・裁量性を発揮しつつ、国と地方が構想段階から協働して施策を推進することにより、日本全体として最適な循環型社会づくりを進めていきます。
(2)魅力的な国立公園づくり
自然公園は、傑出した自然の風景地で、自然とのふれあいの場である一方で、地域においては、重要な観光資源であるとともに、地域住民の生活の場でもあります。
自然公園の管理については、平成12年に国立公園は国が管理することを基本に国と地方公共団体との間で許可権限を見直していますが、17年からさらに施設整備における両者の役割分担を明確にしました。国立公園については、補助金を廃止し国の直轄事業として実施する一方で、国定公園等については、現行の補助金を交付金化して地方公共団体の裁量性を高めることとしました。また、都道府県立自然公園等については、補助金を廃止し地方公共団体に委ねることとしました(図3-2-5)。
国立公園では、今後も国の地方環境事務所(平成17年10月まで自然保護事務所)が中心となって国立公園の保護管理を進めていきますが、地方公共団体においても地域の観光資源や生活の場等を管理する観点から、引き続き国と連携することが必要です。さらに、国と地方公共団体が中心となって、各国立公園の地域的な特色や事情、求められるニーズを勘案して、公園の保護管理に必要な業務や受益者負担も含めた所要経費の分担のあり方等について地域の関係者間の合意を図ること等により、さらに質の高い魅力的な国立公園づくりを行うことができます。
(3)地方環境事務所の設置
環境省においては、地域の実情に応じた機動的できめ細かな環境行政を展開するため、現行の自然保護事務所と地方環境対策調査官事務所を統合し、平成17年10月から全国7ブロックに地方環境事務所を設置することになりました。地方環境事務所には、地方支分部局として、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)や、自然公園法(昭和32年法律第161号)等に規定する権限を委任することができるようになり、地域での機動的できめ細かな対応が可能となります。この事務所を拠点として、地方公共団体、事業者、民間団体、地域住民等と連携しながら、廃棄物不法投棄対策、地球温暖化対策、外来生物対策など、国として軸足を地域に置いた環境施策の展開を進めます(図3-2-6)。