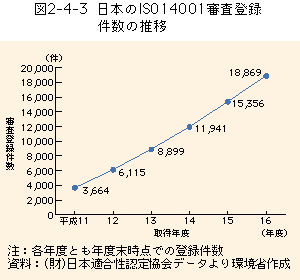
2 企業における環境負荷削減のしくみづくり
環境マネジメントシステムは、企業が環境配慮を確実に進展させる上で基盤となるものであり、多くの企業において積極的に導入が行われています(図2-4-3)。
環境に配慮した経営を先進的、先駆的に取り組んでいるいくつかの企業は、経営方針の中で環境配慮の考え方を明確に示し、その実現のための戦略や具体的な目標、行動計画を策定しています。ある企業は、「環境負荷が自然の再生能力の範囲内に完全に抑えられている社会」を長期的に目指す姿とし、事業活動におけるすべての環境負荷について総量の削減目標を明確にした「2010年長期目標」を設定しています。この目標を踏まえ、「リユース部品使用量を20倍以上向上」など、全17の目標項目について「環境行動計画」を策定しています。
また、いくつかの企業では、事業活動における環境配慮をすべての部門で徹底するため、環境目標の達成状況を業績評価基準の一つに位置付け、達成した成果を評価するしくみを構築しています。
コラム 環境の業績評価の取組
ある企業は、環境保全活動は通常業務と切り離されたものであってはならないとの考えから、各個人・部門が上げた成果を評価する「環境業績評価」を平成14年度から導入しました。各部門の環境保全活動を適正に評価する項目として、「二酸化炭素排出量の削減」「廃棄物総量に対するリサイクル率の向上」「エコプロダクツの販売比率の向上」の3項目を定め、グループ全体で取組を進めています。この業績評価制度により、環境戦略が事業計画に組み込まれ、環境保全に関する業務も他の業務と同様に評価されるようになります。
こうした環境配慮の取組をより確実なものにするため、事業所ごとの内部監査に加え、グループ企業や海外の事業所を含めた広範囲な監査体制を構築する例や、環境負荷に関わるデータの管理システムを構築することによって、監視を強化する例が見られます。ある企業では、国内外の生産子会社に「環境リスクマネージャー」を設置し、日常的な環境リスクの低減に取り組むとともに、社内の環境経営情報システムを活用し、各社の二酸化炭素排出量、廃棄物量、化学物質量等の環境データを収集・管理し、環境負荷に関するデータを共有することで、企業グループ全体の環境管理を強化しています。
企業が自主的に測定・集計した環境情報の信頼性や透明性を高めるためには、第三者がデータ検証役や成果の監視役等として参画することが有効な手段となります。ある企業では、平成24年度までに二酸化炭素排出量を14年度比で6%削減するという目標について、基準年の排出量の測定を第三者機関である監査法人が検証し、NPOが目標の達成状況を確認することを協定により約束しています。