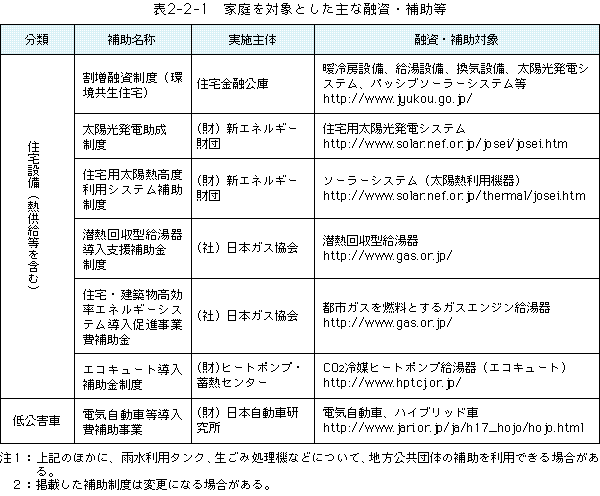
3 家庭における自発的取組を支えるしくみ
(1)環境負荷量の可視化・定量化
企業や地方公共団体の中には、家庭における環境負荷削減のための具体的な取組方法を示すとともに、節約の効果を目に見える形で確認するため、家庭に「環境家計簿」を配付しているところがあります。環境家計簿は、家庭において電気、ガス、水道、ガソリン等の使用量を記録し、環境に配慮したライフスタイルの習慣付けを行うものです。単に配付するだけでなく、一定期間後に回収を行い、現状と改善の結果を把握し、家庭へその結果をフィードバックすることで一定の成果を上げている企業や地方公共団体もあります。
北九州市では、平成16年12月から17年1月までの2か月間「環境パスポート事業」の実証実験を行いました。この事業は、市民による空き缶や古紙等の回収、環境イベントの参加などの活動をポイント化することで、博物館の入場料や商品券として利用できる地域通貨に活用するとともに、個人や市民全体の取組の成果を通知表として示し、環境への貢献度を表すものです。15年度に環境省が行った調査によると、環境問題に対する考え方として「個人の行動がどの程度環境保全に役立つのかよくわからない」とする人が全体の約57%を占めています。具体的な行動のためには、環境負荷の量だけでなく、こういった個人の取組や行動が環境の保全にどの程度貢献するのかをより具体的に目に見える形で示していく仕組みの一層の充実が求められます。
(2)融資・補助等による支援
企業や地方公共団体、公益法人等において、省エネ家電や低公害車の導入、住宅の省エネ工事や家庭用燃料電池の設置等を促進するために、家庭を対象とした融資や補助による支援を行うものが数多く見られます(表2-2-1)。日本政策投資銀行では、平成17年度から、家庭・OA機器など省エネ法に基づく特定機器の省エネ基準を満たす機械器具(トップランナー機器)を取得してリースを行う事業等に対する低利融資制度を開始しています。今後、こうした事業の活用により、家庭やオフィスにおいて省エネ効果が大きいトップランナー機器が低コストで導入されることが期待されます。