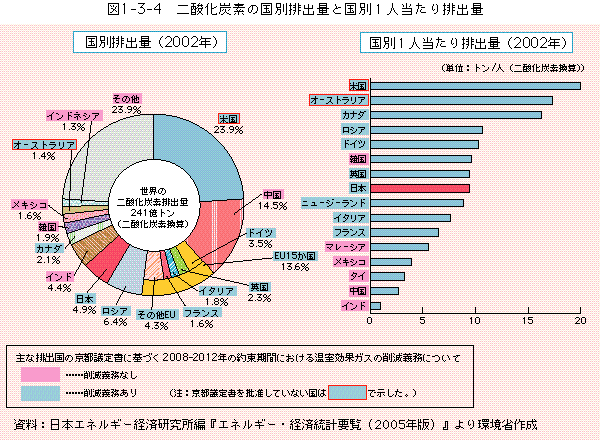
3 次の枠組みの姿は
京都議定書は、数値約束の差異化や吸収源の扱いなど、各国のさまざまな主張を取り入れた枠組みとなっています。京都議定書の第1約束期間の終了する2013年以降について、衡平で実効ある枠組み(いわゆる次期枠組み)を構築するため、条約における共通だが差異ある責任及び各国の能力に従い気候系を保護すべきという原則を踏まえつつ、米国や開発途上国を含むすべての国が参加する共通のルールを構築していくことが重要です。
(1)最大の排出国の参加が不可欠
現在、京都議定書に参加していない米国は、世界最大の温室効果ガス排出国であり、国際的な地球温暖化対策を実効性あるものとするためには、次の枠組みへの米国の参加が不可欠です(図1-3-4)。
米国では、州レベルで温室効果ガス削減目標の設定や排出量取引等を行い、企業レベルでも自主的に排出量の削減や排出量取引の実施に取り組むなどの動きがあります。連邦政府の政策を含め、米国の動きに今後も注目していく必要があります。
(2)開発途上国の具体的努力が必要
これまでの世界の温室効果ガス排出量は、先進国からの排出が多くを占めていましたが、今後、2010年にも開発途上国の排出量が先進国を上回る見込みです(図1-3-5)。
開発途上国における1人当たりの排出量は先進国と比較して依然として少ないこと(図1-3-4参照)、過去及び現在における世界全体の温室効果ガス排出量の最大の部分を占めるのは先進国から排出されたものであること、各国における地球温暖化対策をめぐる状況や対応能力には差異があることなどから、先進国が開発途上国の対策を協力・支援することが必要です。そこで、開発途上国では、クリーン開発メカニズムにより先進国の支援を受け、相互の信頼関係を築きながら、温室効果ガス排出量を削減する動きがあります。また、国全体の排出量はすでに相当程度大きく、今後もさらに排出量の増加が見込まれる開発途上国については、排出量削減に向けた一層の努力が必要になるとの認識が広がりつつあります。実効性のある温暖化対策を進めるためには、次の枠組みにおいて開発途上国における実質的な排出抑制が行われるような仕組みが必要です。