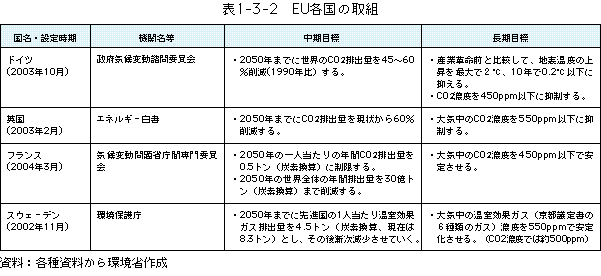
2 京都議定書の先へ
(1)次の枠組みに関する議論が始まっている
大気中の温室効果ガス濃度の安定化のためには、京都議定書の第1約束期間以降も、さらに長期的、継続的な温室効果ガス排出量の削減が必要になります。
2004年(平成16年)12月にブエノスアイレスで開催された条約の第10回締約国会議(COP10)では、中長期的な地球温暖化対策に向けた議論が行われました。さらに、先進国と途上国との信頼関係を築く上で、途上国の関心が高い「適応策」については、途上国への資金支援や人材育成支援を内容とする「適応策と対応措置に関するブエノスアイレス作業計画」が採択されました。
2005年(平成17年)5月にはCOP10で開催が決まった「政府専門家セミナー」が開催され、中長期的な将来の行動に向けて、効果的で適切な対策を展開していくための行動について情報交換が行われました。
(2)中長期的な観点からの取組の必要性
条約の究極目標である温室効果ガス濃度の安定化のためには、京都議定書のような短期的な数値目標の達成に向けた対策に限らず、中長期的な観点から対策を講じることが必要となります。
究極目標の達成のために、どのレベルの濃度の安定化が必要なのか、どのタイミングで世界全体の温室効果ガス排出量を減少方向に転換させなくてはならないのか、そのときの総排出量はどの程度にすればよいのか、という点について、科学的な知見の充実を含め、積極的に検討していく必要があります。また、温暖化問題の特質を踏まえれば、意識の変革、社会システムの変革、技術の開発・普及・投資などに取り組むとともに、中長期的な観点からどのような姿の社会をつくっていくか検討し、対策を講じていく必要があります。
コラム EUにおける長期目標の設定
EUでは、長期的な観点から、1996年(平成8年)には既に「産業革命以前のレベルから気温が2℃以上上昇しないようにする」という目標に合意しており、平成17年3月の欧州理事会でもその旨が確認されました。また、EU各国でも具体的な長期目標を掲げる動きがあります(表1-3-2)。