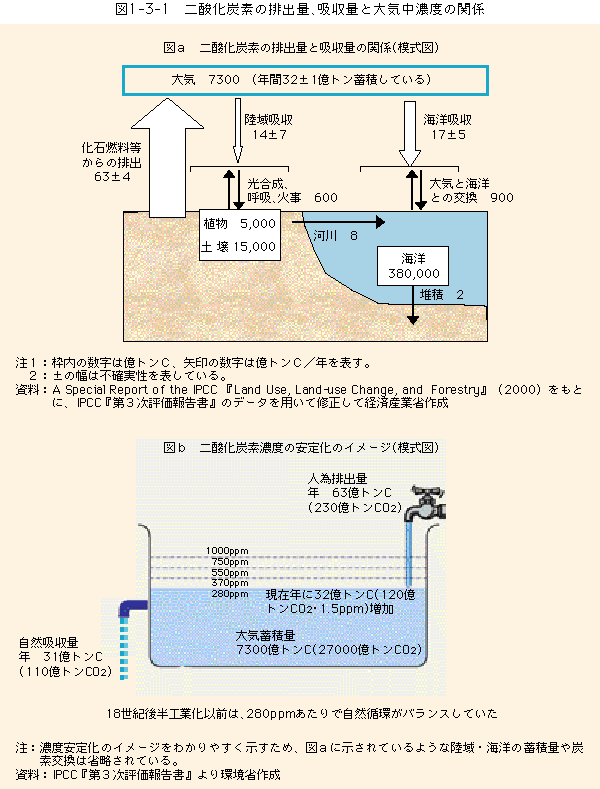
1 条約の究極の目的に向けて
条約は、「気候系に対して危険な人為的干渉を及ぼすこととならない水準において大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させること」を究極の目的としています。そして、安定化の水準は、「生態系が気候変動に自然に適応し、食料の生産が脅かされず、かつ、経済開発が持続可能な態様で進行することができるような期間内で達成されるべき」としています。
(1)温室効果ガス濃度を安定化させる
大気中の温室効果ガス濃度の安定化とは、大気中に排出される温室効果ガスの量と、海洋や陸上生態系によって吸収される量とが平衡することによって、大気中の温室効果ガスの濃度が一定の状態に保たれることをいいます。現在、化石燃料の燃焼などの人の活動に伴って、年間約63億トン(炭素換算)の二酸化炭素が排出されていますが、地球の純吸収量(自然由来の排出量を差し引いた自然吸収量)は約31億トンと推計されており、年間約32億トンが大気中に蓄積されて、濃度が上昇し続けています(図1-3-1)。
大気中の温室効果ガス濃度がどの程度の水準で安定化するかは、安定化するまでの温室効果ガスの累積の排出量によって決まります。今後、温室効果ガスの増加が続いた場合、どの程度の温暖化がどの程度の確率で生じ、それによりどのような影響が生じるのかを科学的に評価し、いつまでにどれだけ削減するのかを政策的に決定しなければなりません。
(2)さらに大幅な削減が必要
温室効果ガス濃度の安定化水準に関しては、いまだ国際的な合意が形成されていませんが、IPCC第3次評価報告書では二酸化炭素の450、550、650、750、1000ppmの5つの濃度を例として安定化にいたる排出パスを推計するとともに、二酸化炭素排出量や濃度、気温上昇の関係などを予測しています(表1-3-1)。
これらの推計によると、いずれの濃度で安定化を図るにしても、今後、二酸化炭素排出量の大幅な削減(50〜80%)が必要となります(図1-3-2)。
今後、二酸化炭素の排出量を大幅に削減したとしても、直ちに二酸化炭素濃度や気温、海面上昇が安定化するわけではなく、百年から数千年もの時間的なずれが生じます(図1-3-3)。
京都議定書の第1約束期間は2012年(平成24年)までですが、温室効果ガスの排出量と、地球温暖化の影響との間の時間的なずれを考慮すると、第1約束期間以降の国際的な枠組みについて、直ちに検討していく必要があります。
削減対策が遅れた場合、同じ温度目標を達成するためには、後からより大きな対策を取る必要があり、5年の遅れでさえ大きな違いをもたらすことが複数のモデルにより示され、また、排出削減対策が20年遅れた場合、その後、必要となる削減速度が3〜7倍になる可能性も指摘されました。