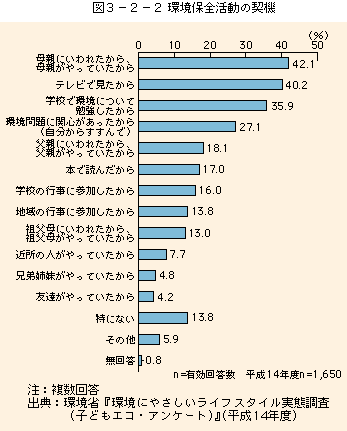
2 環境教育の推進に向けた具体的な方策
(1)専門家の育成
環境教育の推進を図る上で、専門家の育成が重要です。専門家には環境に関する知識だけでなく、社会に関する幅広い知識、現場での経験、問題解決に当たってのリーダーシップや異なる主体間の調整を行うコーディネート能力も必要です。こうした専門家を短期間で育成することは難しく計画的な育成システムの開発が求められるところであり、環境カウンセラー登録制度など既存の人材制度を改善・充実することが必要です。さらに民間で行われている人材育成・認定事業の信頼性を向上するため、「環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律」に基づき、人材認定等事業を登録する制度を整備し、円滑に運用していくことが求められます。なお、学校の教職員については、養成課程の中で環境教育に関する講座や実習への参加を奨励するほか、採用後の研修においても環境教育が十分に配慮される必要があります。
(2)活動の場の提供
環境教育は、知識の習得にとどまらず、体験が重視されるべきです。具体的な地域の自然体験や社会体験を行うことによって、環境問題を自らの課題として考え、問題解決の能力や態度を身に付け実践するというプロセスが重要であり、こどもエコクラブ等の地域における活動の場の提供が必要です。ハード・ソフト両面における方策として、例えば、エコスクールの充実・普及とそれを通じた住民を含めた環境学習の展開が必要です。
また、学校教育等において環境教育を受けた生徒・学生が、社会に出た時、引き続き地域社会の環境に関する取組に参画できるような活動の場を提供できるよう、各関係機関が連携し、環境教育の成果が継続していく仕組をつくることが必要です。
(3)家庭、学校、民間団体、事業者、行政の課題
環境保全を行った子どものきっかけについて調査すると、母親の発言や行動を挙げる回答が最も多く(図3-2-2)、子どもに対する家族の役割が重要です。また、小中学校は身近な地域単位ごとにあることから、各地域における環境教育学習の拠点となることが期待されます。環境保全活動を実施している民間団体も、民間団体の役割として環境教育や環境学習を重視しており(図3-2-3)、その充実が求められます。
企業も環境教育を行っています。平成14年度で約4分の3の企業が従業員に対する環境教育を実施しています(図3-2-4)。地域の代表的な企業などでは民間団体と協力して地域の子どもたちなどの環境教育に取り組んでいる例もあり、今後、活発になることが期待されます。
行政には、学校、事業者、民間団体などが行う環境教育に対しての人的、技術的、財政的な支援の拡充のほか、国内外の先進的な事例の把握、環境教育に関する実態調査などが求められています。また、行政自らも環境保全活動の主体として職員を教育し、環境保全活動に取り組むことが求められています。また、こうした各関係者間のパートナーシップの構築が重要です。