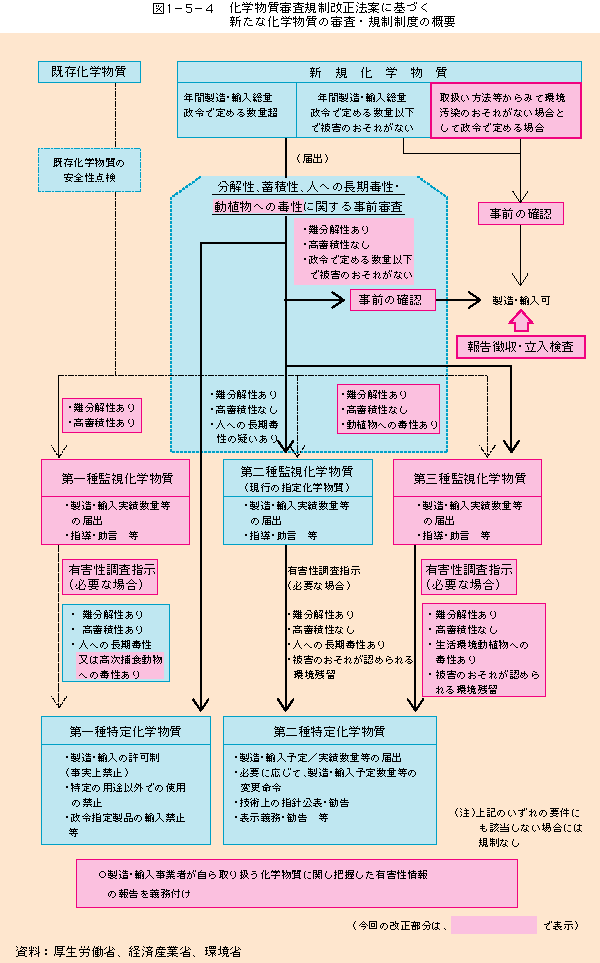
3 環境リスクの低減及びリスクコミュニケーションの推進
(1)化学物質審査規制法に関する取組
ア 化学物質審査規制法の施行
化学物質審査規制法では、製造又は輸入の前にあらかじめ届け出られた新規の化学物質について、難分解性、高蓄積性及び人の健康に対する慢性毒性等の有無に係る審査を実施することとしています。これらの性状をすべて有する化学物質を第一種特定化学物質として指定し、事実上、製造、輸入、使用等を禁止しています。また、高蓄積性ではないものの難分解性であり、かつ慢性毒性等の疑いがある化学物質を指定化学物質として指定し、製造数量などの実績数量の届出を義務付けています。さらに、製造等の状況からみて相当広範な地域の環境において相当程度残留していることにより健康被害を生ずるおそれがあると見込まれる場合には、製造・輸入事業者に有害性の調査を指示できることとしています。その結果、慢性毒性等を有することが判明し、健康被害を生ずるおそれが認められた場合には、第二種特定化学物質として指定し、製造・輸入予定数量の届出、取扱に係る技術上の指針の遵守、環境汚染の防止措置等に関する表示を義務付けるとともに、必要に応じ、製造・輸入予定数量の変更を命令できることとしています(図1-5-4)。
平成14年度は309件の新規化学物質の製造・輸入の届出があり、審査が行われました。平成14年9月に「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」の締結に当たってマイレックス及びトキサフェンが第一種指定化学物質に指定され、また、平成14年12月に指定化学物質として60物質が追加され、平成14年度末現在、第一種特定化学物質としてPCB等13物質、第二種特定化学物質としてトリクロロエチレン等23物質及び指定化学物質としてクロロホルム等676物質が、それぞれ指定されています。また、平成15年1月にビス(トリブチルスズ)=オキシド(TBTO)が含まれてる印刷用インキを、輸入してはならない製品に追加指定しました。
イ 今後の化学物質の審査及び規制のあり方に関する検討
これまで、化学物質審査規制法においては、人の健康被害を防止するため、新たな工業用化学物質の有害性を事前に確認し、その有害性の程度に応じた製造・輸入などの規制を講じてきましたが、諸外国においては、人の健康と並んで環境(生態系)への影響にも着目した審査・規制を行うとともに、化学物質の有害性のみでなく、環境中への放出可能性も考慮したより効率的な審査・規制を行うことが一般的であり、平成14年1月のわが国に対するOECDの環境保全成果レビューにおいても適切な制度改正を行うべき旨が勧告されたところです。
このような状況を踏まえ、わが国においても、化学物質の環境中の生物への影響に着目した審査・規制制度を導入するとともに、環境中への放出可能性を考慮したさらに効果的かつ効率的な化学物質の評価・管理を行うために、平成14年10月から、厚生労働省、経済産業省及び環境省の関係審議会(厚生科学審議会、産業構造審議会、中央環境審議会)が、それぞれの専門委員会及び小委員会の合同会合も開催しつつ、今後の化学物質の審査及び規制のあり方について検討し、平成15年1月から2月にかけてそれぞれ答申等を取りまとめました。
その内容を踏まえ、これら3省において化学物質審査規制法改正法案を取りまとめ、平成15年3月に国会に提出しました。
法案では、生態系への影響を考慮する視点から動植物への毒性を化学物質の審査項目に新たに加えることとしています。この審査の結果、難分解性があり、かつ、動植物への毒性があると判定された化学物質については、製造・輸入事業者に製造・輸入実績数量の届出を求めるなどの監視措置を講じ、必要な場合には製造・輸入数量の制限などを行うこととしています。また、リスクに応じた化学物質の審査・規制制度の見直しとして、難分解性及び高蓄積性の性状を有する既存化学物質について長期毒性の有無が明らかになるまでの間も製造・輸入数量の届出の義務付け等一定の管理下に置くこと、環境汚染を通じた暴露可能性が低い新規化学物質については事前の確認及び事後の監視を前提として段階的な審査を可能とすること、化学物質審査規制法の審査項目に係る一定の有害性を示す情報を製造・輸入事業者が入手した場合に国への報告を義務付けること等を規定しています。
(2)「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」(化学物質排出把握管理促進法)の本格施行
1996年2月のOECDによる加盟国に対するPRTR制度*の導入の勧告等、環境保全及び化学物質管理の国際的動向を踏まえ、PRTR制度とMSDS制度*を二つの大きな柱として、事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止することを目的とする特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(化学物質排出把握管理促進法 平成11年法律第86号)が平成11年7月に公布されました(図1-5-5)。
これにより、まず、平成13年1月からMSDS制度が施行され、化学物質及びそれを含有する製品を事業者間で取引する際に、化学物質を適切に取り扱うために必要な情報の提供が法的に義務付けられました。
また、PRTR制度については、平成13年4月から事業者による排出量等の把握が開始され、平成14年4月から都道府県経由での国への排出量等の届出が開始されました。平成15年3月には、事業者から届け出られた平成13年度の排出量等の集計結果及び国が行う届出対象外の排出源(届出対象外の事業者、家庭、自動車等)からの排出量の推計値の集計結果とがあわせて公表されました(図1-5-6、図1-5-7、表1-5-5)。さらに、公表日以後、個別事業所のデータについて、一般国民等からの開示請求を受け付けています。
経済産業省及び環境省では、法に規定された業務を着実に実施するとともに、PRTR制度のさらに円滑かつ確実な実施のため、普及啓発活動や事業者による排出量把握のためのマニュアルの改良等を進めてきました。また、届け出られた排出量以外の排出量の推計精度を向上すべく、推計方法の改善を図ってきました。
(3)ダイオキシン類問題への取組
ア 背景
(ア)ダイオキシン類とは
ダイオキシン類対策特別措置法(ダイオキシン法)では、ポリ塩化ジベンゾ−パラ−ジオキシン(PCDD)とポリ塩化ジベンゾフラン(PCDF)に加え、同様の毒性を示すコプラナーポリ塩化ビフェニル(コプラナーPCB)をダイオキシン類として定義しています。ダイオキシン類は、極めて強い毒性があり、また、分解されにくいため、通常の生活における微量の摂取によっても大きな影響を及ぼすおそれがあります。
ダイオキシン類は、炭素・水素・塩素を含むものが燃焼する工程などで意図せざるものとして生成されます。現在、わが国での主な発生源はごみ焼却施設ですが、その他にも金属精錬などにおける熱処理工程などのさまざまな発生源があります。
(イ)環境中の汚染状況
全国的なダイオキシン類の汚染実態を把握するため、平成13年度にダイオキシン法に基づく常時監視などにより、大気、水質、底質、土壌等の調査が実施されました(表1-5-6)。
(ウ)人の摂取量
平成13年度に厚生労働省が実施した調査では、わが国における平均的な食事からのダイオキシン類の摂取量の推計値は1.63pg-TEQ/kg/日とされています。そのほか、呼吸により空気から摂取される量が約0.039pg-TEQ/kg/日、手についた土が口に入るなどして摂取される量が約0.012pg-TEQ/kg/日と推定され、人が一日に平均的に摂取するダイオキシン類の量は、体重1kg当たり約1.68pg-TEQと推定されています(図1-5-8)。この水準は、耐容一日摂取量*の4pg-TEQ/kg/日を下回っています(図1-5-9)。
イ ダイオキシン類対策の枠組みの整備
ダイオキシン対策は、現在二つの枠組みに基づいて進められています。一つは平成11年3月に「ダイオキシン対策関係閣僚会議」において策定された「ダイオキシン対策推進基本指針(以下「基本指針」という。)」であり、この基本指針では、「今後4年以内に全国のダイオキシン類の排出総量を平成9年に比べ約9割削減する」との政策目標を導入するとともに、排出インベントリーの作成や測定分析体制の整備、廃棄物処理及びリサイクル対策の推進を定めています。
もう一つは、平成11年7月に、議員立法により制定されたダイオキシン法で、平成12年1月15日から施行されました。この法律では、施策の基本とすべき基準(耐容一日摂取量及び環境基準)の設定、排出ガス及び排出水に関する規制、廃棄物処理に関する規制、汚染状況の調査、汚染土壌に係る措置、国の削減計画の策定などが定められています。これらの規定に基づき設定された特定施設及びその排出基準値は表1-5-7のとおりです。
ダイオキシン類の水底の底質の汚染に係る環境基準については、平成14年6月に中央環境審議会からの答申に基づき、同年7月に環境基準(150pg-TEQ/g)を告示しました。同環境基準は、平成14年9月1日から施行されており、あわせて「底質の処理・処分等に関する指針」を策定しました。また、同環境基準の施行を受けて、港湾において同環境基準値を超えるダイオキシン類を含む底質の存在が確認された場合の対策に関する総合的な観点からの技術指針を新たに取りまとめました。
ウ 基本指針に基づく施策
(ア)排出インベントリー
平成14年12月にダイオキシンの排出量の目録(排出インベントリー)の見直しが行われました(表1-5-8)。それによると、平成9年のわが国のダイオキシン類の年間排出量は約7,350〜7,600g-TEQ、平成13年は1,740〜1,760g-TEQで、平成9年からの4年間でおおむね77%の削減がなされたと見積もられています。
(イ)ダイオキシン類に関する検査体制の整備
ダイオキシン類の環境測定における的確な精度管理を推進するために定めた「ダイオキシン類の環境測定に係る精度管理指針」の普及を図るために、平成14年度に環境省が実施するダイオキシン類の環境測定を伴う請負調査について、環境省が測定分析機関に対し同指針に規定された事項等が実施されているかについての受注資格審査を行い、ダイオキシン類に係る環境測定を的確に実施できると認めた機関であることを受注先の要件に加えました。また、「ダイオキシン類の環境測定を外部に委託する場合の信頼性の確保に関する指針」に沿ってダイオキシン類測定を進めました。さらに、分析技術の向上を図るため、地方公共団体の公的検査機関の技術者に対する研修を引き続き実施しました。
(ウ)健康及び環境への影響の実態把握
ダイオキシン類の各種環境媒体や食物を通じた暴露等に関する科学的知見の一層の充実を図るため、血液中のダイオキシン類濃度の測定を目的とした人への蓄積量調査や環境中でのダイオキシン類の実態調査などを引き続き実施しました。
(エ)調査研究及び技術開発の推進
平成14年度においては、特に廃棄物の適正な焼却技術、汚染土壌浄化技術、ダイオキシン無害化・分解技術、簡易測定等に関する技術開発及び毒性評価、環境中挙動、人への暴露評価、生物への影響等に関する調査研究に重点的に取り組みました。
(オ)廃棄物処理及びリサイクル対策の推進
平成11年9月に設定した廃棄物の減量化の目標量を踏まえ、政府全体として一体的、計画的な廃棄物対策を推進しました。
また、循環型社会形成推進基本法をはじめとする廃棄物・リサイクル関連法を整備し、使い捨て製品の製造・販売や過剰包装の自粛、製品の長寿命化等を図るなど製品の開発・製造段階、流通段階での配慮の促進、国民の生活様式の見直し等により、廃棄物等の発生抑制に努めるとともに、循環資源の再使用(リユース)や再生利用(リサイクル)を推進しました。
さらに、学校においては、原則としてごみ焼却炉を廃止したため、今後は適切なごみ処理やごみの減量化等を推進することが重要です。
エ ダイオキシン法の施行
(ア)特定施設の届出状況の把握
ダイオキシン法に基づく特定施設の届出状況について、大気基準適用の特定施設については、平成13年度末現在、全国で1万8,315施設の届出があり、廃棄物焼却炉が1万7,357施設(4t/h以上の大型炉:1,105、2〜4t/hの中型炉:1,714、2t/h未満の小型炉:1万4,538)、産業系施設が958施設(アルミニウム合金製造施設:786、製鋼用電気炉:123等)となっていました。また、平成13年度に、2,595の廃棄物焼却炉が廃止又は排出基準の適用を受けない小さな規模に構造を変更されたことがわかりました。
水質基準適用の特定施設については、平成13年度末現在、全国で4,253施設の届出があり、その大部分(3,635)が廃棄物焼却炉に係る廃ガス洗浄施設・湿式集じん施設・灰の貯留施設でした(図1-5-10)。
(イ)環境の汚染状況の調査
ダイオキシン法に基づき、都道府県等が実施する大気、水質、底質、土壌の汚染状況の常時監視に対し、助成を行いました。
(ウ)特定施設の追加について
平成14年7月にカーバイド法アセチレンの製造に係る施設等4業種の施設を、一定レベル以上の濃度のダイオキシン類の発生が新たに確認された施設として、ダイオキシン法の特定施設(水質基準対象施設)に追加しました(施行は、同年8月15日)。
(エ)土壌汚染対策について
環境基準を超過し、汚染の除去等を行う必要がある地域として、平成14年度に新たに1地域がダイオキシン類土壌汚染対策地域に指定され、対策計画が策定されました。これまでに指定された2地域について、都道府県が実施するダイオキシン類による土壌の汚染の除去等について都道府県が負担する経費を助成しました。
(オ)小規模な廃棄物焼却施設について
小規模な廃棄物焼却炉の構造及び維持管理については、厚生省生活環境審議会廃棄物部会ダイオキシン対策技術専門委員会において検討を行ってきた結果、廃棄物処理法に基づく処理基準による規制を行うことが適当であること等の結論を受け、廃棄物処理法施行規則等の改正等必要な基準の設定及び改正を行いましたが、この基準が平成14年12月から適用されました。
(カ)その他の取組
ダイオキシン法に基づく大気総量規制に関し、その手法の検討を引き続き実施しました。また、ダイオキシン法附則に基づき、臭素系ダイオキシン類の毒性や暴露実態、分析法に関する情報を収集・整理するとともに、環境中の臭素系ダイオキシン類を測定するパイロット調査等の調査研究、排出実態に関する調査研究等を進めました。
また、ダイオキシン問題を解説したパンフレット「ダイオキシン2003」を平成15年3月に発行するなどして、ダイオキシン問題について、国民の理解と協力を得るための各種取組を進めました。
(4)農薬のリスク対策
ア 農薬の環境影響の現状
農薬については、昭和46年の農薬取締法の改正等による使用規制の強化及び科学技術の進展による毒性の低い農薬の開発により、毒性及び残留性の高い農薬は、使用されなくなり、農薬による環境汚染の問題は少なくなってきています。
また、昭和63年頃から農薬による水質汚濁が社会問題化しましたが、平成2年5月に定められた「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針」の着実な運用等により、現在、農薬による水質汚濁問題は改善されつつあります。しかし、本来、農薬の使用は生理活性を有する物質を環境中に放出するものであり、今後とも、人体や環境に悪影響を及ぼすことのないよう、安全性を評価し、適正に管理していく必要があります。
イ 農薬の環境リスク対策の推進
農薬取締法については、平成14年7月末以降に明らかになった無登録農薬問題に対応するため、無登録農薬の製造、輸入及び使用の禁止、罰則の強化等を内容とする改正が行われ、平成14年12月11日に公布されました。これに伴い、新たに、原材料に照らし人畜等に害を及ぼすおそれがないことが明らかなものを登録を不要とする特定農薬及び、農薬使用者が遵守すべき基準を農林水産省及び環境省が協力して定めました。
さらに、国内で販売される農薬については、その使用による人畜や環境への悪影響を未然に防止するため、農薬取締法に基づき毒性、残留性等について評価し登録を保留するかどうかの基準(農薬登録保留基準)を定めています。これらの基準には、1)作物残留に係るもの、2)土壌残留に係るもの、3)水産動植物に対する毒性に係るもの及び4)水質汚濁に係るものがあります。平成15年3月現在、作物残留に係る基準は379農薬について、水質汚濁に係る基準は133農薬について、それぞれに個別に基準値を設定しています。その他の土壌残留に係る基準及び水産動植物に対する毒性に係る基準については各農薬に共通の基準を設定しています。
登録された農薬についても、その使用に伴い、公共用水域の水質汚濁が生じ、その利用が原因となって人畜に被害を生ずるおそれのある農薬については、政令により水質汚濁性農薬に指定し、その使用の規制を行っています。
その他、農薬リスク総合評価システムの確立・推進、農薬の作物残留、水質汚濁、大気中への拡散等環境中等での残留実態についての調査、農薬の生態影響等についての調査研究を実施しました。
(5)リスクコミュニケーションの推進
化学物質は、私たちの生活を豊かにし、また生活の質の維持向上に欠かせないものとなっている一方で、日常生活のさまざまな場面、製造から廃棄にいたる事業活動の各段階において、環境を経由して人の健康や生態系に悪影響を及ぼすおそれがあり、こうした環境リスクに対する国民の不安も大きなものとなっています。
このため、化学物質による環境汚染に関して安全で安心な社会を実現するには、市民、産業、行政が情報を共有し、対話などを通じて可能な限り共通の認識の上に立って環境リスク低減のための合理的な行動ができるようにすること−市民・産業・行政によるリスクコミュニケーション−が必要です。
リスクコミュニケーションの推進には、情報の整備、場の提供、対話の推進が必要です。
環境省では、情報の整備のため、「PRTRデータを読み解くための市民ガイドブック」の作成・配布や、化学物質の情報データベースをホームページに設置するなど、化学物質に関する情報の整備・提供を進めています。さらに、事例集などの関連情報を掲載した「リスクコミュニケーションホームページ」を平成12年から開設しています。また、「地方自治体のための化学物質と環境に関するリスクコミュニケーションマニュアル」の作成・配布等の地方自治体の支援、化学物質と環境に関する教材「エコプラントゲーム」「すごろくコレクター」「つくろう『ポンポコ理想郷』」の作成・公表等の教材の充実に取り組んでいます(図1-5-11)。経済産業省では、事業者向けに「化学物質について理解してもらうために」を作成・配布するとともに、リスクコミュニケーションのホームページを開設しました。
また、場の提供としては、内閣総理大臣の主宰により開催された「21世紀『環の国』づくり会議」報告(平成13年7月)を踏まえ、化学物質の環境リスクについて、国民的参加による取組を促進することを目的に、「化学物質と環境円卓会議」が平成13年12月に設置されました。「化学物質と環境円卓会議」は、市民、産業、行政の代表による情報の共有及び相互理解のための場として、インターネットの活用や地域フォーラムの開催により、国民・各界の意見・要望を集約し、これらの意見・要望を踏まえた対話を通じて、環境リスク低減に関する情報の共有と相互理解を深め、会議での議論やそこで得られた共通認識を市民、産業、行政に発信しようとするものです。
対話の推進には、対話を円滑に進める人材等が必要です。環境省では特に、化学物質に関する正確な情報を分かりやすく伝えることにより、対話の推進に役立つことのできる人材(化学物質アドバイザー)の育成・活用を推進することとし、平成14年度から、化学物質アドバイザーの需要や求められる能力・業務等を把握することを目的に、研修・登録・派遣を試行的に行うパイロット事業を開始しました。
(4)その他の取組
ア 有害大気汚染物質対策
有害大気汚染物質対策については、大気汚染防止法に基づき、ベンゼン、トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレンを指定物質に指定し、指定物質排出施設を定めるとともに、指定物質抑制基準を設定し排出抑制を図っています。さらに、有害大気汚染物質の排出抑制に係る事業者の自主管理取組を促進しています。(自主管理については本章第2節5(1)参照)
イ 化学物質環境汚染実態調査
化学物質の環境中のレベルの調査については、昭和49年度以来実施してきましたが、昭和54年度からは数万といわれる既存化学物質を効率的・体系的に調査し、環境における安全性を評価するため、昭和63年度まで第1次化学物質環境安全性総点検調査を実施しました。平成元年度からは、生産活動等の変化や科学技術の進歩などを踏まえて、調査対象物質の拡大等による調査の充実を図り、第2次化学物質環境安全性総点検調査を開始しました。その後、指定化学物質等検討調査、非意図的生成化学物質汚染実態追跡調査が追加されました。さらに、平成13年度に調査体系の見直しを図り、平成14年度から初期環境調査(初期的な環境残留状況の把握が必要な物質を対象とする)、暴露量調査(暴露量把握が必要な物質を対象とする)及びモニタリング調査(環境残留性が高く、環境基準等が設定されていない物質で、環境実態の経年的把握が必要な物質を対象とする)の3種類からなる調査体系として実施されています。
ウ PCB対策
PCBについては、昭和47年から新たな製造がなくなり、さらに昭和49年に事実上製造・輸入禁止となって以降、約30年間にわたって保管が続けられてきましたが、国はPCB特別措置法に基づき、環境事業団を活用したPCB廃棄物の拠点的処理施設の立地を推進しました。また、これとは別に電力会社等の多量のPCB廃棄物を所有している事業者の中には、自社でPCB廃棄物を処理する取組もあり、PCB特別措置法に定められた平成28年7月までのすべてのPCB廃棄物の処理を目指して取り組んでいます。
また、使用中のPCBを含む電気工作物及び保管されているPCB廃棄物の紛失・不適正処理等を未然に防止するため、事業者は電気事業法及びPCB特別措置法に基づき、保管・使用状況について届出を行うこととなっています。