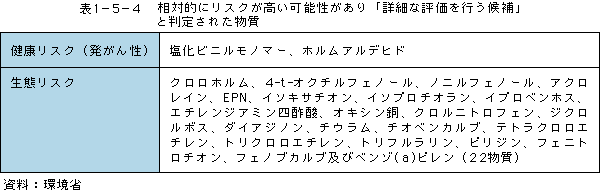
2 科学的知見の充実及び環境リスク評価の推進
(1)化学物質の環境リスク評価*の推進
現在、わが国で約5万種以上流通しているといわれる化学物質の中には、発がん性、生殖毒性等多様な毒性をもつものが多数存在し、これらが大気・水等さまざまな媒体を経由して人や生態系に影響を与えているおそれがあります。
こうした影響を未然に防止するためには、多くの化学物質を対象に、その生産、使用、廃棄等の仕方によっては人の健康や生態系に有害な影響を及ぼすおそれのある化学物質が環境の保全上の支障を生じさせるおそれ(環境リスク)の評価を行い、その結果に基づき適切な環境リスク対策を講じていく必要があります。
平成14年度においては、化学物質の環境リスク評価のための知見の収集を進めるとともに、環境リスク初期評価等について第2次取りまとめを行いました。この中では、人の健康に対するリスク(健康リスク)と生態系に対するリスク(生態リスク)にわたる環境リスク初期評価を13物質を対象として行ったほか、生態リスクについては追加的に69物質を選定して初期評価を行いました。また、環境リスク初期評価の一環として行う発がん性評価の手順を検討しつつ試行的に評価を行い、6物質を対象とした定量的なリスク評価と19物質を対象とした定性的な評価を実施しました。
その結果、発がん性については2物質、生態リスクについてはクロロホルム等22物質が、相対的にリスクが高い可能性があり「詳細な評価を行う候補」と判定されました(表1-5-4)。
また、この生態リスク評価やOECDのHPV点検プロジェクトにおける化学物質の安全性点検に向けて生態系に対する影響に関する知見を充実させるため、平成7年度からOECDのテストガイドラインを踏まえて藻類、ミジンコ及び魚類を用いた生態影響試験を実施しており、平成14年度は42物質について試験を行いました。
(2)内分泌かく乱化学物質(いわゆる環境ホルモン)問題について
平成8年に刊行された、「Our Stolen Future*」という本では、DDT、クロルデン、ノニルフェノールなどの化学物質が人の健康影響(男性の精子数減少、女性の乳がん罹患率の上昇)や、野生生物への影響(ワニの生殖器の奇形、ニジマス等の魚類の雌性化、鳥類の生殖行動異常等)をもたらしている可能性が指摘されています。
このような、内分泌系(ホルモン)に影響を及ぼすことにより生体に障害や有害な影響をおこす外因性の化学物質は、内分泌かく乱化学物質(いわゆる環境ホルモン)と呼ばれています。
内分泌かく乱化学物質問題については、その有害性など未解明な点が多く、関係府省が連携して、汚染実態の把握、試験方法の開発及び健康影響などに関する科学的知見を集積するための調査研究を、国際的に協調して実施しています。
環境省は、平成10年5月に内分泌かく乱化学物質問題への対応方針として、「環境ホルモン戦略計画SPEED'98」を取りまとめ、公表しました。本方針では、科学的研究を加速的に推進しつつ、今後急速に増すであろう新しい科学的知見に基づいて、行政的手段を遅滞なく講じ得る体制を早期に準備することが必要としており、具体的な対応方針として、1)環境中での検出状況、野生生物等への影響に係る実態調査の推進、2)試験研究及び技術開発の推進、3)環境リスク評価、環境リスク管理及び情報提供の推進、4)国際的なネットワークのための努力等を実施することとしています。
本方針に基づき平成10年度からは、一般環境中(大気、水質、底質、土壌、水生生物)での検出状況及び野生生物における蓄積状況等を全国的な規模で調査するなどの取組を実施しているほか、OECDを中心として先進各国が協力・分担して取り組んでいるスクリーニング試験法等の開発に参加しています。さらに、平成11年からは日英国際共同研究、平成13年からは日韓国際共同研究を開始するとともに、平成10年から毎年開催している「内分泌かく乱化学物質問題に関する国際シンポジウム」について、平成14年は広島市で開催しました。
また、環境リスク評価に係る具体的な取組として、平成12年度からは、政府のミレニアムプロジェクトの一環として、3年間で40物質以上の優先物質についてリスク評価を実施することとし、平成12年度は12物質*、平成13年度は8物質*、平成14年度は24物質*を選定し、有害性評価を進めています。
これまでに、10物質について哺乳類(げっ歯類)を用いた人健康影響に関する有害性評価結果を、また12物質について魚類を用いた生態系影響に関する有害性評価結果を取りまとめ公表しました。この中でノニルフェノール及び4-オクチルフェノールについては魚類に対して内分泌かく乱作用を有することが強く推察されました。そのうち、ノニルフェノール及びトリブチルスズの結果についてはOECDにも提供し、各国の専門家の意見を求めました(図1-5-3)。また、平成13年3月には国立環境研究所に環境ホルモン総合研究棟が設置され、同施設を拠点とした質の高い調査研究が進められています。
厚生労働省においては、人に対する健康影響を調査するため平成8年度から文献調査を実施するなど必要な情報の収集に努め、平成10年4月から、「内分泌かく乱化学物質の健康影響に関する検討会」を開催し、同11月に中間報告書を取りまとめ公表しました。また、平成13年12月には、新たに得られた知見、今後実施されるべき調査研究及び行動計画を含む中間報告書追補を取りまとめ公表しました。現在引き続き、研究や必要な調査を推進し、科学的な知見の収集に努めているところです。
経済産業省においては、国際的な動向に留意しながら、厚生労働省と共同で内分泌かく乱作用に関するリスク評価スキームの確立を目指し、スクリーニング試験法の開発等を推進しています。また、内分泌かく乱化学物質に関する現状把握と今後の検討のため、平成14年11月、二つの国際機関SCOPE(国際学術連合評議会環境問題科学委員会)とIUPAC(国際純正応用化学連合)との共催で、内分泌活性物質国際シンポジウムを開催しました。また、内分泌かく乱作用によってもたらされる有害影響(毒性)に対しては、適切なリスク評価に基づいた効果的な対応が必要であることから、化学物質審議会内分泌かく乱作用検討小委員会を中心に、さまざまな科学的情報を収集するとともに、「SPEED'98」の調査対象となった物質のうち、わが国での生産・使用実態がないとされた物質群、農薬取締法に基づき登録されている農薬やダイオキシン等の各種対策が進められている物質群を除いた15物質について有害性評価書を作成し、平成14年4月に公表しました。また、これらのうち有害性を評価するために十分な情報がない物質については、追加試験を実施しています。得られた有害性評価結果を踏まえ、三つの物質群についてリスク評価管理研究会を独立行政法人製品評価技術基盤機構に設置し、リスク評価の検討を行っています。
国土交通省においては、環境省と連携し平成10年度から水環境中の内分泌かく乱化学物質の存在状況を把握するため、全国109の一級河川を対象に、水質・底質・魚類調査を実施するとともに、主要な下水道における流入・放流水の水質調査を実施しています。また、代表河川における挙動や流入実態の調査、河川浄化施設等の除去効果把握調査等を実施し、今後の河川における内分泌かく乱化学物質の管理のあり方について検討を行いました。また、内分泌かく乱化学物質等を分解する微生物を同定するとともに、それらを用いた下水処理過程における効果的な内分泌かく乱化学物質等の除去方法について研究開発を実施しています。
内分泌かく乱化学物質問題に関する国際的な検討の成果としては、平成14年6月、OECDの内分泌かく乱化学物質の試験及び評価に関するタスクフォース会合が東京で開催され、「内分泌かく乱化学物質の試験と評価の概念的枠組み」が策定されました。今後も引き続き国際的な協力体制のもと試験評価戦略等の検討を進めていくこととなっています。
(3)本態性多種化学物質過敏状態について
近年、微量な化学物質に対するアレルギー様の反応により、さまざまな健康影響がもたらされる病態の存在が指摘されています。このような病態については、欧米において「MCS:Multiple Chemical Sensitivity(本態性多種化学物質過敏状態)」等の名称が与えられ研究が進められてきましたが、IPCS(国際化学物質安全性計画)では、化学物質との因果関係が不明確との立場から、この病態を「本態性環境非寛容症」と呼ぶことが提唱されました。わが国では「化学物質過敏症」として一般的に呼称されていますが、その病態をはじめ、実態に関する十分な科学的な議論がなされていない状況です。
このため環境省では、平成9年度に関連分野の研究者からなる研究班を設置し、その実態の把握や原因の究明のための調査研究を開始し、平成12年2月及び平成13年8月にその結果を公表しました。研究班では、このような病態に対し、本態性多種化学物質過敏状態(MCS)という名称を仮に使用し、現時点では、その発症機序や病態(症状・徴候)はいまだ仮説の段階であるとした上で、さらに調査研究を進めています。