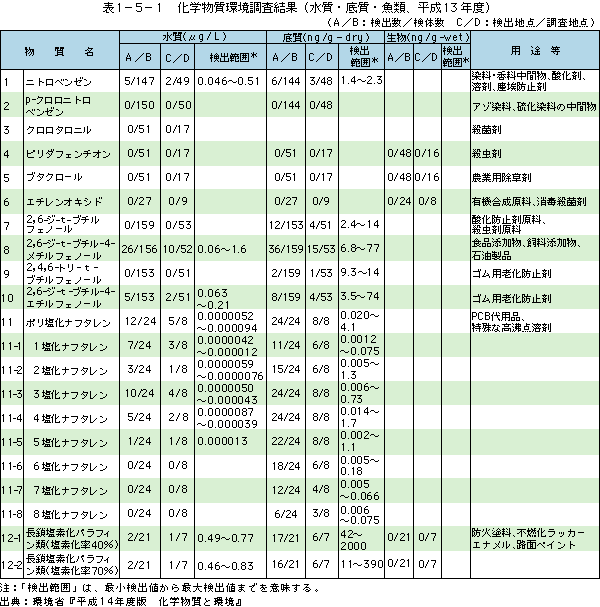
1 化学物質による環境汚染の現状
現代の社会においては、物の生産などに多種多様な化学物質が利用され、私たちの生活に利便を提供しています。また、物の焼却などに伴い非意図的に発生する化学物質もあります。今日、推計で5万種以上の化学物質が流通し、また、わが国において工業用途として化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化学物質審査規制法 昭和48年法律第117号)に基づき届け出られるものだけでも毎年300物質程度の新たな化学物質が市場に投入されています。化学物質の開発・普及は20世紀に入って急速に進んだものであることから、人類や生態系にとって、それらの化学物質に長期間暴露されるという状況は、歴史上、初めて生じているものです。
化学物質の中には、その製造、流通、使用、廃棄の各段階で適切な管理が行われない場合に環境汚染を引き起こし、人の健康や生態系に有害な影響を及ぼすものがあります。
環境省では、化学物質審査規制法が施行された昭和49年度から、化学物質の一般環境中の残留状況を調査しています。平成13年度は、1)環境残留性が疑われる化学物質の状況把握及び残留性化学物質の経年的監視を目的とする化学物質環境安全性総点検調査、2)化学物質審査規制法による指定化学物質等の環境残留状況把握を目的とする指定化学物質等検討調査、3)非意図的生成化学物質の残留性把握を目的とする非意図的生成物質汚染実態追跡調査の3つの調査体系により調査を実施しています。
(1)化学物質環境安全性総点検調査
ア 化学物質環境調査の概要(水質、底質、魚類)
化学物質環境調査は、一般環境中に残留する化学物質の早期発見及びその濃度レベルの把握を目的としています。
平成13年度は、全国57地点を対象とし、水質12物質(群)、底質11物質(群)及び魚類4物質(群)について調査を実施しました。この結果、水質から5物質(群)及び底質から7物質(群)が検出され、魚類からは、検出されませんでした(表1-5-1)。これらのうち、長鎖塩素化パラフィン類については、環境リスク評価を行う化学物質の候補とする必要があるとされました。また、2,4,6-トリ-t-ブチルフェノール及びポリ塩化ナフタレンについては、本調査におけるモニタリング調査の候補物質とする必要があるとされました。
イ 化学物質環境調査の概要(大気)
平成13年度は、全国22地点を対象とし、13物質(群)について調査を実施しました。この結果、11物質(群)が検出されました(表1-5-2)。このうち塩化メチル、塩化エチル、1,1,2-トリクロロエタン及びアクリル酸エチルは、環境リスク評価を行う化学物質の候補とする必要があるとされました。
ウ 底質モニタリングの概要
底質モニタリングは、環境調査の結果等により底質中に残留していることが確認されている化学物質について、その残留状況の長期的推移を把握することにより環境汚染の経年監視を行うことを目的として昭和61年から実施しています。
平成13年度は第一種特定化学物質を中心に、p,p'-DDT等20物質について全国20地点で調査を実施しました。
その結果、対象20物質すべてが検出されました(図1-5-1)。調査対象物質ごとの最高値を記録した地点をみると、大和川河口(7物質)、洞海湾(6物質)、大阪港(5物質)及び隅田川河口(2物質)であり、閉鎖性水域の内湾部の汚染レベルが高いことが示唆されています。
エ 生物モニタリングの概要
生物モニタリングは、第一種特定化学物質及び環境調査結果などから選定した物質について、生物(魚類、貝類、鳥類)中の蓄積状況を把握することにより環境汚染の経年監視を行うことを目的として、昭和53年度から実施しています。
平成13年度は第一種特定化学物質を中心に、PCB等18物質について全国21地点の魚類7種、貝類2種、鳥類2種を対象に調査を実施しました。
その結果、魚類からはPCB、p,p'-DDE等18物質すべて、貝類からはtrans-クロルデン、p,p'-DDE等15物質、鳥類からはβ-HCH、p,p'-DDE等12物質が検出されました(図1-5-2)。
(2)指定化学物質等検討調査結果の概要
化学物質審査規制法の指定化学物質を中心とした物質について、環境中の残留性及び人への暴露経路の調査を行っています。
平成13年度の環境残留性調査では、大気についてはクロロホルムなど6物質を全国31地点で、水質、底質については1,4-ジオキサンを全国35地点で調査しました。また、暴露経路調査では、室内空気については、クロロホルムなど6物質を、食事についてはクロロホルムを全国7地区各3世帯で調査しました。
その結果、環境残留性調査においては、大気では6物質すべてが、水質、底質では3物質すべてが、検出されました(表1-5-3)。また、暴露経路調査においては、室内空気では全6物質が6地区(4物質については、7地区すべて)で検出され、食事ではクロロホルムが7地区すべてで検出されましたが、残留状況及び暴露状況に大きな変化は認められませんでした。
(3)有機スズ化合物に関する環境調査結果
有機スズ化合物による環境汚染の状況については、生物モニタリングと指定化学物質等検討調査の結果をあわせると次のとおりです。
トリブチルスズ化合物は、環境中に広範囲に残留しており、その汚染レベルは、近年ではおおむね横ばいの傾向にあります。
また、トリフェニルスズ化合物は、環境中に広範囲に残留しており、その汚染レベルは、近年ではおおむね横ばいの傾向にあります。
トリブチルスズ化合物及びトリフェニルスズ化合物とも、わが国では開放系用途の生産・使用は確認されていないことを考慮すれば、汚染状況はさらに改善されていくものと期待されています。しかし、未規制国・地域の存在に伴う汚染も考えられることから、今後も引き続き、環境汚染対策を継続するとともに、環境汚染状況を監視していく必要があります(船舶に使用されているトリブチルスズ化合物を含む塗料の禁止については、本章第3節5(1)アを参照)。
また、これらの物質については、内分泌かく乱作用を有する疑いがあるとの指摘があることなどから、関連の情報を含め毒性関連知見の収集に努めることも必要です。
(4)非意図的生成化学物質汚染実態追跡調査結果の概要
一般環境中における非意図的生成化学物質の環境残留性を把握するために昭和60年度から「有害化学物質汚染実態追跡調査」(平成5年度から「非意図的生成化学物質汚染実態追跡調査」に名称を変更)を行っています。平成13年度はPCBについては、水・底質、生物(魚類、貝類)、大気の4媒体を調査しました。その結果、PCBは、昭和47年までに製造、輸入及び開放系用途の使用が中止されましたが、依然として広範な地点の環境中に存在しており、全地点の全媒体において検出されました。 全地球的な汚染監視の観点からも、今後さらにモニタリングを継続しその消長を追跡する必要があるとともに、PCBの環境中の組成等を調査することにより、非意図的生成割合、環境中挙動などの汚染機構の解明に努める必要があります。
(5)大気モニタリングの概要
有害大気汚染物質のモニタリング調査は昭和60年から実施されていますが、平成9年度から地方公共団体(都道府県、大気汚染防止法の政令市)においても本格的にモニタリングが実施されています(測定結果については、本章第2節1(6)参照)。