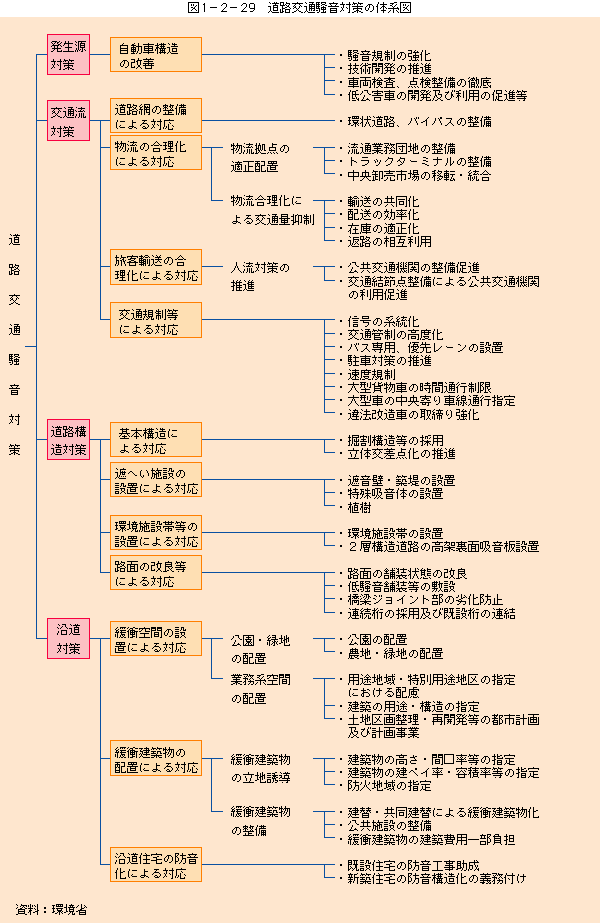
6 地域の生活環境に係る問題への対策
(1)騒音・振動対策
ア 騒音規制法及び振動規制法による規制の実施
騒音・振動対策については、主に騒音規制法(昭和43年法律第98号)・振動規制法(昭和51年法律第64号)に基づき、規制等を実施しています。騒音規制法及び振動規制法では、騒音・振動を防止することにより生活環境を保全すべき地域を都道府県知事(指定都市・中核市・特例市にあってはその長)が指定し、この指定地域内にある、法で定める工場・事業場及び建設作業の騒音・振動を規制するとともに、自動車から発生する騒音の許容限度を環境大臣が定め、市町村長は、都道府県公安委員会等に対して道路交通に起因する自動車騒音・道路交通振動について対策の要請等ができることとされています。
イ 工場・事業場及び建設作業による騒音・振動対策
(ア)工場・事業場
騒音規制法及び振動規制法では、指定地域内にあって金属加工機械等の政令で定める特定施設を設置している工場・事業場(以下「特定工場等」という。)が規制の対象となりますが、指定地域内の特定工場等の総数は平成13年度末現在でそれぞれ208,779、122,078です。平成13年度には、騒音規制法及び振動規制法に基づく改善勧告がそれぞれ3件、苦情に基づく行政指導がそれぞれ918件、158件行われました。
住工混在の土地利用により、現に騒音・振動公害が発生し、問題となっている地域では、防音施設や振動防止施設の設置等の騒音・振動防止対策、当該地域からの工場・事業場の移転等が公害対策の重要な手段となっています。騒音・振動が問題となる工場・事業場の多くは中小規模であり、資金的な面等から移転が困難な場合が多いため、中小企業金融公庫等により工場移転についての融資等が行われています。また、適切な規制の在り方を検討するため、建設作業場から発生する騒音について実態調査を行いました。
(イ)建設作業
騒音規制法及び振動規制法では、指定地域内においてくい打ち作業等の政令で定める特定建設作業を伴う建設工事が規制の対象となりますが、平成13年度に行われた特定建設作業に係る実施の届出件数はそれぞれ55,627件、27,270件です。平成13年度には、騒音規制法及び振動規制法に基づく改善勧告及び改善命令は行われませんでした。また、苦情に基づく行政指導がそれぞれ1,229件、471件行われました。
建設作業の騒音・振動については、低騒音型建設機械・低振動型建設機械の開発が進められていることから、低騒音型の建設機械の採用を促すための仕組みをつくり、開発・普及を促進しています。
ウ 自動車交通騒音・振動対策
自動車本体からの騒音は、エンジン、吸排気系、駆動系、タイヤ等から発生しますが、沿道においては、自動車本体から発生する騒音に、交通量、通行車種、速度、道路構造、沿道土地利用等の各種の要因が複雑に絡み合った騒音として問題となっています。また、道路周辺における振動についても、自動車重量、走行条件及び路面の平坦性、舗装構造、路床条件等の道路構造等の要因があいまって問題となっています。これらの騒音・振動問題を抜本的に解決するため、自動車単体の構造の改善による騒音の低減等の発生源対策、交通流対策、道路構造対策、沿道対策等の諸施策を総合的に推進しています(図1-2-29)。
なお、自動車騒音に関して市町村長が道路管理者等に対して意見陳述を行った件数は、平成13年度は12件でした(表1-2-15)。
(ア)自動車単体対策
自動車の構造の改善により、自動車単体から発生する騒音の大きさそのものを減らす発生源対策として、市街地を走行する際に発生する最大の騒音である加速走行騒音、一定の速度で走行する際の騒音である定常走行騒音、使用過程車の街頭での取締りなどに適用する近接排気騒音の3種類について規制を実施しています。また、暴走族による深夜の住宅地等における爆音暴走の多発が大きな社会問題となっていることから、消音器不備、空ぶかし運転等に対する取締りを強化しています。
しかし、これまでの規制強化にもかかわらず、自動車交通量の増加等により幹線道路の沿道地域を中心に環境基準の達成率は依然として低く、一層の騒音低減が必要です。平成4年及び平成7年に、中央環境審議会から加速走行騒音を1〜3デシベル、定常走行騒音を1〜6.1デシベル、近接排気騒音を3〜11デシベル低減する目標値の設定を中心とした答申がなされました。これらの答申に盛り込まれた目標値は、世界的にみて最も厳しいものでありましたが、政府としては、答申後、4次にわたって自動車騒音の大きさの許容限度の告示改正を行い、道路運送車両の保安基準改正を行いました(表1-2-16)。
(イ)総合的施策
政府では、平成7年12月、道路交通環境対策関係省庁連絡会議(本節4(2)ア(ウ)参照)においてとりまとめられた、「道路交通騒音の深刻な地域における対策の実施方針」に沿って、道路構造対策、交通流対策、沿道対策等の各種対策の総合的実施を図っています。また、前述の実施方針を受け、現在までにほとんどの都道府県等で関係行政機関の参加による道路交通騒音対策のための協議会等が開催され、対策が検討されています。
a 道路構造の改善
道路構造対策としては、環境施設帯や遮音壁等の整備、道路緑化を推進しています。また、低騒音効果のある高機能舗装の敷設、高架裏面吸音板の設置を推進しているほか、高機能舗装の騒音低減効果とその持続性の向上を図るための技術開発等を行いました。
b 交通流対策等
環状道路等幹線道路ネットワーク整備による交通流の分散・円滑化等を進めるとともに、公共交通機関の利用促進や「新総合物流施策大綱」に基づく物流の効率化等に努めました。
また、最高速度規制、大型車の中央寄り車線通行指定、夜間通行止め規制等を実施するとともに、住居系地区等への通過交通の進入を抑制するために、交通規制とコミュニティ道路整備を組み合わせたコミュニティ・ゾーンの形成等を推進しています。
さらに、都市内における円滑な交通流を阻害している違法駐車を防止するため、駐車規制の見直し、危険性の高い駐車違反に重点を置いた取締り、駐車誘導システム等の整備等の総合的な駐車対策を推進しています。
c 沿道環境の整備
沿道対策については、幹線道路の沿道の整備に関する法律(沿道法 昭和51年法律第34号)に基づき、道路交通騒音の著しい幹線道路の沿道について、まちづくりと一体となった沿道環境の整備が促進されています。平成14年度末現在、同法に基づく沿道整備道路は、9路線123kmが都道府県知事により指定されており、34地区94.1kmで沿道地区計画が策定されています。
沿道法に基づく各種支援措置と高速自動車国道等の周辺の住宅防音工事助成の実績は、平成14年度末で、市町村の土地買入れに対する国の無利子貸付は17件、道路管理者による緩衝建築物の一部費用負担は368件、道路管理者による住宅防音工事助成は18,616件、高速自動車国道等の周辺の住宅防音工事助成は58,376件です。
エ 航空機騒音対策
一定の基準以上の騒音を発生する航空機の運航を禁止する耐空証明(旧騒音基準適合証明)制度については、逐次規制の強化が行われ、昭和53年に強化された騒音基準に適合しない航空機については、平成14年4月1日以降運航を禁止しました。
また、緊急時等を除き、新東京国際空港及び東京国際空港(A滑走路及びB滑走路に限る。)については午後11時から午前6時までの間、大阪国際空港については午後10時から午前7時までの間、航空機の発着を禁止しています。さらに、大阪国際空港においては、午後9時以降定期便のダイヤを設定しないこととしています。
(ア)空港周辺対策
発生源対策を実施してもなお航空機騒音の影響が及ぶ地域については、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和42年法律第110号)等に基づき空港周辺対策を行っています。同法に基づく対策を実施する特定飛行場は、東京国際、大阪国際、福岡等15空港であり、これらの空港周辺において、学校、病院、住宅等の防音工事及び共同利用施設整備の助成、移転補償、緩衝緑地帯の整備、テレビ受信料の助成等を行っています(表1-2-17)。
また、大阪国際空港及び福岡空港については、周辺地域が市街化されているため、同法により計画的周辺整備が必要である周辺整備空港に指定されており、国及び関係地方公共団体の共同出資で設立された空港周辺整備機構が関係府県知事の策定した空港周辺整備計画に基づき、上記施策に加えて、再開発整備事業、代替地造成事業等を実施しています。
コミューター空港、ヘリポート等については、環境基準が適用されない小規模なものが多く、平成2年9月に制定したこれらの騒音問題の発生の未然防止を図るために必要な環境保全上の指針を踏まえて、諸施策を実施しています。
(イ)防衛施設周辺における航空機騒音対策
自衛隊及び在日米軍の使用する飛行場周辺の航空機騒音については、自衛隊機等の本来の機能・目的からみてエンジン音の軽減・低下を図ることは困難なため、音源対策、運航対策は、消音装置の設置・使用、飛行方法の規制等についての配慮が中心となっています。在日米軍における音源対策、運航対策については、日米合同委員会等の場を通じて協力を要請しており、厚木、横田、嘉手納及び普天間の各飛行場における航空機の騒音規制措置が合意されています。
自衛隊等の使用する飛行場に係る周辺対策としては、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和49年法律第101号)を中心に、学校、病院、住宅等の防音工事の助成、移転補償、緩衝緑地帯の整備、テレビ受信料の助成等の各種施策が実施されています(表1-2-18)。
なお、平成14年度末現在28飛行場周辺について同法に基づく区域指定がされており、住宅防音工事の助成等が実施されています。
オ 新幹線鉄道騒音・振動対策
(ア)対策の実施
東海道・山陽・東北及び上越新幹線については、「国鉄改革後における新幹線鉄道騒音対策の推進について」(昭和62年3月閣議了解)及び環境庁長官の勧告等に基づく運輸大臣の通達を受けて、鉄道事業者が対策を実施しました。
具体的には、平成10年度から平成14年度末まで「第3次75デシベル対策」として、防音壁のかさあげ、改良型防音壁の設置、レール削正の深度化、バラストマットの敷設、低騒音型車両の開発等各種の騒音・振動対策を実施してきました。
また、騒音レベルが75デシベルを超える区域に所在する住宅及び70デシベルを超える区域に所在する学校、病院等に対し従来から防音工事の助成等を実施しており、申出のあった対象家屋についてはすべて対策を講じています。また、東海道・山陽新幹線において、振動レベルが70デシベルを超える区域に所在する住宅等の防振工事の助成及び移転補償等を実施しており、申出のあった対象家屋についてはすべて対策を講じています。さらに、北陸新幹線高崎・長野間についても、環境基準等の達成に向け、鉄道事業者等による騒音・振動対策の推進を図っています。
さらに、騒音・振動対策及び障害防止対策をより効果的に実施するため、(財)鉄道総合技術研究所を中心として、有効な騒音・振動防止対策の開発等を推進しています。
カ 在来鉄道騒音・振動対策
新幹線以外のいわゆる在来鉄道については、新設又は高架化等のように環境が急変する場合の騒音問題を未然に防止する必要があるとの観点から、「在来鉄道の新設又は大規模改良に際しての騒音対策の指針」(平成7年12月)(表1-2-19)を踏まえ、騒音対策の適切かつ円滑な実施に努めています。
キ 近隣騒音対策(良好な音環境の保全)
近年、営業騒音、拡声機騒音、生活騒音等のいわゆる近隣騒音は、騒音に係る苦情全体の約1/4を占めており、重要な対策課題となっています。近隣騒音対策は、各人のマナーやモラルに期待するところが大きいといえますが、各地方公共団体においても取組が進められています。平成13年度末現在、深夜営業騒音については49都道府県及び政令市で、拡声機騒音については53都道府県及び政令市で条例が制定され規制がなされています。
また、各地域における地方公共団体や住民等の良好な音環境を保全しようとする取組を支援するため、平成8年度に「残したい“日本の音風景100選”」を選定し(図1-2-30)、平成14年度には、認定地で活動する団体等の参加により、第6回音風景保全全国大会が愛媛県松山市において開催されました。
ク 低周波音対策
人の耳には聞き取りにくい低い周波数の音がガラス窓や戸、障子等を振動させたり、心身に影響を及ぼしたりするとの苦情を、平成13年度は地方公共団体において全国で110件受け付けました。
低周波音問題の改善を図るため、低周波音に関する知見を収集するとともに、近年の苦情内容の変化を受けて、改めて発生実態の解析を行いました。
(2)悪臭対策
ア 悪臭防止法による規制の実施
悪臭対策については、悪臭防止法(昭和46年法律第91号)に基づき、工場・事業場から排出される悪臭原因物の規制等を実施しています。悪臭防止法では、都道府県知事(指定都市、中核市及び特例市においてはその長)が規制地域の指定及び規制基準の設定を行うこととしており、平成13年度末現在、全国の55.2%に当たる1,792市区町村(637市、996町、136村、23特別区)で規制地域が指定されています。平成13年度は、悪臭防止法に基づき、改善勧告が7件行われ、改善命令に至ったものはありませんでした。このほか、規制地域内の悪臭発生事業場に対して11,376件の行政指導が行われました。
複合臭問題等への対策強化を目的として、平成7年に嗅覚測定法*による臭気指数規制*が悪臭防止法に導入されたことを受け、平成14年度は、地方公共団体職員を対象とした講習会、嗅覚測定技術の研修や臭気指数規制による「悪臭苦情対応事例集」の作成等、地方公共団体における臭気指数規制の一層の導入促進に向けた取組を行ったほか、臭気対策の必要性を解説した事業者向けパンフレットを作成しました。
また、臭気指数等の測定を行う臭気測定業務従事者についての国家資格を認定する臭気判定士試験を実施しました。
さらに、近年の悪臭苦情件数の増加に対応した効果的な規制のあり方を検討するため、苦情の発生実態とその要因についての解析調査を行っています。
イ 悪臭防止技術の普及推進
近年特に臭気対策の必要性が高まっている中小規模の事業場が導入可能な脱臭技術の開発・普及を促進するため、比較的安価で維持管理の容易な脱臭技術の公募を行い、脱臭技術適正評価書の作成に必要な比較検討や脱臭効率の実測調査を行いました。
ウ 嗅覚測定法に関する海外動向調査
欧州における嗅覚測定法の標準規格化に適切に対処するため、欧州と日本の測定法の比較検討調査や、諸外国における悪臭に関する法制度や臭気測定体制についての情報収集を行ったほか、効果的な情報発信手法の検討などを行っています。
エ 快適なにおい環境の創造
におい環境の大切さを理解し、身のまわりの悪臭を低減し快適なにおい環境を創造するための市民参加による自主的な地域の取組の推進を図るため、平成13年度に全国のすぐれたかおり風景として「かおり風景100選」を選定し(表1-2-20)、平成14年度は、認定地団体や市民等の参加により、長野県松本市において「2002かおり風景フォーラムin松本」を開催しました。
また、このような良好な環境とその源となる自然や文化を保全・創出しようとする地域相互の情報交換を図るため、環境創造自治体ネットワーク*通信が発行されています。
(3)その他の大気に係る生活環境対策
ア ヒートアイランド対策
ヒートアイランド現象については、都市全体の熱収支バランスを管理する熱の管理の視点が重要であることから、熱の管理に必要な手法として都市環境気候図、数値シミュレーション等について検討を行うとともに、同現象による環境影響についても調査を行っています。
また、平成14年9月には、ヒートアイランド対策関係府省連絡会議(内閣官房都市再生本部事務局、経済産業省、国土交通省及び環境省が参加)を設置し、政府の総合的な取組の推進を図っています。
イ 光害(ひかりがい)対策
光害については、光害対策ガイドライン、地域照明環境計画策定マニュアル及び光害防止制度に係るガイドブック等を活用して、地方公共団体における良好な照明環境の実現を図る取組を支援しました。また、肉眼や双眼鏡等を使った身近な方法による星空観察を通じ、参加者に大気汚染や光害など大気環境問題への関心を高めてもらうことを目的として、全国星空継続観察(スターウォッチング・ネットワーク)事業を実施しています。