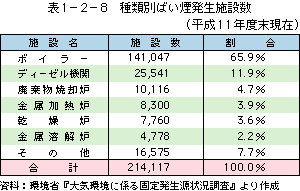
4 大都市圏等への負荷の集積による問題への対策
(1)固定発生源対策
ア ばい煙発生施設
大気汚染防止法では窒素酸化物、硫黄酸化物、ばいじん等をばい煙、その発生施設をばい煙発生施設と定義し、規制等を行っています。平成11年度末現在におけるばい煙発生施設の総数は約214千施設で、種類別にみると、ボイラーが141千施設(66%)と最も多く、次いでディーゼル機関が26千施設(12%)です(表1-2-8)。ばい煙発生施設に対し、平成11年度には、改善命令が1件行われました。
イ 窒素酸化物対策
大気汚染防止法では、ばい煙発生施設の種類及び規模ごとに排出規制がなされており、昭和48年以降、逐次、排出基準の強化・規制対象の追加等の見直しが行われています。
さらに、工場・事業場が集合し、施設ごとの排出規制では二酸化窒素に係る環境基準の確保が困難であると認められる地域(本節1(3)イ(イ)参照)においては、都道府県知事が作成する総量削減計画に基づき工場単位で規制する総量規制が実施されています。
平成11年度における固定発生源からの窒素酸化物総排出量は、年間408百万m3N(837千t)でした(図1-2-20)。これら、固定発生源から排出される窒素酸化物については、低NOx燃焼技術(2段燃焼法、排ガス再循環法、低NOxバーナー等)や排煙脱硝技術等による対策が講じられています。平成11年度末現在における排煙脱硝装置の設置基数は1,439基、処理能力は370百万m3N/hでした(図1-2-21)。
また、大気汚染防止法で規定するばい煙発生施設に該当しない業務用小型ボイラー等の小規模燃焼機器についても、特に大都市地域ではこれらから排出される窒素酸化物の量が無視できないことから、優良品推奨水準としての窒素酸化物排出濃度に係るガイドライン値を定め、これに適合する低NOx型燃焼機器の普及に努めています。
ウ 粒子状物質対策
大気汚染防止法では、固定発生源から排出される粒子状物質について、ばいじん*と粉じん*に区別しており、粉じんはさらに一般粉じんと、特定粉じん(石綿)(本節5(2)参照)に分けられています。
(ア)ばいじん対策
ばいじんについては、ばい煙発生施設の種類及び規模ごとに排出基準が定められており、さらに、施設が密集し、汚染の著しい地域における新増設施設には、より厳しい特別排出基準が定められています。平成11年度における固定発生源からのばいじんの年間総排出量は、75千tでした(図1-2-22)。ばいじん対策としては、適切な燃焼管理や集じん装置の設置等の対策が講じられています。
(イ)一般粉じん対策
一般粉じんを発生する一般粉じん発生施設に対しては、構造、使用及び管理に関する基準が定められています。平成11年度末現在における一般粉じん発生施設の総数は約60千施設で、種類別にみると、コンベアが最も多く35千施設(58%)です(表1-2-9)。
(ウ)浮遊粒子状物質対策
大都市地域を中心に、依然、環境基準達成率の低い浮遊粒子状物質(本節1(4)ア参照)については、移動発生源及び固定発生源を合わせた総合的対策を行う必要がありますが、その発生源が多岐にわたり、また大気中での光化学反応等によって二次的にも生成するなど発生機構が複雑であることから、原因物質の排出実態、二次生成粒子の生成機構等について検討を進めているところです。
エ 硫黄酸化物対策
硫黄酸化物については、大気汚染防止法において、K値規制(地域と煙突の高さに応じて排出が許容される量を定める規則)による施設単位の排出規制に加え、国が指定する24地域において、都道府県知事が作成する総量削減計画に基づき、工場単位の総量規制が実施されています。
平成11年度における、固定発生源からの硫黄酸化物の年間総排出量は、220百万m3N(629千t)でした(図1-2-23)。これら固定発生源から排出される硫黄酸化物については、重油の脱硫や排煙脱硫装置の設置等の対策が講じられており、平成11年度末現在における排煙脱硫装置の設置基数は2,094基、総処理能力は224百万m3N/hです(図1-2-24)。
(2)移動発生源対策
ア 自動車排出ガス対策
大都市地域において、二酸化窒素、浮遊粒子状物質等による大気汚染は依然として厳しい状況であり、その主原因である自動車排出ガス対策が求められています。自動車排出ガスの総量が低減しない理由としては、自動車の単体対策などの対策効果が自動車保有台数の増加(総説図1-1-6参照)に伴う走行量の大幅な伸び(図1-2-25)などに相殺されていることが挙げられます。
(ア)自動車単体対策
自動車排出ガスについては、昭和48年以降、大気汚染防止法に基づく規制を逐次強化し、自動車からの大気汚染物質の排出量を大幅に削減してきたところです(表1-2-10)。
自動車排出ガス低減対策のあり方について、平成8年5月以降、中央環境審議会で審議が続けられ、数回にわたり、答申が出されております(表1-2-11)。平成14年4月には、第五次答申が取りまとめられました(表1-2-12、表1-2-13)。同答申の概要については以下のとおりです。
1)ディーゼル新長期目標
平成17年末までに窒素酸化物等を低減しつつ粒子状物質に重点を置いた世界で最も厳しい規制に強化し、新短期規制(平成15〜16年規制)に比べ粒子状物質で50%〜85%、窒素酸化物で41%〜50%削減すること(図1-2-26、図1-2-27)。
2)ガソリン新長期目標
平成17年末までに二酸化炭素低減対策に配慮しつつ窒素酸化物等の排出ガスの規制を強化し、新短期規制(平成12年規制)に比べ窒素酸化物で50%〜70%削減すること。
3)自動車の排ガス性能を的確に評価するため試験モードを変更すること。
4)ガソリン中の硫黄分許容限度設定目標値を平成16年末までに現行の半分に低減すること。
また、大気環境の改善には使用過程車の排出ガス低減も重要であることから、DPF*等の排出ガス後処理装置の技術的可能性・効果等を検討するため、ディーゼル車対策技術評価検討会を開催し、平成12年7月に中間報告書が、平成13年5月に最終報告書が取りまとめられました。事業者や地方公共団体によるDPFや酸化触媒の装着について補助を行い、普及を推進しています。
(イ)燃料対策
自動車燃料の品質を確保することは、自動車排出ガスによる大気汚染防止に必要な対策の一つであり、大気汚染防止法において、自動車燃料の品質確保のための基準が定められています(表1-2-14)。中央環境審議会答申に基づき、平成16年末までに軽油中の硫黄分の許容限度を0.05質量%以下から0.005質量%以下に、ガソリン中の硫黄分の許容限度を0.01質量%以下から0.005質量%以下に低減することとしており、さらなる硫黄分の低減が検討されています。
(ウ)大都市地域における自動車排出ガス対策
大都市地域における二酸化窒素及び浮遊粒子状物質に係る厳しい大気汚染に対応するため平成13年6月に改正された自動車NOx・PM法(図1-2-28)に基づいて、平成14年4月に総量削減基本方針が閣議決定されるとともに、事業者が自動車を利用する際の判断基準が告示されました。同法のうち、事業者による排出の抑制については同年5月に、車種規制については同年10月に、それぞれ施行されました。自動車NOx・PM法の円滑な施行を図るため、自動車取得税等の軽減措置や政府系金融機関による低利融資等の普及支援策を講じています。
また、道路交通環境が厳しい地域を対象として、警察庁、経済産業省、国土交通省及び環境省で構成される道路交通環境対策関係省庁連絡会議において対策が検討されています。平成14年度においては、10月に「国道43号等の道路交通環境対策の推進について(当面の取組)」(平成12年6月)及び「名古屋南部地域の道路交通環境対策の推進について(当面の取組)」(平成13年3月)に基づく施策の進捗状況をフォローアップするとともに、平成15年2月に「東京都における道路交通環境対策の推進について」を取りまとめ、関係機関の協力の下、各種施策を推進しています。
イ 低公害車の普及促進
大都市地域を中心とした自動車交通に起因する大気汚染問題、CO2等の温室効果ガスによる地球温暖化問題を解決していくことが急務となっているなか、平成13年7月に策定された「低公害車開発普及アクションプラン」に基づき、電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ハイブリッド自動車及び低燃費かつ低排出ガス認定車*を実用段階にある低公害車として位置付け、2010年度までのできるだけ早い時期に1,000万台以上の普及を目指すこととしています。平成14年3月末現在での低公害車(軽自動車を含む)の普及台数は、全国で約305万台(電気自動車約4,700台、天然ガス自動車12,012台、メタノール自動車135台、ハイブリッド自動車74,600台、低燃費かつ低排出ガス認定車約296万台)です。
また、次世代低公害車の本命と目される燃料電池自動車については、平成14年5月に、経済産業省、国土交通省、環境省の副大臣で組織する「副大臣会議燃料電池プロジェクトチーム」が報告書を公表し、その中で、平成22年までに5万台、平成32年までに500万台という普及目標を定めました。また、平成14年12月には、市販第1号となる燃料電池自動車を政府公用車として導入しました。
(ア)普及促進のための補助施策
低公害車の普及を図るためには、低公害車の購入に対するインセンティブを高めるとともに、自動車メーカーによる低公害車の開発を促進することが必要であることから、自動車税のグリーン化*、低公害車の取得に関する自動車取得税の軽減措置、所得税・法人税についての特別償却又は税額控除措置を講じています。また、地方公共団体や民間事業者による低公害車導入に対し、各種補助を行っています。
また、低公害車普及のためのインフラ整備については、国による設置費用の一部補助と燃料等供給設備に係る固定資産税等の軽減措置を実施しており、平成13年度末までに207か所の燃料等供給施設(エコ・ステーション)の整備が行われました。
(イ)政府による低公害車の導入
国の各機関(国会及び裁判所等を含む)においても国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法 平成12年法律第100号)に基づき、一般公用車への低公害車の導入が進められており、平成14年3月末現在で、1,327台(一般公用車のうち19%)が低公害車に切り替えられています。計画では、平成16年度末までにすべての一般公用車を低公害車に切り替える予定です。
(ウ)その他の取組
現行の大型車に代替するジメチルエーテル自動車、次世代ハイブリッド自動車、高性能天然ガス自動車等の次世代低公害車の開発促進を実施しています。
また、わが国で入手可能な低公害車に関する情報を取りまとめた「低公害車ガイドブック」の刊行、東京代々木公園等全国各地で低公害車を一堂に展示する「低公害車フェア」の開催等を行い、低公害車に関する情報の普及活動を実施しました。
ウ 交通流対策
(ア)交通流対策
交通流対策としては、バイパス、環状道路をはじめとする道路網の体系的整備による道路交通の分散、円滑化、駐車場・駐車場案内システムの整備、交差点の改良を図るとともに、新交通管理システム(UTMS)*の一環として、交通管制システムの高度化、光ビーコン*の整備をはじめとする交通情報収集・提供機能の拡充による交通流の分散、信号制御の高度化等による交差点等における交通渋滞の解消、公共車両優先システム(PTPS)の整備による交通総量の抑制等により交通混雑を緩和し、環境への負荷の軽減に努めました。
また、VICS(道路交通情報通信システム)*については、全国展開に向けた積極的な取組を推進し、平成14年度までに全都道府県で運用が開始されました。
(イ)物流の効率化
平成13年7月に閣議決定された「新総合物流施策大綱」等に基づき、物流の利便性及び効率性の向上等に加え、環境負荷を低減させる物流体系の構築と循環型社会への貢献を目指して、共同輸配送の実施や物流拠点の整備等によるトラック輸送の自営転換の推進、交通安全施設等の整備やITSの開発・活用、環状道路等の整備や交差点及び踏切道の改良によるボトルネック解消、環境ロードプライシングの試行的実施等TDM策の推進、環状道路周辺等への物流拠点の立地促進等を進めました。
(ウ)公共交通機関の利用促進
都市におけるバス交通の活性化や交通結節点の整備等による公共交通機関の利用促進を図っています。
エ 微小粒子状物質に関する検討
近年、SPMの中でも微小粒子状物質(PM2.5)*と健康影響との関連が懸念されつつあることから、PM2.5の測定法について調査・検討を実施しました。さらに、PM2.5の健康影響の評価を進めるため疫学調査や実測調査、動物実験等を含む微小粒子状物質等暴露影響調査を実施しました。
ディーゼル排気粒子(DEP)は発がん性や気管支ぜんそく、花粉症等の健康影響等との関連が懸念されていることから、「ディーゼル排気微粒子リスク評価検討会」によるリスク評価を行ってきました。同検討会は、平成14年3月に、「疫学研究からDEPが発がん性を有することを強く示唆している。」と報告し、肺発がんに関してリスクの概算を行いました。
オ 普及啓発施策
窒素酸化物や粒子状浮遊物質の濃度が特に高くなる12月を「大気汚染防止推進月間」に指定し、マイカーの使用抑制や適切な自動車の使用等を国民及び関係機関に呼びかけました。また、年間を通じて「アイドリング・ストップ運動」の推進や、「エコドライブ」の実施を呼びかけました。
カ スパイクタイヤ粉じん対策
スパイクタイヤ粉じん対策については、スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律(平成2年法律第55号)に基づき、平成14年1月現在、18道県の817市町村が環境大臣により指定地域とされ、その地域内でのスパイクタイヤの使用が原則的に禁止されています。また、凍結路面における運転上の注意事項をホームページに掲載し、脱スパイクタイヤの啓発を図りました。
キ 船舶・航空機・建設機械の排出ガス対策
船舶からの排出ガスについては、都市臨海部への影響等の観点からも対策を進めることが重要であり、国際的動向を踏まえ、排出削減技術の動向等を把握して排出削減手法等を検討しています。
航空機からの排出ガスについては、国際民間航空機関(ICAO)の排出基準を踏まえ、航空法(昭和27年法律第231号)により、炭化水素、一酸化炭素、窒素酸化物等について基準が定められ規制されていますが、ICAOにおいてさらなる基準強化が審議されています。こうした国際的動向を踏まえつつ、空港周辺の環境保全のための対策について調査検討を行っているところです。
建設工事に伴う排出ガスについては、公共事業を中心に窒素酸化物等を低減している排出ガス対策型建設機械の使用を推進するとともに、排出ガスをさらに低減した建設機械の開発を促進しています。