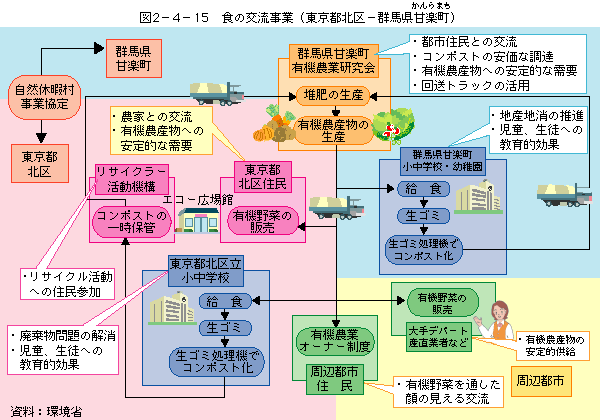
3 外部と連携した地域環境力の充実
地域環境力を備えた取組は、各地で単独で行われるのみならず、地域の枠を越えて地域同士が連携しながら進められている場合も多く見られます。このように地域間で連携をとることは、単にそれぞれの地域内の取組の効果を上げるだけでなく、取組の輪が地域外へと広がることにより、取組の効果が波及的に広がっていく可能性を持っていると考えられます。
(1)他の地域の地域資源を互いに活用した取組
地域全体として地域環境力を備えた取組を行うにしても、地域内だけの取組では地域資源を有効に活用していくことが難しい場合があります。こうした場合、他の地域との連携を図りながら取組を進めることにより、取組を効果的なものとしている例が多くあります。
例えば、東京都北区の小中学校の給食から出る生ゴミで作られるたい肥は、群馬県甘楽町において有機農業に活用され、収穫した野菜などは同区の学校給食で活用されたり、同区内のフリーマーケット*で販売されることにより、リサイクルの輪を広げています(図2-4-15)。
両者が連携する以前、北区では給食などから年間50t以上も出る生ゴミの処理に苦慮していた一方、甘楽町では主力産業であった養蚕業が衰退し、桑畑などの有効活用が課題となっていました。こうした双方の課題を、相互に役割を補完し合いながら解決を図ろうと交流が進められています。
北区内の各小中学校では、この取組を授業で取り上げたり、甘楽町農家に体験学習に行ったりと活用することで、「甘楽の野菜を使った給食は、色が濃いし甘くておいしかったよ」などのコメントも得られ、給食の食べ残しの量が減少するといった効果も表れています。
(2)圏域で連携した取組
地域において、取り組もうとしている課題がその地域より広い範囲での社会経済活動や自然の営みに関わるため、その全体をとらえることなくして効果的な対応が難しい場合があります。このような場合、社会経済活動や自然の営みが行われている圏域を構成している各地域が連携し、一体となって取組を進めている事例があります。圏域連携を効果的なものとするためには、地域において取組を進める場合と同様に、圏域全体で地域環境力を醸成していくことが不可欠であり、そのためにも、各地域が積極的に情報交換し、圏域全体の資源の把握に努めるとともに、相互に目標を共有していくことが重要となるといえます。
例えば、熊本県は、「水の都」としてその生活用水の約8割を地下水に依存しています。しかし、近年では水源かん養域での地下水位が低下傾向を見せており、貴重な水資源の減少が懸念されています。そこで、平成12年11月、緑川(一級河川)の上流に位置する矢部町と流域の下流に位置する熊本市は、森林の持つ水源かん養機能に着目し、地下水の保全に役立てるため、矢部町が土地を熊本市に無償で貸し付け、熊本市が植林・保育を84年間にわたって行うことを内容とする森林整備協定を締結しました。こうした形での森林の整備は、水源のかん養の他にも、育林作業に上流の矢部町民と下流の熊本市民が参加することで、相互の交流の促進や海と山との関連を学ぶ場としても期待が寄せられています。
(3)同様な取組を行っている地域と連携した取組
同様の課題を抱えて取組を行っている地域が相互に連携することにより、それぞれの取組を充実させている例も見られます。
ア 棚田サミット(http://www.yukidaruma.or.jp/tanada/)の開催
棚田は、山間の急峻地を石などを用いて階段状に整地し、谷の水を引いて田としたものです。棚田は山間部での耕作を支えただけでなく、その保水能力から水源かん養に重要な役割を果たしてきましたが、耕作効率が悪いことや農家の高齢化や後継者不足から、その保全が危ぶまれています。高知県梼原町では、平成4年に棚田の保全活動を目的として「千枚田オーナー制度」を開始しました。この制度を通じてかかわりを持つようになった全国のさまざまな立場の人々からの提言を基に、平成7年に第1回棚田サミットが開催されました。サミットの開催を通じて、全国の地方公共団体、個人、団体等が連携を図ることにより、同じ課題を抱える地域間で情報交換や共同研究が進められ、その成果が各地域の取組意識・能力をさらに高めています。棚田サミットを支える「全国棚田(千枚田)連絡協議会」の会員数は、平成7年の設立当初の46(うち地方公共団体会員数24)から平成14年は208(うち地方公共団体会員数73)に増加、平成14年、千葉県鴨川市で開催された第8回サミットには全国から延べ3,225人が参加し連携と取組の輪は広がりを見せています。
「大山千枚田」 千葉県鴨川市提供
イ 路面電車サミットの開催
路面電車は、自動車交通量の増加を背景に「道路の邪魔者」とされ、全国で廃止が進みましたが、近年、渋滞や地球温暖化、大気汚染等の問題から、車社会を再考し都市の再生を図るため見直されています。路面電車は、環境効率や輸送効率に優れバリアフリーであるとともに、その活用により、中心市街地のリモデルと活性化、暮らしやすさの向上という効果が期待されています。路面電車やLRT(低床式路面電車 Light Rail Transit)の活用を提言するNPOの呼びかけにより、平成5年に第1回路面電車サミットが札幌で開催されました。サミットの開催を通じて、情報交換や路面電車を持つ鉄道事業者、路面電車が走る地方公共団体等関係行政機関との交流が進み、路線延長、他の交通機関との連携の強化、路面電車を軸としたまちづくり等が具体化しています。過去に廃止した都市の中では復活の検討を始めたところもあります。平成13年、熊本市で開催された第5回サミットには全国13のNPOと19の事業者などが参加しています。
路面電車の走る町(富山市)
(4)国際間の連携
これまで見てきたような連携からさらに視野を広げ、国際的に取組を展開している事例も出てきています。わが国の地方公共団体では、北九州市や四日市市など、自らの公害経験を活かして公害対策を中心とした環境協力を途上国に対して進めており、地域から世界全体の環境改善へ向けて取組を行っています。また、NGOなどが、地域から始めた環境保全活動の経験やノウハウを世界に発信している事例もあります。
例えば北九州市(http://www.city.kitakyushu.jp/~k2602050/)では、他の地方公共団体が国際環境協力を行う際のモデルとなることを目的に、北九州市が地域資源として持っている公害克服の経験、国際協力の実績及び公害防止技術を体系的に整理することにより、地方公共団体が国際協力を一層効果的・効率的に実施するための手法や仕組を整備し、この事業を通じて構築されたネットワークや環境協力に関する人材の活用体制、研修教材などを活かし、中国大連市をはじめ、アジアの諸都市との間で、共同事業や人材育成を中心とした支援が進められています。
かつて、日本は激甚な公害を経験しました。わが国が環境分野で国際的貢献をしていく上で、このような形で、これまでの公害経験や得意分野を活かした創造的、先導的な環境研究・技術の成果が地域から世界に向けて直接発信されることが、今後一層期待されます。
コラム コミュニティビジネスの特徴
地域コミュニティレベルで地元の住民、企業自らが、公共性・非営利性の高い社会サービス供給や商品の製造・販売などを行い、コミュニティを元気にしていく地域問題解決型のビジネスです(図2-4-14)。従来の企業が行うビジネスとは異なった次のような特徴を持っているとされています。
1)地域の人々が日常生活において抱える問題を解決するところに事業機会、市場を求めるゆえ、公共性、地域貢献性が高い
2)営利的活動と非営利的活動の両者の要素を併せ持っている
3)生活圏としての地域コミュニティを基盤として事業が展開される(ただし、広く世界的な視野を持った事業展開を図っていくものも少なくない)
4)地域コミュニティに密着しているため、商品・サービスの需要者も供給者も共に、地域住民であるというケースが多い
5)地域コミュニティにおける適正規模・適正利益を追求するスモールビジネスである
6)潜在的には高いニーズがありながら、一般営利企業や行政などを通じた既存の供給形態では商品・サービス供給が行いにくかった新しい分野を対象としている
7)地域の中に新たな需給関係を創出することで、さまざまな地域資源の地域内循環を仲介・促進する