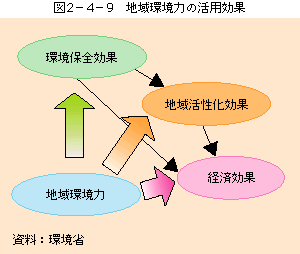
2 地域環境力による地域活性化とその効果
今日、少子高齢化や国際競争力の低下による産業空洞化などを背景として、地域社会の活力が低下しており、その活性化が急務となっています。地域の活性化のためには、その地域の独自性を発見、活用し、他の地域との差別化を図っていくとともに、地域全体が一丸となって問題の克服に対処していくことが重要です。近年、こうした地域の活性化を図っていくために環境の保全に積極的に取り組んでいこうとする動きが高まっています(図2-4-9)。
(1)地域の発展と環境保全との両立・統合
第1節で見たとおり、歴史的には、地域の環境を破壊しながら開発が進められることもあり、従来は、環境を保全することは地域の開発、発展を妨げるものだととらえられることがありました。しかしながら、環境保全の意識が高まっている今日、各主体の間で環境保全型の地域開発の重要性が認識されるようになっており、こうした形での地域開発を進めていくことによって、地域の発展と環境保全の両立・統合につながっていくこととなります。
過去に損なわれた自然環境を取り戻すため、関係行政機関、地方公共団体、地域住民、NPO、専門家等の地域のさまざまな主体の参加により自然再生事業を行うための枠組みを定めた自然再生推進法(平成14年法律第148号)が、平成14年12月に成立しました(図2-4-10)。具体的取組として、釧路湿原において直線化された河川の再蛇行化等により乾燥化が進む湿原の再生を目指す事業や、埼玉県くぬぎ山地区において産業廃棄物処理施設の集積等により失われた武蔵野の雑木林の再生を図る事業などがすでに始まっています。これらの取組は、地域における雇用の促進や他の地域との共生、交流の促進につながるものとして期待され、地域の発展と環境保全を両立・統合させていく取組と位置付けることができます。
(2)地域環境力を活用した地域活性化
地域環境力を備えた環境保全の取組は、地域を活性化させていくために不可欠な地域の独自性の発見や地域一丸となった対応を必然的に行っていくことにもなります。すなわち、地域環境力を備えた取組は地域の環境を保全するとともに、結果的に経済的な効果や地域の活性化を呼び起こすこととなり、地域の発展と環境保全とがともに達成された社会の構築につながっているのです。
実際、地域の活性化を目的として、その手段として環境保全に取り組んでいる例は多く、地域の環境、社会、経済をともによくしていこうとする動きは広がりを見せています。その場合、地域環境力を備えた取組の形態には多種多様なものがあります。以下、地域の活性化にもつながる地域環境力を備えた取組として位置付けることのできるいくつかの動きを見ていきます。
ア サスティナブルツーリズム(大分県湯布院町)
最近、リゾート開発型の観光に対して、サスティナブルツーリズムという考え方が注目されています。リゾート開発型の観光地では、その多くがブームの終焉とともに観光地としての魅力が失われたのに対して、サスティナブルツーリズムは、地域にある、自然、文化、歴史遺産を活用し、時には新たなアイディアを導入することで、環境の保全、地域コミュニティの維持、長期的な経済的利益を同時に達成することに特徴があります。
大分県湯布院町では、町内のゴルフ場開発計画をきっかけに、自然と農村が織り成す景観の美しさ、また、それは後世に引き継ぐべき遺産であることが認識されました。そして、30年も前から、観光業者、商業者、行政、さらに湯布院への訪問者等の協力の下、町の豊かな自然と景観の保全を前提として、安易に商業主義的な観光地をつくるのではなく、まず自分たちが住みやすく、訪れる人に対して誇れるようなまちづくりを行うことで地域の振興を図ってきました。
今日、同町は、豊かな環境を維持しつつ年間300万人以上の観光客が訪れています。サスティナブルツーリズムを具現化したまちといえるでしょう(図2-4-11)。
由布岳と湯布院盆地(大分県湯布院町)
イ エコステーション(東京都新宿区 早稲田商店街)
東京都新宿区にある早稲田商店街では、平成8年に大学の夏季休暇中の夏枯れ対策として商店会の有志が行った環境イベントをきっかけに、空き缶やペットボトル・生ゴミを回収機に入れると、ラッキーチケットが当たるという「エコステーション」の取組が行われています。回収機は商店街の空き店舗に設置され、リサイクルショップが併設されたり、近くの農家の人が野菜を売ったりと、人が集まる地域のふれあいプラザとなっています。
ラッキーチケットの当選者の来店率は、20〜100%となっており、資源も客も回収するシステムとなっています。全国各地の商店街、研究者、行政関係者の視察も多く、修学旅行で見学に来た中学生などには、将来大学に入学した時に商店街で使えるチケットが配られるなどしています。エコステーションの取組によって、商店街の活性化が図られただけでなく、地域コミュニティの形成や環境意識の向上といった効果も現れています。
早稲田商店街での成功をきっかけとして、全国リサイクル商店街ネットワークが組織されたり、平成11年からは「全国リサイクル商店街サミット」が開催されたりと、エコステーションの取組が各地に広がっています。
エコステーション(東京都新宿区) 早稲田商店街
(http://www.eco-station.gr.jp/)提供
ウ エコミュージアム(山形県朝日町)(http://www.town.asahi.yamagata.jp/eco.html)
山形県朝日町では、フランスのアンリ・リビエール(元国際博物館会議会長)が唱えた、「行政と住民が一体となって、その地における人間と自然の関わりあいの歴史、生活、産業、習慣を写し出すような表現力を持たせるシステムをつくろう」というエコミュージアムの概念に基づき、地域づくりを進めています。
朝日町では、地域の中にある自然資源、観光資源のみならず、歴史・文化、産業、人などすべてのものを地域の資源としてとらえています。そして、地域の営みから生まれた遺産(資源)を現地で保存・育成・展示することを通して地域社会の発展に寄与することを目的として、地域全体を一つの博物館と位置付け、歴史、生活、環境を総合的に理解したり、地域の生活、自然環境を体験して味わう場とすることにより、地域の発展に取り組んでいます。平成3年には、自然と人間の共生をテーマに、まちづくりの基本テーマを「楽しい生活環境観、エコミュージアムの町」として掲げ、住んでいる人が主人公として、自分たちの町固有の生活を楽しみ、自分たちの町についてよく理解し、誇りを持って生活していくことを旨とし、ゆとりを楽しむ、自然に親しむ、文化づくりを楽しむ取組がなされています(図2-4-12)。
エコミュージアムの実践による効果としては、1)地域資源の発掘・活用(地域資源の発掘で終わることなく、それを活用して魅力づくりに結び付ける)、2)地域の魅力づくりへの展開(住民主体の多彩な取組に発展させる)、3)まちづくりに向けた体制づくり(各主体のパートナーシップ)、が可能となることが挙げられています。
エ コミュニティビジネスの台頭
地域主導の社会経済づくりを進める地場産業やコミュニティビジネス*を振興していくことにより地域の活性化を目指す動きも見られ、その中には、地域環境力を備えた取組に当たるものも多く見られます。
滋賀県の琵琶湖地域においては、「菜の花プロジェクト(http://www.econavi.or.jp/bdf.html)」が行われています(図2-4-13)。これは、休耕田・転作田に「菜の花」を植えて観光や環境学習用として栽培し、花からは「なたね油」を採油して学校給食や一般家庭などで使い、その廃油を「廃食油燃料化プラント」で精製処理し、軽油の代替燃料として農耕車・自動車・漁船等に使用し、なたね油の採油過程で出た「油かす」は、家畜の飼料にしたり、菜の花畑の「有機肥料」にして有効活用するというもので、環境保全・資源循環型の活動とビジネス活動が両立した取組となっています。
このように地域にある資源を利用してエネルギーに変え、そのエネルギーを地域内で利用するという域内資源循環型の「エコ・コミュニティ」づくりが行われています。
(3)地域環境力を活用した地域活性化の効果
こうした取組を見てみると、地域環境力を備えた取組は、次のような社会的・経済的な効果をもたらすことにより、地域活性化に貢献していると考えられます。
まず、地域環境力を備えた取組は、現存する地域資源を地域のために有効に活用させる原動力となるばかりでなく、地域の人々の生きがい、自己実現、心の豊かさなどにもつながります。また、地域内での幅広い連携を通じて人的交流が活発になることで、地域に共同体意識が生まれ、快適な地域生活をもたらします。こうした豊かな共同体の創造が、地域社会へのさらなる愛着や誇りの意識、地域づくり活動への参画へと相乗的な効果をもたらし、さらには、持続可能な地域づくりとともに、地域独自の文化、知恵・知識を地域の中で蓄積していくことも可能とします。地域の良いところが内外に発信されれば、域外の人々との交流も生まれ、定住人口や企業・事業所等が増えていくことにもつながります。
また、特にコミュニティビジネスのように、その取組が営利的活動の要素を持ったものであれば、これまで地域の中で商品・サービス需要者であることが多かった障害者、女性、高齢者といった人々に、商品・サービス供給者としての新たな就労機会を創出できる可能性を持つなど、地域での経済的な基盤の確立に貢献していくことを可能とします。また、地域外の近隣や企業・事業所等に対しても、新たな商品・サービスの種や供給ルートを提供したり、経営意識等に刺激を与えるなどさまざまな波及的効果をもたらし、新たな産業・市場を創造、拡大していく可能性があります。
コラム 地域社会と一体となった経営による、NPO活動・環境保全活動への投資の促進
(バンクーバー市信用組合 Vancouver City Savings Credit Union)
カナダのバンクーバーにある信用組合は、地域の一員として地域に根ざした経営を行っています。この信用組合は組合員約275,000人からなり、その構成は90%が地域に住む個人、9%が企業、1%がNPOとなっています。
信用組合は、環境、社会、経済が統合した地域の発展という目標を立て、目標達成のための行動計画には、エネルギー効率向上の投資を支援する低利子融資の企画、地域内のNPOのニーズに応えた低利子融資の充実等を掲げています。そして、信用組合は、定期的に監査報告書を公表し、目標達成度について財務的な受益者でありかつ地域社会の一員である組合員に評価してもらっています。監査報告書は、財務情報だけでなく、信用組合が地域の望む価値やニーズに応えたかどうか、という視点から作成されています。
このような取組によって、地域社会の発展という目標を地域と金融機関の両者が共有し、目標に合った資金の流れによって、NPO活動や環境保全活動への投資を促進させる良い循環が生まれています。