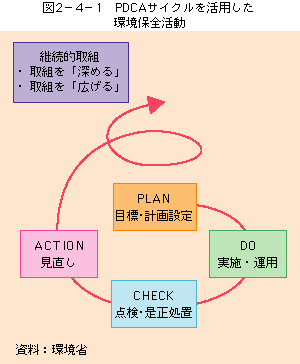
1 環境保全活動の継続
前節で明らかにしたような地域環境力を備えた取組が始められても、その活動がすぐに停滞・縮小し、継続していかない場合が多く見られます。その過程としては、1)取組に不可欠な地域環境力が何らかの形で失われた結果、取組の継続が困難になるケース、2)地域環境力は依然として備わっているものの、地域環境力を具体的な取組へと結びつけていた要因が失われることにより、取組の継続が困難になるケースなどがあります。これらのケースから、活動の継続に必要な手がかりを見ていくこととします。
(1)地域環境力の維持
地域環境力は、前節で見たように、地域の的確な把握と主体間の効果的な連携によって醸成されます。いずれも地域総体として効果的に取組を進めていく上では不可欠なもので、どちらかを欠いても取組の継続は困難になると考えられます。
ア 地域把握の継続と目標のステップアップ
取組を継続していくためには、フォローアップの仕組みを整え、取組の成果を明らかにするとともに、取組の成果や課題を整理・評価することが重要です。こうした活動を効率的・効果的に実施できる仕組みが整えば、常に地域の把握が行われ、適切な取組目標が設定され、その達成に向けて取り組む意識・能力、すなわち地域環境力が継続することとなります。具体的には、例えば、ISO14001で用いられるようなPDCAサイクル*を参考に活動を行っていくことが考えられます(図2-4-1)。
また、取組意識・能力を維持していく観点からは、適切なレベルで取組目標を設定することも重要となります。例えば、最初は、難し過ぎず、やさし過ぎずといった分かりやすい目標設定で取組を始め、当初に設定した目標がほぼ達成できる目途がついたことを踏まえて、目標設定を高くしたり、他の目標を設定し取組の幅を広げている事例もあります。このように活動の手法や方法論について、地域間で情報交換を行い、共有化していくことが有効です。
イ 環境保全活動に取り組む主体の確保
(ア)リーダーの確保
参加型社会のリーダーに求められるのは、コーディネーター(さまざまな人や組織の間の調整やネットワーク作りを行う役割を担う人)型のリーダーシップとされています。このような人材には、専門的な知識や能力だけでなく、環境保全活動を立ち上げたり、リーダーとしてこれを主導したり、関係する主体との間で交流や交渉を担ってきた経験が求められます。地域において各主体の連携を維持していく上でも、このような、取組に参加する各主体を啓発しつつ、それぞれの役割を調整する能力を有する人材が不可欠です。こうした人材が地域を離れたり、活動の第一線から離れたりした場合には、代わりとなる人材がいない限り、その取組は、各主体が共有していたはずの取組目標を見失い、縮小に向かうおそれがあります。
こうした人材を継続的に確保していくためには、環境リーダー養成講座などを活用するばかりでなく、地域における取組の中で人材の育成を図っていくことが重要です。
(イ)活動メンバーの確保
地域において環境保全の取組を進めていくためには、取組を支える幅広い人材、例えば、現場で実際の活動に携わる人材に加え、活動に理解を示し会費等で支える人材、活動を立ち上げ推進できる人材、活動について助言・指導ができる人材も必要となります(図2-4-2)。幅広い人材が揃うことで、活動メンバーが自らの能力の発揮に集中できる環境が整い、責任と誇りをもって活動していくことが可能となります。地域において、こうした人材を確保していくためには、活動メンバーが地域内外に幅広い人的ネットワークを持つように努めるとともに、きちんと体系化された人材育成の仕組みづくりも望まれます。
また、NPOなどが地域の環境保全において中心となって取り組んでいく場合には、その活動についての継続性を確保し、社会的認知を得ていくため、専門知識に加えて会計・組織運営のノウハウ、広報活動、情報収集・発信、政策提言プロセスといった分野で能力を有する人材をその団体が持っている必要があります。広く環境保全に関する国民の関心を高め、その参加を促すことのできる人材も必要です。現在、こうした取組を支える人材が不足している状況にあり、今後、その充実が必要となっています(図2-4-3)。
(2)地域環境力と取組とを結びつける仕組みの維持
東京都「特定非営利活動促進法施行後の市民活動団体の現状と課題に関する調査」(平成12年7月)によれば、地域において市民活動団体が取組を進めていく際、資金や拠点の確保等が活動にあたって現在抱える問題点として挙げられており(図2-4-4)、地域環境力を具体的な環境保全のための取組に結びつけていくことができない場合があります(図2-4-5)。
ア 活動資金の充実
本来、地域で活動する民間団体の活動は、当該地域での協力や地域住民の支持、支援を得つつ、寄付を集めたり自ら収益事業を行うことで持続的に展開されていくことが一つの理想ですが、活動の成果が明らかにならないと地域住民の支持はなかなか得ることができないというのが実際です。環境保全団体の多くは、地域の住民の支持が得られないために資金が集まらない、資金が集まらないために活動成果が上がらず住民の支持が得られないという悪循環に陥り、活動の拡大や継続に苦労している実態があります。環境保全活動団体の年間の財政規模は、100万円以下の団体が46%と、継続的な活動に多くの困難があることが示唆されます(図2-4-6)。
また、NPO自体の問題として、活動の成果について情報を発信し広報していく能力や資金を集める能力が未熟であることが、資金不足を招いている場合もあります。その他、事業費については支援が得られても、組織運営費が足りないことが、組織として十分な活動が継続できなかったり、事業が先細りになったりする事態を招いている場合もあります(図2-4-7)。
イ 活動拠点の充実
内閣府「市民活動団体等基本調査」(平成13年4月)によれば、市民活動団体は、行政や企業等からの支援を団体の59.6%が利用しており、必要な行政支援の内容として49.7%の団体が「活動や情報交換の拠点となる場所の確保・整備」を挙げ、44.1%の団体が「活動に必要な備品や機材の提供」を挙げています。活動に当たって十分な拠点などが確保されているとはいえないのです。地域において各主体が連携して環境保全の取組を進めていく上でも、各主体に関する情報の交換や交流を支援するための拠点や、活動基盤が弱い主体を支援するための拠点が必要な状況にあります(図2-4-8)。
このように資金や拠点となる場所が確保されなければ、地域の中で地域環境力が醸成され、それが具体的な環境保全のための取組へと結実していったとしても、取組はやがては停滞・縮小を余儀なくされます。今後、こうした地域の活動資金や活動拠点をいかに充実させていくかが課題となっています。
コラム リーダーの継続的維持(鹿島ガタリンピック)
佐賀県鹿島市では、「フォーラム鹿島」という市民グループが運営の中心となり、有明海の干潟を活用したどろんこ体験イベント「鹿島ガタリンピック」を20年近く続けています。
干潟という地域資源がこのイベントにより一躍脚光を浴びるようになり、現在ではこのイベントの波及効果により、干潟のどろんこ体験は、中学校等の修学旅行のコースとして通年的に利用され、環境教育の一環として活用されています。
干潟活用以外にもさまざまな地域づくりの活動を行っている「フォーラム鹿島」は、リーダーである代表世話人を継続的に交代しています。特定の個人の資質に頼りきるのではなく、組織全体の持続性に配慮してのことです。
http://www.ujiturn.net/jirei/s63/07.htm
コラム ファシリテーターについて
従来の啓発活動は、行政の活動への理解を得るために、知識がない人に、知識を提供することが主たる目的でした。しかし、「知識」を得ることが必ずしも「実践」には結びついてきませんでした。これからの時代、行政だけでなく、企業も市民もそれぞれが、それぞれの現場で自分達ができることを実践しなければ、環境問題の根本的な解決に至ることは難しいと考えられます。行政や問題への理解を促すだけでなく、実践を促すことが極めて重要であり、各主体が潜在的に持っている解決力・実践力を引き出すことが極めて重要です。そのために、知識を与えるのではなく、持っている力を引き出す機能を担うファシリテーターが重要となるのです。