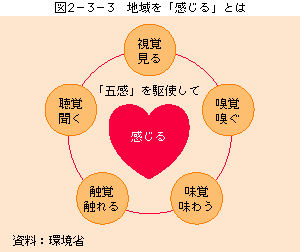
2 地域資源の把握
地域資源を効果的に環境保全の取組に活用していくためには、まずその前提として、自分たちがどういう地域資源を活用できるのか、対象とする地域資源を的確に把握することが必要となります。こうした観点から、地域資源をどのように把握していけば、効果的な環境保全の取組につなげていくことができるのか見ることとします。
(1)「地元学」に見る地域の把握
最近、「地元学」と呼ばれる取組によって、地域の活性化と環境保全を図った地域づくりを推進する動きが、全国のさまざまな地域に広がりを見せています。この取組は、地元に目を向けて地元を知ること、自然と人、人と人との関係を再生することを基本に、熊本県水俣市(http://www.minamatacity.jp/newhp/kankyou.htm)で最初に実践されました。水俣市では、水俣病の発生により、地域の環境、社会、経済のみならず、人と人とのつながりにおいても影響が及んだため、もやい直し(壊れてしまった人々の絆を結び直すこと(もやいとは、船と船を結ぶこと))の意味も込めて取り組まれました。活動に当たっては、まず、水俣川の流域の住民自身による水の流れや使われ方についての調査を基に、地域資源カード、地域人材マップなど地域のさまざまな情報が整備されました。上流部の農山村部や都市部の自然(環境)、生活(文化)・産業調和の再生を図るため、地元学を通じて整備されたこれらの情報を活用して、市の総合計画や環境基本計画の策定、地区環境協定の締結、ISO14001の取得推進、ゴミの分別と市街地の生ゴミ堆肥化による農林業と市街地の連携、エコショップ認定制度や地域の伝統的な環境保全技術を持った人を認定する環境マイスター制度の創設による地場産業の振興、「村丸ごと生活博物館」という水俣市独自のエコツーリズムによる新たな産業の振興などを展開しています。
このように、地元学の取組では、地域の環境を住民自身が調査して、地域の風土と生活文化を掘り起こし、これを活用して環境保全型・持続型のライフスタイルへの転換を図るとともに、風土に根ざした特産品やツーリズムの開発、環境保全型の地域づくりが進められています。
こうした地元学の考え方は、中小規模の都市や農山村に限ったものではありません。大都市において地域を把握していく際にも同じことがいえ、現に大都市でも地元学は広がりを見せています。
(2)地域把握の方法
上記の地元学の取組を踏まえると、地域を的確に把握する方法としては、まず、自分自身でその地域を歩き、探検して地域のあり様について五感を駆使してとらえるという方法が考えられます(図2-3-3)。現場に即した活動の中で、人と環境との関わりを体感できるとともに、新しい発見に結びつき、面白さを育んでいくことが可能となります。また、与えられたものでなく、主体的に自分たちで集めるからこそ愛着がわき、行動にもつながります。その意味で、こうした方法は、地域の把握を具体的な環境保全の取組に結びつけていくための基本といえます。
自分でその地域を書籍やインターネットなどで調べたり、その地域をよく知る人々、例えば昔からそこに住むお年寄り、農林漁業者や職人、そして子どもたちなどに話を聞いてみるという方法もあります。そして、一人ひとりがこのようにして知り得た情報や感じたことを相互に情報交換したり、地域マップや本を作るなどして共同で一つの成果にまとめることは、地域全体の姿を把握していくために有効です。また、自分たちが暮らす地域のことを、地域外の人たちの目を借りて、一緒に歩き、調べることにより、当たり前すぎて気づかなかったことを新しい発見として気づくことがあります。地域を把握していく過程で他の地域との相対比較をしたり、地域外の専門家などの指摘を受け、地域を再発見することも重要なことです(表2-3-1)。
(3)未利用な地域資源の活用の可能性
上記のような方法を用いることにより、利用価値のないものとされてきた資源や、今では埋もれてしまった昔からの地域の経験、すなわち未利用の地域資源が改めて発見され、それを活用した環境保全型の地域づくりや産業の創出へとつながっていく可能性もあります。
例えば山形県立川町では、地域のやっかいものととらえられ、日本三大悪風でもある「清川だし」と呼ばれる強風を逆手にとり、昭和55年から風力発電に取り組んでいます。平成8年には、地球温暖化問題を視野に入れた本格的な風力発電の導入を目指した「立川町新エネルギー導入計画」が策定され、町内の年間の消費電力量約2,200万kWhに相当する電力量を風力発電を中心とした新エネルギーで発電することを目標にしています。現在、町には11基の風車があり、町内の消費電力量の約57.6%に匹敵する発電を行っています。風力発電の他にも、町内で発生する生ごみ全量、畜産廃棄物、もみ殻を混ぜた有機質完熟堆肥の生産に昭和62年度から取り組んでおり、間伐材等森林資源を利用したバイオマス発電や小規模水力発電を計画するなど、町全体で未利用資源の積極的な活用を目指しています(図2-3-4)。
立川町ウインドファーム 山形県立川町
(http://www.town.tachikawa.yamagata.jp/windome/)提供
コラム 地元学とは
地元学とは、郷土史のようにただ調べて知るだけではない。地元の人が主体になって、地域外の人の視点や助言を得ながら、地元を客観的に知って、地域の個性に気づくことから始まる。変化を受け止めて、地域の個性と照らし合わせて、地域独自の生活(文化)を日常的に創りあげていく知的創造行為である。
古びていくに従い美しくなっていく町はいいものだ。しかし、それらは伝統的な町並みや家並みなどの文化的、歴史的遺産や自然を継承し、守って残すという価値観を持ちつづけている努力によって残っている。
その意味で継承し保全することも創造に含まれるだろう。生活文化の創造とは、生活者の内発的な地域づくりに加えて、ものや生活もつくっていくことである。道路や文化施設などのハードに特化してきた地域づくりを見直すことに加えて、農林業に従事する人たちや職人がつくるものづくり、さらに地域の暮らしを楽しむという意味での生活文化づくりも大切にする。
出典:地元学協会資料