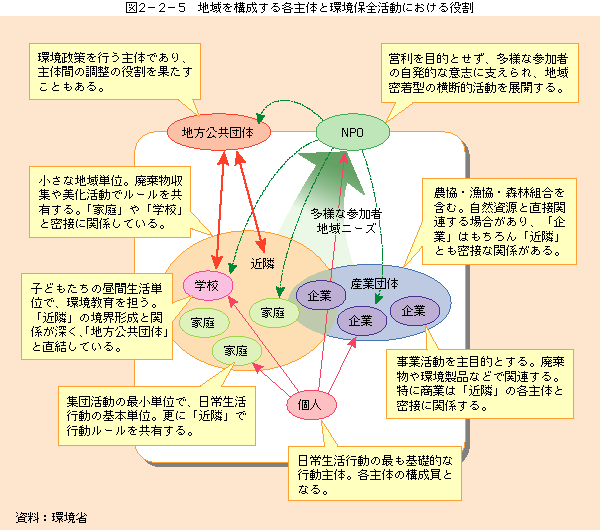
2 地域を構成する主体とその役割
(1)環境保全活動と地域の構成主体との関わり
地域社会は、地域の自然的基盤、社会的基盤の上で、個人、家庭、近隣(自治会など)、学校、企業、地方公共団体、NPOなど多様な主体が社会的・経済的活動を営むことによって成り立っています。地域社会を構成するこれらの主体は、それぞれの立場において地域内における他の主体とさまざまな関係を有しています。その立場と状況に応じて、環境に負荷を与える主体、環境を利用する主体、環境を保全または創出していく主体、環境について学んでいく主体など、さまざまな関わり方を有しており、それぞれの主体相互の間で環境コミュニケーション*がなされています。(図2-2-5)。
ア 個人
個人は、地域における最も基礎的な行動単位です。個人はさまざまな主体の構成員ともなり得る一方で、さまざまな主体と対等な立場で関係する地域社会の一員となることもあります。例えば、ある里山林があったときに、それを残そうとする市民団体もあれば、そこにマンションを建てたいとする企業もあるでしょう。そのとき、その里山林の地権者は、一個人でありながら、他の主体と対等な関係で関わります。また、個人の環境保全活動家が他の主体に大きな影響を与えるような場合もあります。
イ 家庭
家庭は、地域の中で最も小さな組織です。人々は家庭の中でさまざまな日常生活を行うため、環境と密接な日常生活行動をする上での基本単位ともいえます。家庭とは、その構成員がともに同じルールで行動することを求める組織でもあり、家庭の行動はそれが環境に良いのかどうか家族でよく話し合うことが必要です。また、一般には近隣とも密接な関係にあります。
ウ 近隣
近隣は、家庭からのごみの排出や美化活動などで一つのまとまった行動単位となっており、近隣と家庭との関係は密接です。また、近隣は、自治会としての位置付けがなされ、地方公共団体とも密接な関係があります。近隣には、児童会、子供会などがあり、学校区における地区割りとなることもあります。
エ 学校
学校は、子どもたちが昼間のほとんどを過ごす生活単位です。このため、学校における環境教育を一層充実するとともに、学校内での子どもの行動が、どのように環境と関わっているかを考えることが重要です。また、PTAを通じて、親同士をつなげます。
オ 企業
企業は、営利事業を主目的とする主体です。事業活動に伴う排出物、廃棄物、騒音、振動、悪臭などで地域の環境と密接に関わる場合があります。一方、企業は、環境配慮型製品を開発・販売したり、従業員を介して環境保全活動を行ったりする主体でもあります。地域内での他者との関係は一律ではありませんが、商業(商店街)などでは、近隣と密接に関係する場合があります。
カ 産業団体
産業団体は、組合等の業界団体や商工会議所、農協や漁協、森林組合などを含みます。これらは、それぞれの業種における大きな方針づくりなどを担う場合、環境経営などの考え方の有無が地域の環境に大きな影響を及ぼす可能性があります。地域の自然資源と直接関係する団体もあり、この場合、環境と密接に関連します。また、集落など近隣との関係が大きいこともあります。
キ 地方公共団体
地方公共団体は、地域の環境政策を担う主体であり、地域の環境保全と開発の方向性を定める上で重要な役割を果たします。地域の環境基本計画を地域の各主体とともに策定・実行するなど、地域の各主体間のコーディネーター役を果たすこともあります。また、議会などを介して地域の声を集約し、施策に反映したり、法的な手続の窓口となったりします。
ク NPO
NPOは、公益的な活動を行うため、個人が自発的な意志で集まって組織した営利を目的としない団体を指します。図2-2-6に示すようにどのような団体までNPOとするかさまざまな範囲がありますが、本章では図2-2-6で「狭義のNPO」としている範囲をNPOと呼ぶことにします。
多様で多次元な社会のニーズを市民参加によって実現しようとする機運がますます高まりを見せている今日、公益を実現する担い手として不可欠の存在となりつつある主体として、NPOを核とした市民セクターの重要性が増大しています。市民が地域社会の主人公であるとの自覚が高まり、団体を組織した上での自発的な活動が活発化しているところです(図2-2-7)。
NPOは、その目指す使命の実現に向けて、行政や営利を目的とする企業には期待できないような柔軟性に富んだ多様な活動を、即応的に地域密着型で展開できるという特性を持っています。また、行政の個別分野を超えた横断的な活動ができるとともに、市民や消費者の立場から行政や企業の活動をチェックする機能や、市民に近い存在として市民活動を促す機能も有しています。環境分野でも、リサイクルの推進、ナショナルトラスト等の自然環境保全、国際交渉や政策立案過程での提言などの活動がNPOにより行われ、その役割はますます大きいものとなりつつあります。
NPOは、テーマを持ったコミュニティ(テーマ型コミュニティ)として構成されることが多く、さまざまな職種や属性からなる人々で構成されます。例えば、環境分野のNPOについては、組織の成立目的がすでに環境保全であるため、環境と密接な関わりを持つことはもちろん、同じ目的に向かって、構成員が一致団結しやすい特徴があります。こうした成立形態からも既存の各主体とのしがらみが少なく柔軟な活動を行いやすい面があります。
(2)環境保全活動と地域の主体構成から見た地域特性
地域の中での交流は、居住地域や居住形態によって度合いが異なり、居住地域・形態別の調査では、都市部よりも農村部の方が、また、マンションよりも戸建ての方が、それぞれ近隣との交流対象が多いという傾向が見られます(図2-2-8)。
また、総務省「平成13年社会生活基本調査」によれば、地域の人口規模によって、環境保全の取組の傾向に違いが見られ、人口規模が小さい所では、行動する人の数は比較的多いものの1人当たりの行動日数は比較的少なく、逆に人口規模が大きい所では、行動者率は低いものの平均行動日数は多いという傾向となっています(図2-2-9)。
以上のようなことから、人口規模の違いで交流度合いが異なり、交流度合いが異なれば、環境美化や環境保全活動といった地域活動への参加の仕方にも差が生じる可能性があります。