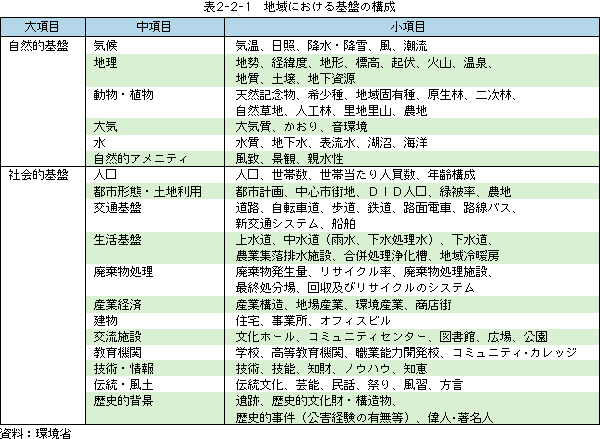
1 地域における基盤の構成と地域特性
(1)地域における基盤の構成
地域というものを見渡してみると、地域を構成し、特徴付けるさまざまな基盤があります。このような地域の基盤は、例えば、温暖か寒冷か、雨や雪が多いのかなどの気候、土地の起伏の緩急、動植物の種類・分布、大気、河川・湖沼・海洋といった自然的基盤、また、鉄道や道路などの交通、上下水道や廃棄物処理施設、文化ホールなどの教育・文化施設の他、さらには、地域に根ざす伝統や風土、歴史といった社会的基盤があります。大きく分けるならば、地域を構成している基盤は自然由来のものと、人間が作り出した社会的なものに分類することができるでしょう。地域を構成する自然的な基盤、社会的な基盤には、上記に掲げるもののほか、例えば表2-2-1に掲げるようなものが考えられます。
(2)大都市、中都市、農山村における基盤と環境との関わり
地域を大きく大都市(3大都市)、中都市(中核市)、農山村(1万人以下の町村部)の3つの地域に分類し、いくつかの基盤を例に地域と環境との関わりの傾向を見ていくこととします。例として、東京都区部・大阪市・名古屋市を大都市、人口30万人程度の中核市である秋田市・富山市・高知市を中都市、山形県立川町・三重県宮川村・宮崎県綾町を農山村として抽出し、地域を構成する基盤として人口、土地利用、運輸を取り上げ、地域による特徴をとらえていきます。
ア 大都市
人口については、大都市では他の地域と相対的に比較して、世帯人員が少なく、高齢化率は低めである傾向が見られます(図2-2-1)。第1章第1節で述べているように、世帯数の増加は、エネルギー消費量や水の使用量の増加につながるものです。
土地利用について見てみると、森林面積は非常に少なく、都市公園の整備がされています(図2-2-2)。都市部における緑の存在は、ヒートアイランド現象*の防止にも効果があると考えられています。さらに、道路や工場付近に樹木が植えられれば、緩衝地帯としての役割も果たします。
1人1日当たりのごみ(一般廃棄物)収集量は、他の地域と比較して多い傾向にあります(図2-2-4)。これは大都市ほど、商業業務系ごみが多いことや、単身世帯が多いため外食や中食(持帰り用弁当、宅配ピザ、百貨店・スーパーマーケット等で販売される惣菜等の総称で、レストラン等の飲食店における食事(外食)と家庭内で調理した食事(内食)の中間に位置付けられ、家庭外で作られ家庭内で消費される食事を指していう。)の機会が多いこと、小売店舗が多く購買機会が多いことなどが考えられます。
イ 中都市
人口については、中都市では大都市と比較して、世帯人員がやや多く高齢化率もやや高めですが、農山村ほど高齢化率は高くありません(図2-2-1)。
交通手段における自動車の分担率は、この10年間で全ての地域で増加していますが、人口規模が小さい都市ほど分担率の増加が大きい傾向にあります。また、人口当たりの乗用車の保有台数は、中都市や農山村の方が、大都市に比べて多い傾向があり、その伸び率も高くなっています(図2-2-3)。これは、中都市・農山村での、鉄道・バスといった公共交通機関の未発達以上に、これらの地域での公共交通機関の衰退が考えられます。1人当たりの交通エネルギー消費は大都市よりも、中都市が多くなっています。
ウ 農山村
人口については、農山村の方が世帯人数が多く、高齢化率が高くなっています(図2-2-1)。
また、農山村には豊かな森林資源が存在しています。森林は、国土の保全、水源のかん養、自然環境の保全、公衆の保健、地球温暖化の防止、林産物の供給等の「多面的機能」を有しています。農山村で農業生産活動が行われることによって、国土保全、地下水かん養、生態系維持等の「多面的機能」が発揮されています。
世帯規模と1人1日当たりのごみ収集量の関係を見ると、世帯規模が大きいほどごみ収集量が少ない傾向が見られます(図2-2-4)。環境省「環境にやさしいライフスタイル実態調査」(平成14年5月)によれば、「環境に重要な役割を担う者」として国民を挙げる比率は町村部で高い(表2-2-2)という傾向が見られます。
(3)持続可能な都市と農山村
このように、都市と農山村では、地域における基盤の違いにより、環境との関わりが異なります。このため、それぞれが目指すべき地域づくりの将来像も違ってくるはずです。持続可能な都市や農村のモデルとして、近年提唱されている2つの考え方を紹介します。
ア 持続可能な都市
近年、都市においては、スプロール(虫食い状開発)による環境破壊、中心部の衰退による社会的損失、都市域の拡大と低密度化による自動車交通量の増大やエネルギー消費の増大等の問題が発生し、持続可能性が十分には達成されていません。これに対し、都市の再生と持続的な発展の方向性の一つとしてコンパクトシティ(都市の相対的高密度化)という考え方が提唱されています。
一般的にコンパクトシティでは、1)都市と農村の土地利用を明確に区分することで都市域の拡大を抑制、2)公共施設、商業施設、都市公園等の都市機能を一定の範囲内に適度な密度で機能的に配置、3)職住の近接、4)都市内の移動を公共交通中心とする等を目指します。ヨーロッパでは環境保全とくらしやすさの双方を実現する持続可能なコンパクトシティの概念を用いたまちづくりが、1990年代から次々と実践されています。
イ 持続可能な農山村
農山村には、自然と人間の関わりの中で調和し形成された生態系の中に、多様で有用な自然的・社会的資源が豊富に存在しています。しかし、近年、農山村では、社会経済構造の変化により農地の耕作放棄、里山の放置などの問題が発生し、農山村における環境の維持管理システムの崩壊が見られ、農山村の持続可能性を保っていくため、その社会システムの転換が求められています。
近年、「エコビレッジ」と呼ばれる、環境との共生、地域物質循環、自律を基調とした地域コミュニティの形成が世界的に広がっています。これは、1970年代にオーストラリアの学者ビル・モリソンが提唱したパーマカルチャーという考え方を具体的に実践するなどして、行われているものです。パーマカルチャーとは、パーマネント(永続性)、アグリカルチャー(農業)及びカルチャー(文化)からなる造語であり、環境への負荷の少ない持続的農業を基本とする社会を構築するというものです。1)地球への配慮(土壌、各種の生物、大気、森林、微生物、動物、水などを含む、すべての生物・無生物に対する心配り)、2)人間への配慮、3)余剰物の分配(余った物や労力は地域社会や次世代に公平に分配する)、により実践されます。日本においても、このような地域づくりが見られるようになってきています。