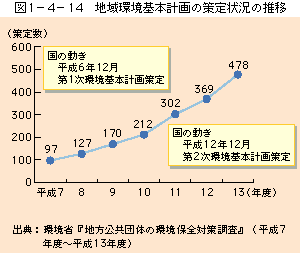
2 一人ひとりと行政との相互関係
(1)一人ひとりの取組を支える行政の取組
ア 新たな枠組みづくりや制度の導入
一人ひとりのライフスタイルの変革を促す新たな枠組みづくりとして、例えば以下のような、計画の策定や制度の導入が進められています。
(ア)地域環境基本計画
地方公共団体の環境保全に関する基本的な考え方を明らかにした地域環境基本計画の策定が各地で進んでいます(図1-4-14)。地域環境基本計画においては、地域の環境の保全や創造に関する取組の目標や、その実現のための方向性等が示されています。最近では、日常生活や通常の事業活動からの環境負荷が今日の環境問題の主な要因となっていることから、事業者や行政の取組に加え、住民一人ひとりの役割として、ライフスタイルを変革し、環境に配慮した生活を進めることなどが盛り込まれるようになっています。
(イ)経済的手法の活用
社会経済システムに環境配慮を織り込むための仕組みの一つとして、製品・サービスの取引価格に環境コストを適切に反映させるために経済的負担を課す環境に関する税、課徴金や預託払戻制度(デポジット制度)、排出量取引制度等の経済的手法*があり、これらは都市・生活型公害や廃棄物問題、地球温暖化の原因となる二酸化炭素の排出に見られるような不特定多数の者の日常的な社会経済活動から生ずる環境負荷を低減させる点で有効性が期待されています。
経済的手法の導入に際しては、他の手法との比較を行いながら、環境保全上の効果、国民経済に与える影響、技術革新を促進する効果、適用に当たって必要とされる行政コストなどを総合的に考えて、その適切な活用について検討することが必要であり、また新たな負担を国民に求める可能性もあることから、一人ひとりの理解と協力を得るよう努力しなければなりません。
地方公共団体においては、平成12年4月施行の地方分権一括法によって法定外目的税の制度が創設されたことから、自然環境の保全に配慮した行動や買い物時に受け取るレジ袋の削減等、日常生活のさまざまな場面における環境配慮を促すため、経済的手法の一つである環境に関する税の導入が進められています。
岐阜県では、中部山岳国立公園内を走る「乗鞍スカイライン」を通り山頂駐車場に入り込む自動車に課税し、税収を環境影響評価や自然環境指導員の設置等の乗鞍地域の自然環境の保全対策に充てる乗鞍環境保全税を創設しました。この新税は、平成15年2月に総務大臣の同意が得られたことから、乗鞍スカイラインが開通する5月から導入する予定とされています。
また、東京都杉並区では、平成14年3月、区内のスーパーや商店で買い物をした際に受け取るプラスチック製の手提げ袋(レジ袋)1枚につき5円を課税するという環境目的税条例が制定されています。条例の施行時期は未定となっていますが、本制度では買物袋を持参することで、この税の支払いは不要になることから、いずれはごみとなるレジ袋の削減につながる仕組みとして提案されています。
イ 社会資本の整備
日常生活における自動車交通需要が高まるにつれ、一人ひとりの日常生活に起因する交通がもたらす環境への負荷が大きくなっています。こうした状況の中、一人ひとりが環境負荷の少ない交通手段の利用や、より環境負荷の少ない方法による自動車の利用を進めていくことが必要ですが、そのためには、一人ひとりの取組を支えていく社会資本の整備が不可欠です。
鹿児島県加世田市では、平成7年に「サイクルシティかせだ」を誓言(取組を誓うとの意味から誓言)し、自転車道やサイクリングターミナル等自転車を利用しやすい環境の整備を進めています。また、岡山市では、平成6年度からパーク・アンド・ライドシステムを導入していますが、平成12年3月からは自動車からバスへ交通手段の転換を図るパーク・アンド・バスライドシステムの運用を開始しました。市では駐車場の配置を工夫したり、乗り換えるバスの定期券は通常より5割引に設定する等、本システムの利用の促進を図っています。地方公共団体では、こうした形での基盤づくりが進められています。
ウ 一人ひとりの取組を支える人材の提供
一人ひとりが環境保全への取組を進める際、環境保全に関する専門的な知識や豊富な経験を有する人からの助言や情報の提供を受けることで、より効果的で適切な取組が促進されます。
環境省では、環境保全に関する取組について豊富な実績や経験を有する等、一定の要件を備えた環境カウンセラー*の登録制度を実施し、環境カウンセラーの連絡先や専門分野等の情報を環境保全に関する取組や活動を行おうとしている人々に対して提供しています。
また、全国各地で行われる自主的な環境保全活動を一層活性化させるため、平成15年1月、地方公共団体やNPO等を対象に、環境保全活動への環境省職員の参加要望を受け付ける窓口を開設するとともに、環境省職員の自主的な参加を支援する体制を整備しました。
さらに、化学物質や環境リスクについて中立的かつ客観的な情報の提供を行い、リスクコミュニケーションを推進する化学物質アドバイザー(仮称)の講習・登録・派遣を試行的に行うパイロット事業を開始しました。
エ 環境情報等の発信
国や地方公共団体では、インターネットを含むさまざまな媒体を通じて、広く環境情報の提供が行われていますが、第3節で見たように、より使いやすく整備された環境情報を入手しやすい形で提供する必要があるとともに、さらに環境に関して無関心な人に向けた積極的な広報活動も欠かせません。
政府では、「エコジャパンサポーターになろう。」と題して、「環境技術先進国ニッポン」が「環境生活先進国」となるための一人ひとりのライフスタイルの見直しについて、テレビスポットや新聞広告等を利用し呼びかけるとともに、地球温暖化防止で世界をリードするため、一人ひとりが取り組める「エコジャパンプラン」についての意見を募集しています。
(2)一人ひとりの環境政策への参画
近年、新たな計画などを策定する際のパブリックコメント手続きが導入されたことや、一人ひとりが閣僚等と直接対話できるタウンミーティングなどの開催により、一人ひとりが日常生活の中で感じた疑問や生じた問題、さらには具体的な提案を意見として発信する機会が創出され、その意見が政策などに反映されるようになってきています。
また、特に地方公共団体における環境保全施策の実施に当たっては、内容を検討する審議会などでは従来の学識経験者などに加え、地域住民の中からも委員が選任されるケースが出てきており、一人ひとりが積極的にその策定の過程に参画することが可能となってきています。さらには、埼玉県志木市において、市民団体の活動が広がり行政の取組に影響を与え最終的には市民参加による環境基本計画の策定に至ったように、一人ひとりの取組が行政を動かし、住民と行政の協働により環境保全施策が実施される例もみられます。
海外に目を向けると、ヨーロッパでは、環境に関する情報へのアクセス権や意志決定における住民参加等を保障することを目的としたオーフス条約*がUNECE(United Nations Economic Commission for Europe 国連欧州経済委員会)において2001年(平成13年)10月に発効しており、国際的にも一人ひとりの環境政策への参画を確保する制度の整備が進められつつあります。
このように、一人ひとりの行政への意見発信や政策の決定過程等への参画が進み、その意見などが行政の政策に反映されることで、一人ひとりがより主体的、積極的に取組を進めていきやすくなり、その結果、わが国全体として、一人ひとりの取組が一層活性化するものと考えられます。